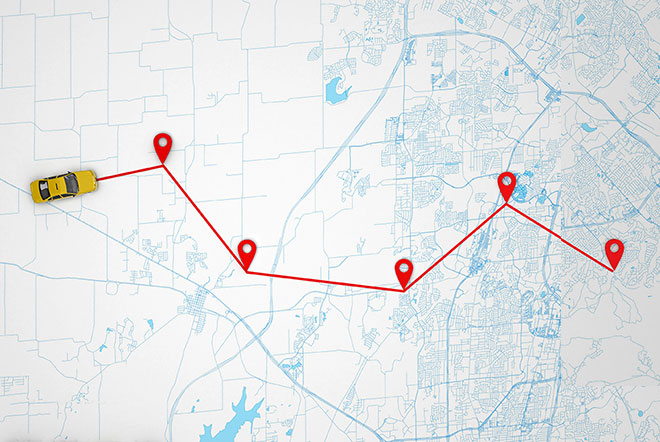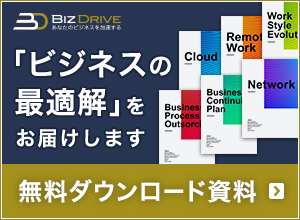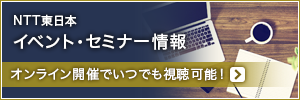2022.11.15 (Tue)
テクノロジーでビジネスの現場が変わる!(第14回)
いまどきの企業PRに不可欠、Twitterスペースとはなにか

アメリカの自動車大手テスラ社の経営者、イーロン・マスク氏が買収したことで話題のTwitter。テキストタイプのSNSとして不動の地位を築いていますが、近年、テキストの短文投稿以外の機能として、新たに音声交流機能「スペース」を追加したことでも注目を集めています。スペースとはいったいどのようなものなのか、2022年初頭からのクラブハウスブームが落ち着いたなか、なぜいま音声SNSに再び注目が集まるのか。スペースの概要や注目される理由、企業活用の事例などについて紹介します。
文字と音声を行き来する「スペース」とはなにか?
Twitterの「スペース」は、2021年5月にリリースされた音声SNS機能です。投稿画面にあるアイコンを押すだけで音声を流すことができるため、仲間内での世間話、識者の講演、タレントのトークなど、日々多くの音声コンテンツの配信に利用されています。
スペースの大きな特徴は、「ツイート(短文投稿)と地続きであるところ」です。たとえば、Twitterのメインコンテンツである短文投稿で気になることをつぶやき、投稿がバズり始めたタイミングでスペースを始めるなど、テキストから音声によるコミュニケーションへシームレスに移行できるよう設計されているのです。
スペースを開始すると、開始の告知とリンクがツイートできるようになり、さらにフォロワーのタイムライン上部にテーマや参加者が簡易表示されたアイコンが現れます。フォロワーは、アイコンからスペースにアクセスすることが可能です。ツイートついでに途中参加したり、複数のスペースを渡り歩いてまたツイートに戻ったりと、テキストあるいは音声によるコミュニケーションを行き来できる点、気軽に配信や参加ができる点、フォロワーに即時かつ直接的にリーチできる点が、ほかの音声SNSにはない大きな強みと言えるでしょう。
ほかにも、Twitterアカウントをもたないユーザーも参加できる点、アーカイブ機能を備えている点、有料チケット制を活用してマネタイズできる点など、さまざまな特徴を有しています。
プロモーションに活用する企業も、スペースの活用事例
現在、スペースは、主に一般のユーザーに利用されていますが、企業での利用事例も少しずつ増えています。企業はどのようにスペースを活用しているのでしょうか。話題になった事例を見ていきましょう。
最初に紹介するのは、味の素冷凍食品が2022年2月26日の「シュウマイの日」に向けて行った施策です。「#シュウマイペアリング総選挙」と銘打ちユーザーにシュウマイに合うお酒をツイートしてもらい、最終日にスペースを利用して、著名な料理研究家やタレントになどによる「開票式」「打ち上げ」を実施しました。「シュウマイに関するツイートが前年同日の2倍に増加した」「スペースの再生回数が12万7,000回を記録した」など、大きな成果を残しています。
次に紹介するのは、WOWOWです。WOWOWはスペース上で、お笑いタレントおよび映画評論家と一緒にWOWOWの映画を鑑賞する「こがけんのみんなでシネマ」を開催しました。ハッシュタグ「#みんなでシネマ」をつけてツイートすればテキストで感想を拡散させることもでき、音声を聞きつつテキストでの交流が楽しめるような施策です。
ほかにもタニタ、わかさ生活、集英社など、多くの企業がスペースを利用しています。味の素冷凍食品のようにキャンペーンの一環として大々的かつ計画的にスペースが利用されることもあれば、特にテーマなどなく日常のツイートのような感覚でスペースが実施されることもあり、各社がさまざまな使い方を試みています。
企業がスペースを活用する際の注意点は?
最後に、企業がスペースを利用する際の注意点を確認しておきましょう。
もっとも気を付けたいのが、発言の内容です。雑談の延長のような雰囲気で気軽に配信できるため気が緩みがちですが、炎上につながるような失言をしてしまうとテキストで拡散する可能性があります。あくまでTwitterであることを忘れず、丁寧な発言を心掛けましょう。
また、雑談の場としてルールを決めずに運営してしまうと、中身のないコンテンツになってしまうことも少なくありません。フォロワーの減少につながることがないように、適宜テーマを設けたり、スピーカーを指定・変更するなどして、飽きさせない工夫をしましょう。
スペースは、企業にとって多くのメリットが期待できる新しい情報発信の場です。ブランディングやPRにつながるだけでなく、「ライブコマースと相性がよい」と考えられており、参入を検討する企業も増えています。「デジタルマーケティングに注力したい」「新しいSNS施策を考えている」という企業なら、注目しておいて損はないでしょう。
連載記事一覧
- 第1回 出張が不要になる?新技術「ホロポーテーション」 2016.07.15 (Fri)
- 第2回 AIがオフィスの空気を管理すれば生産性は上がる? 2016.08.29 (Mon)
- 第3回 目は口ほどにものを言う、「感情認識」の新ビジネス 2016.09.28 (Wed)
- 第4回 仕事中の危険を未然に防ぐ「バイタルデータ」とは 2016.10.14 (Fri)
- 第5回 社会インフラを激変させる可能性を秘めた仮想通貨 2017.10.03 (Tue)
- 第6回 企業が仮想通貨で資金調達する時代は到来するか? 2018.03.26 (Mon)
- 第7回 東大廣瀬教授が語る「本気のVRが企業教育を変える」 2021.02.19 (Fri)
- 第8回 建設業界で注目のDX「デジタルツイン」とは 2021.09.14 (Tue)
- 第9回 中小企業こそDXに向く。町工場・今野製作所の挑戦 2021.12.10 (Fri)
- 第10回 小売業の広告販促DX「リテールメディア」の始め方 2021.12.10 (Fri)
- 第11回 「小売業再建のプロ」が語る、利益率UPのヒント 2022.03.01 (Tue)
- 第12回 年4億円コスト削減を達成した地方製造業のIoT活用術 2022.03.04 (Fri)
- 第13回 「幻の日本酒」が安定供給できた裏にデータ活用あり 2022.06.27 (Mon)
- 第14回 いまどきの企業PRに不可欠、Twitterスペースとはなにか 2022.11.15 (Tue)
- 第15回 雇用確保につながる可能性も、覚えておきたい「給与のデジタル払い」2022.12.21 (Wed)
- 第16回 なぜ世界の小売店が「リテールメディア」に参入しているのか?2023.03.06 (Mon)
- 第17回 経済効果は2兆円!女性の悩みを解決するフェムテックとは2023.03.06 (Mon)
- 第18回 バブル期京都でDX実現! 24時間稼働の無人工場2023.03.15 (Wed)
- 第19回 どうする「2024年問題」物流DXの課題と事例2023.03.30 (Thu)
- 第20回 なぜ企業や自治体が「VTuber」を起用するのか? 2023.03.30 (Thu)
- 第21回 未来を予測し先手を打つ。「AI需要予測」の活用術2023.03.30 (Thu)
- 第22回 顧客の本音を読み解く「センチメント分析」の活用法2023.03.30 (Thu)
- 第23回 「気象ビッグデータ」が売上増とロス削減に貢献する2023.03.30 (Thu)
- 第24回 消費者から信頼感を得るには、トレーサビリティ向上が不可欠2023.04.28 (Fri)
- 第25回 健康のDX「パーソナライズド・ニュートリション」2023.09.08 (Fri)
- 第26回 「Web3」がもたらすビジネスや社会への影響とは2023.09.08 (Fri)
- 第27回 「観光DX」は日本の観光業をどう変えるのか?2023.10.04 (Wed)
- 第28回 大手企業も導入「リーガルテック」で何が変わる?2023.10.04 (Wed)
- 第29回 情報漏えいの原因を解析「デジタルフォレンジック」2023.10.04 (Wed)
- 第30回 関東大震災から百年、災害対策はどう進化したのか?2023.10.04 (Wed)
- 第31回 ITに疎くてもDXはできる!老舗食品企業の挑戦2023.11.22 (Wed)
- 第32回 極地でも高速通信「スターリンク」の可能性2023.12.21 (Thu)
- 第33回 インフラの「老朽化」は、最新技術でメンテナンスできる2024.01.24 (Wed)
- 第34回 新たな個人データ収集方法「ゼロパーティデータ」とは2024.01.24 (Wed)
- 第35回 2024年4月から限定解禁「ライドシェア」の可能性2024.01.24 (Wed)
- 第36回 AIが奪うのは仕事ではなく電力?生成AIのエネルギー事情2024.02.09 (Fri)
- 第37回 トークン経済で市場に好循環は起こるのか?2024.03.01 (Fri)
- 第44回 バス運行を効率化「AIオンデマンド交通」の可能性2024.03.29 (Fri)
- 第45回 生成AIとの対話が成長を促す「AIコーチング」2024.03.29 (Fri)
- 第46回 広告に続々登場「AIタレント」の弱点とは2024.03.29 (Fri)
- 第47回 訪日客が日本のファンになる鍵は「AI」にあり2024.03.29 (Fri)
- 第48回 脳と機械が繋がる「ブレインテック」の可能性2024.03.29 (Fri)
- 第49回 打ち上げが本格化。民間企業の宇宙ビジネスの今2024.03.29 (Fri)
- 第50回 バイヤーもサプライヤーも歓迎!?「自動交渉AI」2024.03.29 (Fri)
- 第51回 医療・建設業界で導入が進む「自律型ロボット」とは2024.03.29 (Fri)
- 第42回 6G、7Gで世界はどう変わるのか?「Beyond 5G」の可能性2024.03.22 (Fri)
- 第43回 脱炭素の効果はブロックチェーンで証明できる2024.03.29 (Fri)
- 第38回 総務省が認可「Wi-Fi 7」とは何か?2024.03.29 (Fri)
- 第39回 総務省が発表「モバイル市場競争促進プラン」とは?2024.03.29 (Fri)
- 第39回 インボイスにも対応「IT導入補助金2024」を解説2024.03.29 (Fri)
- 第40回 文章生成AIの理想的な使用法とは?東京都がガイドラインを公開2024.03.29 (Fri)
- 第41回 新たなテクノロジー「光の半導体」とは何か?2024.03.29 (Fri)
- 第52回 訪日観光客が増えるとトラブルも増える!?オーバーツーリズムをどう解決するか2024.05.22 (Wed)
- 第53回 ウェブアクセシビリティが義務化。どう対処する?2024.07.11 (Thu)
- 第54回 決済時間を1/2に短縮「タッチ決済」が普及中2024.07.12 (Fri)
- 第55回 なぜEUは、生成AIを規制しようとしているのか2024.07.12 (Fri)
- 第56回 2024年10月につくば市でスタート「インターネット投票」とは?2024.08.08 (Thu)
- 第57回 7月実施完了。デジタル庁の「フロッピーディスク」使用規定撤廃の方針とは2024.08.08 (Thu)
- 第58回 Googleが動画作成ツール「Google Vids」をテスト開始。どんなツール?2024.08.08 (Thu)
- 第59回 「パーソナルAI」が、ビジネスを代行する時代が来ている2024.08.13 (Tue)
- 第60回 多言語対応や旅行プラン作成も!観光業での生成AI活用法2024.08.13 (Tue)
- 第61回 GoogleもMicrosoftも参入。「生成AI検索」は何が凄いのか2024.09.24 (Tue)
- 第62回 Googleの生成AI「Gemini」は、ChatGPTと何が違うのか?2024.09.24 (Tue)
- 第63回 DX人材は生成AIにどう向き合うべきか?経産省がデジタルスキル標準を改訂2024.10.08 (Tue)
- 第64回 能登半島地震で被害を受けた通信インフラはどのように回復したのか?2024.10.08 (Tue)
- 第65回 政府が世界から誘客する「デジタルノマド」とはどんな人たち?2024.10.08 (Tue)
- 第66回 まずは何から"生成"する?総務省が生成AIの入門書を発表2024.10.08 (Tue)
- 第67回 Web会議の新たなパートナー。耳を塞がないヘッドホンが登場2024.10.08 (Tue)
- 第68回 行政こそ生成AIが効く!都城市に「自治体DX」の進め方を聞く2024.10.09 (Wed)
- 第69回 なぜコープさっぽろは、AIに"人間らしい"要素を求めたのか2024.10.09 (Wed)
- 第70回 Officeの買い切り版が新発売。サブスク版とは何が違うのか?2024.11.21 (Thu)
- 第71回 携帯電話の番号に「060」が開放された理由とは2024.11.21 (Thu)
- 第72回 自動車内でWi-Fiが使い放題のサービスが登場2024.11.22 (Fri)
- 第73回 根拠を元に回答を生成「Perplexity」(パープレキシティ)の魅力2024.11.22 (Fri)
- 第74回 Wi-Fiの電波が1km先まで届く!?「Wi-Fi HaLow」とは2024.11.22 (Fri)
- 第75回 誤差はセンチメートル級。衛星測位システム「みちびき」が導く未来2024.12.20 (Fri)
- 第76回 市場拡大中!AIで進化する音声認識技術の今2024.12.24 (Tue)
- 第77回 ブランドイメージ向上に効果あり。「香りマーケティング」の今2024.12.24 (Tue)
- 第78回 図表を自動で作成する生成AI「Napkin.ai」が登場2024.12.27 (Fri)
- 第79回 Googleの新ルール「サイト評判の不正使用」とは何か?2024.12.27 (Fri)
- 第80回 水道の老朽化が進行中......解決のカギはAIにあり2024.12.27 (Fri)
- 第81回 ユーハイムの「バウムクーヘン専用AIオーブン」に込められた思いとは2025.01.21 (Tue)
- 第82回 山形の小さな町が、デジタル住民票を発行。西川町が進める自治体DXとは2025.01.21 (Tue)
- 第83回 コインランドリーはIoTでより便利になる!「スマートランドリー」の可能性2025.01.21 (Tue)
- 第84回 物流の仕組みを変える「フィジカルインターネット」とは2025.01.30 (Thu)
- 第85回 新SNS「ブルースカイ」はX(旧Twitter)と何が違うのか2025.03.27 (Thu)
- 第86回 鉄道会社から百貨店まで。なぜ異業種が銀行サービスを始めるのか2025.03.27 (Thu)
- 第87回 黒字転換に成功し、Googleとの提携も発表。「note」好調の理由2025.03.27 (Thu)
- 第88回 富士山の裾野に今秋誕生。トヨタの実験都市「ウーブン・シティ」とは2025.03.27 (Thu)