
【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり
NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。
地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。
まちづくりのヒント(第30回)
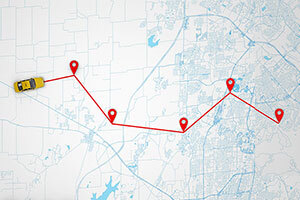
高齢化や人口減少が進む地域では、住民の移動手段の確保が大きな課題となっています。従来の路線バスは採算が取れずに縮小されるケースが多く、公共交通の維持が難しくなっています。特に高齢者や免許を返納した人にとって、生活圏内での移動手段の確保は日常生活の質を維持するうえで欠かせません。
そのため、こうした背景から、住民の需要に応じて運行するデマンド交通が注目されています。タクシーや小型バスを活用し、事前予約やオンデマンド配車によって運行するこの仕組みは、住民の移動を支え、地域の交通手段を補完する役割を果たしています。バスだけでなくタクシーにおいても、複数の人による乗り合い方式を採用しているケースも多く、地域によって多様な運行方法が存在しています。
もちろん、デマンド交通は導入すれば必ず成功するわけではなく、そこには課題もあります。デマンド交通方式を採用しても運営にコストがかかることに変わりありませんので、利用者が定着しなければ自治体の財源を圧迫し、継続は困難になります。
特に、コミュニティバスの利用減少を理由にデマンド交通へ移行した自治体では、かえって利用者が減った事例もあります。そこには、高齢者が予約の手間を負担に感じたり、「デマンド」という名称が利用者に伝わりにくかったりすることが考えられます。
そのため、安定した利用率を維持するには、住民に周知し、「わかりやすく」「便利で使いやすい」と感じてもらわなければなりません。持続可能な運営を実現するには、採算性を確保しながら利用者のニーズを的確に把握し、適切な施策を講じることが求められます。
デマンド交通のコストの問題を解消するには、利用者を定着させて収益を増やすことと運行や業務の効率化を図り、コストを削減するという2つの面で対策が必要です。多くの自治体では、利用者の増加を促す施策や、効率的な運行を実現するための工夫を重ねており、実際に行われているいくつかの方法を紹介します。ひ
新たに整備したデマンド交通を住民に利用してもらうために、多くの自治体では広報活動を強化しています。利用してもらいやすいように割引券・無料クーポンの配布などを通じて利用促進を行う場合もあります。また、利用者の多くを占める高齢者へのアプローチとして、自治会や老人会を通じた広報活動も有効です。
さらに、デマンド交通は自治体が整備するものではありつつも、住民に「自分ごと」として考えもらうことも重要です。例えば住民が運行のアイデアを出したり、利用促進のための活動に関与したりなど、「住民参加型」の仕組みを取り入れると、地域に根付いた持続可能な交通システムへと発展させることができます。
岐阜県輪之内町では、デマンドバスの利用促進と持続可能な運営のため、データ活用や広報活動を強化しています。ログデータを活用して利用状況を分析し、需要の取りこぼしを最小限に抑えるとともに、住民の声を反映し、朝夕の路線延伸や便数の増加を迅速に実施しました。その結果、定期路線の利用者が増加し、デマンドバスの活用も安定していると言います。
また、広報・PR活動を定期的に行い、自治会や地域イベントを通じた周知のほか、高齢者向けの回数券の半額助成などの施策を導入しました。さらに、「良いサービスも営業なしでは利用されない」との考えから、職員が積極的に住民にサービスを紹介するなど、利用定着に向けた取り組みを進めています。
参考:輪之内町地域公共交通計画
https://town.wanouchi.gifu.jp/wp-content/uploads/77dc5c579965e66931a594b218d3c91a.pdf
デマンド交通は需要に応じた運行のために無駄を削減できることがメリットですが、一人の利用ばかりに配車されてしまえば、それも非効率的な運行になります。そのため、一度の配車でいかに複数の人に乗り合ってもらえるかが重要です。しかし、実際には1便あたりの平均利用者が1人程度にとどまり、非効率な運行となっているデマンド交通が多という実態があります。
乗り合いの促進には、利用者の行動パターンを考慮した工夫が必要です。乗合タクシーの事例では、運行時間やエリアをある程度固定し、需要を集約することで効率化を図っています。また、デマンド交通はオンデマンドという特性上、ダイヤ設定がない場合が多いですが、ある程度運行時間の目安を設けることで、「その時間に来るなら乗ろう」という動機づけにつながり、利用の安定化が期待できます。
また、乗合率を高めるには乗り合いによって利用者にメリットをもたせるという方法もあります。例えば、あわら市の乗り合いタクシーでは、複数人で乗車した際に1人乗車のときよりも運賃を割り引くことで、複数の人が示し合わせてタクシーを利用しやすくなるようにしています。
一方で、デマンド交通には、予約が増えると運行便数が増加し経費が急激に膨らむという課題もあります。さらに、配車待ち時間が延びて予約が取りづらくなるなど、利用者にとっての不便さも生じます。そのため、一定の利用増加が見込まれる場合は、逆に定時運行の路線バスへの切り替えも検討する必要があります。
デマンド交通を持続可能にするには、利用者が使いやすい環境を整え、乗り合いを促進する運用の工夫を取り入れるとともに、コストとのバランスを慎重に管理することが重要です。
デマンド交通の効率的な運営には、デジタル技術の活用が重要な役割を果たします。近年では、AIを活用した運行ルートやスケジュールの最適化技術が登場し、予約受付や配車業務の負担軽減が可能になっています。適切なデマンド交通向けシステムを導入することで、オペレーターの業務を効率化し、よりスムーズな運行を実現できます。
また、利用者向けには、スマートフォンアプリを活用し、予約の手続きを簡素化するなど利便性を向上させる取り組みも進んでいます。アプリを通じてリアルタイムで車両の位置や運行状況を確認できる機能もあるため、利用者の不安を軽減し、利用促進につなげることができます。
利用データを蓄積・可視化・分析できるのもデジタル技術のメリットです。利用者の動向を把握し、新たな計画の立案から運行の調整、改善までのサイクルを継続的に回すことで、より持続可能な運営につなげることができます。
デマンド交通の運営には、デジタル技術を活用したシステム(IT活用型)と、タクシー無線などを用いた手動の配車管理(非IT型)の選択肢があります。どちらを採用するかは、地域の特性や利用者数、運営体制によって異なります。
利用者が多く配車や運行管理の業務量が多い場合は、IT活用型の運営によって効率化が期待できます。特に、利用状況のデータを詳細に分析し、運行ダイヤや曜日の見直しを行うことでより最適なサービス提供が可能になります。一方、需要や登録者数が少ない場合は、ITシステムの導入によるメリットは限定的です。そのような場合は、タクシー無線などを活用した手動の配車管理といった非IT型のほうが運営コストを抑えつつ柔軟に対応できる可能性があります。
システムを導入するのには、ある程度の費用がかかります。そのため、利用者数や登録者数が十分でない場合、コストが負担となる可能性があります。逆に、利用者が多くサービスが安定している地域では、システム導入により業務の効率化とサービス向上が期待できるでしょう。ただし、導入前に費用対効果を慎重に見極めることが重要です。
以上のように、昨今従来型の方式に変わって有効とされるデマンド交通であっても運営のためには自治体側の工夫が欠かせません。住民のニーズや意見を引き出し積極的に関与してもらい、逆に自治体側からは継続的な広報強化の取り組みが必要です。
運行の効率化の観点では、乗り合い率を高めたりデジタル技術を活用して業務の効率化を行ったりする取り組みが必要です。もちろん、運行の方式や必要なデジタル技術は各自治体によって異なるため、慎重な検討が必要です。
デマンド交通は単なる移動手段ではなく、地域の暮らしを支える大切なインフラです。地域に根ざした持続可能な交通モデルを築くために、課題を1つずつ解決し、より多くの住民が安心して利用できる仕組みを整えていきましょう。

【地域交通】地域のパートナーとしてそのまち”ならでは”のまちづくり
NTTグループでは地域循環型社会の実現に向けてグループの総力を結集し、分野横断型で地域の価値を創造し、持続可能なまちづくりを推進しています。
地域交通のソリューションやお役立ち情報などを紹介しています。
資料ダウンロード
さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。