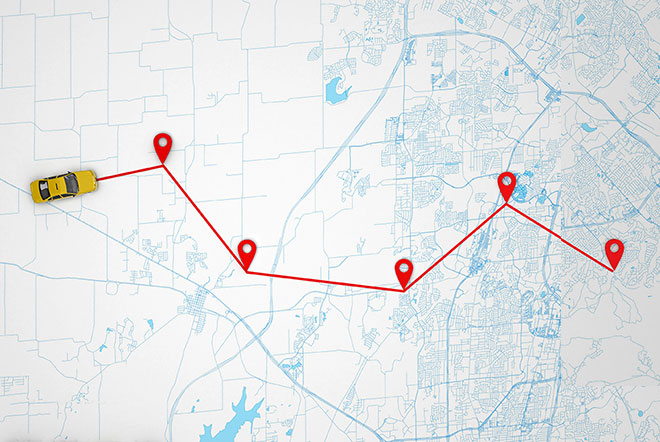2021.02.19 (Fri)
テクノロジーでビジネスの現場が変わる!(第7回)
東大廣瀬教授が語る「本気のVRが企業教育を変える」
VRは技術継承の切り札になれるのか。VRが企業内での教育や訓練にもたらす可能性について、東京大学の廣瀬通孝名誉教授に話を伺いました。

<目次>
クレーム対応も爆発火災対応もVRで訓練
VRなら「人の体を借りられる」
サッカー協会が求めていたVRは「サッカー」ではない?
企業のバーチャルに対する本気度は高まっている
外出なしでも「徒歩6000歩相当」の効果を得られるか
クレーム対応も爆発火災対応もVRで訓練
コロナ禍では移動や出勤などさまざまな制約が課されることになり、企業にとっては社員への教育・訓練の実施が難しくなってきました。そこで注目を集めているのが「バーチャルリアリティ(VR)」です。
VRはコンピュータモデルとシミュレーション技術を用いて人工的に作られたデジタル空間を現実であるかのように疑似体験させる技術です。代表的な例としてヘッドマウントディスプレイを装着して仮想空間を覗き込む手法が知られています。
1990年代初頭に第1次VRブームが始まり、その後エンターテインメントやゲームの世界を中心に活用され、昨今の第2次VRブームへと至ります。一般の人にとってはVRを業務で利用するというイメージはまだまだ薄いかもしれませんが、そんな中「幅広い産業界へ応用できる」と考えているのが、日本におけるVR研究の先駆者の1人として知られる東京大学大学院 廣瀬通孝名誉教授です。
「第1次のブームでは、VR自体の研究開発である『For VR』が中心でしたが、現在は『VRを使って何ができるか』という応用志向、つまり『by VR』の研究開発が進んでいます。その中で有望なのが教育・訓練分野への応用。エンターテインメントやゲームに代表されるように、VRの最大の特長は『疑似体験』です。そこに着目したとき、業務を疑似体験できるVRは、各企業の日頃の教育はもとより技術やノウハウを継承していく用途に最適なのです」(廣瀬教授)
実際に、社内教育の例として廣瀬教授が紹介したのはサービス産業での接客応対です。「サービスVRシミュレーターで、例えばお辞儀の仕方やお客様の目を見て話す方法を訓練したり、お客様からのクレームを含むさまざまな要求に対して適切な手法を模索したりと、おもてなしや接客業務にVRを使おうと検討する企業が出てきています。東京大学も多くの企業と連携しており、接客対応VRに関してはすでに検証が進んでいます」(廣瀬教授)
廣瀬教授がもう1つ紹介したのは、消防士の訓練への活用です。
「最近は都市の強靭化によって大きな火災が減少傾向にあります。それはそれで良いことなのですが、新人消防士のOJT(On-the-Job Training)の機会が減ってしまい、突然の大規模火災に新人がうまく対応できないことが心配されています。そこで、どのような状況であればその場にとどまり消火を続けていいのか、煙がどういった状態になると危険なのか、急激な爆発はどのような瞬間に起こるのかといった火災現象をVRシミュレーターで再現し、訓練できるようなシステムを消防の方々と一緒に開発しています」(廣瀬教授)
VRなら「人の体を借りられる」
廣瀬教授は、コストの観点からもVRを活用するメリットは大きいといいます。
「航空会社では昔からフライトシミュレーターを使ってきました。異常事態の体験ができますし、失敗した場合もその状況を再現して見直すことも可能です。ただし最大の欠点は非常に高価だということ。そこでより安価なVRが使えないかと研究中です。これが実現すれば、パイロットだけでなく客室乗務員の訓練も可能になるなど、適用範囲が格段に広がります。航空会社以外のサービス会社全般での訓練にも活用できるようになるでしょう」(廣瀬教授)
技術継承におけるVRのメリットは単なる「疑似体験」にとどまりません。廣瀬教授はその利点として「人の体を借りられること」を挙げます。

東京大学
名誉教授
廣瀬 通孝氏
「例えば、訓練機でパイロットを訓練する際に、訓練生が下手な動きをすると隣に座っている教官が代わりに操縦を行います。このとき訓練生は、まるで自分が正しく操縦しているような感覚を体験できるでしょう。これを自分の体のレベルでも行えるだろうというのが『融合身体』の基本的な考え方です。こうすることで細やかな身のこなしが要求されるような作業の訓練が、より高いレベルで可能となると期待しています。まさにVRならではの訓練でリアルを超えた体験が実現するのです」(廣瀬教授)
サッカー協会が求めていたVRは「サッカー」ではない?
もっとも、VRでは再現できないものも数多く存在すると廣瀬教授は指摘します。
「例えば医療とVRは親和性が高い領域だといわれますが、物理的な接触を必要とする開腹手術はまた別の話です。医療用シミュレーターも、実際の力覚を正確に再現することは難しく、同様に味覚の再現ができない調理VRもまだまだ普及が困難だといえます。スポーツシミュレーターであっても、実際のスポーツのように全力疾走を体験する仕組みは難しいでしょう」(廣瀬教授)
こうした技術的な再現性は課題の1つです。しかし、実は現場における課題の本質は、技術者が考える問題ではないケースもあります。
「サッカー協会がシミュレーターに興味を持っていると聞き依頼を受けましたが、最初はVRでは実際にコートを走り回るような体験ができないため、開発するのは相当大変だと私は感じていました。ところが、サッカー協会が求めていたのはサッカーを体験するシミュレーターではなく、『背丈の大きな外国人に囲まれる状況を体験できるVR』だったのです。U18の日本代表の中には海外旅行未経験の選手も多く、“試合で体格の大きい外国人選手にいきなり囲まれると、それだけで萎縮してしまうのではないか”ということをサッカー協会は懸念していました。VRでそのような状況を体験しておくだけでも海外に行くハードルが下がるのではないかと考えたそうです」(廣瀬教授)
廣瀬教授は、これは他の分野にもいえることだといいます。
「例えば、接客力を強化したいと考えるコンビニエンスストアに接客シミュレーターを導入するとします。この場合、確かに対面での接客力は訓練できます。しかし、実際の接客では店内にいる目の届かない他のお客様のことも考えながら接客しなければなりません。目の前のお客様だけに集中し、他のお客様の存在に気づかず接客できないということが問題になってしまうケースがあるのです。これでは、いくら接客方法を学んでも根本的な問題解決にはつながりません。そういった現実での課題と研究者が考えている課題とのギャップを埋めることも重要です」(廣瀬教授)
企業のバーチャルに対する本気度は高まっている
このように技術継承や教育・訓練という場面でVRの活躍が期待されています。さらにこの状況に拍車をかけるように2020年は新型コロナウイルスの感染拡大がきっかけとなり、VRをはじめとするさまざまな技術産業が大きく変化しました。これまでのロードマップが崩れ、5~10年後の完成を目指していた技術を前倒しで開発する動きも見られます。
「コロナ禍を受けて、VRに対する企業の本気度や期待が大きくなってきました。以前は社外へのアピールの一環としてVR分野を企業の広報的な感覚で手掛けていた企業も、今では本業であるリアルビジネスが成り立たなくなった際に、どうバーチャルビジネスを成り立たせるか議論するようになりました。これは技術の進歩が要因ではなく、人の意識が変わったためです」(廣瀬教授)
また、不確実性が高まったコロナ禍において、よりビジネスを成長させている企業もあります。
「VRと同じように『体験を生成する』という観点から言うと、物質的なものではなくデジタルを通した体験を提供するGAFAのような企業は、拡大解釈するとVRの世界に存在する企業です。だからこそコロナ禍でも業績が好調なのです。ビジネスにVRを取り入れるのではなく、すべてをVRに移行してしまってもいいと思います。コロナ禍を救う特効薬はVRしかないといっても過言ではありません」(廣瀬教授)
外出なしでも「徒歩6000歩相当」の効果を得られるか
このように、VRのニーズが拡大していく一方、新たに登場する技術をいかに活用できるかが今後の発展にポイントになると廣瀬教授はいいます。
「これから5Gといった低遅延・大容量の通信環境が整備されるにあたり、VRの技術はより身近なものになるでしょう。もちろん、技術は道具でしかなく、普及にはその技術を使って何ができるかが重要となります。これからはコンテンツの時代です。社会の需要を探り、その需要に対して5Gなどの新たな技術がVRと組み合わさり、コンテンツにどのようなメリットをもたらすのかを考えていく必要があります」(廣瀬教授)
今後の取り組みについて廣瀬教授は以下のように述べます。
「東京大学の先端科学技術研究センター(先端研)が大手自動車部品メーカーのデンソーの支援を受けて社会連携講座『モビリティゼロ』をスタートさせました。移動することの本質は何なのかを、将来的に移動がゼロとなった場合まで含めて再定義し、新しい技術を開発していこうというものです。交通、運輸、自動車といった移動手段、つまりモビリティをゼロから考え直そうというプロジェクトです。モビリティゼロは、2050年に現実となる新しい社会を想定したものです。人が外出して出歩く必要もなくなるという選択肢も考えようという長期的な取り組みだったのですが、コロナ禍で急速に社会が変わり、すぐにでも取り組むべきテーマになりました」(廣瀬教授)
究極的には「体を動かす」という行為自体の代替手段を考える必要もあります。
「出歩く必要がなくなったとしても、動くことは人間の本質です。脳の活性化のために外に出て動き回り、1日6000歩は歩くべきだといわれますが、コロナ禍ではなかなか達成できません。それをVRによる刺激で補おうという研究も始めました。もちろん、エコノミー症候群のように医学的な問題は、実際に体を動かさなければ防げません。ただ、“歩く”という意味の中には、コミュニケーションや脳の活性化など、情報的側面も多く、VRで置き換えられる機能もあるはずなのです」(廣瀬教授)
廣瀬教授はVRが持つ無限の可能性に期待を寄せており、自身もその一端を担えるよう研究開発に取り組んでいきたいと意気込んでいます。
「現在のVRはまだまだ発展途上にあります。しかし、ニューノーマルの社会に変わろうとしている今、バーチャルとリアルな世界をつなぐVRに大きな転換期が訪れています。VRも『恐竜型VR』から『哺乳類型VR』へと進化するわけです。自宅にいながらにして外出しているような状況を作り出し、時には瞬時に海外にも出かけて刺激を受けられることは、今後の社会の到達点ともいえるのではないでしょうか」(廣瀬教授)
<インタビュイープロフィール>
廣瀬 通孝(ひろせ みちたか)
東京大学名誉教授。同大学工学部専任講師、助教授、同大学の先端科学技術研究センター(先端研)教授兼情報理工学系研究科教授を経て、現在の同大学先端研サービスVRプロジェクトリーダーに至る。VR技術をはじめ、マルチモーダルインターフェース研究、複合現実感・ウェアラブルコンピュータ研究などの研究・開発を行う。
© 2021 NTTCom Online Marketing Solutions Corporation
連載記事一覧
- 第1回 出張が不要になる?新技術「ホロポーテーション」 2016.07.15 (Fri)
- 第2回 AIがオフィスの空気を管理すれば生産性は上がる? 2016.08.29 (Mon)
- 第3回 目は口ほどにものを言う、「感情認識」の新ビジネス 2016.09.28 (Wed)
- 第4回 仕事中の危険を未然に防ぐ「バイタルデータ」とは 2016.10.14 (Fri)
- 第5回 社会インフラを激変させる可能性を秘めた仮想通貨 2017.10.03 (Tue)
- 第6回 企業が仮想通貨で資金調達する時代は到来するか? 2018.03.26 (Mon)
- 第7回 東大廣瀬教授が語る「本気のVRが企業教育を変える」 2021.02.19 (Fri)
- 第8回 建設業界で注目のDX「デジタルツイン」とは 2021.09.14 (Tue)
- 第9回 中小企業こそDXに向く。町工場・今野製作所の挑戦 2021.12.10 (Fri)
- 第10回 小売業の広告販促DX「リテールメディア」の始め方 2021.12.10 (Fri)
- 第11回 「小売業再建のプロ」が語る、利益率UPのヒント 2022.03.01 (Tue)
- 第12回 年4億円コスト削減を達成した地方製造業のIoT活用術 2022.03.04 (Fri)
- 第13回 「幻の日本酒」が安定供給できた裏にデータ活用あり 2022.06.27 (Mon)
- 第14回 いまどきの企業PRに不可欠、Twitterスペースとはなにか 2022.11.15 (Tue)
- 第15回 雇用確保につながる可能性も、覚えておきたい「給与のデジタル払い」2022.12.21 (Wed)
- 第16回 なぜ世界の小売店が「リテールメディア」に参入しているのか?2023.03.06 (Mon)
- 第17回 経済効果は2兆円!女性の悩みを解決するフェムテックとは2023.03.06 (Mon)
- 第18回 バブル期京都でDX実現! 24時間稼働の無人工場2023.03.15 (Wed)
- 第19回 どうする「2024年問題」物流DXの課題と事例2023.03.30 (Thu)
- 第20回 なぜ企業や自治体が「VTuber」を起用するのか? 2023.03.30 (Thu)
- 第21回 未来を予測し先手を打つ。「AI需要予測」の活用術2023.03.30 (Thu)
- 第22回 顧客の本音を読み解く「センチメント分析」の活用法2023.03.30 (Thu)
- 第23回 「気象ビッグデータ」が売上増とロス削減に貢献する2023.03.30 (Thu)
- 第24回 消費者から信頼感を得るには、トレーサビリティ向上が不可欠2023.04.28 (Fri)
- 第25回 健康のDX「パーソナライズド・ニュートリション」2023.09.08 (Fri)
- 第26回 「Web3」がもたらすビジネスや社会への影響とは2023.09.08 (Fri)
- 第27回 「観光DX」は日本の観光業をどう変えるのか?2023.10.04 (Wed)
- 第28回 大手企業も導入「リーガルテック」で何が変わる?2023.10.04 (Wed)
- 第29回 情報漏えいの原因を解析「デジタルフォレンジック」2023.10.04 (Wed)
- 第30回 関東大震災から百年、災害対策はどう進化したのか?2023.10.04 (Wed)
- 第31回 ITに疎くてもDXはできる!老舗食品企業の挑戦2023.11.22 (Wed)
- 第32回 極地でも高速通信「スターリンク」の可能性2023.12.21 (Thu)
- 第33回 インフラの「老朽化」は、最新技術でメンテナンスできる2024.01.24 (Wed)
- 第34回 新たな個人データ収集方法「ゼロパーティデータ」とは2024.01.24 (Wed)
- 第35回 2024年4月から限定解禁「ライドシェア」の可能性2024.01.24 (Wed)
- 第36回 AIが奪うのは仕事ではなく電力?生成AIのエネルギー事情2024.02.09 (Fri)
- 第37回 トークン経済で市場に好循環は起こるのか?2024.03.01 (Fri)
- 第44回 バス運行を効率化「AIオンデマンド交通」の可能性2024.03.29 (Fri)
- 第45回 生成AIとの対話が成長を促す「AIコーチング」2024.03.29 (Fri)
- 第46回 広告に続々登場「AIタレント」の弱点とは2024.03.29 (Fri)
- 第47回 訪日客が日本のファンになる鍵は「AI」にあり2024.03.29 (Fri)
- 第48回 脳と機械が繋がる「ブレインテック」の可能性2024.03.29 (Fri)
- 第49回 打ち上げが本格化。民間企業の宇宙ビジネスの今2024.03.29 (Fri)
- 第50回 バイヤーもサプライヤーも歓迎!?「自動交渉AI」2024.03.29 (Fri)
- 第51回 医療・建設業界で導入が進む「自律型ロボット」とは2024.03.29 (Fri)
- 第42回 6G、7Gで世界はどう変わるのか?「Beyond 5G」の可能性2024.03.22 (Fri)
- 第43回 脱炭素の効果はブロックチェーンで証明できる2024.03.29 (Fri)
- 第38回 総務省が認可「Wi-Fi 7」とは何か?2024.03.29 (Fri)
- 第39回 総務省が発表「モバイル市場競争促進プラン」とは?2024.03.29 (Fri)
- 第39回 インボイスにも対応「IT導入補助金2024」を解説2024.03.29 (Fri)
- 第40回 文章生成AIの理想的な使用法とは?東京都がガイドラインを公開2024.03.29 (Fri)
- 第41回 新たなテクノロジー「光の半導体」とは何か?2024.03.29 (Fri)
- 第52回 訪日観光客が増えるとトラブルも増える!?オーバーツーリズムをどう解決するか2024.05.22 (Wed)
- 第53回 ウェブアクセシビリティが義務化。どう対処する?2024.07.11 (Thu)
- 第54回 決済時間を1/2に短縮「タッチ決済」が普及中2024.07.12 (Fri)
- 第55回 なぜEUは、生成AIを規制しようとしているのか2024.07.12 (Fri)
- 第56回 2024年10月につくば市でスタート「インターネット投票」とは?2024.08.08 (Thu)
- 第57回 7月実施完了。デジタル庁の「フロッピーディスク」使用規定撤廃の方針とは2024.08.08 (Thu)
- 第58回 Googleが動画作成ツール「Google Vids」をテスト開始。どんなツール?2024.08.08 (Thu)
- 第59回 「パーソナルAI」が、ビジネスを代行する時代が来ている2024.08.13 (Tue)
- 第60回 多言語対応や旅行プラン作成も!観光業での生成AI活用法2024.08.13 (Tue)
- 第61回 GoogleもMicrosoftも参入。「生成AI検索」は何が凄いのか2024.09.24 (Tue)
- 第62回 Googleの生成AI「Gemini」は、ChatGPTと何が違うのか?2024.09.24 (Tue)
- 第63回 DX人材は生成AIにどう向き合うべきか?経産省がデジタルスキル標準を改訂2024.10.08 (Tue)
- 第64回 能登半島地震で被害を受けた通信インフラはどのように回復したのか?2024.10.08 (Tue)
- 第65回 政府が世界から誘客する「デジタルノマド」とはどんな人たち?2024.10.08 (Tue)
- 第66回 まずは何から"生成"する?総務省が生成AIの入門書を発表2024.10.08 (Tue)
- 第67回 Web会議の新たなパートナー。耳を塞がないヘッドホンが登場2024.10.08 (Tue)
- 第68回 行政こそ生成AIが効く!都城市に「自治体DX」の進め方を聞く2024.10.09 (Wed)
- 第69回 なぜコープさっぽろは、AIに"人間らしい"要素を求めたのか2024.10.09 (Wed)
- 第70回 Officeの買い切り版が新発売。サブスク版とは何が違うのか?2024.11.21 (Thu)
- 第71回 携帯電話の番号に「060」が開放された理由とは2024.11.21 (Thu)
- 第72回 自動車内でWi-Fiが使い放題のサービスが登場2024.11.22 (Fri)
- 第73回 根拠を元に回答を生成「Perplexity」(パープレキシティ)の魅力2024.11.22 (Fri)
- 第74回 Wi-Fiの電波が1km先まで届く!?「Wi-Fi HaLow」とは2024.11.22 (Fri)
- 第75回 誤差はセンチメートル級。衛星測位システム「みちびき」が導く未来2024.12.20 (Fri)
- 第76回 市場拡大中!AIで進化する音声認識技術の今2024.12.24 (Tue)
- 第77回 ブランドイメージ向上に効果あり。「香りマーケティング」の今2024.12.24 (Tue)
- 第78回 図表を自動で作成する生成AI「Napkin.ai」が登場2024.12.27 (Fri)
- 第79回 Googleの新ルール「サイト評判の不正使用」とは何か?2024.12.27 (Fri)
- 第80回 水道の老朽化が進行中......解決のカギはAIにあり2024.12.27 (Fri)
- 第81回 ユーハイムの「バウムクーヘン専用AIオーブン」に込められた思いとは2025.01.21 (Tue)
- 第82回 山形の小さな町が、デジタル住民票を発行。西川町が進める自治体DXとは2025.01.21 (Tue)
- 第83回 コインランドリーはIoTでより便利になる!「スマートランドリー」の可能性2025.01.21 (Tue)
- 第84回 物流の仕組みを変える「フィジカルインターネット」とは2025.01.30 (Thu)
- 第85回 新SNS「ブルースカイ」はX(旧Twitter)と何が違うのか2025.03.27 (Thu)
- 第86回 鉄道会社から百貨店まで。なぜ異業種が銀行サービスを始めるのか2025.03.27 (Thu)
- 第87回 黒字転換に成功し、Googleとの提携も発表。「note」好調の理由2025.03.27 (Thu)
- 第88回 富士山の裾野に今秋誕生。トヨタの実験都市「ウーブン・シティ」とは2025.03.27 (Thu)