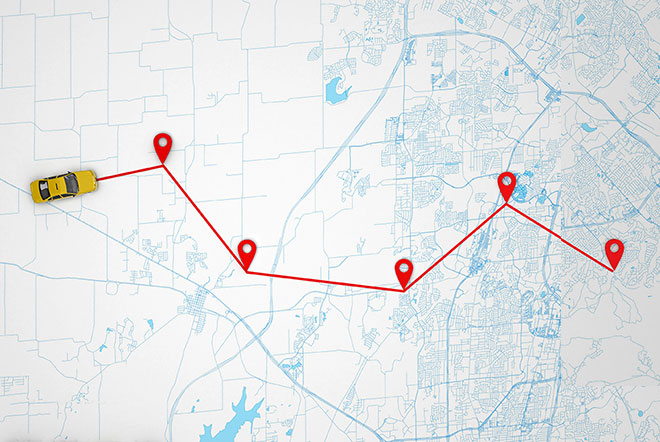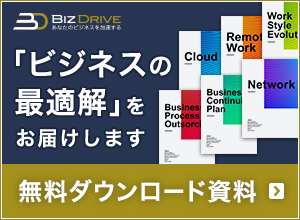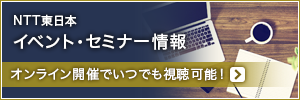2023.01.30 (Mon)
理想的な会社の在り方とは(第30回)
国内企業も続々実施、企業の長期的な成長に必要なSXとは

SDGsの達成やカーボンニュートラルの実現に向けて企業の意識変革が進む中で、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)が注目されています。本記事では、SXが提唱された背景やSXの概要、SXを推進するためのポイント、企業のSX事例などをご紹介します。
企業と社会のサステナビリティを同期化させることが必要
近年は、テクノロジーの発達にともない新たなビジネスモデルが続々と生まれています。一方で、気候変動、コロナ禍、紛争、エネルギー問題などが重なって、ビジネスの不確実性が増していることから、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)の時代とも言われています。さらに、SDGsの達成やカーボンニュートラルの実現など、世界全体で取り組まなければならない課題も存在します。このような時代を生き抜くため、企業に対しては利益追求だけでなく、ESG(環境・社会・ガバナンス)の視点をもちつつ、長期的な視点で事業に取り組むことが求められています。こうした状況を背景に、SXが注目を集めています。
SXとは、企業が「稼ぐ力」とESGの両立を図るため、経営の在り方や、投資家との対話の在り方を変革するための戦略指針です。経済産業省が2020年8月に中間取りまとめを行った「サステナブルな企業価値創造に向けた対話の実質化検討会」の報告書の中ではSXが示されており、問題解決の方向性についても述べられています。
SXの推進に必要な3つのポイントとは
前述の報告書の中で、SXを推進するために次の3つのポイントを示しています。
1点目は、自社の強みやビジネスモデルを中長期で持続化・強化し、事業ポートフォリオ・マネジメントやイノベーションなどに対する種まきなどの取り組みを通じて、企業のサステナビリティを高めていくことです。
2点目は、不確実性に備えて、社会のサステナビリティをバックキャスティング(あるべき未来を描き、そこから逆算して現在行うべき活動やその優先順位を決める思考方法)し、企業の稼ぐ力の持続性・成長性に対する中長期リスクとオポチュニティ(事業機会)双方を把握して具体的な経営に反映させていくことです。
3点目は、不確実性が高まる中で企業のサステナビリティを高めていくために、将来に対してのシナリオ変更がありうることを念頭に置き、企業が投資家と共同して中長期的な価値創造ストーリーを磨き上げ、企業経営のレジリエンス(適応力)を高めていくことです。
そして、企業経営のレジリエンス強化に欠かせないのが、米カリフォルニア大学バークリー校ハース・ビジネススクールのデイヴィッド・J・ティース氏が提唱した戦略経営論である「ダイナミック・ケイパビリティ(企業変革力)」です。ダイナミック・ケイパビリティには次の3つの力が求められます。
・感知(センシング):脅威や危機を感知する能力
・捕捉(シージング):機会をとらえ、既存の資産・知識・技術を再構成して競争力を獲得する能力
・変容(トランスフォーミング):競争力を持続的なものにするために、組織全体を刷新し、変容する能力
これら3つの力を獲得するためには、DX(デジタル・トランスフォーメーション)が必要です。企業のSXは、DXが前提となると言っても過言ではないでしょう。
さまざまな事業領域でSXが進んでいる
国内外でSXに取り組む企業はすでに現れています。ある一般消費財メーカーは、消費者が持参した容器に洗剤を充填できる機器を開発。プラスチック容器を削減しながら、自社の製品を購入してもらうようにしました。
また、傘のシェアリングサービスを展開する企業は、使い捨て傘をできるだけ減らす取り組みを進めて、各地に傘スポットを設置。スマートフォンアプリで傘を低コストで利用できるようにして、環境負荷の低減を図りました。
ほかにも、ある流通小売企業は、オリジナル商品で使用する容器包装を2030年までに50%、2050年までに100%、環境配慮型素材にすることを目標にしています。同企業の店舗では、生鮮食品などの量り売りなど販売方法を工夫するなど、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。
いまや企業にとってSXは「やったほうがいいもの」ではなく、「やらねばならないもの」になっています。不確実性が増す時代のなかで企業が長期的に成長していくには、SXを推進して企業と社会のサステナビリティを同期化させることが必要なのです。
連載記事一覧
- 第31回 先進企業に見る、男性育休取得の3つのメリット2023.03.06 (Mon)
- 第32回 Z世代の知見生かす「リバースメンタリング」の効果2023.05.30 (Tue)
- 第33回 DE&I推進がもたらす、イノベーション創出と人材確保2023.06.13 (Tue)
- 第34回 米国では標準化。セキュリティの新たな考え方「SBOM」2023.09.08 (Fri)
- 第35回 増える「ビジネスケアラー」介護離職を防ぐカギは2023.10.04 (Wed)
- 第36回 10月から開始「ステマ規制」で何がNGになるのか?2023.10.04 (Wed)
- 第37回 高齢化社会がさらに進行「2025年問題」に打つ手はあるか?2023.12.21 (Thu)
- 第38回 契約社員が多い企業は要注意。「労働条件明示」の新ルールがスタート2023.12.21 (Thu)
- 第39回 2024年秋施行「フリーランス新法」で遵守すべきこと2023.12.21 (Thu)
- 第40回 非正規労働者の正社員化をサポートする助成金が拡充2024.01.17 (Wed)
- 第41回 2024年12月アナログ無線機が使用不可に!電波法改正のポイント2024.01.24 (Wed)
- 第42回 協業でもコラボでもない「コレクティブインパクト」の可能性2024.03.01 (Fri)
- 第43回 自然を軽視する企業は評価されない?「TNFD」の考え方2024.03.01 (Fri)
- 第62回 医師も時間外規制。医療の2024年問題の解決法とは2024.03.29 (Fri)
- 第57回 DX加速のカギ「リスキリング」を進めるヒント2024.03.29 (Fri)
- 第56回 ビジネスは「逆算」で考える。リーン・マネジメントとは2024.03.29 (Fri)
- 第58回 DXを円滑に推進するためのチームづくりとは?2024.03.29 (Fri)
- 第59回 現場とリモートのいいとこどり。ハイブリットワーク導入のポイント2024.03.29 (Fri)
- 第60回 3年以内に3割退職。Z世代の離職を防ぐ方法とは?2024.03.29 (Fri)
- 第61回 女性活躍の証「くるみん・えるぼし」認定を受けるメリットとは2024.03.29 (Fri)
- 第44回 2023年10月から開始「ステマ規制」で何が禁止されたのか?2024.03.29 (Fri)
- 第45回 「2024年問題」解決のカギは◯◯を省くことにあり2024.03.29 (Fri)
- 第46回 2023年12月からスタート「アルコールチェック義務化」とは?2024.03.29 (Fri)
- 第47回 アルコール摂取は「1日◯g」まで!厚労省がガイドラインを公表2024.03.29 (Fri)
- 第48回 「賃上げ」につながる価格交渉とは?公取委が公開2024.03.29 (Fri)
- 第49回 介護離職が増加中。仕事と介護を両立する方法とは2024.03.29 (Fri)
- 第50回 生成AIで作った文章・画像は、著作権法に違反していないのか?2024.03.29 (Fri)
- 第51回 4割の企業は、従業員のメンタルヘルスを放置している?2024.03.29 (Fri)
- 第52回 花粉症にはテレワークが効く!?2024.03.29 (Fri)
- 第53回 原作改変は法律違反?企業が知っておきたい著作権の話2024.03.29 (Fri)
- 第54回 自社コンテンツが「海賊版」に利用された時の対処法2024.03.29 (Fri)
- 第63回 経営戦略として「介護」を考える。経産省がガイドラインを公開2024.05.22 (Wed)
- 第64回 元従業員こそ優れた人材である。アルムナイ採用の可能性2024.07.11 (Thu)
- 第65回 Googleマップの「星」はコントロールできるのか?2024.07.12 (Fri)
- 第66回 各地で大雨が発生中。企業は水害にどう備えるべきか2024.08.08 (Thu)
- 第67回 大手企業や自治体も続々導入「週休3日」は実際どうなのか?2024.08.08 (Thu)
- 第68回 企業の6割が「DX人材が大幅に不足」。解消法はどこにあるのか2024.09.24 (Tue)
- 第69回 落雷がPCを壊す!?「雷サージ」はどう防げば良いのか2024.09.24 (Tue)
- 第70回 2025年4月施行、育児休業制度の改正ポイントとは?2024.09.24 (Tue)
- 第71回 あの大企業も導入。「ジョブ型人事」は何が優れているのか?2024.10.08 (Tue)
- 第72回 どうすれば「労働者に選ばれる職場」が作れるのか?厚生労働省の資料から読み解く2024.10.08 (Tue)
- 第73回 人手不足解消につながるか。経産省が進める「ニューロダイバーシティ」の可能性2024.10.18 (Fri)
- 第74回 11月1日にフリーランス新法が施行。企業が気をつけるべきこととは2024.10.18 (Fri)
- 第75回 SNSでの誹謗中傷に、企業はどう対策すれば良いのか2024.11.22 (Fri)
- 第76回 子育てはデジタルでどう変わるか?「保育DX」の今2024.12.24 (Tue)
- 第77回 その「No.1」の表示は大丈夫?消費者庁が実態調査2024.12.26 (Thu)
- 第78回 人事を客観的に判断する「ピープルアナリティクス」の可能性2025.01.30 (Thu)
- 第79回 パタハラにご注意!2025年4月より育児・介護休業のルールが改正2025.03.27 (Thu)
- 第30回 国内企業も続々実施、企業の長期的な成長に必要なSXとは2023.01.30 (Mon)