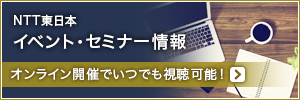各種セミナー情報や、イベント開催のご案内、出展レポートなどをご紹介します。
まちづくりのヒント(第12回)
中野市に聞く、公用車を保有せずリース化するメリットとは?
- 公開日
- 2026-01-28

中野市では、公用車の車両管理における職員の負担やコストの削減のため、令和6年4月に、市で所有する車両の大半をリース会社に売却し、その車両をあらためてリース契約する「リースバック」を行いました。さらに、環境施策の一環として、EV車(電気自動車)4台もリースにて導入しています。
なぜ中野市は、公用車をリース化したのでしょうか? 背景や実現までのプロセスについて、中野市の担当者に伺いました。
-
<導入いただいたソリューション>
・日本カーソリューションズと連携した公用車のリース化支援
<ソリューション導入効果>
・管理体制の合理化により、労務費をコストダウン
・車両管理業務を45項目から6項目まで減少
・業務を削減したことで、予算の管理に関する事務の煩雑さを軽減
・車両管理に関わる職員の人件費を削減
<NTT東日本選定のポイント>
・職員の労力削減やコストダウンなど、公用車管理の課題解消するための最適なサービスの提案
約100台の公用車の管理・整備が手間に
――公用車をリース化することに決めたきっかけを教えてください。
小栗氏:中野市ではもともと約100台の公用車を所持しており、我々が所属する企画財政課でも、特別会計や企業会計で管理する公用車を除く80台ほどを管理していました。これらの車検やタイヤ交換といった整備に関わる発注や支払いはすべて市で行っており、管理のためのコストや、職員の業務負担が課題となっていました。
リース化のきっかけは、車両管理における課題の解決策を考えていた時に、NTT東日本から日本カーソリューションズの「リースバック」の紹介を受けたことです。
リースバックとは、所有している車両をリース会社に売却し、その車両をあらためてリース契約するというものです。リース後も使用中の車両をそのまま利用できる上、所有車両とリース車両が混在することも無いため、車両管理における課題の解消にもつながると考えました。令和6年の4月に公用車75台をリースバックしました。

総務部 企画財政課 管財係 副主幹 小栗裕子氏
――公用車をリース化するにあたって、何か特別な準備をしたのでしょうか?
小栗氏:準備としては、まずは中野市に適した公用車の台数を把握することから始めました。リースバックに先立ち、日本カーソリューションズからGPS機能が付いたデバイスを借り、約100台の公用車に設置し、約2カ月にわたって公用車の運行実績データを収集しました。
その結果、公用車を12台削減しても問題ないことがわかり、リースバックする台数も決めることができました。削減する公用車は、今後の車検のタイミングで順次廃車にしていく予定です。
――中野市のように、公用車のほとんどをリース化するケースは、ほかの自治体でもあるのでしょうか?
小栗氏:公用車のリースはほかの自治体でも行っていると思いますが、中野市のように公用車の大半を一気にリース化するケースは珍しいかもしれません。今回、リースバックに切り替えることができたのは、中野市が庁内で公用車を一括管理していたことも要因の一つではないかと感じています。
中野市では数年前まで、各課で公用車を管理し、空いている車両がなければ他の課にお願いして使用するという方法を取っていました。しかしこれでは、各課で車両を管理するスタッフを置かなければならず、非効率です。
そこで数年前から、特別な車両を除き、一般的な公用車を企画財政課で一括管理する方法に変更しました。現在は所属に関係なく、職員が各自で空いている車両をウェブ上のシステムで予約・申請できるようになっています。

中野市のVTuber・信州なかのが描かれた公用車。車両は1台のみでイベント時の使用が多いが、予約・申請すれば職員たちは自由に乗車することが可能。
「リースバック」で管理の手間を省略。職員への意外な効果も
――公用車をリース化するにあたって、特に苦労したことはありますか?
小栗氏:どのタイミングでリース化するかは悩んだポイントの一つでした。年度末にしようか、車検が少ない時期にしようか、いろいろと考えていましたが、日本カーソリューションズから「年度が切り替わるタイミングでリース化するのが、管理もしやすいのでは」とアドバイスを受けたことで、最終的には4月1日からリース化することを決めました。
リースバックの契約締結後は、もともと所持していた公用車を使用しながら名義変更などの手続きを進めていきました。特にトラブルなく切り替えることができて、今も問題なく車両の管理や利用ができています。
――リース化したことによる効果を教えてください。
小栗氏:リース化により、これまで市で行っていた車両管理業務を45項目から6項目にまで減らすことができました。具体的に削減できた業務としては、車検や整備に関わる発注・支払い、タイヤ交換の業務などです。車検漏れや自賠責保険の失効の防止や、予算に関する事務作業の煩雑さを軽減することにもつながっています。さらに業務が削減されたことで、車両管理に割く人員も2人から1人に減らすことができました。
意外な効果としては、職員たちが「借りている車両」であることを意識して、今まで以上に車両の扱い方に気を遣うようになった点もあります。リースバックによって多少の財政負担はあったものの、それ以上に大きなメリットがあったと考えています。

総務部 企画財政課 政策推進係 主事補 高橋悠氏
カーボンニュートラルを目指しEV車も導入
――公用車の一部をEV(電気自動車)化した経緯についても教えてください。
高橋氏:EV車を導入した背景には、国が掲げる2050年のカーボンニュートラルの実現を狙ったものです。
中野市がリースバック前に所持していた公用車のほとんどがガソリン車で、環境性能の高い車は、ハイブリッド車が2台あるのみでした。中野市内でもまだまだガソリン車が多く走っている印象があり、市民の皆さんへ環境施策の理解を深めてもらうため、公用車にEV車4台を導入し、他の車両と同様にリース化をしました。
――EVは充電が必要です。ガソリン車と比べ、運用に手間取ることはありましたか?
高橋氏:もちろん導入にあたっては、充電場所や充電器の数について考える必要がありました。庁内で検討した結果、常に人の目がある車両事務所の近くに駐車スペースと台数分の充電器を設置することに決めました。
通常の車両と異なる点はこのくらいで、大きなハードルはありませんでした。導入後も特に問題なく、職員たちも他の車両と同じようにEV車を利用しています。
高齢者向けタクシーを検討中。EVの増車も予定
――モビリティの分野において、中野市がこれから取り組もうと考えていることを教えてください。
高橋氏:現在導入を検討しているのが、AIデマンド予約システムを活用した交通施策です。
中野市では、免許を返納する70歳以上の高齢者が年々増えており、移動手段の確保が課題です。現在も、路線バスなどの公共交通がない一部地域に限り電話予約によるタクシー送迎を行っています。そこで、高齢者の方が通院や買い物をする際に利用しやすいよう、ドアツードア型の乗り合いタクシーの導入を検討しています。
現在は、今年度中の実証開始を目指して準備を進めています。市で用意したミニバン型乗用車を使用する予定で、実際にどのくらいのニーズがあるのか、そもそも乗り合い型という形でうまく運用できるのかなどを探っていきたいと思います。加えて、乗り合いタクシーの予約はスマートフォンに限定しているので、そこが障壁にならないかどうかも検証しながら、実現に向けて取り組みを進めていきたいです。
小栗氏:公用車に関しては、今後さらにEV車の台数を増やしていきたいと考えています。駐車場の敷地や充電器の数なども含めて検討していく予定です。
――今後、NTT東日本に期待することを教えてください。
高橋氏:NTT東日本が現在行っている、EV駆動用のバッテリーの残存性能に関する実証実験に期待しています。
EV車の環境性能は高いものの、充電時間や航続距離など、課題があるのも現状です。こうした課題が解消されていけば、中野市の交通・モビリティのEV化もさらに加速していくと考えています。
今後もEV車のデメリット解消、ひいてはEV車の普及につながるような取り組みに期待したいと思います。
-
<組織名>
長野県中野市<概要>
長野県の北東部に位置する人口約4万2千人の市。北東に高社山、北西に斑尾山の2つの山を配し、気候は昼夜の気温差が大きく、降水量は少なめ。果物の栽培に適しており、特にリンゴやブドウは全国でも有数の生産量を誇る。エノキタケをはじめとするキノコの栽培も盛ん。アクセスは北陸新幹線の長野駅から、長野電鉄に乗車し約30~40分。市内には上信越自動車道の信州中野IC、豊田飯山ICも存在する。
資料ダウンロード
さまざまな業種・業態・規模のお客さまのビジネスに役立つ資料や、NTT東日本の各種サービスのパンフレット、ご利用ユーザーさま向けのマニュアルをダウンロードいただけます。