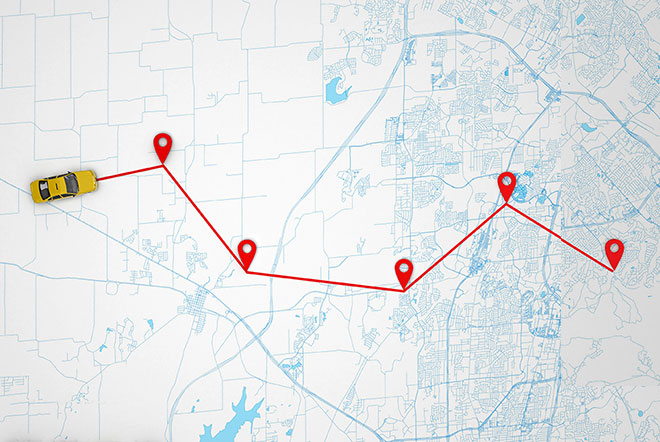将棋の7大タイトルである「名人」「棋聖」「王位」「王座」「竜王」「王将」「棋王」を1年のうちに同時制覇するという初の快挙を成し遂げた羽生善治氏。前編では、羽生氏がプロ棋士となり、初めてタイトルを獲得するまでの話から、困難な状況においてプレッシャーを克服する方法などについて聞いた。
後半では、七冠を達成したときのエピソードとともに、将棋に対する考え方や勝負において心がけていることなどを詳しく聞いた。七冠達成後も長年にわたって第一線で活躍し続けている羽生氏は、どのような勝負哲学によって高い勝率を維持し、モチベーションを保ってきたのか。また長年、将棋界を牽引してきたトップ棋士である羽生氏に、“チャンスを見極める”という将棋だけでなくビジネスにおいても貴重な意見を語っていただいた。
勝負勘は、体調が万全でないほうが研ぎ澄まされる
――七冠制覇をしたときは、対局数も多かったと思いますが、精神や身体のコンディションはどうだったのですか。
あの頃はとにかく忙しかったですね。移動と対局が毎日ずっと続くので、次第に自分がどこにいるのかわからなくなっていきました。対局の疲れから回復し、作戦を考えて次の対局に臨むという流れが通常なのですが、その間隔がどんどん短くなっていって、前の対局を検証しないまま、ずっと走り続けていく感じでした。
この頃に、年間89対局という記録を達成しました。ひとつの対局に2日間かかることもあるので、計120日間くらいは対局していたことになります。
勝負勘というのは、忙しいときや疲れているときのほうが研ぎ澄まされるものです。休養が十分に取れているときというのは、気分はすっきりしているけど、細かい判断は鈍ることがあります。ある程度の負荷をかけたほうが、いい結果を産むということですね。
あと、1日の中でも、朝起きて絶好調のときは意外と試合の結果があまり良くありません。また、好調が1日ずっと続くというのはめったにありません。最初は少しのんびりしているくらいのほうがいいです。
――七冠制覇のときは、前年に「あと1タイトルを獲れば七冠」というところまで行って失敗しましたが、次の年に見事に勝ち取りました。
前の年に負けたときはもちろんショックでしたが、終わって1週間後には次のタイトル戦が始まったので、失望している暇はありませんでした。すぐに気持ちを切り替えて、「来年も狙うぞ」といったことはまったく考えず、目の前の一局を丁寧に積み重ねることしか考えませんでした。
再挑戦のときは、あとふたつ勝てば七冠くらいの頃になってから、初めて意識しましたね。最後の王将戦のときは、高熱が出ている状態で対局したので、プレッシャーを感じる暇もありませんでした。将棋は考えすぎてもダメなこともあるので、逆に余計な力が入らず良かったと思います。
「わざと」自分が損をする一手とは
――「考えすぎてもダメ」というのは意外ですね。将棋というのは先を読んですべて理論的に考えるものではなく、ときには勘に頼ることも必要なのでしょうか?
将棋の場合、ひとつの局面で大体80通りの可能性があると言われています。その80通りの中から3つの手を選び、10手先を読もうとすると、組み合わせは3の十乗、つまり6万手くらいになってしまいます。
6万手読むというのは大変です。実戦で起こる10手先は想定できないことも多いので、対局中は、全体の可能性から見るとほんのひとかけらしか見えていないところで判断していることが多いですね。
もちろん大まかな方針や戦略は考えていますが、実際には、その場その場で対応していくというケースのほうが多いです。“出たとこ勝負”で、相手の一手を見てまた判断するということですね。想定外のことが起きて当たり前という世界なので、理詰めで考えても割り切れない部分はどうしても生じます。
――将棋の駒という限られたリソースをやりくりしながら勝利するために、ふだんから心がけていることはありますか?
盤上でいつも心がけているのは駒の損得ではなく、“効率”ですね。すべての駒がきちんと働いている状態のほうが、バランスが良いことが多いです。実は“歩”がとても大事です。どこに歩があるのか、手持ちの歩が2枚なのか3枚なのかということによって、局面がまったく異なってくるケースが実に多くて、そのような小さな違いが形勢を分けることが多いので気を遣っています。
あと、対局中に「やる手がない」という場面も実はけっこう多いです。そのような状態で自分に手が回ってくると困るので、わざと損して、後で自分にとって一番いい状態になるように相手に手を渡すこともあります。そうすることで、「この手に対してはあの手」と、相手の出方に対応できる手をできるだけ多く用意した上で待つわけです。
カードゲームにたとえると、お互い10枚くらいのカードを持っていて、「このカードを出したらこのカードを出しますよ」という状態にして、相手に順番が回れば、何が来ても大丈夫という状態になります。
将棋の用語で「含みを持たせる」という言葉がありますが、1手指すときに、攻めるけど、攻めることによって守りのための1手も残しておくとか、想定外のことが起きてもきちんとリカバリーできるような手を指すことを表しています。この含みを持たせることが将棋では大事なのです。
――プロ棋士同士の戦いでは、終盤に逆転することが多いとも聞きます。
それは最後の詰め(勝負を決める準備)のところが意外と難しいからです。ゴルフのパットに似ていて、あと3メートルくらいのところでも、微妙に傾斜があるとか、強く打ちすぎると向こう側に行ってしまうとか、プロ同士で対局すると、そのような詰めから詰み(王手を防げない状態)に向かうところで、形勢逆転ということが多くあります。
特定のタイミングで詰みに持っていかないと負けというケースも多くて、たった一手で勝負が決まるということもよくあります。
そういう場面でミスをしないために普段から心がけているのは、小さな違いに気が付くことですね。たとえば自動車のレースで、1cmの違いが掴めれば、相手に接近しても、ギリギリでぶつからずに追い越せます。そういう小さな違いを突き詰めていくことが勝負では大事だと思います。
移り変わりが早いときにこそチャンスあり
――特定のスタイルにこだわらない、オールラウンドプレーヤーを目指しているとお聞きしましたが、それはなぜですか?
昔から特定の手にはこだわらないほうでした。「色々な手を試してみたい」という好奇心もあるし、「この形しかできない」となると、違う形を避けなければならないので、それが嫌だという思いもあります。どんな手が来ても大丈夫なら、作戦の幅も広がるし、指していても楽しいです。
もちろんひとつの形を突き詰めるというやり方でもいいのですが、せっかく多くの可能性があるのに、ひとつに絞ってしまうのはもったいないと思うのです。自分の中では、将棋において新しい手を発見することがモチベーションになっているし、とても大事にしています。
――今、新しく挑戦していることはありますか?
将棋の世界で今、最も大きく変わっているのは将棋ソフトの進化です。最近では半年に1回は新しいバージョンが出るので、色々と試しています。今後は将棋ソフトをいかにうまく練習や研究に使うかが、プロ棋士の腕の見せ所になると思います。
将棋というのは、基本的には伝統文化の世界なのですが、盤上で行われている戦いは完全にテクノロジーの世界なので、常に最先端のものを取り入れていく必要があります。

――新しい技術やトレンドを積極的に取り入れていかなければならないのは、ビジネスに通じるものがありますね。日本の経済も、変化が激しく先の見えない状況の中で、不安に感じている経営者が多いと思われますが、そのような経営者に向けて一言アドバイスをお願いします。
「先が見えない」と言っても、本当に先が見えている人って実はあまりいないと思うのですよ。自分が見えてなくても、他の人が見えなければ同じなので、あまり気にする必要はないと思います。
そして、移り変わりが早いということは、そこにはチャンスが必ず訪れるはずです。チャンスをどれだけ早く見極めて、自分の持ち味を殺さないようにしつつ、最先端のスタイルに合わせて活用することがビジネスでも将棋でも大事だと思います。
連載記事一覧
- 第1回 厚切りジェイソンに聞く!芸人と役員 両立の秘密 2016.08.19 (Fri)
- 第2回 厚切りジェイソンが力説!日本企業はココがおかしい 2016.08.26 (Fri)
- 第3回 H.I.S.澤田会長に聞く、電話1本で起業した苦労と工夫 2016.09.15 (Thu)
- 第6回 ジャパネットの高田明前社長が会長職に就かない真意 2016.10.27 (Thu)
- 第7回 イジメ、裏切り…OKWAVE兼元社長が歩んだ試練の半生 2016.11.10 (Thu)
- 第8回 ホームレスから社長、OKWAVE兼元社長が起業するまで 2016.11.24 (Thu)
- 第9回 ビジネスマン兼教育者、藤原和博氏が日本企業を斬る 2016.12.09 (Fri)
- 第10回 藤原和博氏に聞く、100万人に1人の人材を育てる方法 2016.12.16 (Fri)
- 第11回 “倒産寸前”はとバスをV字回復に導いた社長の苦闘 2017.01.06 (Fri)
- 第12回 はとバスを窮地から救った本当の「現場重視」とは? 2017.01.13 (Fri)
- 第13回 入社3年目で社長に。一風堂を継いだ清宮俊之とは? 2017.02.03 (Fri)
- 第14回 一風堂が目指す「変わらないために変わり続ける」とは? 2017.02.10 (Fri)
- 第15回 突然の業績不振、無印良品元社長はどう対処したのか 2017.04.14 (Fri)
- 第16回 無印良品をV字回復へ導いた「経験主義」の否定 2017.04.21 (Fri)
- 第17回 「泡沫候補」東国原英夫はなぜ有権者に選ばれたのか 2017.05.19 (Fri)
- 第18回 東国原英夫の改革は、椅子を変えることから始まった 2017.05.26 (Fri)
- 第19回 “目標120%” 「PlayStation 4」開発責任者の心得 2017.06.02 (Fri)
- 第20回 PlayStation開発 120%の力の使い道 2017.06.16 (Fri)
- 第21回 落語家・柳家小せん × 「空気を読む力」= ? 2017.06.30 (Fri)
- 第22回 「プレッシャーは克服しない」柳家小せんの仕事観 2017.07.14 (Fri)
- 第23回 「経験が必ずしもプラスにならない」羽生善治の心構 2017.07.28 (Fri)
- 第24回 羽生善治は、わざと損する一手でチャンスを作る 2017.08.10 (Thu)
- 第25回 「読者のことを考えるのは傲慢」羽田圭介の気構え 2018.02.09 (Fri)
- 第26回 「時間と集中力の無駄遣いはダメ」羽田圭介の仕事観 2018.02.23 (Fri)
- 第27回 コシノジュンコ流「異業種交流から始まる顧客開拓」 2018.03.27 (Tue)
- 第28回 コシノジュンコが考える、日本の今後と仕事への姿勢 2018.03.29 (Thu)