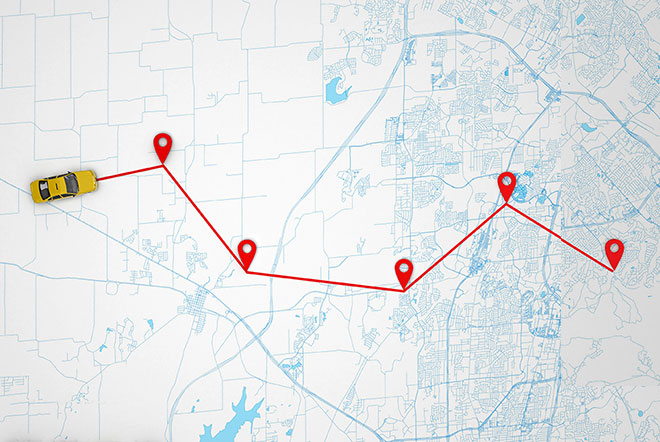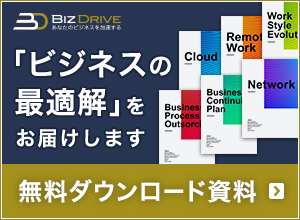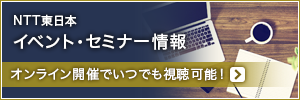自分に似せた「アバター」や、それを使って仮想空間で仕事や会話をする「メタバース」への関心が急速に高まっている。ロボット研究で知られる大阪大学の石黒浩教授はアバターロボットを実用化する新会社AVITA(アビータ)を設立し、大阪ガスや塩野義製薬など5社が出資。「アバターは研究の段階から事業化の段階へ入った。インターネットが登場したときと同じくらいのインパクトが今まさに起こりつつある。日本企業が世界を主導できる好機かもしれない」と語る石黒氏。アバター・メタバースを活用すれば人は開放され、もっと自由に働けるようにもなると言う。真意を聞いた。

AVITA
代表取締役CEO
石黒浩氏

日経BP 総合研究所 主席研究員
杉山俊幸
仮想空間上のアバター(分身)やインターネット上の仮想空間「メタバース」という概念をいかにビジネスに落とし込めば成功に近づくのか──。多くの企業が関心を寄せる分野だが、まだ勝者はいない。
会社設立までして、ビジネスを始める一人が石黒浩氏だ。ロボット研究の第一人者として知られ、AVITA(アビータ、東京・渋谷)という会社を作っている。
人に関わるロボットにこだわる
連載記事一覧
- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)
- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)
- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)
- 第4回 カインズが"デジタル"ホームセンター、新しい顧客体験を提供 2021.10.25 (Mon)
- 第5回 タイヤも売る会社へ─DXでサステナビリティ実現へ 2021.10.25 (Mon)
- 第6回 AIなどデジタルで持続社会─AGC、「二刀流人財」の生かし方 2021.11.05 (Fri)
- 第7回 アサヒが掲げる新概念FaaS―DXでサステナブル社会を目指す 2021.11.05 (Fri)
- 第8回 サステナブルなサーモン、漁網で鞄って知ってます? 2022.02.18 (Fri)
- 第9回 アバター・メタバースでもっと自由に働けるワケ 2022.03.01 (Tue)
- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)
- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)
- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)
- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)