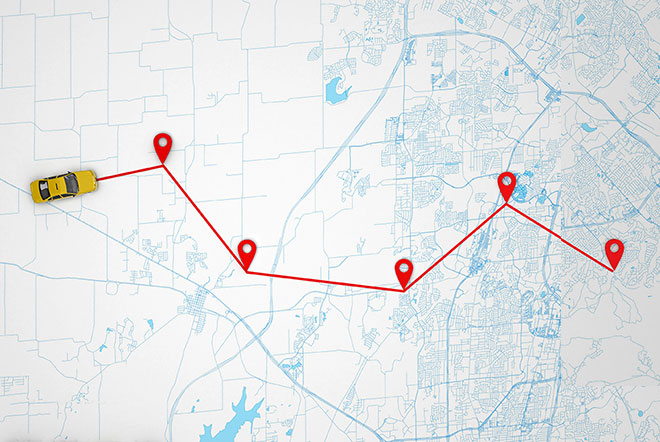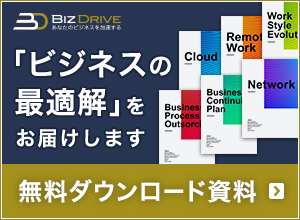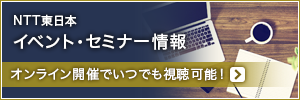とりわけ過剰な在庫は悪と言われる。ところが、「トラスコならある」と得意先に思ってもらう独自の在庫哲学を貫き、2021年度の業績見通しを上方修正したトラスコ中山。機械工具の卸で47万ものアイテムを即日出荷する。実現したのはDXによるところが大きい。21年6月には名古屋大学との産学連携、AI開発のシナモン、物流ロボットのGROUNDとの資本業務提携を発表。業界で最速、最短、最良の物流を目指す。提携秘話を中山哲也社長に聞いていると、同社最大の次世代物流拠点「プラネット愛知」に賭ける壮大な想いが見えてきた。

トラスコ中山
代表取締役社長
中山 哲也 氏
独自の在庫哲学を持ち、成長につなげている会社がある。機械工具の卸であるトラスコ中山。業界の常識、習慣、定説を塗り替える。そうした意識を常に持ち、中山哲也社長は教科書どおりの経営を疑ってかかる。
「在庫はあると売れる」

トラスコ中山の最大の物流センター「プラネット埼玉」
売れない在庫は置かない。それが一般論だが、「在庫はあると売れる」と中山氏は語る。在庫は必要最小限に抑えるのが一般論だが、「在庫は成長のエネルギー」だと中山氏は考える。経営指標では在庫回転率という数字がよく使われるが、中山氏が重視するのは「在庫ヒット率を重視」。顧客にしてみればトラスコ中山の在庫回転率なんて関心がない。だから顧客からの注文のうち、どれだけ在庫から出荷(ヒット)できたか、という数値を大切にする。

日経BP 総合研究所 主席研究員
杉山 俊幸
どれくらいの在庫ヒット率かは後ほど紹介するとして、47万もの商品アイテムを効果的に取りそろえ、効率的に届けていく。2030年には100万アイテムを扱う計画だ。これだけ膨大な在庫の数。欠かせないのがデジタルの活用である。だからこそ、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みにも力が入る。
信用もない、お金もない、人材もない
連載記事一覧
- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)
- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)
- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)
- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)
- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)
- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)
- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)