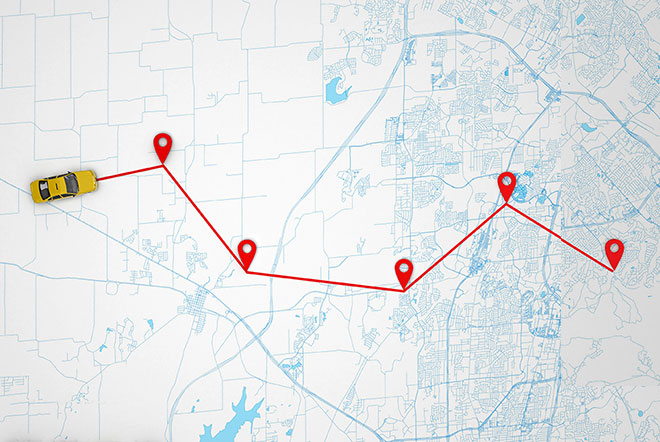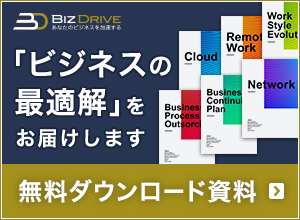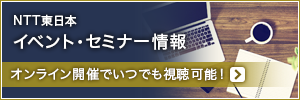持続的社会に向けての取り組みが待ったなしの状況になっている。もちろん大企業だけの課題ではなく、地方の中小企業も無縁ではいられない。ただこの問題、単なるコスト増ととらえて打開策を見つけるのか、それとも大きな企業変革の好機と位置づけて、新商品開発などに生かしていくのかによって、今後の企業の在り方を左右する。海洋プラスチックごみを使って製造した鞄や、木質バイオマス発電の排熱を使った魚の養殖など、持続的社会への対応を商品の"売り"につなげる動きも、地方で始まっている。地方創生に詳しい事業創造大学院大学の伊藤聡子客員教授が地方発サーキュラーエコノミーを語る。

事業創造大学院大学客員教授
伊藤聡子氏
「ある意味、必然だと思うんですよね」。持続的社会への取り組みが政府や企業で急速に進んでいることを受けて、事業創造大学院大学の伊藤聡子客員教授はこう見る。「毎年のように起きる大きな自然災害を見て、みなさん、何かがおかしいと実感しているのではないでしょうか」。
トヨタ、そしてアップルも

日経BP 総合研究所 主席研究員
杉山俊幸
トヨタ自動車は2021年末に、電気自動車(EV)の世界販売台数を30年に350万台とする目標を発表した。燃料電池車(FCV)と合わせて200万台としていた従来目標を一気に引き上げた。世界で進むEV化の流れにやや懐疑的とみられていたトヨタが、そうした見方を払拭したいとの狙いが透けて見える。
米アップルはiPhoneなど自社の全商品で、同じく30年までにサプライチェーン(供給網)で排出される二酸化炭素を実質ゼロにする方針を表明している。取引先を含めた形でここまで具体的な表明をするのは一部の先進企業にとどまっているが、持続的社会への動きは広がりこそすれ縮小する気配はない。
こうした動きは世界的な大企業にとどまらない。むしろ日本の地方に根付く中小企業の取り組みにこそ豊かな発想に基づくダイナミックな変革の事例が多い。そんな世界へ伊藤氏が誘ってくれた。まず紹介するのが出身地でもある新潟県の事例。
新潟発のサーキュラーエコノミー
連載記事一覧
- 第1回 淡路島から日本そして世界を変える―パソナ南部代表、不退転の挑戦 2021.10.15 (Fri)
- 第2回 DXでめざす、昔ながらの個人商店―ツルハ鶴羽社長、旭川から全国を臨む 2021.10.15 (Fri)
- 第3回 DXで独自の在庫哲学―トラスコ中山社長がこだわるワケ 2021.10.15 (Fri)
- 第4回 カインズが"デジタル"ホームセンター、新しい顧客体験を提供 2021.10.25 (Mon)
- 第5回 タイヤも売る会社へ─DXでサステナビリティ実現へ 2021.10.25 (Mon)
- 第6回 AIなどデジタルで持続社会─AGC、「二刀流人財」の生かし方 2021.11.05 (Fri)
- 第7回 アサヒが掲げる新概念FaaS―DXでサステナブル社会を目指す 2021.11.05 (Fri)
- 第8回 サステナブルなサーモン、漁網で鞄って知ってます? 2022.02.18 (Fri)
- 第11回 小売業のDX、「大胆なIT投資」と「外部データの活用」を急げ 2022.04.06 (Wed)
- 第12回 デジタルツインの活用進む建設業界のDX リモートワークで業務効率を向上へ 2022.04.11 (Mon)
- 第13回 循環型ショッピングをしたくなる意外な動機 2022.04.11 (Mon)
- 第14回 移動スーパー、"買いもの弱者"救って快走の裏事情 2022.04.11 (Mon)