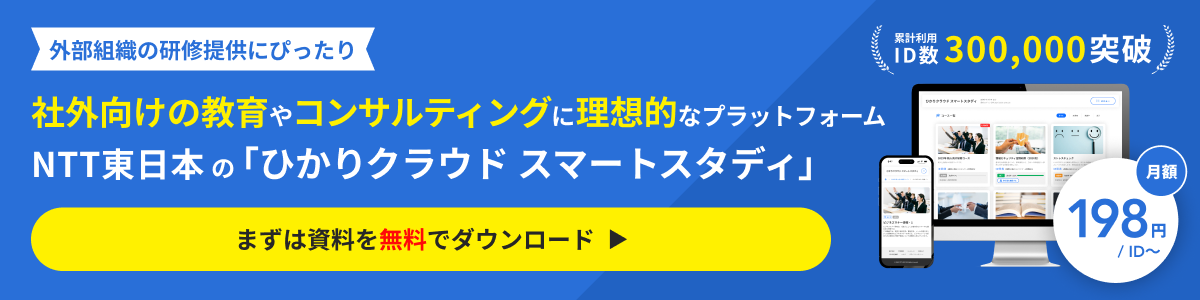【eラーニングとは?】導入メリット・デメリットや最新トレンドを徹底解説
-
2024.11.14 (木)Posted by NTT東日本

ビジネスのDX化が進む中、企業教育におけるeラーニングの重要性が高まっています。しかし、企業がeラーニングを導入する際には、そのメリットを理解し、効果的な運用戦略を立てることが重要です。
これまで集合研修で行っていた新人教育や人材育成をeラーニングで行うことにより、教育を効率化できるとして多くの企業が導入していますが、具体的にはどのような効果を得られるのでしょうか。
本記事では、企業教育におけるeラーニングの基本から導入メリット、実践におけるポイントと留意点について詳しく解説していきますので、導入を検討している企業のご担当者さまはぜひ参考にしてください。
NTT東日本では、月額198円~ご利用可能なeラーニングを提供しています。これからeラーニングのご導入やお切替えをご検討中の方は、ぜひ2週間も無料トライアルで使用感をお試しください。
>> NTT東日本のeラーニングを詳しく知る
オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

目次:
1eラーニングとは?

eラーニングとは、パソコンやスマートフォン・タブレット端末を利用して、オンラインで学習する方法のこと。eラーニングのeは、電子的を意味する「eletcronic」の頭文字をとったものです。
従来行われていた、一つの会場に従業員を集めて行う集合研修とは違い、時間や場所に制約されずオンライン上で学習を進められます。そのため、自分のペースで知識を学べるという特徴があり、従業員のスキル向上や新しい知識の習得を促す効果的な手段として、導入する企業も多くなりました。
研修の内容も、新人研修からコンプライアンス研修、ハラスメント研修と多岐にわたり、学習用のテキストとなる文字情報や図表を使った方法から映像やアニメーション、CGやVRを使った研修まで、受講者に興味をもたせる学習方法を選択できます。
また、eラーニングは教育の質を維持しつつ、コスト削減と効率的な学習管理が可能です。従業員個々の学習進捗や理解度を見える化することで、それぞれのニーズに合わせた教育計画を立てられるため、組織全体の知識レベルの底上げができます。
>> 月額198円~利用できるNTT東日本のeラーニングを知る
なお、eラーニングと類似のものとしてモバイルラーニングという学習形態もあります。モバイルラーニングとは、mラーニングとも呼ばれる、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末を使用した学習形態のことです。詳しくは、以下記事をご覧ください。
>> モバイルラーニングとは?メリット・デメリットを解説
LMSとの違い
eラーニングと似たものに、LMS(Learning Management System)があります。LMSとは学習管理システムのことで、eラーニングでの学習進捗や受講者情報、研修カリキュラムなどを一元管理する専用システムのことです。
LMSの主な機能には、受講者情報や受講進捗管理、試験データ管理、成績や修了証の発行などさまざまなものがあります。
なお、eラーニングを行う際に使用する、eラーニングの教材を管理・運用するシステムをeラーニングシステムといいます。eラーニングシステムは、広義でeラーニングのためのさまざまなシステムやツールを総称する言葉で、学習コンテンツの作成・配信や学習管理システム、成績・進捗管理などさまざまな機能がついていることが特徴です。
つまり、eラーニングシステムの中にLMSの機能が含まれるという解釈ができます。
>> LMSとeラーニングの違いとは?導入のメリット・デメリットを詳しく解説!
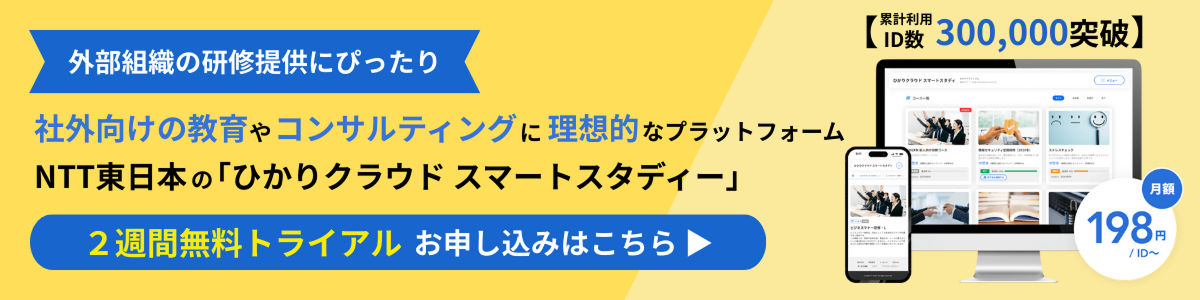
2eラーニングを導入する目的

eラーニングの導入目的には、人材育成の質の向上やコスト軽減、業務効率化などが挙げられます。eラーニングの導入目的例を表にまとめたので参考にご覧ください。
| eラーニングの導入目的の例 | |
| 業務に必要なスキル・知識や資格の習得 | ビジネスにおける業務をスムーズかつ効率的に行うためにスキルや知識習得、資格勉強を導入目的とする。 |
|---|---|
| コスト軽減 | 対面の集団研修のような従来型研修では、会場を用意したり紙の教材を用意したりといったコストがかかるため、研修コストの軽減を目的とする。 |
| 業務効率化 | 対面研修における計画から実施、評価までのプロセスは人事などの担当者が行う必要があったが、eラーニングの学習管理システムを活用すればこれらのプロセスの自動化が可能。研修に関する業務の効率化を目的とする。 |
| 人材育成の質を向上 | 対面研修では、各社員に対して均一な教育ができなかったり、研修内容や体制が属人化しやすかったりする。eラーニングで幅広い教材から社員にあった学習機会を提供し、 を効率的かつ効果的に行うことができる。 |
| 法令対策 | 令和2年6月1日の労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正により、パワーハラスメント対策が義務化。さまざまな法令知識のインプットを目的とする。 |
| 内部統制、法令順守 | 内部統制や法令遵のためにコンプライアンス教育の実施を目的とする。 |
なお、eラーニングで行うハラスメント研修とコンプライアンス研修については、以下記事もあわせてご覧ください。
>> eラーニングでハラスメント研修!メリットや効果的な研修方法を徹底解説!
>>【eラーニング×コンプライアンス研修】メリットと留意点やポイントを徹底解説!
3eラーニングの歴史と最新トレンド

急速に需要を伸ばしているeラーニングですが、どのように誕生し今に至っているのか、eラーニングの歴史と現在の市場価値について簡単に解説していきます。
20世紀の学習方法~eラーニングの登場
はじめに、20世紀の学習方法からeラーニングの登場までの推移を表にまとめました。eラーニングが重要視された背景の理解にお役立てください。
| 段階 | 詳細 |
|---|---|
| eラーニング登場前の学習形態 | eラーニングが登場する前の20世紀では、教室における直接指導に依存していた。徐々にテクノロジーを活用した学習形態も登場し始め、テレビ教材やビデオ教材を導入するようになった。 しかし、受講者は受動的な学習をせざるを得ない学習形態であるため、学習提供者からのフィードバックができないことが大きな課題だった。 |
| eラーニングの登場 | 2000年頃、日本政府は「e-JAPAN構想」を推進したことから、eラーニングが一般的に広まり始めた。同時に企業でもeラーニングによる社員研修制度を導入し始め、当時はCD-ROM※を用いてコンピューター上で行う学習が主流だった。 しかし、CD-ROMでeラーニングを行うには個別に作成したものを配布しなければならず、教材の更新が難しいという課題があった。 |
| 近年のeラーニング |
これまでの課題を解決したのが、現代では主流となっているインターネットを活用したeラーニング。インターネット上に設置された学習管理システムにより、受講者が自身のスマートフォンやパソコンなどの端末からアクセスでき、個別に教材を用意する必要がなくなったため大幅なコスト削減と作業効率の向上を実現した。 |
※CD-ROM:Conpact Disc-Read Only Memoryの略。CD(コンパクトディスク)とコンピューターを活用して、内蔵したデータを呼び出すための外部記憶装置のこと。
2024年のeラーニング市場と今後の動向
eラーニング市場は2019年まで緩やかに成長していましたが、2020年以降急速に拡大しました。2023年度におけるeラーニングの国内市場規模見込は、前年比0.9%減の3,690億円で、法人向けBtoB市場は1,140億円(前年比6.0%増)、個人向けBtoC市場は2,550億円(同3.8%増減)です。
また、2024年の予測では、BtoC市場は減少すると言われているものの、BtoB市場は引き続き拡大していく見通しが立てられています。これは、DX推進やリスクへの対応としてeラーニングが主流となりつつあり、企業の内部研修として広がっていることが大きな要因です。全体としては、2023年比0.1%増の3,693億5,000万円の市場規模が想定されています。
参照:株式会社矢野経済研究所 eラーニング市場に関する調査を実施
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3512
今後のeラーニングでは、学習データの分析や受講者ごとにカスタマイズされた学習計画の提案などでAIの活用が注目されており、顔認証技術の導入による不正防止の取り組みも進んでいます。ほかにも、医療分野における手術手技の練習や建築設計の3DモデリングなどVR技術の活用も見られ、さまざまな最新技術とeラーニングの融合が期待されています。
なお、現在のeラーニングのトレンドとして押さえておきたいものに、EdTechがあります。EdTechとは、Education(教育)とTechnology(科学技術)を組み合わせた造語で、教育におけるイノベーションに関わるものの総称のことです。詳しくは、以下記事をご覧ください。
>> EdTech(エドテック)とは?具体例やメリット・デメリットを紹介
また、eラーニングの市場についてより詳しく知りたい方は、あわせて以下の記事も確認してみてください。
>> eラーニング市場の現状と今後の展望予測|需要の高まりとeラーニング市場の成長
4eラーニングシステムの種類

eラーニングシステムは、オンプレミス型とクラウド型の2種類に分類されます。それぞれの特徴をわかりやすく解説していきますので、導入を検討している企業は参考にしてください。
オンプレミス型eラーニングシステム
オンプレミス型eラーニングシステムは、企業が自社のサーバー内に構築する学習システムです。
企業にとって、情報の保護は極めて重要です。オンプレミス型eラーニングシステムは、外部のネットワークと接続されていないため、データの漏えいリスクが著しく低下します。とくに機密性が高い情報を扱う企業にとって大きなメリットです。
また、社内のサーバーを使用するため、企業独自の教材や研修プログラムを安全に配布・管理できるのも大きな特徴です。
クラウド型eラーニングシステム
クラウド型eラーニングシステムは、外部のサービス会社が提供するクラウドサーバーにアクセスし、そのサービスを利用する形式になります。
クラウド型の最大の特徴は、自社のサーバーでシステムを構築する必要がない点です。すでに開発されているプラットフォームを利用するため、新たなシステムの開発や設定にかかる時間を節約できます。UIも使いやすく設計されているため、社員が新しいシステムに慣れる際の負担の軽減も可能です。
また、クラウド型の利用により、初期費用や維持管理にかかるコストを大幅に削減できます。とくに、予算に制限のある中小企業や早急にeラーニングを導入し活用したい企業にとって大きなメリットです。
低コストかつ迅速に導入が可能であり、中小企業から大企業まで幅広く利用できます。
>>【eラーニングの導入費用は、どのくらい?】費用の内訳やタイプ別費用の相場などを分かりやすく解説!
>>eラーニングにはどんな種類がある?企業向けeラーニングの講座カテゴリー・対象者・視聴スタイル別に詳しく解説
5eラーニングの種類

eラーニングには、汎用的なものから職種に特化したものまでさまざまな種類があり、幅広い学習に対応できることが特徴です。eラーニングの種類における主な講座の例について、以下の表にまとめました。
| eラーニングの種類 | 講座の例 |
|---|---|
| 社会人基礎を身につける汎用性タイプ | ・ビジネスマナー講座 ・コンプライアンス講座 ・営業職向け講座 |
| プログラミング等のスキルアップタイプ | ・ビジネスライティング講座 ・プレゼンテーション講座 |
| 医療や酪農等の職種特化タイプ | ・各資格の講座 ・(医療の例):看護師・院内スタッフ育成講座 ・(酪農の例):酪農大eラーニング |
| マネジメント業務等の管理業務タイプ | ・人材育成講座 ・ハラスメント防止講座 |
なお、詳しいeラーニングの種類や分類などについては、以下の記事もあわせてご覧ください。
>> eラーニングにはどんな種類がある?企業向けeラーニングの講座カテゴリー・対象者・視聴スタイル別に詳しく解説
6eラーニングの導入に必要なもの

eラーニングを本格的に導入するためには、下記の5つが必要です。
eラーニングは導入すればすぐに活用できるものではありません。スムーズに開始できるよう、eラーニングの導入に必要なものを把握し、準備するようにしましょう。
LMS(学習管理システム)
LMSとは、eラーニングの学習効果を高める上で欠かせない、学習管理システムのことです。LMSには学習スケジュールから評価まで幅広く管理できる機能が備わっていることから、学習効率の向上やタイムリーな学習進捗の把握などができます。
ただし、LMSは提供している会社が独自に設計した仕様になっているため、eラーニング教材はLMSにあわせて選定が必要です。この弱点により誕生したのが、SCORM(Sharable Content object Reference Model)です。
SCORMは、eラーニングにおける国際標準規格のことで、eラーニング教材を連携させるために必要なLMSの仕様を定義しています。詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてご確認ください。
>> SCORM(スコーム)とは?仕組みについて解説!
前述のとおり、eラーニングを導入する際には、業務効率化を実現できるLMSと呼ばれる学習管理システムは欠かせません。具体的な機能の中でも、重要な機能として以下の5点が挙げられます。
- ● 教材を受講者へ配信する機能
- ● 学習進捗状況の管理をする機能
- ● テストの作成、実施、レポートの受け取りをする機能
- ● テスト結果やレポート分析を行う機能
- ● コミュニティの管理をする機能
なお、LMSについては以下記事でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
>> LMS(学習管理システム)とは?なぜeラーニングに必要なのか
学習コンテンツ
eラーニングシステムの効果的な運用には、質の高い学習コンテンツの準備が不可欠です。学習コンテンツには、音声のみの教材、講義映像、アニメーションを用いた講義、パワーポイント資料などがあり、組み合わせての利用もできます。
学習コンテンツは、自社でオリジナルの内容を制作できますし、すでにオンラインで提供されている教材やコースを選択しての活用も可能です。外部コンテンツの利用には、サービス提供者との法人契約が必要になるので、契約内容は事前に確認するようにしてください。
動画教材は、eラーニングコンテンツの中でもとくに主流となっており、ブロードバンドの普及により大容量の動画コンテンツを容易に配信できるようになりました。動画は作業のイメージを直感的に伝えられるため、学習効果の向上が期待できます。
据置きカメラやパソコン、スマートフォンで収録されたものが多く、Zoomなどの会議ツールを用いた録画も研修用のコンテンツとして利用されます。
>> eラーニングで自社のオリジナル研修教材を作ろう!
インターネット環境
eラーニングを利用するには、インターネット環境が必要です。環境が整っていない場合は整備する必要があるため、社内の環境については企業が行うようにしてください。
また、受講者に対してもeラーニングを自宅で受講する場合、インターネット接続できる環境であるか留意するとよいでしょう。
活用デバイス
現代では、多くの人がパソコンやスマートフォンを所有しており、eラーニングにおいては中心的なデバイスとしての役割を果たします。企業によっては、貸与したスマートフォンやタブレット端末でeラーニングを受講することもあり、いつでもどこでも学習を進めることが可能です。
受講者への支援・フォロー方法
eラーニングを企業に浸透させ成功させるためには、受講者への適切な支援とフォローが重要です。eラーニングの継続率が低いとされる中、受講者に任せきりにしないための工夫が必要になります。たとえば、受講者が自ら積極的に学習に取り組むような動機づけを行うこと、定期的なフィードバックやサポートを提供するのは有効な手段です。
さらに、人事評価にeラーニングの成果を組み込むことで、学習のモチベーションを高められます。管理する側の支援とフォローにより、受講者は学びを継続しやすくなり、eラーニングの成果を最大限に引き出すことが可能になるのです。
また、eラーニングを導入する準備において、活用できる助成金を知りたい企業もあるでしょう。実際にeラーニングには、人材開発支援助成金といった種類の助成金が活用できます。詳しくは、以下の記事をあわせてご確認ください。
>> eラーニング導入に助成金・補助金が利用できる!種類と申請の手順を解説
7eラーニングの導入メリット

eラーニングを導入するメリットは、以下の通りです。
eラーニングは、学習をスムーズかつ効率的に進められることが特徴としてあげられます。以下のメリットを確認し、ぜひ導入を検討してみてください。
時間と場所を気にせず受講できる
eラーニングの最大の魅力は、時間や場所を自由に選択できることです。ネットに接続できる環境を用意できれば、好きなときに気軽に学習できます。時間がなかなか取れない場合や自宅で学習したいと考えている場合など、eラーニングであれば課題の改善ができるでしょう。
柔軟性が高い
eラーニングは、学習環境を柔軟にできることが大きなメリットです。例えば、一度に大勢が受講できたり、期限などなく自分のペースで学習できたりするなどします。また、教材のオリジナリティも高く、内容の更新性も高いので、常に最新の情報で学習可能です。
学習効果が高まる
eラーニングは、学習効果が高まることも大きなメリットです。同じ講義や教材を繰り返し使いやすいので、反復授業に向いています。また、従業員の進捗や理解度を数値化できる特徴もあり、一人ひとりに合った学習コンテンツを提供できます。
さらに、教材の均一化により従業員の学習の質まで均一化できることから、企業に合った人材育成にもつながります。
コスト削減がしやすい
eラーニングは、基本的にオンラインで完結する学習形態であるため、従来型の研修と比較してコスト削減がしやすいのがメリットです。ただし、新たにeラーニングシステムを導入する費用や運用費、教材作成費などがかかります。
導入費用としての初期費用は多めにかかりますが、基本的にランニングコストがかかりにくいことが特徴です。
>> eラーニング導入のメリットとは?企業側と受講者側それぞれの視点でご紹介!
8eラーニングの導入デメリット
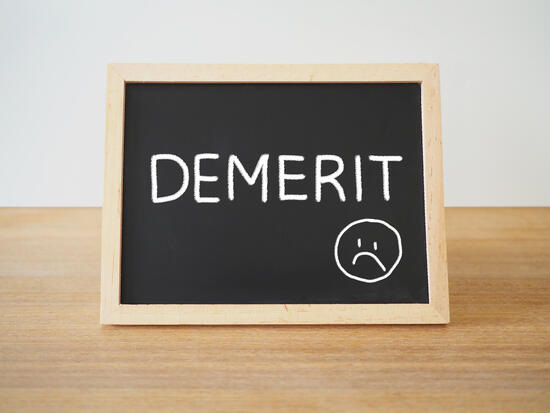
eラーニングを導入するには、以下のようなデメリットもあります。
eラーニングの導入を検討している場合は、これらのデメリットも考慮しましょう。
実践研修に向いていない
eラーニングは知識の伝達に優れていますが、実践的なスキルを身につける際には限界があります。手を動かす業務や対人スキルのように、実際の行動を通じて学ぶべき技能は、動画やテキストのみの学習では不十分です。
eラーニングで得た知識の定着や実践への移行が課題になるため、効果的な学習を実現するために、研修実施前に計画性をもって取り組むことが大事になってきます。
受講者のモチベーション維持が難しい
eラーニングは学習形態の特性上、受講者同士の交流が減ったり、その場で質疑応答ができなかったりするのが特徴です。双方向のコミュニケーションが取りにくいため、従業員によってはモチベーション維持が難しい場合もあるでしょう。
eラーニングによる学習は基本的に受動的で、画面に長時間向き合うことになります。また、一緒に受講する仲間との関わりもないため、孤独感を感じる場合もあるでしょう。さらに、近年ではショート動画が流行り、動画を倍速で再生をする人も多いので、長時間の動画視聴に慣れていないケースも考えられます。
eラーニングのモチベーションを維持するためには、マイクロラーニングの視点を取り入れるのがおすすめです。マイクロラーニングとは、1回当たり数分程度の短い時間で行う学習を指します。詳しくは、以下記事をあわせてご確認ください。
>> マイクロラーニングとは?特徴やメリットまで詳しく解説!
>> 流行りのマイクロラーニングの作り方|作成時の注意点を紹介
教材制作やeラーニングシステムの導入コストがかかる
eラーニングを実施するには、eラーニングシステムを導入し、教材の制作を行わなければなりません。教材制作には手間がかかることから外部委託するケースも多く、外注にかかる費用が発生します。
また、eラーニングシステムの導入の際は、オンプレミス型やクラウド型などタイプにもよりますが、5万〜300万円ほどの初期費用がかかります。サービスの選び方によって初期費用が大きく変動するため、複数のサービスを比較して慎重に導入検討を行いましょう。
下記の記事では、eラーニング導入の失敗例をご紹介しています。ぜひあわせて確認し、導入の失敗リスクを減らしましょう。
>> 意味のないeラーニングはやめるべき?失敗から学ぶeラーニングの効果を最大限に引き出す方法を解説
9eラーニングを有効活用するための8つのポイント

eラーニングを有効活用する際には、8つのポイントに着目してください。
- ● 導入目的を明確にする
- ● コミュニケーション機会を設ける
- ● 受講する際のルールを作る
- ● 効果をモニタリングする
- ● 受講者への支援とフォロー環境の充実
- ● eラーニングですべてを学ぼうとしない
- ● モチベーションを維持する工夫をする
- ● 自社に合ったeラーニングシステムを導入する
導入ポイントを知ることで、スムーズかつ効果的なeラーニングの活用ができます。今後、企業内においてeラーニングを管理する担当者は覚えておくとよいでしょう。
導入目的を明確にする
eラーニングシステムといってもさまざまなものがあり、それぞれが異なる特徴をもっているため、まず導入目的を明確にしましょう。自社にとって、広範囲のトピックをカバーする汎用的なシステムが適しているのか、特定の業務や技能に特化した訓練が必要なのかによって、選ぶeラーニングシステムは変わってきます。
また、研修内容に応じて、既存のコンテンツを利用するか独自に開発するかも検討してください。
自社で作成する場合は、現場のニーズに合わせたカスタマイズが可能ですが、リソースと時間が必要です。一方、外注する場合は、専門的な知識や技能をもつベンダーから高品質なコンテンツをすぐに入手できますが、コストがかかるため導入予算に合わせなければなりません。それぞれのメリット・デメリットを考慮する必要があります。
コミュニケーション機会を設ける
eラーニングの導入時は、コミュニケーション機会を創出するための仕掛けも必ず検討しましょう。受講者同士でつながれるSNSの活用や、LMS内の交流機能の活用のほかに、オンライン学習と実際の場での学習機会を組み合わせる方法などがあげられます。
受講者間のコミュニケーションはモチベーションの維持や情報交換に不可欠であるため、eラーニングだけに依存せず、対面での研修やディスカッションの機会、チャット機能やビデオ会議ツールを活用した受講者同士のコミュニケーションが取れる場を定期的に設けていきましょう。
受講する際のルールを作る
受講者の負担を適切に管理し、効果的な学習環境を確保するために、受講者が学習を進める時間帯やルールについて明確に定めることが必要です。
たとえば、就業時間内に受講を奨励したり、22時以降や休日に学習する場合は特別手当を支給したりするなど、時間外労働に関するルールを設けると受講者のモチベーション向上にもつながります。
なお、ルール策定を行う際には、eラーニングを労働時間に含めるかどうかを決めることも重要です。具体的なeラーニングの労働時間の策定方法や例については、以下記事をあわせてご確認ください。
>> eラーニングは労働時間に含まれるのか?パターン別で紹介
効果をモニタリングする
企業は従業員の知識向上やスキル習得など、特定の目標を達成するためにeラーニングを導入しますが、モニタリングを通じて受講者が目標達成しているかを確認し、学習状況が思わしくなければ、改善点を指示するのも大切です。
モニタリングは、受講者の成果を評価し、eラーニングの効果を最大限に引き出すためのポイントとなります。
受講者への支援とフォロー環境の充実
eラーニングシステムは、受講者の学習進捗や理解度を管理できる機能を備えています。管理者は受講状況をチェックし、学習の進行が遅い受講者や理解度が低い受講者に対して、適切なサポートを提供する仕組みを構築するようにしましょう。
効果的な支援とフォロー環境の整備をすることで、受講者は自分に何が足りないのかはっきり自覚し、足りない部分を集中的に学習できるため学習効率が向上し、結果的に人材の底上げにつながります。
eラーニングですべてを学ぼうとしない
eラーニング導入時の重要なポイントは、eラーニングと集合研修を適切に組み合わせることです。eラーニングには、ディスカッションや実技トレーニングなどは難しいという一面があります。
すべての学習をeラーニングで完結させるのではなく、ときには集合研修やOJTなどを組み合わせて、足りない部分を補いながら学習環境を提供しましょう。また、IT技術の進化により、動画配信の技術やテレビ会議システムを活用して、実技やシミュレーションを補完できます。自社にあった教育手法の組み合わせを検討し、効果的な学習環境を構築しましょう。
モチベーションを維持する工夫をする
eラーニング研修は、受講者のモチベーション維持がネックになる場合が多いです。いつでも学習できるという環境から、どうしてもモチベーションが上がらない受講者もいるものです。
学習管理システムは、受講者の学習状況に合わせてメールを配信して学習を促せますが、それだけでは不十分でしょう。すべてを自動で行ってくれるシステムに頼りすぎずに、集合研修を定期的に取り入れたり、eラーニングを活用している社員を表彰したりするなど、受講者のモチベーションを維持するための工夫が必要です。
自社に合ったeラーニングシステムを導入する
たとえば、従業員のスキル向上や業務プロセスの効率化というように、どのeラーニングが自社のニーズに合うのかを検討する必要があります。
従業員の誰が、どのタイミングで、どんな学習コンテンツが必要なのかを正確に把握し、ケースによってはカスタマイズ可能なeラーニングシステムの導入も検討が必要です。
また、学習提供だけでなく効果的な管理も重要といえます。適切なタイミングでコンテンツを提供し、進捗をモニタリングする仕組みを構築し、従業員のスキルアップと業務反映の効果を最大化できるよう心掛けてください。
10【企業の導入事例】eラーニング活用方法

最後に、実際にeラーニングを導入した企業の成功事例をご紹介します。企業によって導入目的はさまざまですが、どの企業もしっかりとした目的とゴールを設定していることが成功の秘訣であることがわかります。
数あるeラーニングシステムの提供会社の中でも、企業からの信頼が厚いNTT東日本のひかりクラウド スマートスタディの導入成功例を、導入きっかけや導入効果から紐解いていきますのでぜひ導入する際の参考にしてください。
株式会社アイテムさま
株式会社アイテムさまは、法人向けに通信サービスや機器を販売しています。太陽光発電パネルの販売など多方面に事業を拡大しており、従業員数も約2000名を超える大企業です。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入理由
技術革新が進む中、毎年のように新しく登場するサービスについての知識を学ぶために、すべての従業員に研修を行う必要が生じました。しかし、自社勤務の従業員以外にも、販売、製造と各部署で働く従業員が多いため、全社員のシフトを調整して集合研修を行うのは難しいと判断しました。
また、従業員数も企業の成長に伴い多くなり、テストの採点や添削、受講管理をするのが負担になってきたためeラーニングの導入の検討をはじめたのです。
社員に求められる研修を提供するため、さまざまなeラーニングがある中でも、低コストでさまざまなeラーニングコンテンツを配信できるひかりクラウド スマートスタディを選択しました。これまで培ってきた集合研修とひかりクラウド スマートスタディを組み合わせることで、スキル以外に知見やマインドを浸透できると判断したのも導入の決め手となっています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入効果
オンラインで研修を受けることで、シフト調整の手間が軽減されました。さらに、テスト結果を一元管理できるので、これまで数日かかっていた採点や添削をする必要がなくなり、集計されたテスト結果をもとに、苦手克服のアドバイスなどに注力できています。
・今後の活用方法
会社全体の知識、スキル向上を目指し、機能のフル活用を検討しています。コンテンツを収納するための容量拡張も検討しており、より管理者と受講者がスムーズにコミュニケーションを取れるライブ機能を導入し、今以上に受講者のモチベーションが維持できる学習環境の整備をする予定です。
参照:ひかりクラウド スマートスタディ公式サイト クラウド型のeラーニングプラットフォームを活用して研修の受講管理を効率化し、学習効果も向上させていく(2019年2月現在)
https://l-cloud.jp/case/item/
株式会社ネクスコ・パトロール関東さま
NEXCO東日本グループの子会社として約700名の従業員を抱えているのが株式会社ネクスコ・パトロール関東さまです。関東地区を中心に高速道路の安全を提供しています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入理由
新人研修や管理職研修を行っているものの、中間層の研修を実施できておらず、全社員に研修の機会を平等に与えたいという思いから、さまざまな研修を行えるeラーニングの導入を決めました。
また、言葉だけでは伝わらない作業の訓練や動作などを動画教材で発信したり、講師によって教え方にばらつきが発生したりするのを防ぎ、統一性のある研修を行いたいという思いも、導入理由のひとつです。
1名あたり198円~で利用ができる低コストが、ひかりクラウド スマートスタディを導入した一番の理由といえます。不正なアクセスができないようセキュリティ面も充実しており、何よりNTT東日本というネームバリューで安心感が増したということです。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入効果
従業員は、勤務時間がそれぞれバラバラなので、自分のペースで学習できるeラーニングは、効率的な学習ができていると好評を得ています。研修を管理している従業員からも、受講者の研修に対する興味度合いが違うと報告を受けているそうです。
また、独自の学習コンテンツを作成して、研修したい内容を配信できるので、質の高い研修を行えています。
・今後の活用方法
今後は、さらに動画機能を活用し、集合研修では伝わりにくかったコンテンツをどんどん発信していくための環境整備に注力していきます。
また、女性に特化した研修や、これまで行えなかった中間層への研修などの実施、コミュニケーションの場を設け、今以上に従業員のモチベーション維持に努め、さらに高い人材育成を行えるような環境整備をする予定です。
参照:ひかりクラウド スマートスタディ公式サイト eラーニングで独自の研修を反復学習し知識の醸成・浸透を図る(令和5年4月1日現在)
https://l-cloud.jp/case/nexco/
ミアヘルサ株式会社さま
ミアヘルサ株式会社さまは、介護サービスや保育園、調剤薬局など、高齢化社会に必要な街づくりに向けた地域包括ケアを展開している大手企業です。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入理由
企業上場によって、プライバシーマーク研修やコンプライアンス教育などの研修が必要になった頃にコロナ禍が直撃し、集合研修ができなくなったことをきっかけにeラーニングによるオンラインシステム導入を検討しました。
コストパフォーマンスやセキュリティ面の安心感、管理・運用がしやすさを考慮し、ひかりクラウド スマートスタディの導入を決定したとのことです。社内のグループウェアと紐づけし、200ヵ所の事業所と2,800名の従業員が、誰でも簡単に受講できる環境に整備されています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入効果
コスト面の削減とオンライン学習による時間の効率化に成功しています。また、受講者を自動管理できるので、パワーポイントやPDFでデータを各事業所から送ってもらう必要がなくなり、労力軽減を実現できました。さらに、テストの実施により、研修自体の質を向上でき、人材の底上げにも寄与しています。
・今後の活用方法
薬局で働く従業員向け、また各事業部向けの独自の研修を検討しています。
参照:ひかりクラウド スマートスタディ公式サイト セキュリティを担保しながら200を超える拠点への研修をオンライン化 (2022年7月時点)
https://l-cloud.jp/case/miaherusa/
社会福祉法人県央福祉会さま
従業員数約1500名を抱える社会福祉法人県央福祉会さまは、障がい者支援や高齢者介護を目的として福祉・医療・介護事業を幅広く展開し、神奈川県内に110を超える事業所を設けています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入理由
正社員よりもパートやアルバイトなどの非常勤が多く、通常業務の忙しさにより事業所ごとに職員の質にばらつきが出ていました。職員の質の均一化を図りたくても事業所が多く、定期的な集合研修を行えない状況を踏まえ、eラーニング導入を検討したようです。
福祉や医療関連の研修は、文字で見るよりも動画で研修する方法が効果的と判断し、数あるeラーニングがある中でも、ライブやビデオなどさまざまな動画配信ができ、マルチデバイスに対応するひかりクラウド スマートスタディの導入を決定しました。
また、独自に作成していた職員教育用DVDを、ひかりクラウド スマートスタディにアップロードできることで、コストや手間を軽減できることも導入の決め手となっています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入効果
好きな時間に利用できることもあり、非常勤職員の研修参加が積極的になりました。また、直感的に操作できるため、年齢が高めの従業員も無理なく研修に参加できています。
・今後の活用方法
各分野にあるいろいろなノウハウをコンテンツ化して、今後の職員教育に活かしていきたいと考えており、それぞれの役職にあった研修ノウハウの蓄積も行う予定です。
参照:ひかりクラウド スマートスタディ公式サイト 時間の制約をなくし職員の質とモチベーションを保つ(2018年4月現在)
https://l-cloud.jp/case/kennou/
ウエラプロフェッショナルさま
女性に人気のヘアケア製品「イルミナカラー」をはじめ、世界的に有名なドイツ生まれのブランド「ウエラ」の国内生産を手掛けているウエラプロフェッショナルさまです。美しさを求める女性のための製品を、全国各地の美容事業者に提供しています。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入理由
ブランド製品の販売促進のため、来店した利用者の髪質を見てカウンセリングを行い、的確にアドバイスできる知識を美容師にもってもらいたいという思いがありました。しかし、自社の製造者が研修したくても、美容師の業務が忙しいため理解できるまで説明するのが困難と判断しeラーニングの導入を決めたとのことです。
研修を文字だけでなく、動画も使って行いたいと考えていたところ、ビデオコンテンツの配信オプションがあるひかりクラウド スマートスタディを導入しました。決め手になったのは、理解度を把握するために行うテストの出題形式が、記述式や選択式など内容に合わせて選べることと、初期費用の安さです。
・ひかりクラウド スマートスタディ導入効果
文字だけでなく、ヘッドマッサージやカウンセリングについての動画コンテンツをオリジナルで配信し、美容師の理解度が向上したといえます。どこでも学べると好評で、商品販売促進の目的も達成しました。
全10問のテストも作成し、美容師ごとの理解度を管理して足りない部分はアドバイスするなど、学習の効率化も実現できています。
・今後の活用方法
現在は約3割の美容師が研修を受けている状況ですが、さらに受講者を増やしていきたいと考えています。また現在、テストで好成績を残した美容師に「ケアロジスト」という称号を与えていますが、新たに上級者向けのテストを作成し、好成績者には「エリートケアロジスト」という称号を設ける仕組みを構築する予定です。
参照:参照:ひかりクラウド スマートスタディ公式サイト eラーニングで美容師への教育を支援ヘアケア製品の販売促進につなげる(2017年6月現在)
https://l-cloud.jp/case/uera/
11eラーニング導入をお考えならNTT東日本の「ひかりクラウド スマートスタディ」
eラーニングによる研修は、業務効率化やDX化を実現できるだけでなく、コスト軽減や学習効果の向上などのメリットをもたらします。
eラーニングシステムにはさまざまな種類がありますが、その中でもおすすめが「ひかりクラウド スマートスタディ」です。
ひかりクラウド スマートスタディはクラウド型のeラーニングシステムで、企業ごとのニーズにあわせてオリジナル学習コンテンツが作成でき、月額費用は1名あたり198円~とリーズナブルです。
2週間の無料トライアルでお試し利用もできるため、はじめてeラーニングシステムの導入を検討している方はぜひ、下記から詳細をご確認ください。
※ひかりクラウド スマートスタディは、eラーニングプラットフォームのため学習コンテンツは含まれておりません。
>> 「ひかりクラウド スマートスタディ」は【コチラ】
なお、eラーニングにはさまざまな種類の講座があり、研修や従業員への学習機会の提供に役立ちます。具体的な講座については、以下の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
>> eラーニングの講座一覧を一挙公開!どんな講座が人気なの?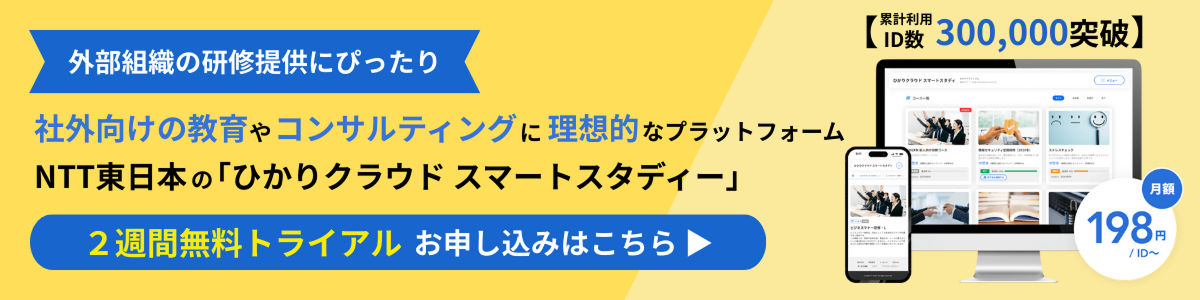
記事監修者
NTT東日本 ビジネス開発本部 松田優健
1995年12月17日生まれ、東京都出身。
明治大学商学部卒業後、2018年にNTT東日本株式会社に文系職として入社。
営業職として中小企業向けのコンサルティング営業を経験した後、
ビジネス企画・開発部門でe-learningの販売促進やデジタルマーケティングに従事。
e-learningの開発にも携わるソフトウェアエンジニアとして、フロントエンド・バックエンドの両方を経験し、現在はひかりクラウドスマートスタディのプロダクトオーナーとして従事。