年末調整をしても確定申告をしなくてはいけない?確定申告が必要なケースを紹介!
-
2023.2.10 (金)Posted by 北森 雅雄

給与所得を得ている会社員やサラリーマンの方で、自分が確定申告をしなければいけないのか分からないとお悩みの方は多いのではないでしょうか。
一般的なサラリーマンは会社が年末調整をしているので税金の計算が済んでいるということが多いです。しかし、年末調整で計算できない所得については自分で確定申告をしなければならない人もいます。
そこで本記事では「確定申告と年末調整の仕組み」について紹介します。
サラリーマンが確定申告をしなければならないケースについて詳しく紹介するので、参考にしてください。
1. サラリーマンは年末調整をすれば確定申告は不要?
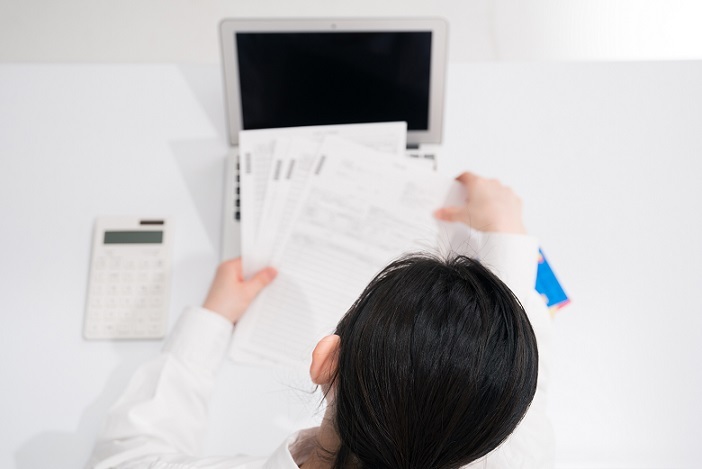
年末になるとサラリーマンなど会社勤めの人は年末調整の手続きでバタバタした覚えのある人は多いのではないでしょうか。
年末調整と確定申告はいずれも所得税を計算するために必要です。会社が年末調整をしてくれるため、社員であるサラリーマンの人は確定申告をする手間が省けます。
ここでは、年末調整の仕組みや年末調整と確定申告の違いについて確認していきましょう。
1
年末調整とは?
年末調整は会社が社員や従業員の所得を計算して税金の過不足を精算する手続きです。従業員は会社が年末調整をしてくれるおかげで税金を正しく計算することができます。
年末調整は通常11月から12月という年末に行われる手続きです。年末調整の担当者は従業員の所得額や所得額控除などを計算します。1年間の納税額に過不足があった場合、年末調整によって所得税が過不足している金額を精算します。
従業員は年末調整で所得控除を受ける際に必要な書類を会社に提出します。例えば、各種保険料控除を受けるために保険会社から発行された証明書を提出する必要があります。
2
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告の違いは手続きを誰が行うのかという違いがあります。
年末調整は先ほども紹介したように、会社が従業員の所得を計算して税務署へ申告する手続きです。一方、確定申告は従業員自らが税務署へ所得額を申告する手続きです。
会社勤めの方は会社が年末調整をしてくれるため、多くの場合は確定申告の必要がありません。確定申告が必要なケースは年末調整では計算しきれないケースになります。
|
<年末調整と確定申告の違い> |
3
確定申告の期限に注意!
確定申告の期間は「2月16日から3月15日」となっています。この期間に前年の所得について計算を行い、所得税を計算して税務署へ確定申告をしなければなりません。
なお、所得税の納付期限も確定申告の期限である3月15日となっています。
確定申告の期限に間に合わないと本来支払うべき税金のほかに無申告加算税あるいは延滞税が課せられます。無申告加算税は50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントが加算された金額です。
4
確定申告をしないとどうなる?
納税は国民の義務であり、年末調整も確定申告もしない状態だと無申告加算税あるいは延滞税などのペナルティが課せられます。
多くのサラリーマンにとっては年末調整で所得税の計算が済んでしまうため、わざわざ確定申告をする必要はないかもしれません。次の項ではサラリーマンにとって確定申告が必要なケースを詳しく解説していきます。
2.確定申告が必要なケース

確定申告をしなければいけない人はどんな場合でしょうか?
以下のケースに該当する場合、確定申告が必要となる場合があります。
- ●複数の会社から給料を受け取っている場合
- ●2000万円以上の給与がある場合
- ●20万円以上の事業所得がある場合
- ●投資による所得がある場合
- ●再就職して年末調整をしなかった場合
- ●年末調整の提出書類に不備があった場合
確定申告をすることで払いすぎた税金を還付金として取り戻せるかもしれません。確定申告の時期には自分が確定申告が必要な条件に該当していないかチェックしてみましょう。
1
複数の会社から給料を受け取っている場合
複数の会社から給料を受け取っている場合、確定申告が必要な場合があります。
会社が年末調整をしてくれるのは1人につき1社のみです。そのため、複数の会社から給料がある場合は1つの会社に1年間の給料をまとめる必要があります。最も給料が多い会社に年末調整をまとめるのが一般的です。
年末調整で他の会社からの収入を申告しない場合、自分で確定申告をする必要があります。
2
2000万円以上の給与がある場合
サラリーマンなどの給与所得者は年末調整できる金額に上限があります。
所得税法では確定申告を必要としない給与所得者の条件として、1か所から得ている給与の金額が2,000万円以下である給与所得者と定められています。(所得税法121,122)
そのため、2,000万円を超える給与所得がある場合は年末調整ではなく自分で確定申告をする必要があるのです。
3
20万円以上の事業所得がある場合
副業で20万円以上の事業所得がある場合は事業所得を確定申告する必要があります。例えば、クラウドソーシングや自由業を営んでいる場合は売上によって得た所得について申告しなければなりません。
なお、20万円以上の金額は売上ではなく所得によって判断します。事業所得は事業に必要な経費(支出)を売上(収入)から控除できます。例えば、売上が20万円であっても経費が5万円ある場合は所得は15万円(=20万円ー5万円)となり、確定申告の必要はありません。
4
投資による所得がある場合
株式売買など投資によって利益を得た場合、投資によって得た利益を確定申告する必要があります。
例えば、株式売買によって利益が出た場合は譲渡益として税金の計算をしなければなりません。ただし、特定口座を作っている場合に「源泉徴収あり」と設定することで税金の支払が完了するため確定申告の必要はありません。
外部リンク:利子所得と配当所得の課税方法|国税庁
5
不動産所得や譲渡所得がある場合
不動産所得や譲渡所得がある場合、その所得を確定申告する必要があります。
不動産所得とは土地や建物などの不動産を売却、あるいは家賃収入がある場合に得た金額です。不動産所得の金額は「総収入金額 - 必要経費」で計算されます。
譲渡所得とは土地や建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得です。譲渡所得の金額は「収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額」で計算されます。
不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁
譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁
6
再就職して年末調整をしなかった場合
転職などによって他の会社に再就職した場合、年末調整は12月末に在籍している会社で年末調整を行うことになります。その場合は前職で発行された源泉徴収票を転職先に提出します(複数回転職をしている場合はすべての源泉徴収票を提出する)。
源泉徴収票を提出しなかった場合は前職の給与について税金の計算ができなくなるため、自分で確定申告をする必要があります。
7
年末調整の提出書類に不備があった場合
年末調整では保険料の控除証明書や住宅ローンの残高証明書を提出することで控除を受けられます。
年末調整でこれらの提出書類に不備があった場合、あるいは提出を忘れていた場合は自分で確定申告をすることで控除を受けられます。
3.サラリーマンにできる節税対策

確定申告をする際、所得控除などの制度を利用することによって支払う税金を少なくできる節税対策ができます。
確定申告をした結果、税金を払いすぎてしまった場合は還付金を受け取ることも可能です。
ここでは、所得税の計算方法について確認していきながら節税対策としてできる具体的な方法を確認しましょう
1
所得税の計算方法
所得税の計算は以下のように計算されます。
「課税所得=(税込年収)-(給与所得控除)」
「所得税=(課税所得×税率)―(税額控除額)」
所得税を計算する場合は、税込年収から給与控除額が差し引かれます。例えば、年収が400万円(4,000,000円)の場合は427,500円を差し引いた3,572,500が課税される所得金額です。
以下は課税される所得金額と給与控除額の一覧表です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 給与控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁
2
生命保険料控除を活用する
生命保険や介護医療保険料、個人年金に加入している場合は一定の金額について所得控除を受けられます。これを生命保険料控除といいます。
3
住宅ローン控除を活用する
住宅ローンを使用している場合、「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン控除を受けられます。
住宅ローンによる控除を受ける場合、金融機関から発行される住宅ローンの年末残高証明書が必要です。
4
NISAを活用する
投資によって利益を得ている場合、その所得についてNISA制度を利用することによって節税対策になります。
NISA(少額投資非課税制度)とは一定金額の範囲内で購入した金融商品についての所得(利益)が非課税になる、つまり税金がかからなくなる制度のことです。
4.確定申告は「おまかせ はたラクサポート」がおすすめ!

個人事業主や副業のあるサラリーマンなど副業所得のある方が確定申告をするなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。
確定申告をするためには正しく帳簿をつけなければなりません。会計ソフトを使うことによって確定申告に必要な事務作業を大幅に効率化できますよ。
1
記帳業務をサポート
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」は会計業務を自動化することで面倒な記帳業務を効率化します。
副業所得を計算する際に正しく帳簿をつけることは意外と難しいものです。会計ソフトを使うことで会計の知識がなくてもスムーズに確定申告に必要な帳簿作りができます。
青色申告に必要な条件である複式簿記もクリアできるため、節税対策にも繋がるのです。
2
初期導入費用は不要!
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」はクラウド型のシステムであり、初期費用0円で始められます。
インターネット環境さえ整っていれば簡単に導入できるので確定申告の対策が可能です。
確定申告には期限があるので、期限間近に慌てないためにも早めに記帳の準備をおすすめします。
| プラン | 初期費用 | 月額基本料 |
追加ID |
| スターター | 不要 |
1,298円 |
ー |
| スタンダード | 不要 |
2,618円 |
396円 |
5.まとめ
サラリーマンなどの給与所得者は会社が年末調整をしてくれることによって所得税の計算が正しくされます。
サラリーマンの方であっても年末調整で計算しきれない場合は自分で確定申告をしなければなりません。例えば、副業で事業所得が20万円以上ある場合は事業所得について帳簿を作成して確定申告をする必要があるのです。
事業所得の計算なら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。確定申告には複雑な会計知識が必要ですが、会計ソフトを使うことでスムーズに確定申告の処理を進められます。
年末調整や確定申告を正しくすることで節税対策に繋がり、還付金が還ってくる場合があります。所得税の正しい計算方法を知ってお得に節税対策をしてください!
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
