【保存版】勤怠管理とは?意味や目的、方法を分かりやすく解説!
-
2023.4.17 (月)Posted by 北森 雅雄

「勤怠管理とは何か、どうやって勤怠管理を行えば良いのか」でお悩みではないでしょうか?
勤怠管理には法的な義務があり、適切な給与計算や従業員の健康管理を行うためにも重要な業務です。
この記事では、勤怠管理の概要と目的、項目、方法、注意点について解説します。
業務効率化と働き方改革関連法に対応したクラウド勤怠管理サービスについても解説しているので、ぜひ最後までお読みください。
1.勤怠管理とは
勤怠管理とは、企業が従業員の労働時間や休憩時間を正確に把握することです。
勤怠管理の「勤怠」は、従業員の出勤状況を意味しています。
タイムカードやICカードによって従業員がいつ出勤・退勤したのかは確認できますが、打刻された時間が就業時間通りなのか、残業しているのかは分かりません。特に、変動労働時間制を採用している企業では、各従業員の労働時間を把握することは困難です。労働時間の管理を従業員に任せてしまえば、残業時間が多くなりすぎたり、健康が悪化するまで残業したりするかもしれません。
従業員の正確な労働時間を管理するためには、企業側が適切な方法で勤怠を行う必要があります。
1
誰が行う仕事なのか?
勤怠管理は、主に労務を担当する部署が行う業務です。労務部や労務課を設けていない企業では、人事部で行われています。規模の小さい企業では、総務部や経理部が兼務する場合もあります。
2
対象は?
勤怠管理を行う必要があるのは、労働基準法の労働時間の規定(労働基準法第4章)が適用されるすべての事業所です。
勤怠管理の対象となるのは、以下のケースを除くすべての労働者です。
- 労働基準法第41条に定める者
- みなし労働時間制が適用される労働者
- 事業場外労働を行う労働者の労働時間のうち、みなし労働時間制が適用される時間
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
引用:労働基準法
上記の「労働者」には、正社員だけでなく契約社員、パート、アルバイトも含まれます。
ただし、企業が直接雇用していない個人事業主やフリーランスは対象ではありません。
2.勤怠管理の目的

企業が勤怠管理を行う目的は以下の通りです。
- ●法令順守
- ●適正な給与計算
- ●従業員の健康管理
- ●長時間労働の抑止
- ●計画的な年次有給休暇の取得
勤怠管理を行うことで企業側にどのようなメリットがあるのかを解説します。
1
法令順守
以下のような勤怠管理にかかわる作業は、労働基準法及び労働安全衛生法で義務づけられています。
- ●企業が労働者の労働時間を把握すること(労働安全衛生法 第68条の8の3)
- ●労働関係に関する重要な書類の保存(労働基準法 第109条)
- ●正確な賃金の支払い(労働基準法 第3章及び第4章)
- ●従業員の健康管理(労働安全衛生法 第3章 安全衛生管理体制)
第六十六条の八の三 事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。
引用:労働安全衛生法
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
引用:労働基準法 第109条
2
適正な給与計算
企業は従業員にすべての賃金を支払う義務(労働基準法 第24条)があり、残業や休日出勤を指示した場合は割増賃金を支払う必要(労働基準法 第37条)があります。
従業員がどのくらい残業したのか、休日に出勤したのかは、勤怠管理で勤務状況を把握していなければ分かりません。
従業員に正確な賃金の支払いを行うためには、従業員の勤務状況を把握したうえで、正確な給与計算が必要です。
3
従業員の健康管理
企業は、従業員の健康管理を義務付けられています。
企業は労働基準法36条に基づく労使協定を従業員と締結することで、法定労働時間を超えて働かせることが可能です。しかし、残業時間が長すぎれば、従業員が体調を崩すこともあるでしょう。従業員の残業時間を把握することで、過重労働を未然に防ぐことができます。
4
長時間労働の抑止
近年では過重労働による過労死が発生しており、社会問題にもなっています。
厚生労働省が定めている時間外労働時間の上限を超えた従業員が脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害が原因で死亡した場合、過労死と認定されるかもしれません。
原則として、企業は従業員に「1日8時間・1週40時間」を超えて働かせることはできません。(労働基準法 第32条)
労働基準法36条に基づく労使協定を従業員と締結することで法定労働時間を超えて働かせることが可能ですが、上限を超えて時間外労働をさせるのは違法です。(労働基準法36条4項・5項)
5
計画的な年次有給休暇の取得
企業には、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者に対し、最低5日の年次有給休暇を取得させる義務があります。(労働基準法第39条7)また、年5日の年次有給休暇の時季指定は、従業員に意見を聴取し尊重する必要があります。
年次有給休暇を取得するかどうかは従業員が決定しますが、年次有給休暇の取得状況の管理を従業員に任せてしまうと、企業側は実際に取得したかどうかが分かりません。
年5日の年次有給休暇の時季指定義務がある従業員は誰なのか、いつまでに取得させなければいけないのか、実際に取得したのかどうかを把握するためには、勤怠管理によって年次有給休暇の取得状況を管理する必要があります。
3.勤怠管理の項目
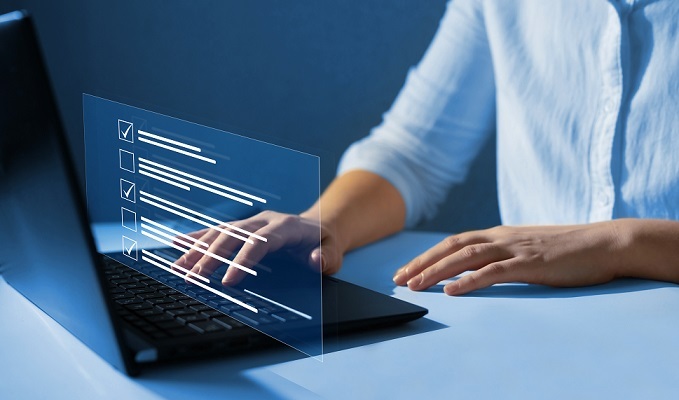
艦隊管理で把握すべき項目とはどのようなものがあるでしょうか。
人事・労務が把握するのは、出退勤時刻や時間外労働時間だけではありません。有休日数や出勤日数など、把握すべき項目は数多くあります。一般的に人事・労務が勤怠管理で把握すべき項目は、以下のとおりです。
1出勤時刻・退勤時刻
労働時間を正確に把握するために、出勤時刻・退勤時刻を記録する必要があります。タイムカードやICカードを利用している場合は、打刻した時間が出勤時刻・退勤時刻です。
出勤時刻の前に仕事の準備をさせたり、退勤時刻後に仕事をさせたりすれば、違法な残業とみなされる恐れがあります。
基本的に分単位での打刻が前提となっており、15分単位・30分単位で記録・管理することは認められていません。
2勤務時間・労働時間・休憩時間
正確な給与計算を行うためには、勤務時間・労働時間・休憩時間を記録し、集計する必要があります。
勤務時間とは、出勤時刻から退勤時刻までの時間です。労働時間は、勤務時間から休憩時間を差し引くことで算出されます。
企業は、労働時間が 6時間を超えた従業員に休憩を与える義務があります。(労働基準法第34条)与える休憩時間は、労働時間が 6時間を超え8時間以下の場合は最低45分、8時間を超える場合は最低60分です。
3時間外労働時間
本来、法定労働時間を超えて従業員を働かせることはできません。ただし、労働基準法36条に基づく労使協定を従業員と締結している場合に限り、法定労働時間を超えて働かせることができます。また、休日に出勤させることも可能です。
法定労働時間を超えて働かせた場合、22時から5時までの間に働かせた場合、休日に働かせた場合には、時間外手当を支払う義務があります。
4所定労働時間
変動労働時間制を採用している場合は、残業時間を計算するために所定労働時間を管理する必要があります。
所定労働時間とは、企業が定めた労働時間です。変動労働時間制を採用している場合は、所定労働時間が法定労働時間が上回っていても時間外労働にはならず、時間外手当は発生しません。ただし、所定労働時間を超えて働かせた場合は時間外労働となります。
5出勤日数・欠勤日数・休日出勤
企業は、従業員に対し毎週少なくとも1回の休日、あるいは4週間を通じ4日以上の休日を与える義務があります。(労基法35条1項、同条2項)
上記の休日を法定休日と言います。また、法定休日以外に与えた休日は法定外休日です。
労働基準法36条に基づく労使協定を従業員と締結している場合に限り、法定休日・法定外休日に働かせることができます。
休日出勤させた場合には時間外手当が発生しますが、出勤日が法定休日か法定外休日なのかで割増率が異なります。法定休日に出勤させた場合が35%割増、法定外休日の場合は25%割増です。
6年次有給休暇
年次有給休暇は賃金が発生する休日なので、法定休日・法定外休日と区別するためにも記録・管理する必要があります。
前述したように、年5日の年次有給休暇を従業員に取得させることは企業の義務です。計画通りに消化しているかを確認しておくことも重要です。
また、繰り越しできる年次有給休暇の上限は20日までで、2年を超えて消化されなかった場合は繰り越しができず消滅します。
4.勤怠管理の方法
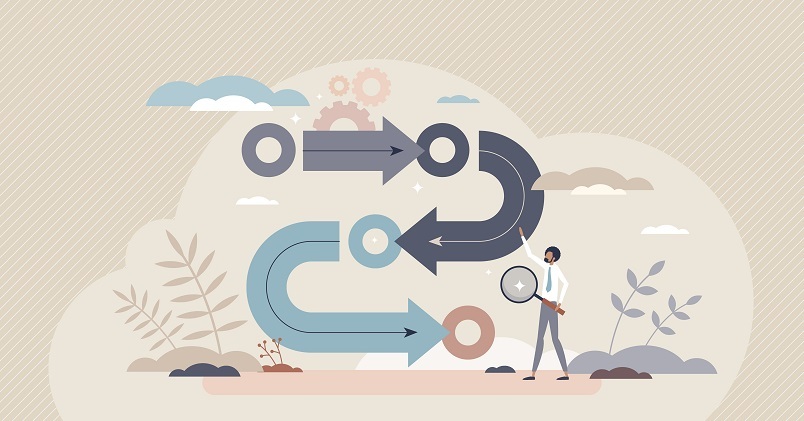
勤怠管理の主な方法は以下の4つです。
- ●手計算
- ●エクセル
- ●システム
- ●アプリ
企業規模や従業員数などから、適切な勤怠管理方法を選択することが重要です。
それぞれの具体的な方法とメリットデメリットをご紹介します。
1
手計算
従業員数が少なく、従業員の労働時間が固定されている場合は、手計算で勤怠管理を行うことが可能です。
タイムカードなどから勤務時間や残業時間をノートに転記し、月間の労働時間を集計します。アナログなやり方なので誰でもできますが、転記ミス・集計ミスがないかをチェックする必要がある点がデメリットと言えるでしょう。
2
エクセル
表計算ソフトのエクセルで勤怠管理する場合、集計作業が簡単に行えます。業務で利用する機会が多いソフトなので、使い方を教える必要もありません。
ただし、タイムカードからエクセルへ転記する際に入力ミスが発生したり、入力時に不正が発生したりする可能性があります。
3
システム
勤怠管理システムとは、勤怠管理業務を支援するソフトウェアです。
勤怠管理システムを利用すれば、以下のような機能が利用できます。
- ●出退勤データの入出力
- ●勤務シフト作成
- ●労働時間の自動集計
勤怠管理システムには、パソコンにインストールして利用するタイプ、インストールを必要とせずインターネットに接続して利用するクラウドタイプ、自社サーバーにシステムを構築するオンプレミスタイプの3種類があり、無料で利用できるものもあります。
4
アプリ
勤怠管理アプリとは、スマホやタブレット端末を利用して勤怠管理を行うアプリです。
アプリ単体で勤怠管理を行うタイプと、勤怠管理システムと連動しているタイプの2種類があります。テレワークを行っている従業員がいる場合は、勤怠管理アプリの導入を検討しましょう。
5.勤怠管理の注意点
勤怠管理で注意が必要なケースが雇用形態・勤務環境などによって変わってきます。主な注意するケースは、以下の5つです。
- ●パート・アルバイトの場合
- ●テレワークの場合
- ●変動労働時間制の場合
- ●みなし労働時間制の場合
- ●扶養控除範囲内に収める場合
順番に解説していきます。
1
パート・アルバイトの場合
パート・アルバイトは勤務日や勤務時間、休憩時間が一人ひとり異なるケースが多く、計画していた勤務時間を変更することもあります。事前にシフト表を作成し、勤務時間や休憩時間を正確に把握することが重要です。
2
テレワークの場合
テレワークの場合は実際に働いている姿が目に見えず、タイムカードやICカードなどで就業時間を確認することができません。
始業・終業時刻や休憩時間、残業時間といった客観的なデータをどうやって記録するかが問題となります。
始業・終業時にWEB会議システムで報告させる、クラウドツールなどで作業状況を監視するといった方法が取られることもあるようです。
テレワークでは自己申告が基本となるため、不正が発生しない仕組み作りが必要になります。
3
変動労働時間制の場合
変動労働時間制を採用している場合は月ごとに休日日数と所定労働時間が異なるため、労働時間を月単位だけでなく年単位でも管理する必要があります。
変動労働時間制では、所定労働時間内であれば、1日の労働時間が法定労働時間を超えても残業代は発生しません。ただし、所定労働時間を超えて残業させれば時間外手当が発生します。
法定労働時間と所定労働時間の両面から実際の勤務時間と照らし合わせ、残業なのか、休日出勤なのかを判断し、正確な勤怠管理を行いましょう。
4
みなし労働時間制の場合
みなし労働時間制とは、実際の労働時間にかかわりなく、所定労働時間を労働時間とみなす制度です。外回りの営業などの「事業場外みなし労働時間制」、弁護士などの特定業務に適用される「専門業務型裁量労働制」、企画や立案、調査、分析業務に就いている労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」の3種類があります。
みなし労働時間制においても所定労働時間が法定労働時間を超えていれば残業となり時間外手当が発生し、休日に出勤させれば休日手当も発生します。
みなし労働時間制だからといって勤怠管理が不要なわけではありません。
5
扶養控除範囲内に納める場合
従業員が配偶者扶養控除の範囲内で働くことを希望している場合、収入が扶養控除範囲内に納まるように勤務時間を管理することをおすすめします。
勤務時間や勤務日数を従業員が管理することで大まかな収入をコントロールすることは可能ですが、収入が扶養控除範囲ギリギリで働いている場合、数時間の残業でも扶養から外れてしまうケースもあるでしょう。
従業員が安心して扶養控除内で働くためには、企業側が従業員と勤務状況を共有し、適切に勤怠管理することが重要です。
6.まとめ 勤怠管理ならクラウド型サービスの導入がおすすめ
勤怠管理を行う上では、さまざまな雇用形態への対応と、注意点に対しての対策が必要です。
そこで、おススメなのが、システム・アプリをブラウザ上で利用できるようにしているクラウド型サービスの導入を検討されるのがおススメです。
手書きの勤務シフト表や表計算ソフトなどによるアナログな勤怠管理より業務上の負担が少なく、ソフトをパソコンにインストールする手間もかかりません。
NTT東日本が提供する「KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート」では、勤怠管理に欠かせないさまざまな機能が利用できます。
- ●勤務状況が目視できない場合でも勤怠状況をリアルタイムで把握できる
- ●日々打刻されたデータを就業ルールに沿ってリアルタイムに集計
- ●「時間外労働の上限規制」や「有給休暇5日以上取得義務」に対応
- 社外で働く従業員の勤務状況が把握できない、勤務時間の入力や集計の負担を軽減したい・効率化したい方におススメです。
- 無料体験もできますので、是非お気軽に以下のリンクより無料体験をお申し込みください。
-
勤怠管理ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

-
勤怠管理 アプリ
 スマホで使える勤怠管理アプリのすすめ
スマホで使える勤怠管理アプリのすすめこの記事では、勤怠管理アプリとは何か、勤怠管理アプリを導入するメリット・デメリット、勤怠管理アプリの選び方、おすすめの勤怠管理アプリをご紹介します。
勤怠管理アプリとは、スマホやタブレットでの打刻に対応した勤怠管理システムです。
従業員が私用のスマホに勤怠管理アプリをインストールすることで、テレワーク中や出張などで社外にいる場合でも打刻が行えます。 -
勤怠管理 クラウド
 クラウドタイプの勤怠管理システムを解説!【少人数・中小企業】
クラウドタイプの勤怠管理システムを解説!【少人数・中小企業】この記事では、クラウドタイプの勤怠管理システムの特徴や導入するメリット・デメリット、おすすめのクラウドタイプの勤怠管理システムを紹介します。
クラウドタイプの勤怠管理システムとは、オンライン上で勤怠管理が行えるシステムです。ソフトをパソコンにインストールしたり自社サーバーにシステムを構築したりする必要がないので、テレワークや社外営業の従業員が多い中小企業におすすめです。
-
勤怠管理 エクセル
 エクセルで勤怠管理表を自作する方法を解説
エクセルで勤怠管理表を自作する方法を解説関数かマクロを活用することでエクセルで勤怠管理表を作成できます。関数・マクロが設定済みのテンプレートなら、専門知識がなくてもエクセルの勤怠管理が可能です。ただし、従業員の打刻には別に対応する必要があり、就業規則や法的な知識も必要になります。
-
勤怠管理 システム
 勤怠管理システムとは?種類や機能、導入するメリット・デメリット、選び方を解説
勤怠管理システムとは?種類や機能、導入するメリット・デメリット、選び方を解説勤怠管理システムとは、勤怠管理に関する業務をサポートするシステムです。導入方法や料金、機能などさまざまな違いがあります。この記事では、勤怠管理システムとは何か、利用できる機能、導入するメリット・デメリット、自社に合った選び方を解説しています。
-
勤怠管理 無料
 勤怠管理を無料で行う方法と無料の勤怠管理システムの課題を解説
勤怠管理を無料で行う方法と無料の勤怠管理システムの課題を解説無料の勤怠管理システムは、有料のものと比べると利用人数や機能、データ保存期間・容量、サポートに制限があります。使い方によっては実質的にデメリットがないこともあるため、自社の環境・目的を確認した上で導入するようにしましょう。