確定申告に必要な提出書類をわかりやすく解説!
-
2023.3.14 (火)Posted by 北森 雅雄

「確定申告の際に提出する書類」がわからないと悩まれていませんか。
確定申告書をする際には所得を証明する書類を準備しなければならないなど、面倒な準備が付き物です。
オンラインで確定申告ができる「e-tax」では提出書類の準備を簡略化できるというメリットがあります。
そこで本記事では確定申告書をする際に必要な書類の一覧についてまとめました。
e-taxで確定申告をする際の手続きについても紹介するので、「確定申告で何の書類を準備すればいいのかわからない」という場合に参考にしてください。
目次:
1.確定申告書に必要な提出書類

確定申告をする際は税金の計算が正しいことを証明するためにいくつか書類を添付する必要があります。
具体的に提出する書類として、以下の書類を税務署へ提出します。
- ●収入を証明する書類(源泉徴収票の原本)
- ●医療費などの控除を証明する書類(医療費や社会保険料などの控除を受ける場合)
収入を証明する書類として、会社から発行される源泉徴収票などを添付します。
医療費や社会保険料を支払っている場合、所得から控除して税金の計算を有利にできます。その際に控除を証明するための証明書が医療機関や保険会社から発行されるので、書類を添付する必要があります。
|
【確定申告に必要な提出書類】 ・給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本) |
1
確定申告の流れ
確定申告の手続きは「確定申告書」を準備し、必要な提出書類を準備して税務署へ提出するという流れです。
確定申告書には住所や氏名など基本情報のほか、所得金額や納税額といった情報を記入します。
確定申告の提出方法は税務署へ持参あるいは郵送するほか、e-taxを使ってオンライン上で申告する方法があります。
2
書類の添付方法
郵送で確定申告書を提出する場合、「添付書類台紙」に提出書類を貼り付けます。
台紙にはのりしろがプリントされているので、のり付けして書類を添付しましょう。
3
確定申告書Aと確定申告書Bの違い
確定申告の際には「確定申告書A」と「確定申告書B」を選択します。サラリーマンなどの給与所得者で給与以外の収入がない場合は確定申告書Aを選びましょう。
両者には取り扱える所得に違いがあります。一般的に、給与所得者であるサラリーマンは確定申告書Aを提出します。副業をしている方は事業所得を得ているため、確定申告書Bを提出します。
| 書類の種類 | 対象となる人 | 取り扱える所得 |
| 確定申告書A | 会社員など給料を貰っているサラリーマンなど | 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得 |
| 確定申告書B | 個人事業主など | 全ての所得 |
2.確定申告をする際の注意点とよくある質問
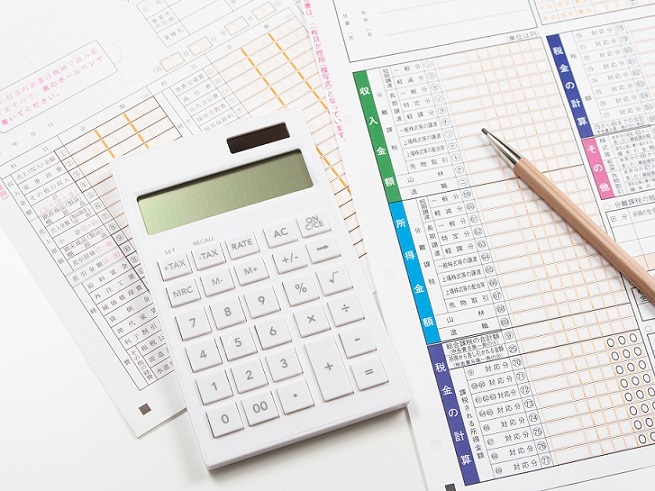
確定申告をする際にこのような悩みはないでしょうか?ここでは、確定申告をする際に気になる疑問点について回答していきます。
- Q.会社員も確定申告が必要?
- Q.原本はコピーでも大丈夫?
- Q.確定申告の期限はいつ?
確定申告は全国で毎年2,000万人を超える納税者が確定申告をするため、税務署などの相談窓口は混雑します。
国税庁ではよくある問い合わせへの回答を掲載しているので、合わせて参考にしてください。
外部リンク:確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
1
会社員も確定申告が必要?
確定申告は1年間の所得を計算して税務署に申告するための手続きです。
全ての国民は納税の義務があるため、1年間の所得を正しく計算しなければなりません。しかし、会社員などの給与所得者は会社が代わりに税金の計算をしてくれるため自分で確定申告をする必要がありません。
会社員など企業勤めのサラリーマンの場合、お勤めの会社が「年末調整」という処理をしてくれます。年末調整とは会社が年末に税金の過不足を精算してくれる制度のことです。
ただし、年末調整では計算しきれない税金については自分で確定申告をする必要があります。
年末調整で計算できない確定申告の例として、以下のケースが挙げられます。
|
<サラリーマンや会社員が確定申告をしなければならないケース> ・給与が2000万円を超える場合 |
2
原本はコピーでも大丈夫?
確定申告の添付書類は原本、すなわち最初に発行されたものを添付するべきでしょうか?
確定申告の提出書類には「原本でなければならないもの」と「コピー(写し)で構わないもの」の2種類があります。
以前は源泉徴収票の原本を提出する必要がありませんでしたが、2019年(平成31年)の税制改正によって源泉徴収票の提出は必要なくなりました。
保険料(生命保険料や社会保険料)の控除を受ける場合、原本の提出が求められます。会社員の方は年末調整で保険料の控除証明書類を提出しなければならないので、忘れずに準備しましょう。
マイナンバーカードなどの個人情報を証明する書類はコピー(写し)での提出が認められています。
なお、e-taxで確定申告をする場合はこれらの提出書類を省略、あるいはコピー(写し)での提出が認められる場合があります。
|
【確定申告あるいは年末調整で原本を提出する必要がある書類】 |
3
確定申告の提出期限はいつ?
確定申告の期間は例年2月15日から3月15日までとなっています。
税務署で確定申告をする場合、申告期限の終了間際は税務署が混雑する場合があるので期限に余裕を持って確定申告をしましょう。
なお、納税の期限は確定申告の提出期限と同日となっています。確定申告の提出と合わせて忘れずに納付してください。
3. e-taxは提出書類が不要?

e-taxは国税庁が提供しているインターネット上で確定申告ができるサービスです。
ユーザーである納税者にとってはe-taxを使うことで税務署の窓口に行かずとも確定申告が済ませられるというメリットがあります。
1
e-taxで省略できる提出書類
電子申告という形式であるため、一部の書類を電子ファイルで提出することができます。
e-taxで確定申告をすれば提出書類が一部不要となる場合があります。例えば、生命保険料控除の証明書等についてオンラインで送信することが認められています(発行者の電子署名が付与されている場合に限る)。
e-taxでは確定申告の提出について、第三者作成書類(保険料の控除証明書類など)は記載内容を転記することで証明書の提出を省略できます。
提出書類の可否については年度ごとに異なる場合があるので、国税庁のホームページなどで最新年度の情報を参考にしてください。
|
<添付を省略できる第三者作成書類(令和4年度)> ・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書 |
2
電子納税が可能
e-taxのメリットとして電子納税できることが挙げられます。
「ダイレクト納付」あるいは「インターネットバンキング」と連携することによって税金の納付ができます。
申告から納税までワンストップで納税を済ませられるため、余計な手間をかけずに確定申告の手続きを完了できるのです。
4.会社員の確定申告に必要な提出書類

先ほども紹介したように、会社員やサラリーマンは年末調整では計算できない所得について確定申告をする必要があります。
確定申告の際に提出する書類として、以下の書類を準備しておきましょう。
|
【会社員が確定申告に必要な書類】 |
1
本人確認書類
確定申告の際はマイナンバーカードなど本人確認書類のコピー(写し)を提出する必要があります。
e-taxで電子申告をする場合、マイナンバーカードを利用することで本人確認がとれるので本人確認書類の提出を省略可能です。
2
ふるさと納税で節税対策
ふるさと納税はサラリーマンに人気の節税対策です。
ふるさと納税とは地方への寄附金を所得から控除できる制度です。寄附した金額に応じてご当地の名産品など返礼品を受けられるため、節税と地方の支援ができる点が人気となっています。
ふるさと納税をした場合は所得から控除するために確定申告が必要です。ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合には確定申告は不要です。
5.個人事業主の確定申告に必要な提出書類

個人事業主やフリーランスは事業で得た所得(事業所得)を申告する必要があります。サラリーマンが20万円以上の副業収入がある場合も確定申告をしなければなりません。
個人事業主が確定申告をする場合に提出する書類はサラリーマンの場合と変わりません。個人事業主の場合は源泉徴収票の代わりに事業の収支がわかる書類を作成する必要があります。
|
【個人事業主が確定申告に必要な書類】 |
1
青色申告で所得控除を受けられる
個人事業主は青色申告をすることで最大65万円の所得控除を受けられるなど節税対策になります。
青色申告とは所得税を正しく納税するための制度です。青色申告では事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
2
個人事業主の節税対策
個人事業主は事業に使った経費を正しく記帳することで節税対策になります。
事業に発生した経費は所得から控除されるため、納税額を計算するうえで有利になるのです。
個人事業主は日ごろから会計ソフトを利用して帳簿をつけることで節税対策に繋がります。
6.確定申告なら「おまかせ はたラクサポート」がおすすめ!
確定申告をするなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。
freee会計 for おまかせ はたラクサポートは会計業務を自動化し、複雑な経理業務を簡略化します。
経費精算のペーパーレスにも対応しているため、電子帳簿保存への対応も可能です。
1
会計業務を自動化!
フリーランスや個人事業主にとって会計業務は専門的な知識が必要であり、億劫な業務と感じる方も多いでしょう。
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」では確定申告の手続きも簡単に進められます。〇×形式の質問に答えるだけで確定申告に必要な書類を作成できるため、複雑な会計の知識がなくても確定申告を完結できます。
2
リーズナブルな料金設定
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」では月額1,298円から導入できます。
クラウド型のツールであるため、インターネット環境さえあれば簡単に利用可能です。
以下は個人事業主やフリーランス向けの「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」の料金表です。
| プラン | 主な機能 | 初期費用 | 月額基本料 |
追加ID(1IDあたり) |
| スターター |
確定申告書の作成・出力 |
不要 |
1,298円/1IDまで |
ー |
| スタンダード |
確定申告書の作成・出力 |
不要 |
2,618円/3IDまで |
396円 |
(初期費用・月額利用料(個人事業主版))
3
安心のサポートサービス
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」では安心のサポートサービスで不明点を解消しながら利用できます。
導入にあたって不安な初期設定の方法などを万全にサポートします。
7.まとめ
確定申告をする際には所得額や所得控除を証明するために提出書類を準備しなければなりません。e-taxによる電子申告なら準備する提出書類を一部省略できます。
手早く確定申告を済ませるなら「おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。おまかせ はたラクサポートでは質問事項に回答するだけで簡単に確定申告の書類を準備できます。「どの提出書類を準備すればいいかわからない…」という場合にもスムーズに確定申告を済ませられます。
確定申告をする際は細かいルールを気にしなければならないため面倒に思うかもしれませんが、ツールを活用して面倒な確定申告を手早く済ませてしまいましょう。
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
