収入印紙はいくらから貼る必要がある?課税文書別に添付が必要な金額を解説!
-
. ()Posted by

「収入印紙の添付はいくらから必要?」
と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
課税文書をやり取りした際に、収入印紙の購入が必要になります。特に200円の収入印紙を利用する頻度が多いので、200円の収入印紙を購入できる場所を事前に把握しておきましょう。
当記事では、収入印紙を貼る必要性、収入印紙の購入が必要な課税文書の金額、収入印紙を購入できる場所、収入印紙の購入が不要な場合について解説します。
収入印紙をいくらから購入すればよいか理解できる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
1.収入印紙の添付はなぜ必要?

そもそも収入印紙を購入して、添付するのはなぜでしょうか。以下では収入印紙の必要性を解説します。
1
印紙税法上、課税文書は印紙税の納付が必要
印紙税法では、課税文書に対して印紙税の納付を求めています。印紙税法とは、契約書や領収書などの経済的な取引に対して課される税金です。この法律の中で、印紙税の納付が求められる20種類の課税文書を明記しています。
契約書や領収書などの課税文書を相手方とやり取りする場合に、印紙税の納付が必要になるのです。印紙税の納付方法はいくつかあり、その中の1つの手段として収入印紙の添付があります。
収入印紙を添付する場合、課税文書の好きな場所に収入印紙を添付して、割印をすることで納税したことになります。
好きな場所に収入印紙を添付してもよいといいつつ、一般的に添付される場所がありますので、よく利用する課税文書の通例は押さえておくとよいでしょう。
2
課税文書は20種類
課税文書には上述した通り20種類あります。例えば以下が課税文書に該当します。
- ●請負に関する契約書
- ●約束手形又は為替手形
- ●株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 など
上述の各課税文書のタイトルと手元の文書のタイトルが一致しないからといって、必ずしも課税文書に該当しないわけではない点に注意が必要です。各課税文書の定義からみて、手元の文書があてはまれば、タイトルが違っても課税文書として見做されます。
2.収入印紙はいくらから必要?
課税文書の場合、収入印紙の添付などにより印紙税の納付が必要です。では、収入印紙はいくらから購入が必要なのか、解説をします。
1
課税文書の種類により印紙税の納付額は異なる
- ●領収書に必要な収入印紙の金額
- ●契約書に必要な収入印紙の金額
領収書に必要な収入印紙の金額
領収書は印紙税法別表1 17号文書に該当します。17号文書では記載金額に対して以下の印紙税の納付を求めています。
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円~200万円以下 | 400円 |
| 200万円~300万円以下 | 600円 |
| 300万円~500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円~1,000万円以下 | 2,000円 |
| 1000万円~2,000万円以下 | 4,000円 |
| 2,000万円~3,000万円以下 | 6,000円 |
| 3,000万円~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円~1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円~2億円以下 | 40,000円 |
| 2億円~3億円以下 | 60,000円 |
| 3億円~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円~10億円 | 150,000円 |
| 金額記載のないもの | 200円 |
つまり、領収書の場合、50,000円を超える取引をした場合に200円の収入印紙の添付が必要になります。
契約書に必要な収入印紙の金額
- ●不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
- ●地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
- ●消費貸借に関する契約書
- ●運送に関する契約書
上述の契約書上に記載された金額に対して、納付が必要な印紙税額は以下の通りです。
| 契約金額 | 印紙税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円~50万円以下 | 400円 |
| 50万円~100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円~1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1000万円~5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円~1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円~5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円~10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円~50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円~ | 600,000円 |
| 金額記載のないもの | 200円 |
つまり、10,000円以上の契約書を作成する場合には200円~の収入印紙の購入が必要になります。
2
記載金額に消費税額は含めるのか
領収書や契約書上に記載された金額を元に印紙税の納付額が決定します。しかし、課税文書の中には、消費税が記載されている/いないケースがあります。
消費税を含むかどうかで、収入印紙を添付すべきかどうか(領収書であれば50,000円以上か以下か)の判断が異なります。以下では課税文書に消費税を含む場合と含まない場合について解説します。
課税文書に消費税が記載されている場合
課税文書に消費税額が記載されている場合、消費税額を抜いた金額で印紙税の納税金額を決定します。例えば、以下の場合の領収書は総額が50,000円以下になるので、印紙税の納付対象外と整理できるのです。
- ●53,000円(税抜き価格 48,182円 消費税額 4,818円)
- ●53,000円(うち消費税額4,818円)
- ●53,000円(税抜き価格 48,182円)
課税文書に消費税が記載されていない場合
課税文書に消費税額が明記されていない場合、消費税額を含む額を元に印紙税の納税金額を決定します。例えば、以下の場合の領収書は50,000円以上になるので、印紙税を納付する必要があるのです。
- ●53,000円(左記以外の記載はなし)
- ●53,000円(税込)
以上のように総額としては同一であっても、課税文書上の消費税の記載方法によって、印紙税の納付要否が変わります。したがって、収入印紙を購入する際には消費税の記載方法にも気を付けた方がよいです。
3.収入印紙はどこで買える?いくらから買える?

領収書であれば50,000円以上、契約書であれば10,000円以上の場合、印紙税の納付が必要になります。この時、多くの場合に収入印紙を添付するかと思いますが、収入印紙はどこで購入ができるのでしょうか。収入印紙を購入可能な以下の場所を例に解説をします。
- ●購入場所①:郵便局
- ●購入場所②:法務局
- ●購入場所③:コンビニ
購入場所①
郵便局
郵便局の場合、31種類あるほぼすべての収入印紙を購入できます。また、平日であれば9:00-17:00で購入が可能ですので、購入がしやすい点もメリットです。
一部の郵便局では、土日も空けている場合もあるほか、24時間営業の店舗もありますので、最寄りの郵便局の稼働状況を確認してみてください。
購入場所②
法務局
法務局の場合、31種類すべての収入印紙を購入可能です。法務局には登記などの際に訪れることもあるでしょうから、その際にまとめて必要分を購入すると効率的に対応ができるでしょう。
購入場所③
コンビニ
コンビニの場合、24時間営業している上に、施設数も多いため、収入印紙を購入しやすい点がメリットです。
ただし、多くのコンビニでは200円の収入印紙のみを取り扱っているため、200円以外の収入印紙を購入する場合には郵便局など他施設をご利用ください。
また、コンビニの場合、各社でポイント制度を実施しています。このポイントを利用することで間接的にクレジット払いにより収入印紙を購入できます。少しでも節約して収入印紙を購入したい場合にはポイント活用もご検討ください。
4.収入印紙の購入が不要な場合がある
課税文書であっても、そもそも印紙税を納付しなくてもよい場合があります。以下では、印紙税を納付しなくても良いケースを解説します。
- ●場合①:クレジットカード払いをする場合
- ●場合②:電子契約などを利用する場合
場合①
クレジットカード払いをする場合
印紙税の納付対象は、金銭の受け渡しをする取引です。クレジットカード払いをする場合、金銭の受け渡しはクレジットカード会社から店舗という形式をとりますので、印紙税の納付対象外になります。
したがって、個人でクレジット決済をしていれば、どれだけ高価な買い物をしたとしても、印紙税を納付する必要はないのです。
場合②
電子契約などを利用する場合
印紙税法上、印紙税を納付する対象を課税文書としています。課税文書とは、”紙”を想定しているため、電子契約や電子領収書のような電子文書は想定していないのです。したがって、電子契約などの電子文書を利用してやり取りをすれば、印紙税は非課税になります。
実際に、国会や国税庁から出ているFAQ上でも電子文書は非課税である旨を確認できますので、安心して電子文書をご利用ください。
電子契約など電子文書を利用する場合には、専用ツールの利用がおすすめです。電子契約の場合、電子契約サービスを利用するとよいでしょう。
電子契約サービスを利用した場合、印紙税が非課税になるだけでなく、契約業務そのものを効率化し、コスト削減を実現できますので、投資対効果も十分です。
5.まとめ 収入印紙はいくらから必要か把握しておこう
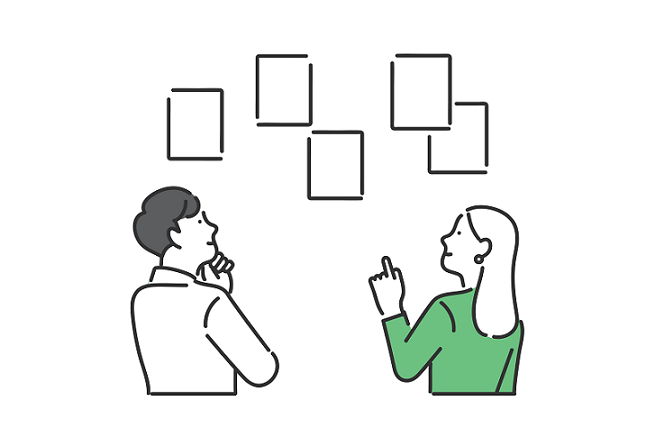
契約書や領収書などのよく利用する課税文書については、いくらから収入印紙の添付が必要か確認しておきましょう。もし、収入印紙を添付していない旨を国税調査時に指摘された場合、ペナルティが課される場合もあります。
また、電子契約などの電子文書を利用すると印紙税そのものを非課税にできます。電子契約サービスなどを利用すると業務効率化、コスト削減も期待できますので、導入がおすすめです。
NTT東日本では印紙税法にも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
