【2023年最新】請求書発行ソフトの選び方とは?おすすめ4選も紹介!
-
2024.4.05 (金)Posted by 北森 雅雄
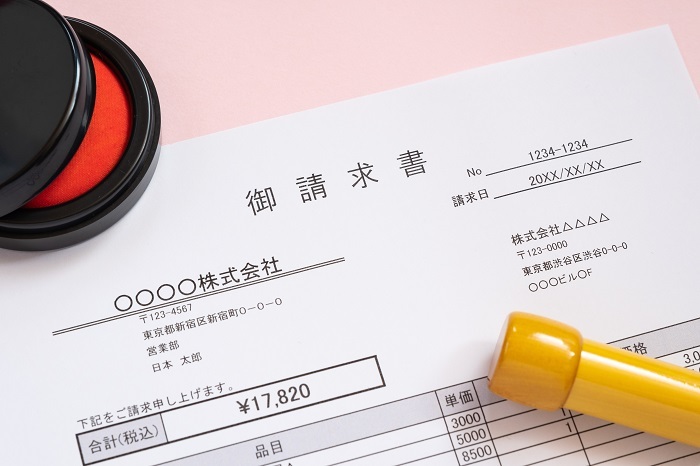
電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の施行などの影響により、請求書発行システムの導入を検討している企業が増えています。請求書発行システムは現在たくさん存在しますが、自社に必要な機能が搭載されているかを検討して、活用することが重要です。
請求書発行ソフトがなぜ必要なのか、請求書発行ソフトの選択方法、おすすめの請求書発行ソフト3選を紹介します。
1.請求書発行ソフトとは何か
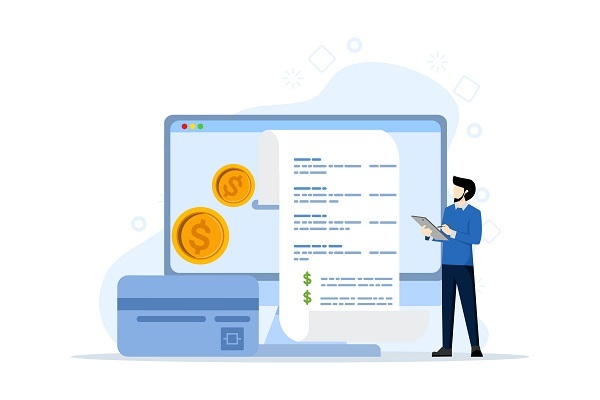
請求書発行ソフトとは、電子請求書の発行・送付を効率化するソフトウェアです。従来紙で行っていた請求業務を電子化することで、業務効率化や工数、コスト削減を見込むことが可能です。
2023年8月現在では、請求書発行ソフトはクラウドが主流となっていますが、一部オンプレミスのソフトもありますので、自社に適した形態のソフトを選択するようにしましょう。
請求書発行ソフトで実現できる業務として例えば、以下の業務がありますので、自社がどのような業務を電子化して、効率化を目指したいのか明らかにする点が重要です。
- ●請求書をはじめ、納品書や明細書の電子発行
- ●請求書上への自社や取引先情報の自動記入
- ●作成した請求書から納品書などへの自動変換
- ●紙請求書の発送代行
- ●請求金額に基づいて分析レポートの自動生成
- ●請求・会計ソフトとのシステム連携
- ●口座連携による入金消込機能
2.請求書発行ソフトが求められる理由

株式会社グローバルインフォメーションによる市場調査「電子請求書の世界市場 2023-2027」によれば、請求書発行ソフト市場は2021年~2026年の間に年間平均21.43%で世界市場が成長すると想定されています。
この勢いは日本市場も同様の水準です。以下ではなぜ、電子請求書市場(請求書発行ソフト市場)が伸びているのか、理由を解説します。
1
電子帳簿保存法対応で発行・保存業務の工数が増えている
日本においては2022年1月に電子帳簿保存法が改正され、メールなど電子取引した国税関係書類は電子保存が義務化されました。請求書は税法上で国税関係書類に該当しますので、電子請求書としてやり取りする場合には、電子帳簿保存法に基づいた保存が必要です。
この電子帳簿保存法に基づいて電子請求書を保存しようと考えると、主要三項目(請求年月日、請求先名、請求金額)による検索、タイムスタンプの付与など、いくつか対応すべき事項があります。
これらの対応事項により、電子請求書の発行・保存業務の工数が2022年1月以降、劇的に増えているのです。※正確には電子帳簿保存法の電子保存義務化対応は2024年1月から
このような背景があり、電子請求書の発行・保存業務に対する効率化需要が出てきているため、請求書発行ソフト市場は拡大傾向にあります。
2
インボイス制度対応でバックオフィスの負荷が増えている
2023年10月に施行されるインボイス制度により、適格請求書の適正保存が必要になります。
2023年10月以降、例えば受領した適格請求書が適格請求書発行事業者によって発行されているか、適格請求書としての要件を満たしているかを確認する必要があるのです。この対応によりバックオフィス業務の負荷は大きく増加すると想定されています。
既存の人員でインボイス制度対応による業務負荷増加を吸収しようと考えると、キャパオーバーしてしまうことが分かっているため、バックオフィス業務の効率化に乗り出す企業が多いです。
このような背景があり、電子請求書の発行・保存業務に対する効率化需要が出てきているため、請求書発行ソフト市場は拡大傾向にあります。
3.請求書発行ソフトの選び方

請求書発行ソフトの選び方はいくつかありますが、代表的な評価ポイントは以下の通りです。
- ●選び方①:業務形態に適したソフト
- ●選び方②:自社利用のシステムとの連携可否
- ●選び方③:セキュリティへの機能充足
- ●選び方④:法律対応への機能充足
- ●選び方⑤:取引先が利用する画面のUI
選び方①
業務形態に適したソフト
自社の業務形態に適した請求書発行・保存ができるか確認が必要です。例えば、コンサル企業など、案件単位で取引するケースが多い場合、案件単位で請求書含む帳票類の保存をしたいニーズがあります。
同一の企業内に複数の案件がある場合、案件別に帳票を参照できなければ、集計業務が煩雑化するだけでなく、帳票の検索自体も遅滞し非効率になるでしょう。
案件単位で管理するために、請求書上に案件Noを付与し検索可能な状態にできるなど、業務形態に適したソフト選びが重要です。
選び方②
自社利用のシステムとの連携可否
導入予定の請求書発行ソフトが自社の請求システムや会計システムと連携できるかが確認ポイントです。
電子請求書を作成する場合、請求情報が必要になります。この点、例えば請求書発行ソフトと請求システムが密連携している場合には、開発することなく、請求情報を請求書発行ソフトで作成した電子請求書上に反映させることが可能です。
また、APIで直接連携できない場合にはCSVファイルを請求書発行ソフトにインポートして対応できるかについて確認が必要になります。
いずれにしろ、請求書発行ソフトにどのように請求システムや会計システム上から請求情報を連携するかによって、業務効率が大きく変わりますので確認しておきましょう。
選び方③
セキュリティへの機能充足
多くの請求書発行ソフトはクラウド上で稼働します。クラウド上で自社が要求するセキュリティ水準を満たすことができるかが確認ポイントになるでしょう。
データの保存先や暗号化状況、二要素認証やIP制御の可否など確認事項は多数ありますので、事前にセキュリティチェックシートを作成してベンダーに回答を求めるとよいです。
監査法人による内部統制監査やシステム監査時には、クラウドシステム上でのパスワード管理(複雑性など)が監査対象になる場合もありますので、情報システム部門だけでなく、内部統制室も含めて検討が必要になります。
選び方④
法律対応への機能充足
請求書は税法上の国税関係書類に該当しますので、各種税法に基づいた保存が必要です。例えば、法人税法に基づいた7年以上の保存、電子帳簿保存法 電子取引要件に基づいたタイムスタンプ付与などの真実性確保、主要三項目による検索などが保存時に求められています。
このような法律上で求められる各要件に対して、請求書発行ソフト上で機能的に満たすことが可能か確認が必要です。
例えば電子帳簿保存法対応をしている目安として、JIIMA認証の取得有無があります。このように各法律に対応している目安として認証などを参考にすると、システム選定がしやすくなりますので、ぜひ参考にしてください。
選び方⑤
取引先が利用する画面のUI
請求書発行ソフトを利用する場合、多くのケースで相手方にアカウントを払い出し、専用画面から受領した電子請求書を確認する運用になります。
この時、相手方が利用する専用画面のUIが使いやすいか、滞りなく請求業務を完結できるかが確認ポイントです。UIが使いづらく請求業務に躓くと、質問を受けるのは請求書発行ソフトを導入した企業自身です。
相手方が利用する専用画面の使いやすさが、直接請求業務の効率化につながると考えてもよいでしょう。
4.おすすめの請求書発行ソフト
2022年1月に改正された電子帳簿保存法や2023年10月に施行されるインボイス制度など、各種税法に対応した機能が搭載済みです。
また、法対応だけでなくその先の業務効率化を見据えてAIOCRの活用をすることができる点も魅力的でしょう。AIOCRを利用することで、紙請求書を検索可能な状態で自動電子化できます。
出典:BtoBプラットフォーム請求書公式サイト 2023年8月時点の情報です。
5.まとめ 自社に適した請求書発行ソフトを選ぼう
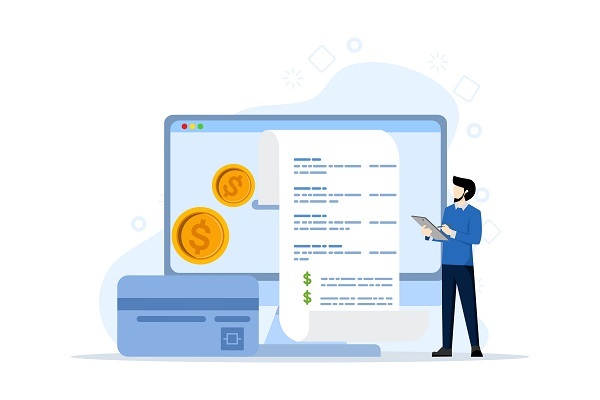
市場に多数ある請求書発行ソフトの中から自社に適した請求書発行ソフトを選択する際、重要になるのは請求書発行ソフトに対して何を求めるのか要件が明確になっていることです。
請求書発行ソフトを選択する際には法要件への適応や外部システム連携の可否など、当記事で紹介したポイントも参考にしながら、要件を明確にする段階から進めましょう。
NTT東日本では、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。
ぜひ一度ご検討ください。
-
電子請求書ならサービスとサポートをセットに!
 電子請求書 無料体験申込フォーム
電子請求書 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子請求書をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。

