電子請求書の受け取り側におけるメリット・デメリットとは?保存方法含めて解説
-
2023.6.29 (木)Posted by 北森 雅雄

「電子請求書を利用する際、受け取り側のデメリットはある?」
「電子請求書の受け取り側における注意点を知りたい」
とお考えではありませんか。
電子請求書配信システムなどを利用して電子請求書を授受すると業務効率の上昇を期待できます。一方で請求書を電子的にやり取りすると電子帳簿保存法への対応や電子請求書のシステム上における長期保存が必要になる点などに注意が必要です。
当記事では受け取り側において、電子請求書を利用する場合のメリット・デメリット、受け取り側が電子請求書を利用する際の注意点までをご紹介します。
電子請求書を利用する際、受け取り側が検討すべき論点が網羅されていますので、ぜひ最後までお読みください。
1.電子請求書とは電子的受け取った請求書のこと

そもそも、電子請求書とは何でしょうか。電子請求書とは電子的にやり取りした請求書全般を指す言葉です。例えば、以下のような手段によるものは全て電子請求書に該当します。
- ●電子請求書をメールに添付して授受する
- ●Webサイト上から電子請求書をダウンロードする
- ●クラウドサービス上で電子請求書をやり取りする など
電子請求書と一言でいっても、授受方法は多数考えられるため、自社で利用している、または、予定の授受方法に基づいて業務効率化などを検討することが重要です。
2.電子請求書のメリットは大きいが、受け取り側の負担もある
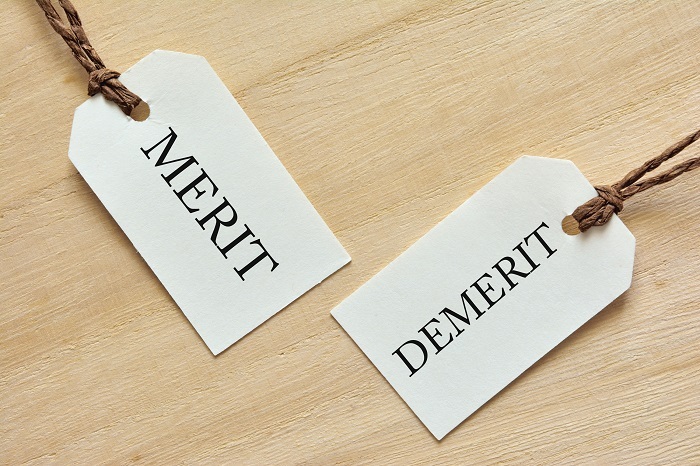
電子請求書を利用することで、請求業務の効率化を期待できます。なぜなら、紙の請求書を送付・受領するために要していた時間を大幅に効率化できるからです。したがって、電子請求書を利用した場合のメリットは大きいとも判断できます。
一方で電子請求書を利用した場合には、手段を紙から電子に変更したがためのデメリットもありますので注意ください。
1
電子請求書を利用する受け取り側のメリット
受け取り側が電子請求書を利用する場合のメリットは大きく以下の2点です。
- ●請求業務のリードタイム短縮
- ●請求情報の利活用が可能
請求業務のリードタイム短縮
紙の請求書を受領した場合、受け取り側で開封し請求書の確認作業が必要になります。この点、電子請求書であれば、電子上で確認ができるうえに、出社も必要でないことから、請求業務にかかるリードタイムの短縮が期待できるのです。
特に2023年10月以降はインボイス制度の施行によって、請求業務上での確認作業が増えます。したがって、確認作業を効率化できる意味で電子請求書の利用は受け取り側にとって、メリットが大きいです。
請求情報の利活用が可能
請求書を電子で受領することで、請求書データの活用を推進できます。例えば、請求書PDF上の文字情報に対してOCRを利用することでデータ化し、会計・販売管理システムに連携するなどの利活用が想定できるでしょう。
また、インボイス制度が施行された後、適格請求書上の事業者番号突合が業務として新たに追加されます。この突合作業も、事業者番号をデータ化さえできれば、システム上で自動化することが可能です。
このように業務の効率化の前提として、請求書情報のデータ化がありますので、データ利活用の意味で電子請求書の受領はメリットが大きいです。
2
電子請求書を利用する受け取り側のデメリット
請求業務のリードタイム短縮などメリットが受け取り側にとってメリットの大きな電子請求書ですが、一方でデメリットも存在します。電子請求書の受け取り側におけるデメリットは大きく以下2点です。
- ●電子帳簿保存法対応が必要
- ●社員教育が必要
電子帳簿保存法対応が必要
電子請求書をメールなどで受け取った場合、受け取り側は電子帳簿保存法 電子取引要件を満たして保存する必要があります。もし、要件を満たさずに保存をしている旨を国税調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しなどのリスクがありますので注意が必要です。
電子帳簿保存法は2022年1月に改正法が施行され、2024年1月にも法改正が予定されていますので、法要件を理解した上で対応が求められています。
社員教育が必要
電子請求書を電子帳簿保存法などの各種税法に基づいて保存しようとする場合、社員教育が必要です。紙の請求書で管理していた場合でも社員教育が必要でしたが、電子でやり取りする場合においても例えば以下のように電子向けに社員教育方法を検討する必要があります。
- ●電子請求書をワークフローに添付する際の入力ルールを周知する
- ●電子請求書を格納する監視フォルダを案内する
- ●電子請求書へのファイル名リネームの命名規則を周知する など
3.受け取り側が注意すべきポイント

電子請求書の受け取り側として特に注意すべきポイントがあります。以下では代表的な注意点をご紹介します。
1
受領した電子請求書は原則的に印刷して保管してはいけない
2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、電子的に受領した電子請求書は電子保存が義務化されました。※宥恕措置により2024年1月までに電子保存をすればよいです。
2021年12月以前までは電子請求書を紙出力して保存していた企業が多数ですが、この紙保存措置が今後認められない点に注意してください。
また、宥恕措置により2024年1月まで紙保存措置廃止の対応期限が伸びていますが、2024年1月までに紙出力して保存した文書は紙を原本として長期保存する必要があります。
電子請求書を一度紙に出力して保存し、再度紙を電子化することは認められていない点にも注意が必要です。
2
電子帳簿保存法 電子取引要件を満たして保存する
電子請求書は電子帳簿保存法 電子取引要件に基づいた保存が必要です。電子帳簿保存法 電子取引要件では大きく以下2つの要件を満たして電子請求書の保存を求めています。
- ●要件①:可視性
- ●要件②:真実性
要件①:可視性
可視性とは、特定の電子請求書を整然、明瞭かつ速やかに提示することを求める要件です。可視性を構成する要件はいくつかありますが、特徴的な要件は検索性要件です。
検索性要件では税務調査時にダウンロードの求めに応じられるのであれば、以下主要3項目により検索ができればよいとされています。
- ●請求年月日
- ●取引先名
- ●請求金額
もしダウンロードの求めに応じられない場合には追加で以下により検索ができる必要があります。
- ●範囲検索
- ●複数条件検索
要件②:真実性
真実性とは、受け取り側が電子請求書を受領した後に電子請求書が改ざんされていないことを証明する要件です。電子帳簿保存法 電子取引要件では以下3つの手段の内、自社に都合のよい方法を一つ選択して対応できるとされています。
- 1.タイムスタンプ付き電子請求書の受領、または、タイムスタンプの付与
- 2.訂正削除が考慮されたシステムの利用、または、訂正削除ができないシステムの利用
- 3.訂正削除の防止に関する事務処理規程の作成および運用
一度ダウンロードした電子請求書の真実性担保には注意が必要
電子請求書を相手方が提示したWebサイト上から受け取り側がダウンロードして取得する場合が多いです。
この場合、上記で提示した「訂正削除が考慮されたシステムの利用、または、訂正削除ができないシステムの利用」による真実性の確保ができない点に注意ください。
|
問4 |
つまり、Webサイトに限らず、何かしらから一度ダウンロードした電子請求書は改ざんが可能であるため、「訂正削除が考慮されたシステムの利用、または、訂正削除ができないシステムの利用」による真実性の確保ができないとされているのです。
3
同一の請求書を紙と電子で受け取った場合、どちらを原本とするか決める
電子請求書と紙請求書の両方を受け取り側が受領する場合があります。この場合、書面を原本として保存して問題ありません。
|
問13 |
ただし、相手方との事前取り決め次第では、電子請求書を原本とすることも可能です。したがって、電子請求書と紙請求書のいずれを原本とするか、相手方と認識を併せる必要があるでしょう。
4.まとめ 電子請求書の受け取り側も電子帳簿保存法対応をしよう
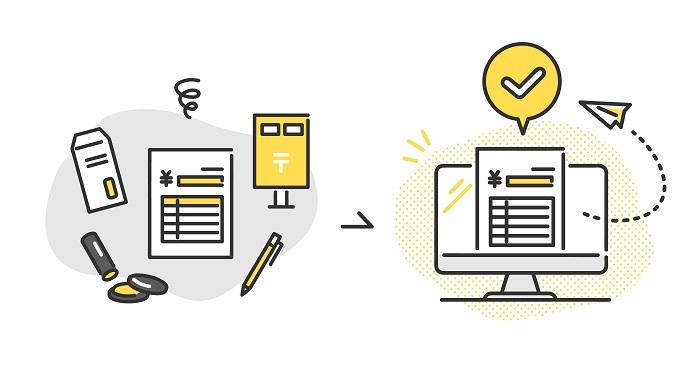
電子請求書の利用は受け取り側としても、バックオフィス業務の効率化の観点からするとメリットの大きな提案です。
一方で電子請求書を利用する場合、受け取り側も電子帳簿保存法などの各種税法への対応をする必要がある点に留意ください。
したがって、もし電子請求書を自社システムから発行し送付するのであれば、電子帳簿保存法などの法律に対応したシステムを選ぶようにしましょう。
NTT東日本では、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ一度ご検討ください。
-
クラウド電子請求書ならサービスとサポートをセットに!
 クラウド電子請求書 無料体験申込フォーム
クラウド電子請求書 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
