人気設備「宅配ボックス」の設置で空室対策と社会貢献を
-
2023.1.19 (木)Posted by
■人気設備の宅配ボックス
「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても入居が決まる」ランキングで、単身物件で4位、ファミリー物件で6位の宅配ボックス。今回は、入居者獲得に有効な宅配ボックスの導入について調べてみます。

■「通販」といえば 今や、ネット販売です。
かつて、通販と言うと「カタログ販売」が主流でした。「千歳会」「ニッセン」といった通販カタログを見て、ほしい商品をハガキなどで送る。テレビ通販の「ジャパネットたかた」が新しい流れを起こし、企業ではアスクル、子供関連ではベネッセなどが有名でした。 こうした日本企業の通販の歴史をひっくり返したのがAmazonです。2009年、アマゾンの通販売上高が2510億円となり、日本の「通販・通教売上ランキング」で一位となりました。(通販新聞社調べ) 以来、新型コロナ感染拡大もあり、「ネットで物を買って自宅に届けてもらう」という行為はかなり普通になりました。いわゆる「ニューノーマル」の一環と言えます。

■配送員にとって、再配達の負荷が年々あがる。
ネット通販が増えて、激務となっているのは、配達の問題です。2016年には、配達員が荷物や台車を何度も放り投げる様子を捉えた動画がネット上に公開され、大きな社会問題となりました。動画そのものは、「なんて不届きな」という声もありましたが「たしかにあまりに可愛そうだ」という共感を呼んだのです。
不在届が社会問題化し、配送会社の過重労働も社会問題になりました。2017年には、配送会社に勤めている人たちからも、春闘で荷物の取扱量を制限してほしいと声があがり、人手不足なども大きな問題となりました。
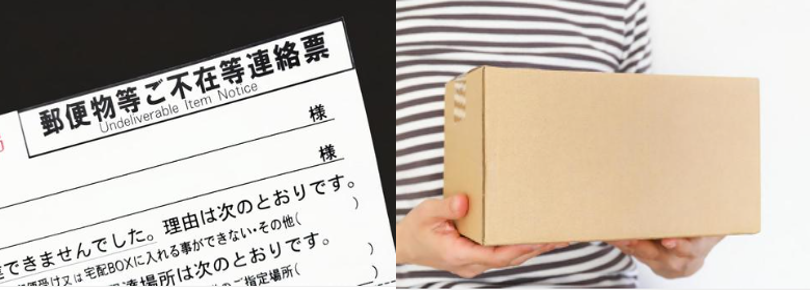
■2018年、官民共同で 解決策を探求。
こうした問題は社会問題となりましたので、国も乗り出します。宅配業者のドライバーの負担が増え、労働力不足が深刻化するなか、それを改善する為、「宅配事業者(ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便など)」と「EC事業者(Amazon、楽天など)」そして「国(経済産業省、国土交通省、環境省)」の三者が、「宅配事業とEC事業の生産性向上連絡会」を設置されたのです。
そこで議論され、今後進めていくことになったのが、「宅配物の受け取り方法の多様化」という事でした。
つまり、社会問題を解決していくためにも、変化していく社会に対応する為にも「宅配ボックス」という設備は、強力な国家施策のひとつとなっているのです。

■宅配ボックスの普及は、社会貢献
宅配ボックスがあれば、「急な用事でも配達があるから出かけられない」「仕事で留守にしていたら受け取れなかった」「再配達を依頼するのが面倒」「再配達を手配してから、保育園から呼び出しがあり、子供のお迎えに行ったら、また不在通知になった」といった混乱が避けられます。
また、「お風呂に入っていた」「トイレに入っていた」「赤ちゃんが泣き止まない」といった、在宅で手が離せないときにも便利です。
女性の単身の方は「ドアを開けると部屋が丸見えになるので、配達員さんに見られたくないので、宅配ボックスに入れてもらう」といった使い方をしていることもあります。「不在がちだが、〇時にはほしい」といった方も、宅配ボックスがあれば安心というわけです。

■ネットに接続された宅配ボックスは 人気が高い
昨今は、インターネット無料物件も増えており、建物にネットワークがつながっているという先進的な物件も出ています。こうした物件では、「宅配ボックスに荷物が届くと、ネットで居住者のメールに連絡が届く」という物件もあります。
また、エントランスのモニターがネットにつながっていて、エントランス解除時に「宅配ボックスに荷物が届いています」といったメッセージが出る物件もあります。
また、「クリーニングを宅配ボックスで受け渡しする」というサービスもあります。宅配ボックスに衣類を入れておくと、クリーニング屋さんが集荷してくれます。そして、クリーニング済みの衣類を宅配ボックスに届けてくれるというサービスです。クリーニング屋さんの営業時間内に届けられないビジネスマンにとっては、便利なサービスですから、当然、空室対策にもかなり有効です。

■ネット対応している宅配ボックスは長期利用なども監視できる
こうした便利な宅配ボックスですが、「いつまでも荷物をとり出さない」といったことも問題になっています。なかには、配達業者さんと同じように、「宅配ボックスに自分の荷物を保管しておく」といった困った使い方をする人もいます。
そこで、ネットの登場です。ネットワークで長期利用し続けている人を把握し、その人に「荷物を受け取ってください」「倉庫代わりに使わないでください」と管理会社から注意喚起をする事が可能です。こうした設備の投入は、オーナーや管理会社からも喜ばれています。
なにも入れないで入居者が勝手に利用していたなどの不正利用もネットにつながっていれば防げます。

■Amazonは、「置き配」にも着手
再配達を抑制するために諸外国で有効な打ち手とされているのは「宅配ボックス」だけではありません。不在でも、玄関先に置いて行けば、再配達はなくなる、という事で、Amazonは2019年10月に「置き配」を実証実験しました。2020年3月からは標準の配達方法を「置き配」にするという大胆な戦略転換を行っています。30都道府県で、初期設定を「玄関先に配達する置き配」として、顧客から指定がない場合は留守、在宅問わず、玄関先に商品を届けています。
しかし、この置き配を阻んでいるのは、「オートロック」です。日本では分譲マンションも賃貸物件もオートロックを設置している物件が多く、置き配だけでは再配達の抑制とはならないのです。
昨今では、Amazonは、オートロックを解除するためのシステムの無償提供や、仮に置き配で盗難に遭遇した場合の補償対応もして、こうした社会情勢に対応しています。
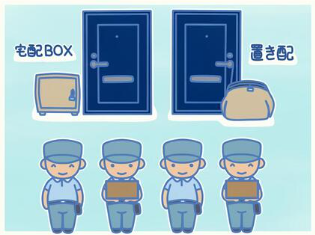
■コロナ禍で伸びる宅配需要。宅配ボックス設置は、まさに国策
新型コロナ感染で、ますますネット通販の利用は増え、ヤマト運輸・佐川急便・日本郵便の主要3社の荷物の取り扱い件数は、2019年39億9,600万個→2020年44億1,300万個→2021年45億9,400万個と増えています。とはいえ、配送員さんの激務は続いており、再配達の抑制は必要です。再配達はそれだけガソリン代などのコストがかかり、自然環境にも負荷がかかります。Co2削減という観点でも再配達は減らすべきでしょう。
ネット通販という社会の変化に対応し、空室対策をするとともに、社会貢献をしていくためにも、宅配ボックスの設置をしていきましょう。

-
執筆:上野 典行(うえの のりゆき) 【プロフィール】プリンシプル住まい総研 所長
1988年慶應義塾大学法学部卒・リクルート入社。リクルートナビを開発後、住宅情報タウンズ・住宅情報マンションズ編集長を歴任。現スーモも含めた商品・事業開発責任者・ディビジョンオフィサー・賃貸営業部長に従事。2012年1月プリンシプル住まい総研を設立。All Aboutガイド「賃貸」「土地活用」。日管協・研修副委員長。全国賃貸住宅新聞連載。全国で、講演・執筆・企業コンサルティングを行っている。

