【わかりやすく】会計ソフト購入時の仕訳は?勘定科目や入力方法を解説
-
2023.4.25 (火)Posted by 北森 雅雄

事業で発生した取引を正しく把握し、決算や確定申告をスムーズに行うためには、会計ソフトを利用することが欠かせません。会計ソフトを導入する際はレシートや領収書を保管し、購入時の代金を費用として忘れずに計上しましょう。
本記事では、会計ソフト購入時の仕訳方法や使うべき勘定科目などについて解説します。インストール型・クラウド型といった種類や、購入時の金額に応じた処理方法についてもくわしく解説しますので、 ぜひ最後までご覧ください。
また、会計ソフトの基本を知りたい方は、こちらの記事を読む前に以下の記事もあわせてご覧ください。
\あわせて読みたい/
会計ソフトのおすすめはどれ?特徴・料金を徹底解説!
目次:
1.勘定科目とは

そもそも勘定科目とは、事業を営む上で生じた取引を分類するために使われるものです。取引の生じた日付や金額などと一緒に帳簿に記入することで、取引の内容をわかりやすく記録する役割があります。
勘定科目には以下をはじめとするさまざまなものがあり、取引の内容に応じて適切な勘定科目を選ぶことが求められます。
| 勘定科目 | 内容 |
| 仕入高 | 商品や原材料などを仕入れた際の費用 |
| 売上高 | 商品やサービスを提供することで得た売上 |
| 普通預金 | 普通預金口座の入出金が発生した時に使用する勘定科目 |
| 水道光熱費 | オフィスなどで使用した水道代・電気代・ガス代 |
| 旅費交通費 | 業務に関係する移動の際の交通費、出張の際の宿泊費など |
| 通信費 | 電話やインターネットなどの利用費 |
法人の場合、勘定科目および金額の内訳は「勘定科目内訳明細書」として税務署に提出します。また、適切な勘定科目を使って仕訳を行うことは、納付すべき税額を正しく計算することにもつながります。
2.会計ソフト購入時の勘定科目
会計ソフトを購入した際の勘定科目は何を選ぶべきでしょうか。選択する勘定科目やその考え方、会計上のルールなどについてくわしく解説します。
1
「消耗品費」か「通信費」が一般的
購入した会計ソフトに応じて、消耗品費もしくは通信費の勘定科目を選択します。
- ●消耗品費:インストール型の会計ソフトを購入した場合
- ●通信費:クラウド型の会計ソフトを契約した場合
消耗品費とは、ペンやメモ帳、ソフトウェア、10万円以下の備品など、幅広いものに対して使える勘定科目です。パソコンにインストールして使うインストール型の会計ソフトを購入した際は、この消耗品費を選択します。
それに対して通信費とは、電話料金やインターネットの回線にかかる料金などを支払った時に使うことの多い勘定科目です。インターネットを介して利用するシステムの利用料金を計上することも可能で、クラウド型の会計ソフトはこれに当てはまります。
2
勘定科目の決め方に決まりはない
会計ソフトの勘定科目として一般的なのは消耗品費もしくは通信費ですが、明確な決まりがあるわけではありません。「この場合はこの勘定科目を選びなさい」といった基準が法律で定められているわけではなく、ある程度は自らの裁量で設定することができます。
そのため、自分でわかりやすい勘定科目を新たに作成したり、企業独自のルールに基づいて仕訳を行ったりすることも可能です。
ただし、作成した書類を決算書や確定申告書として税務署に提出するほか、経営陣や金融機関に見せて経営状況をチェックしてもらうなどの機会もあるでしょう。あまりにも適当に勘定科目を設定すると、正しい経営状況が書類に反映できないため、注意が必要です。
3
決めたルールは継続して運用する
会計における考え方として、一度決めたルールをみだりに変更してはいけないという「継続性の原則」があります。例えば、ある物品の購入時に消耗品費を使ったのであれば、その後は事務用品費にしたり雑費にしたりすることなく、継続して消耗品費を使うことが求められます。
決定したルールを何度も変更してしまうと、税務調査で「しっかりと会計業務を行っていないようだ」「不正な費用を計上していないだろうか」などと思われてしまう可能性があります。
税務官に悪い印象を与えて税務調査が不利な方向へ進まないように、一度決めたルールはその後も継続して運用するようにしましょう。
3.会計ソフト(クラウド型)を購入した際の仕訳例
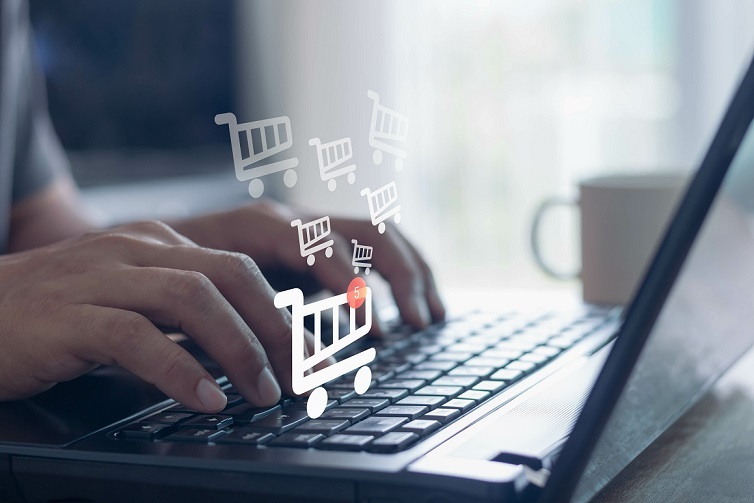
ここからは、会計ソフトを購入した際の実際の仕訳について解説します。
まずはクラウド型の会計ソフトを購入した際の仕訳を「月額料金のケース」「年会費のケース」の2つに分けて見ていきましょう。
仕訳例①
月額料金のケース
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 4/1 | 通信費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
4月1日に普通預金口座から月額料金5,000円が引き落とされた場合には、上記の仕訳を行います。 普通預金口座から5,000円が減り、通信費という費用が5,000円増えたことを意味する仕訳です。
仕訳例②
年会費のケース
| 日付 |
借方 |
貸方 | ||
| 4/1 | 通信費 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
通信費は経費として計上する金額に上限が定められていないため、高額の年会費をまとめて支払う場合でも問題なく計上できます。月額料金の場合と同じく、通信費としてまとめて計上しましょう。
4.会計ソフト(インストール型)を購入した際の仕訳例
インストール型会計ソフトを購入した際の対応方法について、仕訳例や利用できる制度などを解説します。
1
10万円以上の場合は無形固定資産
前述した通り、インストール型の会計ソフトは消耗品費として計上することが一般的です。
しかし、消耗品費は「使用可能期間が1年未満」もしくは「取得価額が10万円未満」であるものを計上する際に使用する勘定科目と定められています。会計ソフトが10万円以上である場合には、消耗品費ではなく固定資産としての計上となることを覚えておきましょう。
固定資産には、設備や車両などの「有形固定資産」と、ソフトウェアや権利など目に見えることのない「無形固定資産」があります。会計ソフトはソフトウェアに該当するため、10万円を超える際には無形固定資産として処理しましょう。
しかし、固定資産は以下の特例を使うことで、事務処理を簡略化したり、節税対策を行ったりすることもできます。
- ●少額減価償却資産の特例(中小企業の特例)
- ●一括償却資産の損金算入
次項から、金額や利用する特例に応じた仕訳方法をくわしく紹介します。
参照: 消耗品費
参照:No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
仕訳例①
10万円未満のケース
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 4/1 | 消耗品費 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
4月1日にインストール型の会計ソフトを5万円で購入した場合には、上記の仕訳を行います。10万円未満であれば消耗品費として一度で計上して構いません。
仕訳例②
10万円以上かつ通常の固定資産にするケース
10万円以上の会計ソフトを購入し、かつ前述した特例を使わず通常の固定資産として計上する場合の方法です。なお、この10万円には購入の際の代金をはじめ、送料やセットアップ料も含めて考えることができます。
<購入時>
| 日付 | 貸方 | 貸方 | ||
| 4/1 | ソフトウェア | 280,000 | 普通預金 | 280,000 |
4月1日に28万円の会計ソフトの代金が普通預金から引き落とされた際は、購入時に料金の仕訳を行います。
<減価償却時>
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 3/31 | 減価償却費 | 56,000 | ソフトウェア | 56,000 |
会計期間の最後の日には減価償却費を計上します。会計ソフトの場合は固定資産の耐用年数を5年と考え、今回は以下の計算式に基づいて減価償却費を56,000円と定めました。
280,000円(取得価額)× 0.2(定額法における償却率)= 56,000円(減価償却費)
上記の仕訳は、ソフトウェアという固定資産の価値が1年で56,000円分減少したことを意味する仕訳です。
参照:No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
仕訳例③
10万円以上かつ少額減価償却資産の特例を適用するケース
少額減価償却資産の特例(中小企業の特例)とは、本来減価償却すべき資産を取得した際、中小企業に限りまとめて経費として計上することを認める制度です。取得価額が30万円以下の固定資産を購入した際に利用できます。
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 4/1 | 消耗品費 | 280,000 | 普通預金 | 280,000 |
この特例を利用することで、取得価額が30万円以下であれば費用として一括して計上できるため、上記のような簡単な仕訳で済ませることができます。減価償却などを気にする必要もないため、会計処理の負担が軽減できるでしょう。
なお、この特例を利用するためには以下をはじめとする条件に該当する必要があります。
- ●取得価額が30万円以下であること
- ●青色申告法人である中小企業者、または農業協同組合等であること
- ●常時使用する従業員の数が500人以下であること(令和2年4月1日以後の取得の場合)
- ●「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を提出すること
国税庁のホームページを参考に、特例が利用できるかどうかをチェックしましょう。
参照:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
仕訳例④
10万円以上かつ一括償却資産の損金算入の特例を適用するケース
一括償却資産の損金算入とは、10万円以上20万円未満の資産を3年に分けて計上するための制度です。
<購入時>
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 4/1 | 一括償却資産 | 180,000 | 普通預金 | 180,000 |
4月1日に18万円でインストール型の会計ソフトの代金が引き落とされた場合、上記の仕訳を行います。「一括償却資産」の勘定科目を使って、資産として計上しましょう。
<減価償却時>
| 日付 | 借方 | 貸方 | ||
| 3/31 | 減価償却費 | 60,120 | 一括償却資産 | 60,120 |
会計期間の最後には、減価償却として上記の処理を行います。ここでは、以下の計算に基づいて60,120円を減価償却費として計上しています。
180,000円(取得価額)× 0.334(3年の償却率)= 60,120円
一括償却資産の損金算入の特例では、通常の5年ではなく3年で減価償却を行うため、上記の仕訳を3年間にわたって行う必要があります。
参照:一括償却資産5.会計ソフトの仕訳に関するQ&A
最後に、会計ソフトの仕訳を行う上で迷いやすいポイントを3つ解説します。
1
サポートを受けた際の費用はどうする?
会計ソフトを利用する中で、使い方や仕訳方法についてサポートに相談すると追加料金が発生することがあります。
サポートを受けるためにかかった費用を経費として計上することができますが、使用する勘定科目にこれといった決まりがあるわけではありません。一般的には、以下の勘定科目を使って仕訳を行います。
- ●消耗品費:会計ソフトの勘定科目とあわせたい場合
- ●支払手数料: 会計ソフトを提供する企業への報酬と考える場合
- ●諸会費:サポートを受けるためのプランの会費などとして考える場合
普段使っている勘定科目や企業のルールを加味して、総合的に判断しましょう。
2
バージョンアップの際の費用はどうする?
バージョンアップの際もサポート代と同じく、明確な決まりがあるわけではありません。消耗品費や支払手数料・通信費など、該当しそうな勘定科目の中から自由に選択します。
インストール型の会計ソフトで、年度の切り替えや税制の改正にあわせてソフト自体を新しく購入し直すのであれば、以前使った勘定科目をそのまま利用しましょう。
クラウド型の会計ソフトでは、月額料金や年会費にすでにバージョンアップ費用が含まれていることもあります。このような場合は、普段の仕訳と同じように処理して構いません。
3
勘定科目を間違えてしまったら?
これまで解説してきた通り、勘定科目の選択には法的なルールが定められているわけではないため、もし勘定科目を間違えてしまってもあまり気にしすぎる必要はありません。例えば、普段は文房具を消耗品費として計上している企業が、誤って雑費として計上してしまっていても、大きな問題となる可能性は低いと言えるでしょう。
税務調査で帳簿を見られれば指摘されることはあるものの、細かいミスを必ずしも厳しく追及されるというわけではありません。しかし、支払うべき税金の金額が変動してしまうような大きなミスであれば、のちに問題になる可能性もあります。
また、会計処理をきちんとおこなっていない企業であるという印象を税務調査の際に与えてしまえば「何か不正を行なっていないだろうか?」と、疑われやすくなるリスクがあります。税務調査をスムーズに乗り切るためにも、日々の仕訳はミスなく行うように心がけましょう。
6.まとめ
会計ソフトの仕訳方法や使用する勘定科目などについて解説してきました。一般的に、インストール型の会計ソフトよりクラウド型会計ソフトの方が、会計処理を楽に行えます。また、インストールや引き継ぎなどにかかる手間を考え、近年はクラウド型の会計ソフトを選択する事業者も増えてきています。
NTT東日本の「おまかせ はたラクサポート」は、以下をはじめとする各ツールを利用し、バックオフィスを一元的に支援します。
- ●freee会計
- ●freee人事労務
- ●freee経費精算
- ●クラウドサイン
- ●KING OF TIME
- ●BtoBプラットフォーム請求書
「バックオフィス業務をまとめて効率化したい」「どんなシステムを導入すべきか迷っている」などの課題がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
-
会計ソフト・サービスとサポートをセットに!
 無料体験申込フォーム
無料体験申込フォームNTT東日本では、会計ソフトをはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
