SASEなら利便性・セキュリティの両立が可能!3つのメリットやゼロトラストの違いを解説
-
2023.4.27 (木)Posted by NTT東日本

「SASEがどういったものか知りたい」「自社にどのような影響があるのかがわからない」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
SASEとは、クラウドサービスを中心とした新しい企業運営の考え方です。テレワークのような働き方の多様化が進む中、従来の情報セキュリティ対策では情報漏えいや生産性低下などの問題が残ります。
SASEの導入により、場所を選ばない快適なネットワークアクセスが実現します。さらに、社内全体のセキュリティ向上も見込めるでしょう。
そこで本記事では、SASEの意味や導入メリットから、構築に必要な要素について解説します。SASEについて簡単に理解でき、デジタル社会でも利益を出し続ける業務形態を実現できますので、ぜひ最後までお読みください。
高度・複雑化するサイバー攻撃へ必要な
最低限のセキュリティ対策をパッケージ化し、
さらに運用・監視をまるっとすべてNTT東日本におまかせ可能!
「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の資料をこちらからダウンロードできます
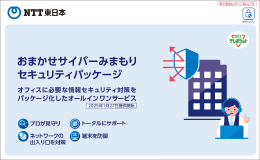
1.SASEとはクラウドサービスを主軸にして企業価値を上げる方法

SASEは、高いセキュリティとネットワークの利便性を同時に実現できる考え方です。SASEを導入すれば、企業の情報資産を守ると同時に、業務拡大が期待できます。
現在のセキュリティシステムは、社外アクセスのみ警戒し、社内ネットワークには自由性を持たせる「境界型」が一般的です。しかし、働き方の多様化が本格的にはじまってから、境界型の考え方ではセキュリティの甘さが目立つようになりました。
テレワークなど外部媒体から社内にアクセスする働き方が一般的になると、社外と社内の境界が不明瞭になるため、情報セキュリティ対策が取れていない箇所からの情報漏えいリスクが考えられます。
また、従来の情報セキュリティ対策では拠点ごとにシステムが複雑に構築され、管理コストが増大するばかりで、遠隔地からの同時接続による動作遅延で、生産性も落ちてしまいます。
SASEは、ネットワークやセキュリティに関する問題をクラウドサービスを中心にして解決します。時間や場所を選ばず、セキュリティが堅牢なクラウドへアクセスし、生産性のアップが可能です。
2.SASEとゼロトラストの違いは運用の実現性

SASEとゼロトラストは、どちらもデジタル化を見据えた企業の新しい考え方であり、運用の実現性に違いがあります。ゼロトラストはセキュリティ構築の概念で、SASEはゼロトラストを土台とした実現のための枠組みです。
まずゼロトラストは「すべてのネットワークを信用しない」考えをもとにしています。社内外のアクセスをすべて疑うことで、セキュリティレベルを向上させる効果が期待できます。
一方で、SASEは、ゼロトラスト実現の方法を意味する言葉です。具体的には、ゼロトラストの概念を中心としながら、企業運営の利便性に着目したセキュリティモデルです。
さまざまな場所から社内システムにアクセスする現代では、従来のセキュリティ方法のままでは資産を守りきれません。そのため、SASEとゼロトラストのような、働き方の多様化に適応する考え方が注目されています。
・ゼロトラストについて詳しく知りたい方は、別記事「ゼロトラスト」をあわせてご確認ください。
3.SASEの導入が注目されている3つの背景

SASEは、デジタル化への対応を背景にして、注目が集まっているシステムです。詳しい背景を知り、SASEが自社の将来に必要か検討するきっかけにしてください。
3-1.クラウドサービスの普及
SASEは、クラウドサービスの情報セキュリティ対策を前提としているため、これからの社会に必要とされています。クラウドサービスとは、ネットワーク上でさまざまな情報にアクセスできるシステムです。
クラウドサービスは外部媒体からの利用となるため、既存のセキュリティシステムでは監視の目が行き届いていません。SASEであれば、すべてのアクセスに対して適切な制御を行い、情報漏えいを防げます。
3-2.多様な働き方の実現
SASEの利用で、どの場所からでも快適なアクセス状況で業務を進められます。現在急激に普及したテレワークは、利便性の面ではいまだ十分な対策を取れていません。たとえば、遠隔地からのアクセスが集中した結果、動作が遅くなるという現象が起きています。
しかし、SASEのシステムを構築すれば、どこにいても動作遅延に悩まされません。アクセスを1つに集中させないしくみができるため、生産性の向上が期待できます。
3-3.セキュリティ強化
SASEは、現在のセキュリティシステムで抱える問題を解決できます。従来のシステムでは、社外からの脅威にのみ対策がされ、社内の情報資産が守れているとは言えません。そのため、社内体制の不備による情報漏えいが、さまざまなところで起きているのが現状です。
SASEは、社内外すべてのアクセスを監視し、異常な動きを検知できる機能を有しています。そのため、不正なコンテンツの流入を防ぎ、セキュリティ強化を実現できます。
4.SASE導入で得られる3つのメリット

SASEには、業務拡大につながるメリットがあります。導入を検討するために、メリットについて理解しておきましょう。
4-1.働き方改革への対応
SASEの利用で、オンラインの通信速度低下を防ぎ、どこにいてもスムーズに仕事ができるようになるため、増加するクラウドサービスの利用にも、問題なくついていけるシステムが構築できるでしょう。
オンライン業務が多くなった現代では、遠隔地からの端末操作が遅くなる問題が発生しています。遠隔でシステム利用をするための施設である「データセンター」にアクセスが集中し、動作遅延が生じているのが原因です。
SASEの考え方であれば、データセンターへのアクセスをせず、直接インターネットでつなぐシステムを実現できます。そのため、どこからでも快適なオンライン業務ができ、働き方改革に適応する企業になれるでしょう。
4-2.機器導入・管理コスト低減
SASEは、複数に散らばるネットワークを1つにまとめるシステム構築が可能です。機器導入・管理コスト両方を低減し、企業の運営を効率化させます。
企業に混在しているさまざまなセキュリティは、それぞれが独立して機能しています。そのため、機器が増大するうえに、管理のコストがかかっているのが現状です。
SASEはクラウド上でセキュリティシステムを一元管理でき、事業所ごとに設置されたセキュリティ機器の多くを必要としません。また、クラウド上だけの管理となり、ICT担当者の負担も減るでしょう。
4-3.セキュリティレベル向上
SASEは、社内外すべてのアクセスに対し認証操作を求めることで、セキュリティに問題が出た場合の対処ができます。従来のセキュリティ方法では、遠隔地からのアクセスに対して、十分な対策ができていません。
個人所有の端末から社内ネットワークにアクセスする場合、認証操作を厳格化しないままでは、不正アクセスの問題が常につきまといます。そのため、SASEの認証操作機能を活用して、セキュリティレベルを向上する必要があるでしょう。
高度・複雑化するサイバー攻撃へ必要な
最低限のセキュリティ対策をパッケージ化し、
さらに運用・監視をまるっとすべてNTT東日本におまかせ可能!
「おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージ」の資料をこちらからダウンロードできます
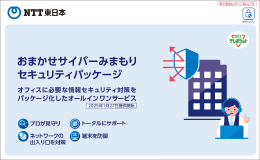
5.SASE導入時の2つの注意点

SASEは、新しい考え方を取り入れる性質上、注意点が存在します。導入前に確認し、リスクを理解しておきましょう。
5-1.専門性のある人材の確保が難しい
SASEには、運用に適した人材の雇用が難しいという問題があります。導入のためには、領域の知識だけでなく、運用開始後の監視を行える人材の確保が必要なためです。
また、SASEはシステムを根本から入れ替える必要があり、導入コストもかかります。そのため、業務の一部をクラウドサービスに置き換えるなど、徐々にSASEの形態へ切り替える方法も考えられます。
NTT東日本のおまかせクラウドアップセキュリティであれば、クラウドサービス上でやりとりするメールに対する脅威を検知可能です。該当メールは社員に届く前の隔離ができるため、開封がきっかけのウイルス感染や情報漏えいの可能性を大幅に減らせます。
運用の専門サポートデスクが利用でき、初期設定だけでなく、万が一のウイルス発生時の駆除サポートも受けられるのが魅力です。クラウドサービス導入に不安のある方は、まずは専任スタッフとの無料相談から検討してください。
5-2.クラウドが停止したときの損失が大きい
SASEは、クラウドサービスに企業のシステムを集中させるしくみです。そのため、クラウドが落ちてしまった際には、企業の大半のシステムがストップしてしまいます。
多くのシステムを組み合わせている従来の企業形態は、リスクが分散されている状態だといえます。一部機能が停止しても、ほかのシステムを利用して作業を進められるためです。
とはいえ、日々の利便性やセキュリティの高さを考えると、SASE導入による業務拡大の効果は大きいと言えるでしょう。
6.SASE導入に欠かせない6つの構成要素

SASE導入を実現するためには、欠かせない6つの構成要素があります。どのような構成になっているかを知るだけで、導入イメージがより具体的になるでしょう。
6-1.SWG|社外ネットワークへのアクセスを安全にする
SWGとは、安全な社外ネットワークへのアクセスを実現するために、主にクラウドサービス上の情報セキュリティ対策を整備するシステムです。不正なコンテンツの流入を防ぎ、利用できるアプリケーションを制御します。
SWGの利用で、不正なユーザーをブロックし、遠隔地からのアクセス元の通信状態を把握できるようになります。
6-2.SD-WAN|各拠点からのアクセスが快適になる
SD-WANは、物理的な機器ではなく、インターネット上のソフトウェアで通信管理をするシステムです。ソフトウェアで通信制御を行うと、遠隔地からの作業で起こる遅延を防げる効果があります。
従来のシステムは、通信の拠点であるデータセンターを経由してアクセスをしています。一方でSD-WANであれば、データセンターにアクセスが集中しないため、遅延のないしくみ作りが可能です。
6-3.CASB|クラウドサービスの情報セキュリティ対策
CASBは、クラウドサービスセキュリティに特化したサービスで、SASEに欠かせない機能を実行するしくみです。社員がクラウドサービスを利用する際に、統一した制御を行ってアクセスルールを適用します。
CASBは、社員のクラウドサービス利用状況を監視し、不正アクセスや情報漏えいを未然に防ぐ効果もあります。また、IT部門の社員が、自身の都合で不要なシステムを構築する「シャドーIT」も検知可能です。
CASBについて詳しく知りたい方は、別記事「CASB」をあわせてご確認ください。
6-4.ZTNA|ネットワークアクセスへの認証システム
ZTNAを導入すれば、社員からのアクセスがあるたびにセキュリティ認証が行われます。そのため、悪意ある第三者からの侵入を遮断できます。
社内外すべてのアクセスを、一旦不正でないか疑うのがSASE導入の役割です。導入を進めるためには、ZTNAのような、社員本人だと証拠づけるための認証システムが欠かせません。
6-5.FWaas|クラウド型の不正アクセス制御
FWaasは、ファイアウォールがクラウド型になったシステムです。ファイアウォールとは、ネットワークの通信を、社内へと通過させるかを判断する機能のことです。
FWaasの導入により、従来のファイアウォールが持つ機能に加えて、クラウド上の資産を柔軟に守れるようになります。
6-6.DLP|特定情報の外部流出対策
DLPとは、クラウド上で行う情報漏えい対策の1つです。特定の機密情報のみを対象として監視し、より強固に情報流出を防ぎます。
重要情報へアクセスしたユーザーを監視し、不正がある場合には挙動をキャンセルさせる機能もついています。クラウドは企業の外側での管理となるため、DLPのような対策が必要です。
7.SASEとは企業価値を上げる新しい考え方!スモールスタートをするならおまかせクラウドアップセキュリティがおすすめ

SASEは、自由な働き方を加速させるためには欠かせない考え方です。セキュリティと利便性を兼ね備えており、安心して遠隔地からのアクセスが可能になります。
SASE導入は、企業のあり方を大きく変えるほどの力を持っているため、導入に踏み切るのは時間がかかるかもしれません。そのため、少しずつSASEの考えを導入することもおすすめできます。
NTT東日本のおまかせクラウドアップセキュリティを利用すれば、クラウド上のメールに関する情報セキュリティ対策が可能です。マルウェア攻撃を事前に検知・隔離するため、社員の開封リスクを減らせます。
専門員による年中無休のサポートが受けられるため、導入もスムーズです。また、ウイルス感染時のウイルス駆除にも対応しています。
業務の一部をクラウド化して、SASE導入のスモールスタートをしたい方は、以下の詳細から確認できますので、ぜひ参考にしてください。
-
おまかせクラウドアップセキュリティ
おまかせサイバーみまもりセキュリティパッケージのトップに戻る
- おまかせセキュリティ事故駆け込み窓口
中小企業のお客さまに対し、情報セキュリティ事故に遭遇した際、これまで培ってきたNTT東日本の情報セキュリティ事故対応ノウハウによって「被害を最小限に抑える」、「事故発生の原因を解析する」、「事故発生前の状態に復旧する」などのサポートを行う窓口です。
- おまかせクラウドアップセキュリティ
クラウドメール、クラウドストレージ上でセキュリティ脅威を検知・遮断する機能に加え、導入支援をセットでご提供。
セキュリティサポートオプションの追加でセキュリティレポートのご提供やウイルス感染時の駆除支援等もご利用いただけます。



