自転車ダイナモの発電量はどれくらい?人力の発電方法について解説
-
2024.4.17 (水)Posted by
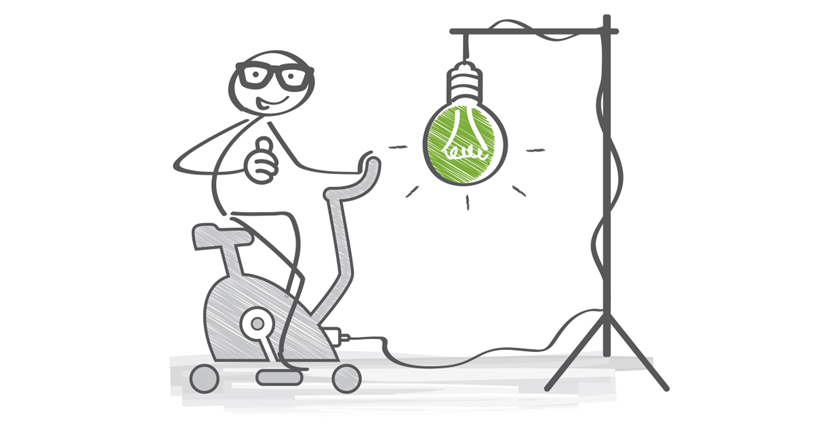

自転車ダイナモの発電量はどれくらい?人力の発電方法について解説
身近な発電システムには、普段乗っている自転車のライトがあります。
一般的なシティサイクルの場合、前輪の中央当たりにライトがあり、タイヤが回転するエネルギーを活用して発電・点灯しています。
しかし、この自転車のライトの仕組みを知らない人は多いでしょう。
この原理を応用することにより、発電方法に活用できる場合があります。
そこで今回は、自転車のダイナモ発電について紹介します。
<目次>
1:自転車のダイナモライトの仕組み
2:自転車のダイナモの出力
3:いわゆる「自転車発電」とは?
4:人力発電のメリット
5:人力発電のデメリット
6:自家発電で万が一に備えることは重要
7:まとめ
1:自転車のダイナモライトの仕組み
 自転車のダイナモライトにはハブというパーツが多く関わっています。
自転車のダイナモライトにはハブというパーツが多く関わっています。
ハブというのはスポークが集まる車輪の中心部、つまり車軸まわりのことです。
ハブダイナモの自転車には発電機がないように見えますが、ランプから出たコードをたどっていくと、前輪のハブ部分にコードが接続されていることがわかります。
実は発電機はハブまわりコンパクトに格納されているのです。
コイルに向かって磁石を動かすと、コイルには誘導起電力が発生して電流が流れます(電磁誘導現象)。
また、コイルに回転磁界を加えると、持続的な交流電流が流れます。
この現象を利用して発電するのが自転車のダイナモです。
自転車では低速走行でもランプが点灯できる工夫が必要です。
そこで、自転車のダイナモには多極着磁(N極とS極の両面で吸着させることができる)されたフェライト磁石が使われます。
マグネット式モーターにはコイルがマグネットロータを囲むインナーロータ型と、マグネットロータがコイルを囲むアウターロータ型があるのですが、自転車のダイナモにも両タイプがあります。
基本原理は同じですが、リブダイナモはインナーロータ型、ハブダイナモはアウターロータ型です。
ハブダイナモ式の自転車ライトの多くは、周囲が暗くなると自動的に発電機が作動してランプを点灯する仕組みになっています。
これはオートライトと呼ばれています。
うっかりと無灯火ということもなく事故防止にも役立ちます。
調べてみるとランプの下部あたりに小さな窓があります。
ここから入ってくる光の照度を光センサが検知して、発電機をON/OFFさせる電気信号を回路に送っているのです。
窓を指で押さえて光を遮断し、前輪を空回りさせると、真昼でもランプが点灯することで確かめられます。
2:自転車のダイナモの出力
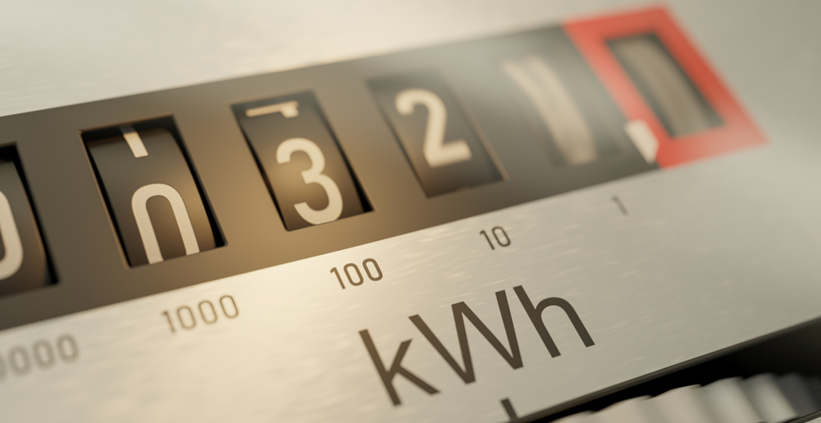 ダイナモの定格出力6V 2.4Wが一般的で、時速15kmで走行した時の値になっています。
ダイナモの定格出力6V 2.4Wが一般的で、時速15kmで走行した時の値になっています。
また、自転車の速度が遅くてもそれなりに発電し速度が速いと発電しすぎないようになっています。
自転車に取り付けてスマートフォンなどの充電を行なうためのキットもあります。
後輪のチェーンを本体のギアに通し、自転車を漕ぐと発電する仕組みで、本体はチェーンステーに固定します。
IPX4レベルの防水機能があり、多少の降雨でも問題なく使えるという優れものです。
発電量は時速5~15km/hの場合で100~300mA、20~30km/hで400~600mA、30km/h超で700~900mA。
直接出力ではなく、内蔵バッテリー(1,000mAh)に蓄電され、そのバッテリーを介してスマートフォンなどへ出力できます。
3:いわゆる「自転車発電」とは?
 自転車を漕ぐ力を使って発電することは可能です。
自転車を漕ぐ力を使って発電することは可能です。
テレビ番組などでも見たことがある方もいるかもしれませんが、自転車を漕いだその電力を使ってクイズに答えるものなどをイメージすると分かりやすいでしょう。
基本的なダイナモと同じ仕組み
自転車による発電方法も基本的にはダイナモと仕組みは同じです。
自転車を漕いでタイヤやギアを回転させることにより、タービンの役割であるコイルを回すことで電気を得ています。
自転車のライトは瞬間的に発電して電球が点灯しますが、一般的な自転車発電は発生した電気をバッテリーに貯め込みます。
これにより、瞬間的には微量な電気であったとしても蓄積することにより利用できるようになります。
50Wほどが上限
自転車発電は人間の力による発電方法であるため、環境に優しいクリーンな発電方法であるといえますが、その発電量は少なく、1時間あたり50Wほどの発電が限界と言われています。
これは自転車のタイヤが接している面が少なく、発電できる規模が小さいためです。
そのため、自転車を漕ぎ続けたとしても生活に必要な電気を賄うことは困難です。
しかし、ダイエットなど移動以外の目的で自転車を漕いでいる人であれば、そのエネルギーを無駄にせずに再活用できるため、プラスな効果があるといえるでしょう。
維持するのが難しい
自転車発電の最大のデメリットは人間の体力には限界があるため、発電し続けることが難しいことです。
実際に自転車運動は有酸素運動であり、炭水化物などのエネルギー消費量が大きいです。
普段から自転車に乗っている人でも1時間以上漕ぎ続けるのは、身体的な負担が大きいです。
ロードバイクが趣味の人であればもっと漕げますが、毎日何時間も漕ぎ続けるのは現実的ではありません。
また、一定のペースで漕いだ方が効率は良いものの、運動時間に反比例して体力は減っていくため、だんだんとペースは落ちていくでしょう。
このように自転車発電はエネルギーを効率良く活用できますが、現実的な発電方法とは言えません。
4:人力発電のメリット
 人力発電は台風や地震などの自然災害が起きて停電してしまった場合でも、自力で発電できるメリットがあります。
人力発電は台風や地震などの自然災害が起きて停電してしまった場合でも、自力で発電できるメリットがあります。
非常用ライトやラジオ、スマートフォンなど、安全を確保する上で最低限必要な小型家電の充電ができるのです。
さらに普段から人力発電しておいた電力を蓄電しておけば、停電時にすぐに電気を利用できます。
火力発電は発電機を回すために大量に燃料を燃やし、地球温暖化の原因である二酸化炭素を大量に排出します。
また、火力発電以外の原子力発電や自然エネルギー発電では、二酸化炭素を排出しませんが、資源の調達や設備の建設中に二酸化炭素を排出します。
一方、人力発電は発電時に排出される二酸化炭素は人の呼吸のみ。資源の調達や大規模な設備の建設も必要がないため、エコな発電といえるでしょう。
人力発電の方法は、自転車を漕いだり、ランニングマシンで走ったりとさまざまです。
いずれも体力を必要とするので、発電することで自然とカロリーを消費できます。
発電しながら運動不足を解消し、健康維持やダイエットができるメリットもあります。
5:人力発電のデメリット
 人力発電の最大のデメリットといえるのが、エネルギーを得るために発電機の回転数を一定に保たなくてはならないこと。
人力発電の最大のデメリットといえるのが、エネルギーを得るために発電機の回転数を一定に保たなくてはならないこと。
必要最低限のペースで回転数(例えば1秒に2回まわすなど)を保つことで発電が可能なので、それよりも小さな回転数では発電できなくなってしまいます。
人間の体力は有限のため、ずっと同じペースで回し続けることは難しいでしょう。
人間が費やす労力に比べ、得られる電力もわずかだと言えるため、効率の悪いこともデメリットです。
そのため人力発電の充電器は、あくまで緊急災害用として用意し、モバイルバッテリーや携帯用の太陽光発電機を併用する必要があります。
他にも、家庭でこれらの発電設備を用意するのはコストがかかります。
スマートフォンなどを充電できるバイクマシンもありますが、相場は10万円以上します。
ただし、これらのバイクマシンは漕いだエネルギーを使い、発電して内部バッテリーが充電されるため、起動に電源を必要としません。
そのため、これらのマシンはコンセントなどの電源がない場所でも利用できます。
6:自家発電で万が一に備えることは重要
 自転車以外にも、手回し式・ペダル式などの手動式発電機があり、手動式発電機はガソリンなどの燃料はもちろん、光や風などの再生可能エネルギーを必要としません。
自転車以外にも、手回し式・ペダル式などの手動式発電機があり、手動式発電機はガソリンなどの燃料はもちろん、光や風などの再生可能エネルギーを必要としません。
人力で回した分だけ発電できるため、災害時にスマホの充電をしたいシーンなどで活躍します。
ただしどんなに頑張っても大きな出力とはならず、冷蔵庫や炊飯器などの家電を動かすには他の自家発電機が必要です。
人力発電機も役に立つことはありますが、地震などの災害時の電力確保を目的をするのであれば、他の自家発電装置があると安心です。
7:まとめ
この記事では、自転車のダイナモ発電について紹介しました。
自転車のダイナモ発電はタイヤが回転するエネルギーを使って電気を生み、ライトが点灯しています。
しかし一生懸命漕いでも、安全のために一定以上の速度になると発電効率が悪くなります。
また、いわゆる自転車発電もライトの点灯と同じ原理で電気が生まれています。
燃料を使用しないクリーンな発電方法ですが、人力には限界があり発電できる電気量は僅かです。
しかし、これらを効率化することにより、次世代の発電方法として期待されているのも事実です。
