確定申告に源泉徴収票はいらない?
-
2023.2.17 (金)Posted by 北森 雅雄
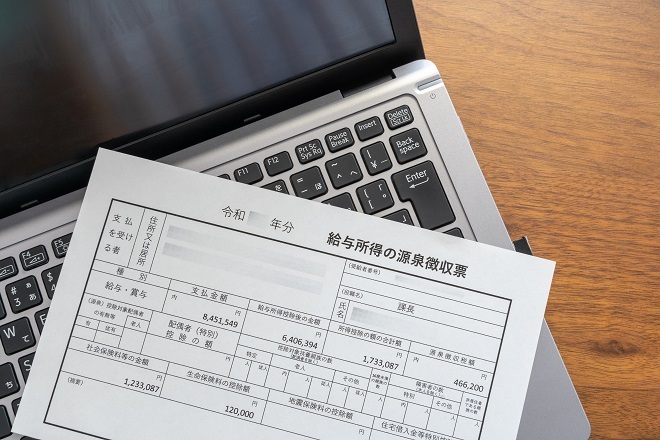
確定申告をするときに源泉徴収票が必要か不要かわからない、と困っている方は多いのではないでしょうか。
2019年(令和2年)4月1日から確定申告の際に源泉徴収票の添付は不要になりました。
そこで本記事では「確定申告と源泉徴収票」の取り扱い方について解説します。
目次:
1.源泉徴収票は原則不要に!確定申告する時の注意点
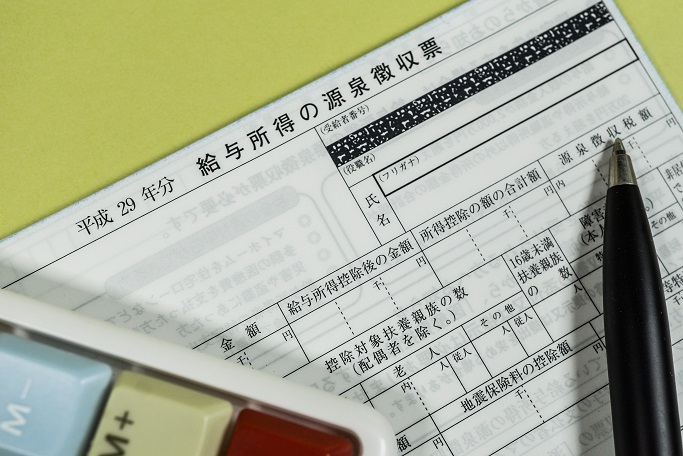
2019年4月より確定申告書に添付する源泉徴収票は原則として不要になりました。
源泉徴収票とは1年間の収入と所得税等を記載した書類のことです。主に会社員が1年間の収入を証明するために使用されます。
以前は確定申告に必ず添付しなければなりませんでしたが、ペーパーレスの推進等の理由を背景に源泉徴収票の添付が不要になりました。なお、国税庁によると源泉徴収票の添付が不要となった理由や目的は「納税者の利便性向上を図る観点から」とされています。
1
源泉徴収票の入手方法
源泉徴収票は1年間の収入が確定した後に会社が発行する書類です。所得税法によって給与を支払う事業者(会社など)はすべての従業員に源泉徴収票の発行を義務付けられています。
源泉徴収票は書類による配布のほか、電子データによって配布されることもあります。
2
源泉徴収票はいつ入手できる?
源泉徴収票は1年間の収入を計算する書類であるため、1年間の終わりに入手できます。
源泉徴収票は12月あるいは1月に給与明細とともに勤務先の会社から従業員に配布されることが一般的です。なお、正社員だけでなくアルバイトやパートなどの非正規社員も給与を得ている従業員として源泉徴収票の配布対象となります。
3
源泉徴収票の再発行はできる?
源泉徴収票を紛失してしまった場合、会社の担当者に申し出れば再発行ができます。源泉徴収票の発行は経理部門などの管理部門が担当していることが多いです。
年の途中に退職してしまった後は会社に申し出れば源泉徴収票の発行ができます。
4
源泉徴収票の発行義務は?
給与などの支払いを受けている方は給与を支払う側の会社に源泉徴収票の発行を依頼する権利があります。所得税法226条によると、その年の翌年の1月31日までに給与支払者(会社)は給与所得者(従業員)へ源泉徴収票を交付すると定められています。
源泉徴収票の発行はすべての事業者(会社)に義務付けられています。そのため、企業は従業員に源泉徴収票の発行依頼に対応する義務があり、これを拒むことができません。
源泉徴収票は書面で交付するほか、電磁的方法によって電子データで交付されることもあります。
なお、源泉徴収票と同様に法律で交付の義務が定められている法定調書は以下の通りです。
| <交付が義務付けられている法定調書> ●給与所得の源泉徴収票 ●退職所得の源泉徴収票 ●公的年金等の源泉徴収票 ●オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書) ●配当等とみなす金額に関する支払調書(支払通知書) ●上場株式配当等の支払に関する通知書 ●特定口座年間取引報告書 ●未成年者口座年間取引報告書(※契約不履行等事由が生じた場合のみ) ●特定割引債の償還金の支払通知書 |
2.源泉徴収票はどんな時に必要?
源泉徴収票は確定申告の時以外にも年収を証明するために活用できます。
源泉徴収票が必要になるのは以下のケースです。
- ●確定申告をする時
- ●収入を証明する時
- ●転職して年末調整をする時
源泉徴収票は自身の所得や収入を証明する重要な書類です。公的な手続きでも多く使用されているので、大事に保管しておきましょう。
1
確定申告をする時
確定申告をする場合、所得額を計算するために源泉徴収票が必要です。
源泉徴収票を添付する必要はありませんが、確定申告は源泉徴収票の情報を元に行うものです。ご自身の所得などを間違いなく記入するために源泉徴収票を用意しておきましょう。
2
収入を証明する時
源泉徴収票には1年間の収入が記載されているため、本人の収入を証明できます。
例えば、金融機関で融資を受ける時やローンを組む際などに収入(年収)の確認を求められるため、源泉徴収票を提出することで収入状況を証明できるのです。
3
転職して年末調整をする時
転職をした年は前の会社から源泉徴収票を貰う必要があります。
退職をしてから他の会社に転職した場合、転職先の会社で年末調整をする際に源泉徴収票が必要です。年末調整は原則として12月末に所属している会社で行うため、転職先の会社で源泉徴収票に基づいて本人の所得を合算します。
一般的に、退職した会社では最後の給与支払いのタイミングで源泉徴収票が交付されます。
転職を複数回している場合
転職を複数回している場合はすべての源泉徴収票が必要です。
例えば、3月にA社を退職してB社に転職、9月にB社からC社に転職するケースではC社にA社とB社で発行された源泉徴収票を提出してC社で年末調整を行います。
12月中に転職した場合
12月中に転職した場合は12月の給与がどこで支払われるかで源泉徴収票の有無が変わります。
一般的に、12月の給与は1月に支払われるため12月中に転職した場合は前職で年末調整することが多いです。12月中に転職した場合の年末調整に関する対応は会社によって異なるので担当者と相談してください。
3.源泉徴収票の種類
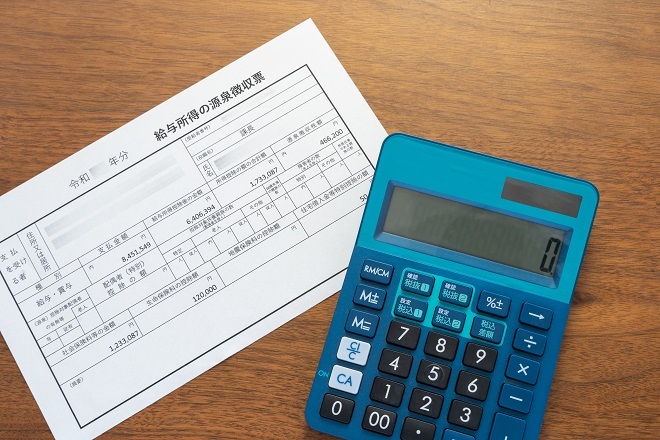
源泉徴収票は給与の支払い状況を記した給与所得の源泉徴収票のほか、以下3種類があります。
- ●給与所得の源泉徴収票
- ●退職所得の源泉徴収票
- ●公的年金等の源泉徴収票
これらの書類は所得税の計算方法が異なるため区別されています。それぞれの源泉徴収票の特徴について見ていきましょう。
1
給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は給与に関する源泉徴収票です。給与は基本的に毎年支払われるものであるため、毎年発行されます。
先ほども紹介したように、給与所得の源泉徴収票は毎年12月から1月ごろに給与所得の計算が確定したタイミングで会社から従業員へ交付されます。
2
退職所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票は退職する従業員に退職金を支払った際に支払われる書類です。退職金の額および源泉徴収された所得金額を記載します。
給与所得の源泉徴収票とは別物であるため、退職した際は2種類の源泉徴収票が交付されることになります。
3
公的年金等の源泉徴収票
公的年金等の源泉徴収票は日本年金機構が国民年金などの年金を受給した人に発行する書類です。
1年間に支払われた年金の額と源泉徴収された金額が記載されています。
4.確定申告に必要な源泉徴収票の内容

確定申告をする際は源泉徴収票を参照しながら本人の所得額などの情報を記入する必要があります。
源泉徴収票には本人の所得を証明するために以下の情報が記されています。
- ●支払金額
- ●給与所得控除後の金額
- ●所得控除の額の合計額
- ●源泉徴収税額
- ●配偶者(特別)控除の額
- ●保険料等の控除額
- ●住宅借入金等特別控除の額
国税庁では源泉徴収票のサンプルが提示されています。
ここでは、確定申告をする際に確認するべき源泉徴収票についてチェックしましょう。
1
支払金額
「支払金額」は会社が従業員に支払ったすべての金額を足したものです。一般的には支払金額がそのまま年収に相当します。
支払金額には給与をはじめボーナス、各種手当など会社が支払ったすべての金額が含まれています。
2
給与所得控除後の金額
「給与所得控除後の金額」は先ほどの支払金額から給与所得の額を差し引いた金額です。
以下は令和2年分以降の給与所得控除を一覧表にしたものです。例えば、課税される所得金額が500万円の場合は給与所得控除額は144万円(5,000,000円×20%+440,000円=1,440,000円)となります。
この場合、給与所得控除後の金額は356万円(500万円ー144万円)という計算になります。
| 給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
| 1,625,000円まで | 550,000円 |
| 1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
3
所得控除の額の合計額
「所得控除の額の合計額」は給与所得控除以外に控除される金額です。
例えば、医療費や社会保険料は所得から控除できます。主な控除の種類として以下の項目が挙げられます。
| <主な控除の種類> ●医療費控除 ●社会保険料控除 ●生命保険料控除 ●地震保険料控除 ●寄附金控除 ●配偶者控除 ●基礎控除 |
4
源泉徴収税額
「源泉徴収税額」は1年間で納めた所得税です。源泉徴収税は毎月および年末調整のタイミングで会社から税務署に納められます。
源泉徴収税額の金額は課税所得額に所得税率をかけて計算します。課税所得ごとの税率および控除額は以下表の通りです。
なお、課税所得額は「①支払金額」から「②給与所得控除後の金額」と「③所得控除の額の合計額」を差し引いた金額です。
源泉徴収税額の金額は会社が年末調整などで計算してくれるため自分で計算をする必要はありませんが、節税対策をするのであれば知っておいて損はないでしょう。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
5.副業の確定申告なら「おまかせ はたラクサポート」がおすすめ!

副業の確定申告をするなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。
副業などで20万円以上の事業所得がある場合は確定申告が必要です。確定申告をする際には帳簿をつける必要があるのですが、自分で帳簿をつけることが面倒だったり方法が分からないという方は多いでしょう。
会計ソフトを使うことで会計の知識がなくても簡単に確定申告書を作成できます。
1
質問に答えるだけで確定申告書が作成できる!
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」では簡単な質問に答えるだけで確定申告書が作成できます。
会計に詳しくない方や控除の条件を知らない方も確定申告書の〇×形式の質問に答えて確定申告の入力を補助してくれます。確定申告書の作成から出力までワンストップで完結してくれるため、忙しい個人事業主の方におすすめです。
| プラン | 主な機能 |
| スターター | 確定申告書の作成・出力 銀行口座やクレジットカードとの同期 請求書の作成 |
| スタンダード | 確定申告書の作成・出力 銀行口座やクレジットカードとの同期 請求書の作成 仕訳データ自動取得 消費税申告 月次推移/資金繰り/売掛/買掛レポート |
2
リーズナブルな導入費用
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」はクラウド型の会計ソフトであるため、初期費用なしで月額1,298円という料金から始められます。
ネット環境さえあれば気軽に導入できるので、確定申告期間のバタバタしている際にもスムーズに始められます。
| プラン | 初期費用 | 月額基本料 | 追加ID (1IDあたり) |
| スターター | 不要 | 1,298円 /1IDまで |
ー |
| スタンダード | 不要 | 2,618円 /3IDまで |
396円 |
6.まとめ
2019年から確定申告の際に源泉徴収票の添付は不要となりました。
源泉徴収票は12月末から1月にかけて従業員の所得が確定した後に会社から従業員への交付が義務付けられています。源泉徴収票は本人の年収や収入状況を示す重要な書類ですので、大事に保管しておきましょう。
会社員の方が20万円以上の事業所得がある場合、年末調整のほかに確定申告が必要です。確定申告をする際は源泉徴収票に記載されている金額等の情報を確認しながら作業をしなければなりません。
会社員の副業など、個人事業主が確定申告をするなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。会計ソフトやサポートサービスを上手く活用して確定申告の負担を減らしましょう!
-
経費精算ならサービスとサポートをセットに!
 経費精算 無料体験申込フォーム
経費精算 無料体験申込フォームNTT東日本では、経費精算をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
