確定申告の期間はどれくらい?正しく申告するためのコツも解説
-
2023.6.02 (金)Posted by 北森 雅雄
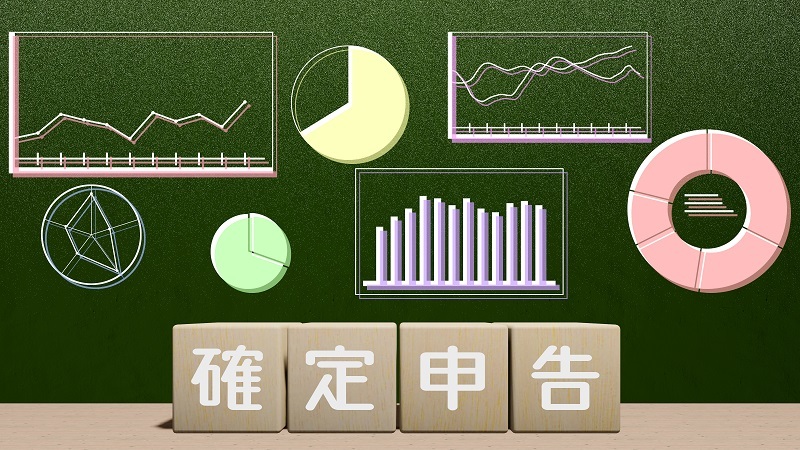
確定申告は、定められた期間内に終わらせる必要があります。しかし初めて確定申告をする場合だと、「確定申告はいつまでに終わらせればよいのか」「期間内に終わらないとどうなるのか」とお悩み中の人もいるのではないでしょうか。
当記事では、所得税やその他税金の確定申告の期間や提出方法、期間内に提出できなかったときのペナルティ、期間内に正しく申告するためのコツなどを解説します。
目次:
1.所得税の確定申告期間|その他税務申告についても解説

個人事業主や会社員が行う所得税の確定申告は、原則として毎年同じ日程での提出期間が定められています。また、法人税や所得税以外の税金、その他税務申告もおおよその期間が決まっています。
税金の種類に応じた準備を行い、期間内に手続きが終わるようにしましょう。以下では、所得税およびその他税務申告の期間を解説します。
1
所得税の確定申告期間は2月16日~3月15日
所得税および復興特別所得税の確定申告の期間は、青色申告・白色申告を問わず、原則として2月15日〜3月16日です。例えば2022年度の確定申告の場合は、2023年2月16日(木)〜2023年3月15日(水)までです。
もし2月16日や3月15日が土日祝日だった場合は、翌日または翌々日に振り替えられます。また、過去の新型コロナウイルス感染症拡大のときのように、やむを得ない世情や災害などが発生したときは、国の判断で期間が延長される可能性もあります。
所得税の確定申告書と一緒に提出する青色申告決算書や収支内訳書も、2月15日〜3月16日が提出期間です。
なお所得税の確定申告をすると、自動的に住民税も申告したことになります。税務署が所在地の自治体へ、確定申告の内容を共有するためです。
所得税の確定申告をしなかったときは、自治体への住民税の申告が必要になります。
2
所得税以外の税金の確定申告期間一覧
所得税以外に確定申告が必要な税金は、法人税・贈与税・相続税・消費税の4種類が主に挙げられます。それぞれの提出期間は次の通りです。
| 税金の種類 | 提出期間・備考 |
| 法人税 |
|
| 贈与税 |
|
| 相続税 |
|
| 消費税・地方消費税 |
|
提出先は、いずれも所轄の税務署です。
3
確定申告と提出期間が同じ書類
青色申告関係の書類である「所得税の青色申告承認申請書」と「青色専従者給与に関する届出書」は、いずれも確定申告しようとする年の3月15日までの提出が必要になります。
所得税の青色申告承認申請書とは、税務署へ「今度から青色申告を行います」と伝えるための書類です。3月15日より後に提出したときは、その年の確定申告は白色申告です。翌年度より、青色申告での確定申告ができます。
次に青色専従者給与に関する届出書を提出すると、事業専従者としての条件を満たした親族へ個人事業主が給与を支払うとき、当該給与を経費として計上できます。
また、他にも3月15日までの提出が必要なのが「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」です。この書類は、減価償却資産の償却方法を変更したいときに、所轄の税務署へ提出します。
4
確定申告以外の税務申告の期間
確定申告で報告する内容は、原則として1年分の収支や所得、納税額です。しかし、ケースによっては準確定申告と呼ばれる、1年未満の期間での収支や所得をまとめる税務申告が必要になります。
またその年の5月15日において、前年度の納税額などを基に算出した基準(予定納税基準額)が15万円以上になると、年3回に分けて納付する予定納税を行います。
それぞれの申告期間は次の通りです。
| 確定申告以外の税務申告・納税 | 申告期間・備考 |
| 相続の準確定申告 |
|
| 出国の準確定申告 |
|
| 予定納税の支払い |
|
5
還付申告・更正の請求の期間
還付申告とは、確定申告の義務がない場合でも、申告することで納めすぎた税金の還付を受け取れるケースで実施できる税務申告です。申告期間は、還付の対象となる年の翌年1月1日から5年間です。
例えば、確定申告をした後に医療控除の申請を忘れていた場合でも、翌年の1月1日から5年間までなら還付申告で対応できます。確定申告と異なり、2月16日〜3月15日の間で実施する必要はありません。
一方で更正の請求とは、確定申告の義務がある人が確定申告・納税を終えた後、税金の納すぎが発覚した場合に行う手続きです。こちらも還付金が受け取れます。法定申告期限から5年以内であれば、いつでも実施できます。
- ●確定申告の義務がなくても還付金が受け取れるときは還付申告
- ●確定申告後に還付金が受け取れると気づいたときは更正の請求
なお、逆に本来の納税額よりも少ない金額で申告していたことが後で発覚した場合は、修正申告の手続きが必要です。
2.確定申告3つの提出方法とそれぞれのメリット・デメリット
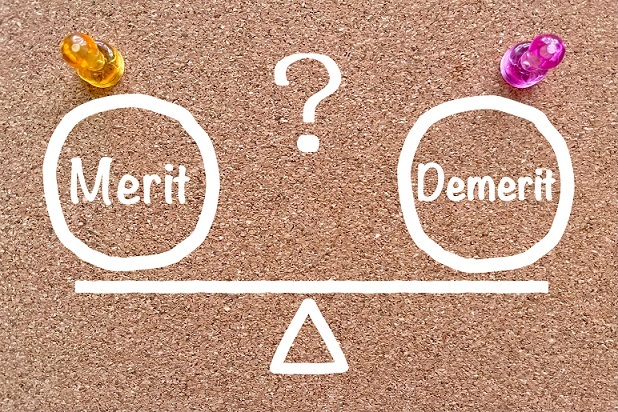
確定申告の提出方法には、「税務署の窓口への直接提出」「郵送・信書便で提出」「e-Taxを利用した電子申告」の3種類があります。どの方法で確定申告をしても問題はありませんが、手続き内容が異なるので提出タイミングに注意しましょう。
提出先は原則として、所属する納税地を管轄している税務署です。個人事業主で別途の届出をしている場合を除き、住所地が納税地となります。住所地を管轄する税務署は、国税庁の「国税局・税務署を調べる」のWebページにて検索可能です。
また、もし確定申告についてわからないことがあるときは、各都道府県ごとに儲けられた確定申告会場にて相談するのもよいでしょう。
以下では、確定申告3つの提出方法とそれぞれメリット・デメリットを解説します。
1
税務署窓口への直接提出
所轄の税務署まで足を運び、窓口にて職員へ直接提出する方法です。書類を準備して提出するだけなので、一番シンプルな方法になります。
税務署窓口にて提出するメリットは次の通りです。
- ●窓口の担当者に書類の不備をチェックしてもらえる
- ●足りない書類や修正があればその場ですぐに教えてもらえる
- ●郵送の準備やe-Taxの操作などが原則として必要ない
- ●その場で確定申告の控えをもらえる
- ●足を運んだ日が提出日になるので、郵送のような提出日のタイムラグが発生しにくい
一方で、次のデメリットも存在します。
- ●一方で、次のデメリットも存在します。
- ●税務署へ赴く時間と労力がかかる
- ●税務署が開いている時間が平日8:00~16:30と決まっている
初めて確定申告する場合であれば、税務署の雰囲気を知っておく意味でも、窓口へ直接提出することをおすすめします。
もし開庁時間に税務署へ行けないときは、税務署の外に設置してある時間外収受箱への投函もできます。投函は24時間土日祝いつでも可能です。
ただし、職員のサポートなどは受けられません。また控えをもらいたいときは、控えの申告書と切手を貼った返信用の封筒を同封して投函しましょう。
2
郵送・信書便での提出
税務署が遠かったり足を運ぶ時間がなかったりなどする人は、郵送や信書便を利用しての提出ができます。郵送・信書便での提出のメリットは次の通りです。
- ●最寄りの郵便ポストや郵便局へ提出すれば手続きが完了する
- ●郵便ポストであれば土日祝日関係なく提出できる
一方で、以下のデメリットも存在します。
- ●消印日が提出日になるので、提出が13~14日のギリギリになると15日に間に合わない可能性がある
- ●郵送料などの費用がかかる
- ●職員に不備のチェックなどを頼めない
郵送や信書便での提出は、初めて確定申告する人より、何度か確定申告して慣れている人におすすめの提出方法になります。
3
e-Taxを利用した電子申告
e-Tax(国税電子申告・納税システム)とは、各税金の申告や法定調書の提出、届出、申請などの各種手続きを、インターネット上で完結できるようにしたシステムです。税金の納付にも対応できます。
電子申告で提出するメリットは次の通りです。
- ●青色申告特別控除を最大額である65万円で適用できる(窓口や郵送は55万円)
- ●自宅などから確定申告の手続きをすべて完了できる
- ●24時間いつでも提出できる
一方で、以下のデメリットも存在します。
- ●マイナンバーカードの発行やID・パスワードの設定などが必要になる
- ●インターネット環境がないと利用できない
政府の方向性からも、今後は電子申告での提出が主流になっていくでしょう。青色申告特別控除の面からも、できる限り電子申告に慣れていくことをおすすめします。
なお、大手の会計ソフトのうち独自の電子申告ツールを搭載しているものは、会計ソフトで入力してそのまま電子申請が完了できます。
3.確定申告が必要な人とは?

確定申告は、原則として一定以上の所得を得た人が行います。申告が必要になる人は条件によって異なり、例えば事業所得を得ている個人事業主と、副業収入を得ている会社員では所得条件が変わってきます。
条件の中でも、比較的対象者が多い確定申告が必要な人は次の通りです。
- ●給与所得を得ておらず、基礎控除の48万円以上の所得を得ている(個人事業主など)
- ●給与所得を得ている人で給与収入が2,000万円を超えている
- ●給与所得を得ている人で、給与以外の所得の合計額(副業や投資で得た収益など)が20万円を超えている
- ●ダブルワーク(雇用契約を2社と結んでいるなど)をしている人で、年末調整されなかった給与の収入金額とその他の所得金額の合計額が20万円を超えている
- ●公的年金に関する所得から所得控除を差し引いたときに、残額がある(公的年金が400万円以下などの条件を満たすときは確定申告の必要なし)
おおまかに分けると、「所得48万円を超えている個人事業主」や「給与以外で20万円超の所得を得ている会社員」が、確定申告の対象になる可能性があります。
また確定申告の義務がない人でも、青色申告特別控除などの青色申告の特典を受けたい人や、住宅ローン控除などの控除を利用したい人は、確定申告が必要です。
4.確定申告が期間内に終わらなかったときのデメリット
確定申告が期間内に終わらなかったときは、次のデメリットが発生します。
- ●青色申告特別控除の適用が最大でも10万円になる
- ●追徴課税が課される
- ●経営状態の把握ができなくなる
- ●確定申告書や決算書の控えがもらえない
とくに個人事業主は、期間外申告になるとデメリットが大きくなる可能性があります。それぞれの詳細をみていきましょう。
1
青色申告特別控除の適用が最大でも10万円になる
本来、青色申告特別控除は電子申告であれば最大65万円までが適用できます(直接提出や郵送の場合は最大55万円)。しかし、期間が終わった後に遅れて確定申告を行ったときは、最大でも10万円の控除しか適用できません。
もし課される所得税率が10%だと、納税額が最大で5万5,000円も変わります。
さらに2期連続で青色申告を期間内で終わらなかったときは、青色申告の承認が取り消される可能性があります。実質的に、青色申告の特典(損益通算・青色専従者給与の経費申請など)がすべて使えなくなるので注意しましょう。
2
追徴課税が課される
期間内に確定申告が終わらないと。追徴課税と呼ばれる追加の納税が発生します。追徴課税の種類は次の通りです。
| 追徴課税の種類 | 概要 |
| 過少申告加算税 | 本来申告すべき所得額より少額で申請し、納税額が少なくなった人に課せられる |
| 不納付加算税 | 源泉徴収税の納付が期日までに行わなかったときに課される |
| 無申告加算税 | 確定申告が期間内に終わらなかったとき、本来納税すべき税額に対して課される |
| 重加算税 | 意図的に所得を隠したり隠匿・偽装したりするなど悪質性が認められるときに課される |
| 延滞税 | 延滞金のように、納付期限から実際に納付した日までの日数に応じて課される |
重加算税の要件でより高い悪質性(億単位の脱税など)があると判断されると、刑事罰が科される可能性もあります。
3
確定申告書や決算書の控えがもらえない
確定申告を行わないと、申告するまで確定申告書や青色申告決算書などの控えがもらえません。確定申告書や青色申告決算書の控えは、次のケースで使用できます。
- ●クレジットカード発行や賃貸契約時の信用情報の証明
- ●取引先や顧客への健全性の証明
- ●金融機関から融資を受けるときの所得金額や事業実態の証明
とくに個人事業主の場合は、信用度の担保のためにも期間内での確定申告を行いましょう。
5.確定申告の内容が間違っているときは修正申告
確定申告の内容が間違っており、なおかつ申告税額が本来より少ない場合は、修正申告によってあらためて正しい数値で確定申告をやり直します。
修正申告は、新しく修正後の数値を反映した、第一表・第二表の確定申告書の2枚を作成し提出します。2022年度の申告より修正申告用の第五表が廃止され、第一表・第二表の修正申告の欄が設けられました。
確定申告の期間後に自分で誤りに気づいた場合は、速やかに修正対応をしましょう。自主的な修正だと、追徴課税額がある程度優遇されます。
もし税務署からの指摘で発覚したときは税務署の更正となり、追徴課税額を多めに支払わなければなりません。時間が経つほど延滞税もかかります。
追徴課税を避けるために、確定申告前には内容に間違いがないか何度もチェックしましょう。
なお、確定申告の期間内に間違いに気づいたときは、修正申告ではなく訂正申告になります。修正が必要なものの、あくまで期間内の手続きに当たるため、追徴課税などのペナルティは発生しません。
6.確定申告を期間内に終わらせるコツ

期間内に確定申告を確実に終わらせるには、日々の帳簿付けや会計に関する業務効率化が重要になります。ここからは確定申告を期間内に終わらせるコツを紹介します。
1
帳簿付けはコツコツと進めておく
確定申告を行うには、収支や所得の計算の根拠となる帳簿付けが必須です。帳簿付けは1年分を短時間で一気に終わらせるのではなく、定期的にコツコツと進めることが大切になります。
定期的にコツコツ進めるメリットは次の通りです。
- ●定期的な確認で取引の抜けや記入漏れを都度チェックできる
- ●直前で焦って進めるよりヒューマンエラーを減らせる
- ●ミスが発覚したときにも余裕を持って修正できる
例えば1年分を短時間で一気に入力して記入漏れや計算ミスがあると、どこを修正すべきか1年分を再度調査するため、混乱が大きくなる可能性があります。
一方で毎日記入・1か月単位でのチェックを実施しておけば、ミスが発覚したときも確認範囲が最大でも1か月分になるので、ミスした箇所の特定・修正がすぐに済みます。
2
請求書や領収書などをしっかりと整理・保管しておく
帳簿への記入や経費の根拠となる請求書・領収書などの書類は、しっかりと整理・保管をしておきましょう。
個人事業主でありがちなのが、「領収書やレシートが見つからない」「明細を見たかったけど、過去の分が遡れなかった」などのミスです。期限ギリギリで焦る前に、普段から保管方法や場所をあらかじめ決めておくことをおすすめします。
整理・保管方法として、いくつか例を紹介します。
- ●保管場所をバラバラにせず一箇所にまとめておく
- ●「◯月分」「クレジットカードでの支払い分」など、属性ごとにファイル(電子ファイル含む)で分けておく
- ●仕事用の口座やクレジットカードを作っておき、プライベートと区別しておく
- ●クレジットカードや事業用口座の明細は早めにダウンロードや転載をしておく
3
会計ソフトを利用する
紙の帳簿やエクセルなどで確定申告のデータをまとめるより、会計ソフトを利用したほうが効率的かつ正確に確定申告が進みます。
会計ソフトを利用するメリットは次の通りです。
- ●簿記の知識がなくても数値を入力するだけで記帳できる
- ●確定申告書や青色申告決算書の作成にも対応している
- ●クラウド型のソフトなら、インターネット環境があればいつでも操作できる
- ●税理士との連携や登録口座との同期などができる
- ●単純な計算ミスを減らせる
- ●種類やプランによっては電子申告や消費税申告などにも対応してくれる
- ●帳簿付け・確定申告以外にも、収支レポートなど経営に役立つ機能・サポートを利用できる
月額費用や操作を覚える労力がかかるものの、業務効率化の面では非常にメリットが大きいです。
4
税理士に代行を依頼する
事業規模が大きかったり経理作業に回す労力がなかったりするときは、税理士に確定申告作業の代行を依頼するのも1つの手です。高い依頼料・顧問料がかかるものの、次のメリットがあります。
- ●高い専門知識や実務経験で正確な確定申告作業を実施してくれる
- ●記帳の代行も依頼できる
- ●顧問契約を結べば定期的な税務や経営、資金繰りについてのアドバイスを受けられる
- ●控除制度や経費申請などの節税についてのアドバイスを受けられる
- ●税理士に作業を任せられる分、こちらは営業活動やクリエイティブな作業に時間を割ける
- ●確定申告書の信頼度が上がる
とくに相続税や贈与税といった税制制度が複雑かつ揉めやすい確定申告は、税理士へ依頼することをおすすめします。
7.期間内に確定申告を終わらせよう!
確定申告の期間内に終わらせるのは、個人事業主やフリーランス、副業会社員にとっての義務です。追徴課税や信用度低下などのリスクを回避する意味でも、正確な期間を把握しておき、正しく確定申告を終わらせるようにしましょう。
期間内に終わらせるには、日々の帳簿付けや書類の整理を面倒くさがらないのがコツです。事業の状況によっては、会計ソフトや税理士の力を借りることも視野に入れましょう。
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
