確定申告書はどこでもらえる?書き方の注意点や提出方法を解説!
-
2023.2.06 (月)Posted by 北森 雅雄
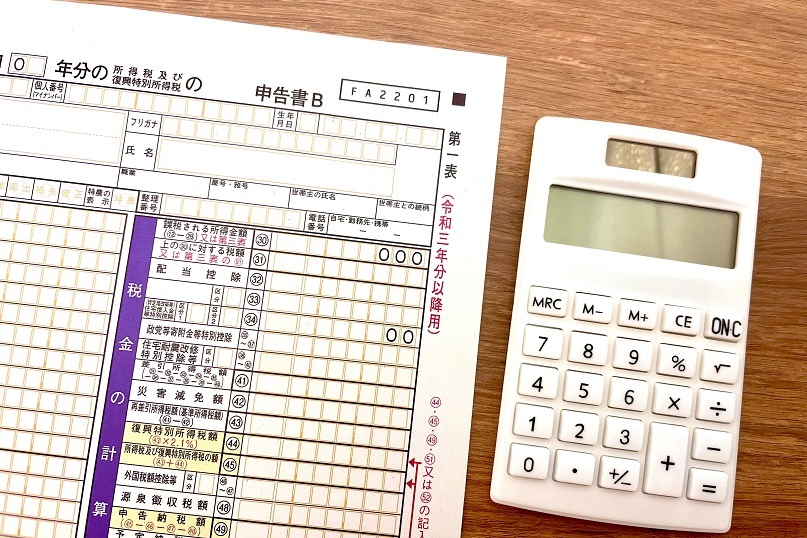
3月に確定申告が迫る際に、初めて確定申告をされるかたは「確定申告書の書き方が分からない」と不安に思う方も多いかと思います。
確定申告書は書類で提出するほか、e-taxを活用してオンラインで確定申告を済ませられるという選択肢があります。
本記事では
- ●確定申告書がどこでもらえるのか
- ●確定申告書を提出するまでのやり方
などの手順について解説します。
確定申告書のやり方をわかりやすく解説していくので、確定申告をされる際に是非参考にしてください。
目次:
1.確定申告書はどこでもらえる?

確定申告をする際には確定申告に必要な情報を記すための申告書(確定申告書類)を記載する必要があります。
確定申告書を入手するためには電子ファイルで入手するほかに、税務署が用意した書類を入手するといった方法があります。
- 1.国税庁のホームページでダウンロードする
- 2.税務署で受け取る
- 3.税務署から郵送してもらう
1
国税庁のホームページでダウンロードする
国税庁のホームページから確定申告書の書式をダウンロードできます。ダウンロードした書式をプリントアウトすることで確定申告書として利用可能です。自宅のパソコンやスマートフォンからダウンロードできるため、税務署へ行く必要がありません。
確定申告書の書類は年度ごとに様式が異なるため、必ず最新年度の書類を手配するようにしてください。
外部リンク:国税庁HP
外部リンク:確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)
また、税務署では「e-tax」による確定申告を推奨しています。e-taxを利用すれば確定申告書を用意しなくてもシステム上で確定申告を完結可能です。(システム上で確定申告に必要な情報を入力する)。
e-taxによる確定申告書では税務署へ行く手間も不要です。確定申告の時期は税務署が混雑するため、面倒な手続きを一部省略できます。
2
税務署で受け取る
確定申告書の書類を手に入れたい場合、税務署に行けば確定申告書のフォーマットを紙で入手できます。
税務署以外にも市区町村の役所や確定申告の相談所などさまざまな場所で確定申告書を配布しているため、お近くの役所を尋ねてみましょう
3
税務署から郵送してもらう
確定申告書を入手する際、税務署へ連絡すれば確定申告書を郵送してもらえます。郵送してもらえばわざわざ税務署へ行く手間が必要ありません。
郵送の手続きには数日かかることもありますので、確定申告の期限(例年は3月15日ごろ)に間に合うようスケジュールに余裕を持って手配をしましょう。
4
確定申告書のAとBの違いとは?
一般的に確定申告書Aは会社員が使う書式で、確定申告書Bは個人事業主が使う書式です。
両者の違いは取り扱える所得の種類に違いがあります。確定申告書Aは給与所得、雑所得、一時所得、配当所得に限られるため給与のみを得ているサラリーマンなど会社員向けの書式となっています。
給与所得とは会社に勤務することによって得られる給料による収入のことです。副業をしているサラリーマンであっても、副業先から給料を得ている場合は確定申告書Aで足ります。
| 書類の種類 | 対象となる人 | 取り扱える所得 |
| 確定申告書A | 会社員など給料を貰っているサラリーマンなど | 給与所得、雑所得、配当所得、一時所得 |
| 確定申告書B | 個人事業主など | 全ての所得 |
2.確定申告書には何を書く?

確定申告書ではフォーマットに基づいて必要な事項を記入します。確定申告書には何を書けばいいでしょうか?
ここでは、一般的な事例として確定申告書Aに記載する事項を紹介します。確定申告書Aは「第一表」と「第二表」の二部に分けられており、それぞれの書類に必要な情報を記入するものです。
1
第一表の記載事項
確定申告書の第一表には個人情報や所得金額など、確定申告をする際に必要な基本事項を記入します。
第一表に書かれた情報によって「納めるべき税金の金額」を決定します。税金を計算するための所得金額および所得から差し引かれる(控除される)金額を記載して納税額を計算するという流れです。
|
<確定申告書の第一表に記載する情報> ・個人情報(住所・氏名・個人番号・性別・生年月日) |
目的2
第二表の記載事項
確定申告書の第二表には所得の内訳や所得から差し引かれる控除額など、補助的な情報を記入します。
また、住民税に関する情報も第二表に記載します。
|
<確定申告書の第二表に記載する情報> ・所得の内訳 |
3.会社員も確定申告が必要?確定申告書が必要な条件とは

多くの会社員やサラリーマンにとっては確定申告の必要がありません。会社が年末調整をしてくれるおかげです。年末調整では会社が所得税の過不足を調整してくれるため、従業員が改めて確定申告をする必要がないようになっているのです。
会社員が確定申告をするべきケースは年末調整では調整しきれない所得税の計算を改める必要がある場合です。具体的な事例として、以下のケースに該当する場合が挙げられます。
- ●給与が2000万円を超えている場合
- ●副業や投資で収入がある場合
- ●控除書類を提出する場合
- ●ふるさと納税などで寄付をした場合
それぞれのケースについて、確定申告の手続きについて確認しましょう。
1
給与が2000万円を超えている場合
給与が2000万円を超えている場合は確定申告が必要です。税法によって年収の総額が2000万円を超える人は年末調整の対象外となるため、自分で確定申告をしなければなりません。
年末調整が行われないと生命保険料控除や社会保険料控除などが控除されないため、税金を払いすぎてしまうことになります。
2
副業や投資で20万円以上の収入がある場合
副業や投資など、複数の箇所から収入がある場合は確定申告をしなければなりません。年末調整の計算は給与所得のみが対象です。本来支払うべき税金を計算するためには自分で確定申告をする必要があります。
ただし、一般NISAやつみたてNISAなどの少額投資非課税制度を利用している場合は投資による収入について確定申告の必要はありません。また、副業による収入が20万円以内である場合も確定申告は不要です。
3
控除書類を提出する場合
サラリーマンなどの給与所得者は控除書類を添付することで特定の出費について控除を受けることができます。所得控除をすることで税金を計算するうえで支払うべき税金が少なくなるため、課税者にとって有利な制度です。
通常は年末調整の際に必要な控除書類を会社へ提出しますが、何らかの理由で提出ができない場合は自分で確定申告をしなければなりません。
例えば、保険料を控除する際は保険会社から受領した保険料の控除証明書を提出します。
| 控除の種類 | 添付する書類 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料の控除証明書 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料の控除証明書 |
| 地震保険料控除 | 地震保険料の控除証明書 |
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書 |
| 住宅ローン控除 | 請負(売買)契約書の写し など |
| 寄附金控除 | 寄附金を送った証明書 |
4
ふるさと納税などで寄付をした場合

ふるさと納税をした際に控除の摘要を受ける場合は確定申告が必要です。
ふるさと納税は応援したい自治体に寄附をする制度です。寄附金を納めることで寄附した金額を所得から控除できます。ふるさと納税で寄附した金額を確定申告することで節税対策になるのです。
ただし、ワンストップ特例制度を利用することで確定申告を省略できます。ワンストップ特例制度はふるさと納税をした後に寄付金控除を受けられる便利な制度です。
4.確定申告書のやり方と提出方法

確定申告書を提出する場合、以下3通りの方法があります。
- ●e-taxで申告する
- ●確定申告書を郵送する
- ●直接税務署へ確定申告書を持参する
1
e-taxで申告する
確定申告をするなら「e-tax」という国税電子申告システムの活用がおすすめです。
e-taxではインターネット等を通じてオンラインで確定申告の手続きができます。e-taxによる確定申告ではわざわざ税務署へ行く必要がないため、混雑期に税務署へ行く手間を省けるというメリットがあります。
e-taxによる確定申告はオンライン上の申告であるため、紙の書類を入手する必要もありません。
e-taxは以下のリンクからパソコンやスマートフォンを通じて確定申告を行えます。
参考リンク:e-tax|国税庁
2
郵送による方法
最寄りの税務署へ確定申告書を郵送すれば窓口で並ばずに確定申告ができます。
確定申告書は「信書」であるため、通常の郵便ではなく「信書便物」として送付する必要があるので注意してください。
3
直接税務署へ確定申告書を持参する
郵送以外にも直接税務署の窓口へ行って確定申告書を持参することが可能です。
税務署では不明点などを相談できるので、不明点があれば直接確認できるというメリットがあります。
ただし、確定申告の期間中、特に3月上旬から中旬など期限間近の期間は窓口の混雑が予想されるのでスケジュールに余裕を持って訪問しましょう。
5.確定申告書の書き方についての注意点

確定申告書を作成する場合は「青色申告」での確定申告がおすすめです。
青色申告とは税金を正しく納めるために制定された申告制度のことで、青色申告をすることで所得控除を受けられるなどの節税メリットがあります。
また、確定申告書は税金を正しく納めるために重要な書類です。確定申告書に誤りがあった場合、「更正の請求」という手続きで確定申告を修正できます。
1
青色申告のメリット
個人事業主などの事業所得者が確定申告をする場合、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
このうち、青色申告は正しく納税を行っていることを証明できる方法です。青色申告をすることで最大65万円の控除が受けられるなどのメリットがあります。
ただし、青色申告をする際は複式簿記の帳簿を残す必要があるなど事務的な作業が必要です。複式簿記とは日々の会計取引について費用の発生や現金の支出などを記録する会計手法です。
正しい納税をするには簿記の知識が必要になることもありますが、節税メリットがあるため可能であれば青色申告がおすすめです。
2
確定申告をしないとどうなる?
確定申告の対象者が確定申告をしないのは納税の義務に違反します。
確定申告をしなければならない人が確定申告をしていなかった場合、ペナルティが課せられます。ペナルティの内容は「無申告加算税」や「延滞税」といった追徴課税です。
確定申告を怠っていると本来支払わなくてもいい税金も支払うことになってしまうため、忘れずに確定申告をしましょう。
3
確定申告を誤った場合
確定申告が誤っていた場合は「更正の請求」という手続きで修正ができます。
納付する税額が多すぎたり少なすぎる場合は更正の請求によって正しい税額を申告しなおしましょう。
税額が申告より多かった場合は申告を修正することで納めすぎた税金を還付金というかたちで返還されます。
税額が申告より少なかった場合は申告を修正し、不足している税額を新たに納付します。確定申告の修正をする場合、過少申告加算税および延滞税がかかる場合があるので注意しましょう。
なお、更正の請求は原則として確定申告の期限から5年以内です。
6.確定申告を早く済ませるなら「おまかせ はたラクサポート」がおすすめ!
確定申告をスムーズに済ませるなら「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」がおすすめです。
取引入力など日々の経理業務をサポートし、確定申告のサポートをします。
クラウド型のシステムであるため、インターネット環境さえあれば初期費用をかけずに利用できます。法人向けサービスはもちろん、個人事業主向けのサポートも万全です。
1
スムーズに記帳ができる!
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」は会計業務をサポートするツールです。
稟議から経費精算、会計業務まで一気通貫することでバックオフィス業務をトータルサポートします。
経理業務を自動化することで決算業務を効率化し、経営状況や財務状況の見える化を実現します。
2
e-taxで確定申告のサポート!
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」を使ってe-taxと連携することで確定申告をスムーズに利用できます。
初めての確定申告は税金の計算から所得控除など複雑な仕組みを理解しなければなりません。「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」では質問に答えるだけで確定申告に必要な情報を入力できるので、複雑な制度を知らなくてもスムーズな確定申告ができます。
7.まとめ
確定申告は税金を正しく納めるために必要な手続きです。
確定申告書は税務署や役所で入手できるほか、国税庁のホームページでダウンロードして入手できます。「e-tax」を使えばインターネットを通じて簡単に確定申告ができるため、郵送手続きや窓口に並ぶ必要がありません。
「freee会計 for おまかせ はたラクサポート」を使えば面倒な確定申告の手続きも簡単になります。会計ソフトに会計データを入力するだけで確定申告の手続きまで完結できるので、会計についての知識に自信がないという方も安心して確定申告ができるソフトです。
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
