請求書発行のタイミングはいつがよい?適切な発行日や法的な注意点を解説!
-
2024.4.05 (金)Posted by 北森 雅雄
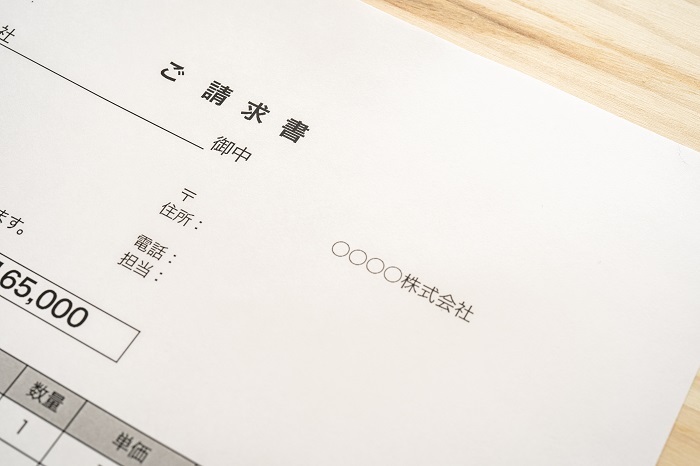
請求書発行のタイミングについて法的に定めはありません。とはいえ、請求書は提供した商品や役務への対価を請求するためのものですので、手元の資金効率を向上させるためにも迅速に請求する必要があります。
請求書発行のタイミング、請求書発行に関する注意点を把握して、迅速な請求業務を実現させましょう。
1.請求書発行のタイミングは法的に決められていない

請求書発行のタイミングについて法的に定めはありません。とはいえ、一般的に発行されるタイミングはあります。
1
そもそも請求書発行は法的に必須ではない
2023年8月現在、請求書発行は法的に義務付けられていません。しかし、消費税の仕入税額控除や相手方とのトラブル防止のため、請求書発行はほぼ必須になっています。
とくに、2023年10月のインボイス制度施行後、適格請求書発行事業者であれば、相手方に適格請求書発行が求められた場合、適格請求書の発行が義務になります。ほぼすべての事業者が請求書の発行が必要です。
|
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています |
出所:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問1
以上のような背景があり、法的に請求書の発行義務が現状ないとはいえ、ほぼ義務であると認識を持っていただくとよいでしょう。
2
請求書に記載される発行日はなぜ必要なのか
請求書への発行日記載も法的に必須ではありません。とはいえ、商取引上、仕入事業者(債務者)は提供された商品や役務へ代金を支払う債務が生じます。この債務に対して、請求書上に発行日を記載することで、請求先に対して債務が生じた日付を明らかにできるのです。
発行日(請求日)が明らかになることで、債権者は債務者に対して、請求をする法的な根拠を持つことが可能です。
|
(債権等の消滅時効) |
以上の背景から債権者は法的な根拠を持って、請求業務を行うために請求書上に発行日(請求日)の記載が必要になります。
3
請求書発行日の一般的な決め方
請求書の発行日は実際に請求書を発行した日付とする場合は稀であり、相手方の締め日に合わせて記載するのが一般的です。
企業には「毎月月末締め、翌々月10日支払い」など、締め日・支払日が決まっている場合が多いため、相手方の締め日・支払日を事前に確認したうえで、請求書上に発行日を記載しましょう。
例えば、以下のケースの場合、請求書発行日は7月31日とします。
- ●7月15日に商品を納品した。請求書を8月3日に送付する。
なお、請求書の送付日については事前に相手方に確認が必要です。事前に送付期日を確認して、期日までに送付できるようにしましょう。
2.請求書発行をする2つのタイミング

請求書は商品や役務に対する代価を請求する際に発行するので、基本的に納品後に発行されます。したがって、請求書の発行は納品時、または、納品後に実施されるのが一般的なようです。
とはいえ、取引量に応じて以下2つのタイミングで請求書を発行する場合がありますので、事前に相手方とどちらのタイミングで請求書を発行する必要があるか確認しておくようにしましょう。
- ●タイミング①:掛売時
- ●タイミング②:都度
タイミング①
掛売時
月に複数回取引を行う場合、掛売を行うケースが多いです。1か月の間に発生した取引を月末などで締め、請求書を発行します。掛売の方式で請求書を発行することで、お互いの業務を効率化できる点が利点です。
利点が大きいため、継続的に取引がある企業の場合、掛売方式で請求書を発行する場合が多いようです。
タイミング②
都度
都度方式とは、商品や役務を提供する都度、請求書を発行する方式です。業務効率の点でみた場合、掛売方式で請求書を発行するケースが多いですが、相手方の中には都度方式で請求書発行を求める事業者もいます。
取引を始めたばかりで信用を得てから売掛方式に切り替えたい企業、単発の取引を想定している企業などの場合、都度方式による請求書発行を求める場合が多いようです。
都度方式の場合、取引が行われる都度、請求書の発行が必要になるため、業務負荷が比較的高くなります。したがって、継続的に取引をすることが確定した時点などのタイミングで掛売方式に切り替えるようにしましょう。
3.請求書の発行日に関する注意点

請求書発行時には注意すべきポイントがいくつかあります。代表的なポイントは以下の通りです。
- ●注意点①:請求書の保存期限は発行日からの起算ではない
- ●注意点②:支払期日は60日以内にする必要がある
- ●注意点③:2か月+7営業日以内に電子請求書は保存する必要がある
- ●注意点④:請求書を再発行する場合、以前に作成した請求書と同発行日にする必要がある
注意点①
請求書の保存期限は発行日からの起算ではない
請求書上の発行日を起点として保存期限が必ずしも決まるわけではない点に注意が必要です。
請求書は税法上の国税関係書類に該当しますので、法人税法上で7年以上の保存があります。この保存は受領した請求書に限らず、送付した請求書も対象であり、税務申告の際に必要な書類です。
|
2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 |
また、この保存期間の起算日は確定申告書の提出期限の翌日からカウントされます。法人の場合、事業年度の末日から2か月後からカウント開始です。つまり、請求書の発行日から保存期間が必ずしも決まるわけではないので、注意しましょう。
注意点②
下請け事業者に対する支払期日は60日以内にする必要がある
下請け事業者を保護する目的で下請代金支払遅延等防止法では、物品を受領した日(役務の提供をした日)から起算して、60日以内、かつ、可能な限り短い期間で下請代金の支払期日を定める必要があります。
|
(下請代金の支払期日) |
商売をするうえでは、支払いサイトを可能な限り伸ばした方が有利ですが、上記法律により下請け業者に対する支払期日は制限されている点に注意が必要です。
注意点③
2か月+7営業日以内に電子請求書は保存する必要がある
電子帳簿保存法 電子取引要件上ではタイムスタンプを付与して真実性(文書が改ざんされていないことを証明する要件)を満たす場合には、請求書上の発行日から最大で2か月+7営業日以内にタイムスタンプを付与する必要があります。
|
問56 「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行う」とは何日以内にタイムスタンプを付与すればよいのでしょうか。 【回答】 |
電子帳簿保存法 電子取引要件では、他同要件上の検索要件対応で請求書上の発行日で検索できる必要がありますので、相手方と発行日をいつとするか認識を合わせた上で、発行日を記載した請求書を渡せるようにしましょう。
仮に2か月+7営業日以内にタイムスタンプを付与できなかった場合には、可能な限り迅速にタイムスタンプを付与して保存することとされているものの、対応漏れがないようにしておくことが重要です。
注意点④
請求書を再発行する場合、以前に作成した請求書と同発行日にする必要がある
業務上、発行者の記載ミスや相手方の紛失により請求書の再発行をする必要が求められる場合があります。この場合、発行日はミスなどをした請求書と同じ発行日にしてください。
また、再発行した請求書であると判別をつけるために、請求書上に再発行印を押すなどして、ミスをした請求書を見分けがつくようにしておくと、親切です。もし、紛失した請求書が発見されたときに、1通目の請求書と見分けがつくからです。
支払期日については、支払期日後に再発行を求められたのであれば、再設定が求められます。契約書上で延滞利息に関する取り決めを交わしていた場合には、延滞利息に関して記載を明記したうえで、支払期日の記載をする必要がある点に注意ください。
4.まとめ 請求書は発行するつもりでいよう

請求書の発行は法的に必須ではないものの、2023年10月のインボイス制度施行以降、多くの事業者で請求書の発行が義務化すると想定されています。
また、請求書上に相手方と合意した発行日を記載することで、無用なトラブルを避け、良好な関係性を築く一つのきっかけになりますので、相手方と合意を得た発行日を記載して請求書を発行するようにしてください。
とはいえ、請求書発行には少なからず工数を伴います。小工数で対応する場合には電子請求書システムを活用するのも一つの手段です。
NTT東日本では、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ一度ご検討ください。
-
電子請求書ならサービスとサポートをセットに!
 電子請求書 無料体験申込フォーム
電子請求書 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子請求書をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
