請求書発行に義務はある?インボイス制度など関連する法律を解説!
-
2024.4.05 (金)Posted by 北森 雅雄

請求書の発行は法律上義務付けられていません。ただし、相手方の消費税仕入税額控除や取引上のトラブル防止を考えると、請求書の発行は実務上ほぼ義務であるといえます。
また、請求書の発行義務以外にも請求書の有効期限や保存方法、保存期間については、民法や法人税法、電子帳簿保存法など、様々な法律が関連していますので、事前に把握しておきましょう。
目次:
1.請求書発行に義務はないが、発行が実務上ほぼ必須
請求書の発行は法律上で義務付けられていません。しかし、以下の理由から実務上、請求書発行はほぼ義務であるといえます。
- ●理由①:消費税の仕入税額控除をするために請求書が必要
- ●理由②:相手方とのトラブル防止のために必要
理由①
消費税の仕入税額控除をするために請求書が必要
相手方が消費税の仕入税額控除をする際、証跡として請求書が必要になるため、請求書の発行は必然的に求められるケースが多いようです。
仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税額を算出する際に、売上に係る消費税から、仕入にかかった消費税を控除できる制度です。仕入税額を控除できない場合、支払う消費税が多くなるため、多くの事業者が仕入税額控除を行います。
理由②
相手方とのトラブル防止のために必要
請求書は取引が行われたことの証跡として利用される場合も多いです。請求書上の取引情報に変更がある場合には、修正した請求書を証明書として保存しています。
つまり、請求書に対して法律上の請求書発行の義務はないものの、認識齟齬を減らし、無用なトラブルをさける機能を持っているのです。
2023年10月のインボイス制度施行後、事業者によっては適格請求書の発行がほぼ義務になる
2023年10月のインボイス制度施行後、適格請求書発行事業者は相手方から発行依頼がある場合には適格請求書の発行が消費税法上、義務になります。
|
適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています |
出所:消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問1
2023年10月に施行されるインボイス制度は、従前どおり仕入税額控除をするためには適格請求書発行事業者が発行した請求書を入手しなければ、仕入税額控除ができない制度です。
従前どおり仕入税額控除をするため、適格請求書発行事業者を仕入先として優先する可能性が高いとされています。したがって、多くの事業者は適格請求書発行事業者になることが予想されているため、適格請求書の発行はほぼ義務になるといえるでしょう。
2.請求書の有効期限は実務上5.5年
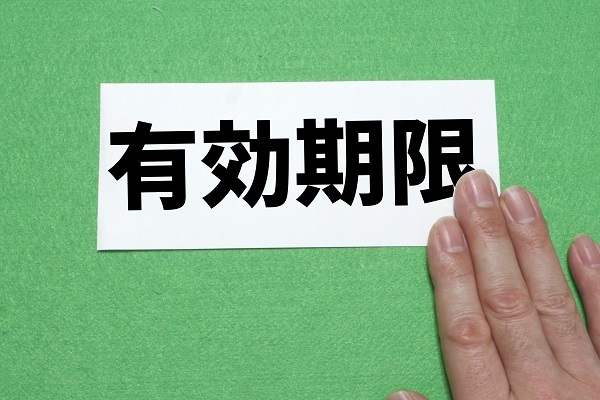
現状、請求書発行は法的に義務ではありませんが、一度発行すれば法的な効力を持ちます。ただし、請求書には最大で5.5年の有効期限がありますので注意が必要です。
1
請求書の有効期限は基本的に5年
請求書は相手方との取引情報の証跡として有効な文書です。もし相手方が支払いを渋る場合に、取引を証明する証跡になります。請求書は債権の一種であると考えられるため、民法上で請求書の有効期限は5年です。期限内であれば証跡として法的効力を持ちます。
|
(債権等の消滅時効) |
2
支払い督促を送付すれば+0.5年
請求書を送付したけれども、相手方が請求に応じない。その場合、基本的に以下の段階を経て督促を実施します。
- 1.メールなどで催促
- 2.催促状の送付
- 3.督促状の送付
例えば上記のような流れを経て内容証明郵便による支払い督促をすることで、さらに6か月間の有効期限延長ができます。
|
(催告による時効の完成猶予) |
つまり、民法上で定められた請求書の有効期限5年と併せて5.5年の法的効力の有効期限を持つことが可能です。
3.請求書の保存期間は基本的に7年
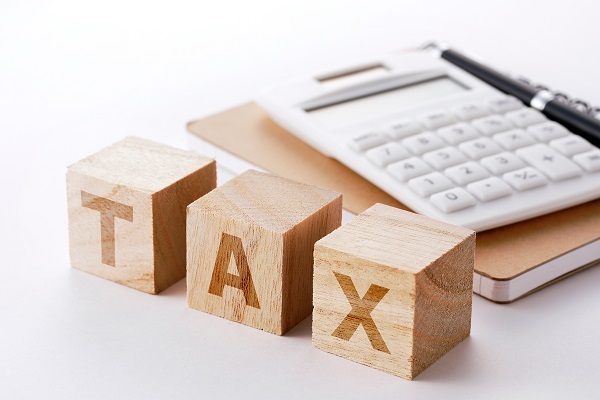
法人の場合、請求書は税法上で最低7年間の保存が必要です。ただし、実務上の保存期間を考えると、保存期間が伸びる可能性がある点に注意ください。
1
保存期間は7年~10年
税法上の国税関係書類に該当する請求書は7年間の保存が必要です。
|
2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 |
ただし、繰越欠損金を見込む場合には10年間の保存が求められています。
|
第二十六条の三 内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合~中略~第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない |
加えて、確定申告書の提出期限の延長特例を受ける場合には、確定申告書の提出期限がさらに2か月延長されます。したがって、最大で10年2か月、法律上は保存を求められています。
2
実務上の保存期間は8年2か月~11年2か月になる場合が多い
法律上、請求書は7年〜10年2か月の保存が求められていますが、実務上は8年2か月〜11年2か月の間保存される場合が多いです。
請求書の保存開始日は確定申告書の提出期限翌日からカウントされます。青色申告法人の場合、事業年度の末日から2か月後がカウント開始日です。つまり、もしカウント開始日当日に請求書を受領した場合、その請求書は8年2か月は最低保存が必要になります。
繰越欠損金を見込む場合についても同様の考え方で、最大11年2か月の保存が求められるのです。したがって、8年2か月〜11年2か月の保存が求められています。
確定申告の延長特例を見込み+2か月保存期間を見込む必要も企業によってはありますが、多くの企業では見込まず、8年2か月〜11年2か月の期間保存する場合が多いようです。
4.請求書を電子的に送付する場合、電子帳簿保存法対応が必要
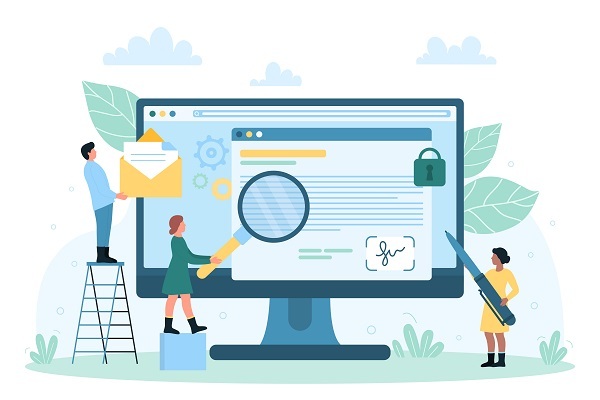
国税関係書類である請求書を相手方にメールなどの電子的な手段で送付する場合、電子帳簿保存法に基づいた保存が必要です。もし、保存要件を満たさず保存している旨を税務調査時に指摘された場合、青色申告の承認取り消しなどのリスクがありますので注意ください。
1
電子取引要件を満たした保存が必要
例えば以下の方法でやり取りした請求書は電子取引に該当するので、電子取引要件を満たした保存が必要です。
- ●メールに請求書を添付してやり取り
- ●電子請求書配信システム経由での請求書のやり取り
- ●EDI経由で請求情報のやりとり など
電子取引要件では以下の要件を満たして保存が必要です。
- ●真実性の確保(タイムスタンプの付与など)
- ●検索性の確保(主要3項目での検索など)
発行した電子請求書に対して、真実性の確保では以下3ついずれかの手段を選択して実施することが認められていますので、各企業で対応がしやすい方法を選択してご対応ください。
- ●タイムスタンプの付与して保存する
- ●訂正削除ができないシステム、または、訂正削除が考慮されたシステムに保存する
- ●訂正削除の防止に関する事務処理規程を作成する
最も簡単、かつ、確実に真実性を確保する手段はタイムスタンプの付与です。一方で、最も初期コストを抑えて対応する方法は事務処理規程の作成です。各企業が重視する点に合わせて選択しましょう。
1
発行システム上でデータレコードして保存する選択肢もある
請求書を発行する際、請求情報を請求システムから帳票作成ツールなどに連携してPDFを作成後、送付する場合も多いです。
この場合、大元の請求システム上で電子取引要件を満たすことができれば、発行したPDFの保存は不要にすることができます。
|
問 41 |
ただし、請求書を発行した際のフォーマット形式を確認される場合もありますので、ご留意ください。
|
なお、税務調査の際には、実際に先方へ提供したフォーマットに出力して確認をさせていただくこともありますのでご協力ください |
5.まとめ 請求書の発行は基本的にしておこう

請求書の発行は法律上必須ではありません。しかし、2023年10月以降、適格請求書発行事業者であれば請求書発行はほぼ義務化される上、実務上でも必然的に求められますので、請求書の発行を推奨しています。
また、請求書発行の義務に関する法律以外にも、法的効力の有効期限や保存期間、保存方法について電子帳簿保存法などの法律が関わってきますので、この機会に目を通してください。
もし対応に漏れがある場合には、対応可能なシステムを導入するなどして確実に対応をしていきましょう。
NTT東日本では、インボイス制度・電子帳簿保存法に対応した「BtoBプラットフォーム 請求書 for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ一度ご検討ください。
-
電子請求書サービスとサポートをセットに!
 電子請求書 無料体験申込フォーム
電子請求書 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子請求書をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
