社印(角印)の電子印鑑の作成方法と効力|無料の作り方とメリット・デメリット
-
2023.4.04 (火)Posted by 北森 雅雄

「社印の電子印鑑を無料で作る方法を知りたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
電子印鑑の社印は、印影画像のスキャンまたはフリーツールを利用すれば無料で作成できます。
無料で作成した電子印鑑の社印は作成が簡単で便利な点がメリットですが、大きなデメリットも存在する点を見落としてはなりません。社印と電子印鑑の特徴と法的根拠について理解できれば、自社に最適な作成方法が見えてくるでしょう。
本記事では、社印と電子印鑑の特徴および無料での作り方を詳しく解説します。
法的根拠に基づく社印の電子印鑑を利用したい時におすすめの方法も分かる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次:
1.社印(角印)の役割とは?

「社印」には、会社の認印としての役割があります。実印や銀行印などとは異なり、会社で日常的に使う印鑑です。
印鑑の枠組みが角が丸い四角形であることから「角印」とも呼ばれています。社印は見積書・請求書・領収書などの書類に押印される印鑑であり、郵便物の収受の際に押印することも可能です。
このように、社印とは簡易的な確認の証拠としての効果を持つ印鑑だといえます。社印の押印は会社の代表者でなくとも行えるうえ、外部に出す書類に使用する機会も多いはず。
不正に複写して悪用されることで損害が生じる恐れがないとは言い切れませんので、社印は契約書などの重要な書類への押印や実印などとの併用をしないほうがいいでしょう。
社印と混同されやすいワードとして知っておきたいのが「社判」です。社判と社印の違いは、簡単にいうとその名称が指し示す範囲。
社判は実印(丸印)・銀行印・認印などを始めとする、会社名義の印鑑すべてを含みます。
一方、社印は会社の認印のみを示す名称です。要するに、社印は社判の一部だということになります。
2.電子印鑑の役割とは?
電子印鑑の役割は、実物の印鑑と変わりません。印影画像をデジタル化したツールが電子印鑑です。
オンライン上で押印が完了する電子印鑑は、昨今の書類やサービスのデジタル化やテレワーク推進の風潮の中で、会社や法人からの注目を集めています。
電子印鑑の種類は、大きく分けて次の2タイプです。
- ●ただの印影画像としての電子印鑑
- ●正当性を証明できる機能を付与した電子印鑑
印影を模写しただけの電子印鑑は、100円均一ショップなどで購入できる大量生産された印鑑と同様の役割を持ちます。作成方法が非常に簡単かつ無料で作成できる反面、法的な効力はありません。
電子印鑑の場合、デジタル上で使用されるという性質から、実物よりも印影の抜き取りや改ざんがしやすいといえます。
一方、電子印鑑が正当に押印されたものであると証明する機能を付け加えたタイプの電子印鑑は、実物の実印と同程度の法的効力を発揮します。
有料サービスの契約を交わす必要がありますが、非常に安全かつ容易にデータ管理ができるようになるのがメリットです。
さらに、ペーパーレス化や業務の効率化によるコスト削減まで考慮すると、有料の電子契約・決裁サービスの利用はむしろコストパフォーマンスが高い手段だといえます。
3.社印の電子印鑑を無料で作る方法

社印の電子印鑑を無料で作るには、主に以下の3つの方法があります。
- ●実物の印影を撮影・スキャンして取り込む
- ●エクセルの図の挿入機能を活用する
- ●フリーソフトなどを使用する
1つずつ説明していきます。
1
実物の印影を撮影・スキャンして取り込む
実物の印影と同じ社印の電子印鑑を作成する方法です。作成は次の手順で行えます。
- 1.実物の印鑑を白い紙に押印する
- 2.撮影またはスキャンして画像を取り込む
- 3.エクセルを開き、挿入タブの「図」をクリック
- 4.「写真」→「図をファイルから選択」の順に進める
- 5.不必要な余白部分をトリミングして画像を整える
- 6.ツールバー内「図の書式設定」の「背景の削除」ボタンを押す
- 7.右クリックで現れるメニューリストから「図として保存」を選択
- 8.PNG形式の図として保存する
実物の印影を利用する方法で電子印鑑を作成すると、実物と同一の印影を手軽に作成できます。
細かい調整を行えば、実物の印鑑で押印した印影と見分けがつかないほど精巧な電子印鑑を作成可能です。
手順8で右クリックしても「図として保存」が表示されない場合、画像を右クリックしてコピーし、ワードに貼り付けてから同作業を行ってください。
2
エクセルの図の挿入機能を活用する
エクセルの「図の挿入」機能を活用し、社印の電子印鑑を一から作成する方法です。
- 1.エクセルを開き「挿入」タブの「図形」をクリック
- 2.「角丸四角形」を選択し、エクセルシート上にドラッグして図形を描く
- 3.図形の上で右クリックし「図形の書式設定」を開く
- 4.「塗りつぶし」をクリックし「塗りつぶしなし」にチェックを入れる
- 5.線の色を朱色に近いカラーに調整
- 6.線の幅を好みのサイズまで太くする
- 7.「図の書式設定」から「文字のオプション」を選択
- 8.「テキストボックス」アイコンをクリックして「文字列の方向」を縦書きにする
- 9.「図形内で折り返す」にチェック
- 10.枠線上で右クリックし「テキストの編集」を選択して会社・法人名を入力
- 11.右クリックしてPNG形式の図として保存する
印鑑の枠組みは18mm~24mm程度の大きさが一般的です。
また、電子印鑑の枠組みおよびテキストの色をグラデーションにすると、押印時のかすれのように見せることができます。
3
フリーソフトなどを使用する
社印の電子印鑑を無料で作成するツールは、以下のソフトやアプリなどが人気です。
- ●クリップスタンプ
- ●電子印影
- ●マイスタンプメーカー
電子印作成フリーツールには、ソフトをダウンロードするものやブラウザ上で作業が完了するアプリなど様々なタイプがあります。
上記のほかにも社印を作成できる無料ツールはありますが、本記事ではWindows11対応のものをピックアップしました。
フリーソフトを利用すれば、まるで実物の印影のような電子印鑑があっという間に完成します。押印方法も簡単なので、急いで簡易的な電子印鑑を準備しなくてはならない時などに非常にありがたいツールです。
ただ、無料の作成ソフトを使用して電子印鑑をする場合、ダウンロードの際に不必要なファイルまで同時に取り込まれることがあります。
また、ウイルス対策などのセキュリティをしっかりと行っていない場合、不慮のトラブルに見舞われる危険性も考慮しなくてはなりません。
このため、電子印鑑作成のフリーツールを使用したい時は、社内の規定を確認し事前に許可を取ってから作業を行ってください。
4.社印の電子印鑑を作成するメリット
社印の電子印鑑を作成して活用すると、以下のメリットが得られます。
- ●効率的な業務遂行が可能になる
- ●コストを削減できる
社印の電子化によるメリットを紹介します。
1
効率的な業務遂行が可能になる
社印の電子印鑑を導入すると、押印にかかる一連の業務の短縮が可能です。せっかく書類がデータ化していても、いちいち出力して押印していると電子化のメリットが台無しになってしまいます。データ出力という雑務がなくなるだけでも、大幅な時間短縮につながるでしょう。
また、書類をデジタル化すると管理が簡単です。紙の書類の整理・検索にかかっていた時間が短くなり、紛失の心配も減らせます。
同時に、社印を電子化すれば社内での文書回覧がスピーディーに行えるようになるでしょう。従来の決裁方法では、決裁権者が不在の場合に業務が滞るという問題がありました。電子印鑑ならどこにいても決裁・押印が可能になるため、ハンコを推すためだけに出社する必要がなくなります。
雑務にかかる時間が削減できれば、社員はより価値のある仕事に専念できますので、生産性の向上にもつながります。取引先との契約成立などもスムーズに行えるため、さらなるビジネス拡大のきっかけになるかもしれません。
加えて、電子印鑑を含む業務のデジタル化はテレワークとの相性がよく、社員のスキルやライフスタイルに合った働き方が実現するでしょう。
2
コストを削減できる
社印をデジタル化すれば、これまで紙の書類を取り扱うためにかかっていたコストを一気に削減可能です。
たとえば、コピー用紙代・インク代などの消耗品費や書類の郵送料金などは大部分が不要になります。
契約書や領収書などに課されていた印紙税を納めずにすむ点もメリットです。
5.社印の電子印鑑を作成するデメリット
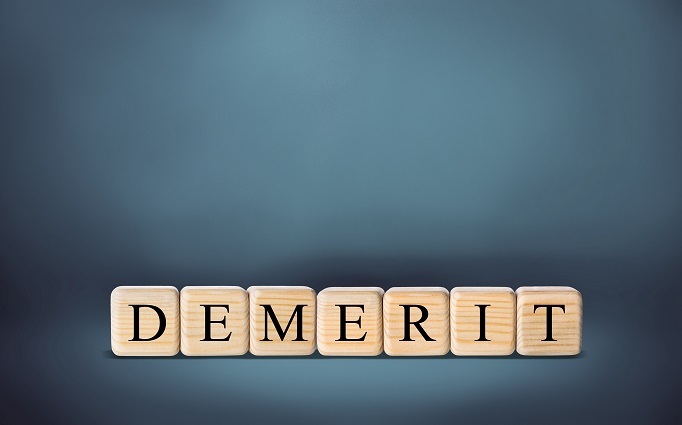
一方、社印の電子印鑑を作成・使用することで生じるデメリットには、以下の点が挙げられます。
- ●厳重なセキュリティ対策を施す必要がある
- ●電子印鑑を使用できない場合がある
社印を電子化するデメリットについて、法改正なども交えて解説します。
1
厳重なセキュリティ対策を施す必要がある
無料で作った電子印鑑を社印にする場合、安全性の低さが大きな問題となるためセキュリティ対策を厳重に施す必要があります。
無料で電子印鑑を作成するのは簡単であるがゆえに、容易に複製されてしまうでしょう。見積書や請求書などの社外文書に押印する社印の電子印鑑を作る際には、無料で作成するのはおすすめできません。
複製や改ざんへの対策として、個別に識別できる情報やタイムスタンプを電子印鑑に付与する方法が挙げられます。しかし、個人や会社単位で電子印鑑に識別データなどを付け加え、管理するのは難しいでしょう。
2
電子印鑑を使用できない場合がある
社印の電子印鑑を作成したからといって、すべての書類に押印可能なわけではありません。
現在、電子化できないと法律で定められているのは以下の4つの契約です。
- 1.任意後見契約書
- 2.事業用定期借地契約
- 3.企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
- 4.特定商取引(訪問販売等)の契約等書面
1~3については公正証書の作成が義務付けられているため、現状では電子書類にはできません。
しかし法務省では、2022年6月に閣議決定された規制改革実施計画において、2025年7月上期を目処に公正証書のデジタル化を認める法律の施行を目指す旨が公表されています。
4についても、特定商取引でのトラブルから消費者を守るために書面での契約が必要となっていますが、2021年6月に特定商取引法が改正されました。
事前に消費者の承諾を得ている場合に限り、電子契約書での交付が可能になることが決定しています。特定商取引の契約等書面の電子化は、2023年6月15日までには施行される予定です。
現在はまだ電子取引や電子印鑑が一般的になっているとはいえない状況であり、法的に認められているとしても取引先の許可を得ないことには電子印鑑を契約や取引に用いることはできません。
とはいえ、近年の法改正からも分かるとおり、取引や書類の電子化は今後も加速度的に進められると考えられます。すべての書類が電子化し、電子印鑑が使えない書類がなくなる日も遠くないかもしれません。
6.社印の電子印鑑の法的効力とは?
社印の電子印鑑には法的効力があるのか?という問いに対しては「YESでもありNOでもある」というのが答えです。
この理由を説明するために、以下の2点に言及する必要があります。
- ●二段の推定に基づく法的根拠
- ●契約上の押印は必須ではない
押印は「二段の推定」により法的な効力を持ちます。
しかし社印や認印などによる押印は、一定の条件を満たせば実印と同様の効力を持つという判例はありはしますが、事実上は二段の押印が適用されることはほとんどありません。
これらの根拠についてそれぞれ解説していきます。
1
二段の推定に基づく法的根拠
"民訴法第228条第4項には、「私文書は、本人[中略]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の中に、本人の押印(本人の意思に基づく押印と解釈されている。)があれば、その私文書は、本人が作成したものであることが推定される。"
引用:経済産業省 | 押印に関するQ&A
要約すると、署名または印影が本人の所有物によるものだという証明ができれば押印は本人が行ったと推定され、当該文書は本人の合意の下で作成していると見なされるということ。
この「推定から推定する」という流れが、法律でいうところの「二段の推定」です。
また、二段の推定は社印にも適用されると示されています。
"「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る(最判昭和50・6・12裁判集民115号95 頁)。
文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であるといえる。"
引用:経済産業省 | 押印に関するQ&A
押印された印影が本人所有の印鑑と同一だと証明できれば、社印でも法的効力を持つということです。この二段の推定を根拠に、電子署名法第3条の規定が定められています。
2
契約上の押印は必須ではない
しかし、経済産業省では、押印がなくても契約が成立するという見解も示しています。
"私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。"
引用:経済産業省 | 押印に関するQ&A
印影は簡単にコピーできてしまううえ、二段の推定はあくまで「見なし」の域を超えないため、絶対的な正当性の証明にはなり得ません。
特に社印や認印での押印は、二段の推定が及ぶケースが極めて少ないのです。
このため経済産業省では、テレワークが増加していくであろう現代において、契約の際に押印を省略または別の手段に代替することが推奨されています。
7.社印の電子印鑑を活用するなら電子契約サービスがおすすめ

会社・法人の社印として電子印鑑を導入するなら、電子契約サービスの利用を検討してみてください。
無料で作成した社印の電子印鑑は実印と比べて法的根拠に乏しく、悪用されると会社全体が大きな損害を被る可能性があります。また、経済産業省が押印以外の手段を証拠とするのが有意義だと位置付けていることから推測すると、時流はいずれペーパーレスだけではなく印鑑レスに向かうとも考えられます。
民事訴訟法第228条4項、電子署名法第2条、および第3条に定められる法的根拠に基づく電子契約サービスなら、電子印鑑より強固な法的効力を発揮します。さらに、管理が手軽で業務効率が数段アップするという大きなメリットを得られるでしょう。
電子契約サービスの導入を検討する際には、以下の点を比較して選択してください。
- ●どの契約に使えるか
- ●通信は暗号化されているか
- ●承認権限の付与ができるか
- ●タイムスタンプ付与できるか
- ●オプション機能が充実しているか
- ●外部サービスと連携できるか
電子契約サービスを比較する際は、セキュリティへの配慮が大きなポイントになります。
電子署名およびタイムスタンプによる認証データの付与を行えるサービスなら、安心して管理を任せられるでしょう。
取引先へのリマインド機能や期限のアラート機能など、電子契約サービスごとに様々なオプション機能が備わっています。また、外部サービスとの連携が行える電子契約サービスもあり、よりスムーズな業務遂行が可能になるでしょう。
8.まとめ
社印とは会社名義の認印のことであり、見積書・請求書などの書類に押印するための印鑑です。
一方、電子印鑑とは印影画像をデータ化したものであり、効力の異なる2つのタイプが存在します。
社印の電子印鑑は無料で作成することも可能です。エクセルやフリーツールなどを用いて作成すれば、非常に簡単かつ短時間で電子印鑑が完成します。
社印の電子印鑑をビジネスや決裁に導入すれば、業務の効率化やコスト削減などの多くのメリットを得られるでしょう。
しかし無料で作成した電子印鑑にはセキュリティ面に大きな不安があり、すべての取引に活用できるとは限らないというデメリットが存在します。
さらに法的根拠を考慮すると、会社が使う印鑑として適しているとはいえません。
会社や法人がビジネスに電子印鑑を導入する際は、電子決裁サービスの利用がおすすめです。電子署名とタイムスタンプを組み合わせて法的効力を担保する電子契約サービスは、セキュリティ対策が万全なうえ業務の効率化につながります。
様々なオプション機能がありますので、しっかりと比較・検討して最適なサービスを選びましょう。
NTT東日本では電子署名やタイムスタンプにも対応した「クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。
ぜひ検討の1つの選択肢としていただければ幸いです。
-
電子契約ならサービスとサポートをセットに!
 電子契約 無料体験申込フォーム
電子契約 無料体験申込フォームNTT東日本では、電子契約をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
