クラウド型勤怠管理システムを利用して打刻するメリットと特徴を解説!
-
2024.4.05 (金)Posted by 北森 雅雄

働き方改革の影響により、厳密な勤怠管理が求められるようになりました。勤怠管理を効率化する手段として勤怠管理システムがあります。一方、クラウド型、オンプレミス型のいずれを選択すべきか悩まれる企業さまも多いようです。
当記事では、クラウド型とオンプレミス型勤怠管理システムの違い、クラウド型勤怠管理システムを導入する際のメリットと注意点、クラウド型とオンプレミス型いずれを選択すべきかの選択ポイント、比較時に見るべき搭載機能までご紹介します。
目次:
1.クラウド型とオンプレミス型の違い
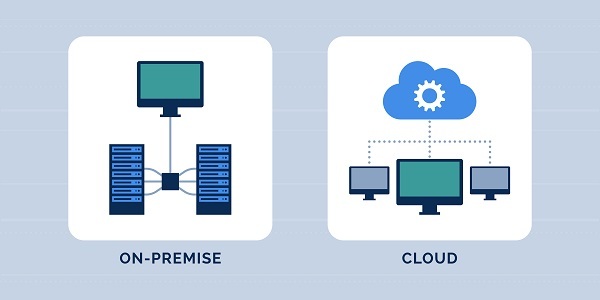
勤怠管理システムにはクラウド型とオンプレミス型があり、違いを理解してシステムの選択が必要です。
クラウド型とは、自社でサーバーを保持せず事業者が提供する環境上で稼働するタイプのシステムです。自社でサーバーの導入やメンテナンスなどが不要であるため、初期費用・ランニングコストを抑え、かつ、サービス登録からすぐに利用できる点に特徴があります。
オンプレミス型は自社でサーバーを保持し、その環境下で稼働するタイプのシステムです。比較的、コストはかかるものの、大規模利用が可能、カスタマイズ性が高いなどの点に特徴があります。
クラウド型とオンプレミス型の違いは以下の通りです。
|
比較軸 |
クラウド型 |
オンプレミス型 |
|
利用開始までの期間 |
短い。サービス契約後、すぐに使い始められるサービスも多い |
長い。サーバーの構築、ソフトウェアのインストールなどによって、最低3か月程度必要 |
|
初期費用 |
安価 |
高価 |
|
維持費用 |
ユーザーごとの従量課金が一般的。ユーザー数が増えるほど利用料が上がる |
自社サーバーの維持・メンテナンス費用がかかる |
|
追加費用 |
比較的低額。自動で法改正などに対応したシステムアップグレードを事業者側で実施 |
比較的高額。追加開発の都度のベンダー依頼、サーバーの買い替え費用などがかかる |
|
推奨される導入規模 |
従業員1,000人未満の小規模 |
従業員1,000人以上の大規模 |
|
カスタマイズ性 |
低い。デフォルト機能以上の開発は難しい |
高い。企業の要件に合わせて追加開発が容易 |
|
セキュリティ性 |
低い。事業者が提供するセキュリティ環境に依存する |
高い。カスタマイズ次第で強固に可能 |
|
サポート体制 |
サーバー運用や機能アップグレードは事業者側ですべて実施 |
保守契約をすることでサポートを受けられる。法改正など、システム変更が必要な場合には自社で対応する必要あり |
|
システム連携の柔軟性 |
提供する連携アダプターやWebAPIにより可能。提供されたツールで対応が難しければ、連携不可 |
柔軟に対応可能。自由にカスタマイズ可能 |
2.クラウド型勤怠管理システムを導入するメリット

上記で紹介したオンプレミス型勤怠管理システムとクラウド型勤怠管理システムを比較した際の、クラウド型勤怠管理システムを導入するメリットは以下の通りです。
- ●自社でサーバーを構築・維持する必要がないため、初期費用・維持費用が低額
- ●法改正に伴ったシステムの自動アップデートなど、サポート体制が充実
- ●無料トライアルを提供している企業が多い
以上のメリットから、クラウド型勤怠管理システムの導入が推奨される企業の特徴は以下の通りです。
- ●従業員数が少なく、低コストで勤怠管理システムを利用したい
- ●システム導入時に高いシステムリテラシーが必要ない
- ●試しに勤怠管理システムを利用してみたい
1
従業員数が少なく、低コストで勤怠管理システムを利用したい
クラウド型勤怠管理システムであれば、サーバーの導入費用や維持費がかからないため、利用環境を整える側面では、低コストで利用ができます。一方、クラウド型の場合、ユーザー数課金の形態をとるベンダーが多い点に注意が必要です。
サーバーの導入費用や維持費用が高いとはいえ、減価償却を加味すれば、従業員数が1,000名を超えるような企業の場合、総所有コスト(TOC)がオンプレミス型と比較して高額になる場合があります。
従業員数によってはオンプレミス型の方が割安になるケースがありますので注意が必要です。クラウド型勤怠管理システムは一般的に従業員数が少なく、低コストで勤怠管理システムを利用したい企業におすすめといえるでしょう。
2
システム導入時に高いシステムリテラシーが必要ない
クラウド型勤怠管理システムは、システムを利用開始するために特別な開発を要しない場合が多いため、システムリテラシーの高低に関わらず利用ができます。
オンプレミス型勤怠管理システムの場合、運用中のシステムにトラブルが起きた場合やメンテナンス時に高いシステムリテラシーが必要になるため、クラウド型の方が利用しやすいとも考えられるでしょう。
3
試しに勤怠管理システムを利用してみたい
クラウド型勤怠管理システムの場合、無料トライアルを用意している事業者が多いです。勤怠管理システムで何が実現できるのか、自社の想像する業務運用を実現できるのか、などを気軽に素早く検証したい企業のおすすめのタイプといえます。
3.クラウド型勤怠管理システムを導入する際の注意点

上記で紹介したオンプレミス型勤怠管理システムとクラウド型勤怠管理システムを比較した際の、クラウド型勤怠管理システムを導入する注意点は以下の通りです。
- ●カスタマイズ性に劣る
- ●現場労働者が多数いる事業体には不向き
1
カスタマイズ性に劣る
クラウド型勤怠管理システムはオンプレミス型ほど、カスタマイズ性には優れていません。就業規則が複雑であるとクラウド型勤怠管理システムでは対応しきれない場合がある点に注意が必要です。
業界や業種固有の就業規則がある場合、業界特化型のクラウド型勤怠管理システムを選ぶか、オンプレミス型を採用し、同業界・業種の導入実績があるベンダーへの相談をおすすめします。
また、労務管理システムや給与計算ソフトと連携する場合、クラウド型勤怠管理システムであると要望を叶えられないケースもあります。
WebAPIを公開していればAPI経由で他システムと連携できることがあるものの、システムが混在している、多数のシステムと連携したい等の場合にはオンプレミス型勤怠管理システムの利用がおすすめです。
2
現場労働者が多数いる事業体には不向き
工場や物流拠点など、現場労働者を多数かかえる事業の場合、現場で打刻を行うオンプレミス型の勤怠管理システムが向いています。
また、自社ネットワークで他の業務システムをつなげている場合、パソコンよりも打刻機やICカードなどの勤怠管理が好まれるため、クラウド型勤怠管理システムは不向きでしょう。
一方で、在宅勤務など遠隔地で働く労働者が多い場合には、ブラウザ上でリモート打刻が可能なクラウド型勤怠管理システムが適している場合が多いです。
4.クラウド型勤怠管理システムの主な機能

クラウド型勤怠管理システムを利用する場合、一般的に利用ができる機能は以下の通りです。
|
打刻機能 |
PC、スマホなどマルチデバイスで対応可能 |
|
集計機能 |
勤務時間、残業時間などを自動集計可能 |
|
ダッシュボード機能 |
個人/組織の勤怠状況をリアルタイムで表示可能 |
|
有給休暇管理機能 |
従業員別に年次有給休暇の取得状況を確認可能 |
|
申請承認機能 |
特別休暇取得時などの申請・承認業務をアプリ内で可能 |
|
その他 |
シフト作成、工数管理など |
製品比較時に特に確認しておきたい機能は以下の通りです。
- ●打刻機能
- ●集計機能
- ●その他(シフト作成機能)
1
打刻機能
マルチデバイスでの打刻に加えて、以下による打刻が可能か確認をおすすめします。知り合いに頼んで代理で打刻などの不正打刻を予防する意図で重要な機能です。
- ●ICカード打刻
- ●指紋認証打刻
- ●顔認証打刻
- ●GPS打刻 など
ICカード打刻とは、SuicaやPasmoなどの乗車券を利用して打刻する方法です。指紋認証や顔認証は、個人の生体データを利用して不正打刻を予防します。いずれの方法であっても不正打刻を予防する効果を期待できますので、ぜひ選定時には確認するようにしてください。
2
有給休暇管理機能
2019年4月の働き方改革による法改正によって、年10日以上の有給休暇を付与されている従業員は年間5日以上の有給休暇を取得することが義務になりました。もし、義務を順守していなかった場合、企業に対してペナルティが与えられることになっています。
勤怠管理システム上で、各従業員が年次有給休暇5日を取得できているか、年度末にまとめて取得することにならないか、確認が必要です。
勤怠管理システムの中には年度末に向けて年次有給休暇を5日取得できていない従業員/管理者に向けてアラートを出す機能を搭載しているシステムもあります。ぜひ確認をしておきましょう。
3
その他(シフト作成機能)
シフト作成機能とは、従業員が提出したシフト希望表を元に、システム上でシフト表を自動作成できる機能です。特に飲食業界など、多数のアルバイトやパートを管理する必要のある業界ではシフト作成機能が重宝されています。
事前に以下のような従業員別の勤務時間を設定することで、シフト表の自動作成が可能になります。シフト作成機能が利用可能かは確認しておきましょう。
- ●フルタイム(9:00-18:00)で勤務する正社員
- ●時短(9:00-15:30)で勤務する正社員
- ●アルバイト(15:00-18:00)で勤務する従業員 など
5.まとめ クラウド型勤怠管理システムで打刻しよう

勤怠管理システムはクラウド型、オンプレミス型と大きく2タイプあります。各タイプ毎に導入した場合のメリット、注意点は異なりますので、自社が勤怠管理システムに求める要件を明らかにして、タイプをまず決定しましょう。
自社でサーバーを持たず小規模・低コストで運用したい場合にはクラウド型の勤怠管理システムがおすすめです。
NTT東日本では労働基準法などに対応した、クラウド勤怠管理サービス「KING OF TIME for おまかせ はたラクサポート」を提供しています。ぜひ一度ご検討ください。
-
勤怠管理ならサービスとサポートをセットに!
 勤怠管理 無料体験申込フォーム
勤怠管理 無料体験申込フォームNTT東日本では、勤怠管理をはじめとして、バックオフィス業務効率化サービスを無料体験できるメニューを提供しています。
実際に、操作画面をみながら、導入の相談をできますので、お気軽にお問い合わせください!
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
