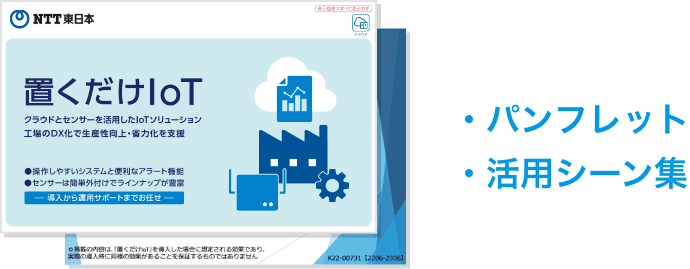クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
どの交通手段がもっとも省エネ?日常生活のエコな移動方法も調査!
-
2024.2.01 (木)Posted by
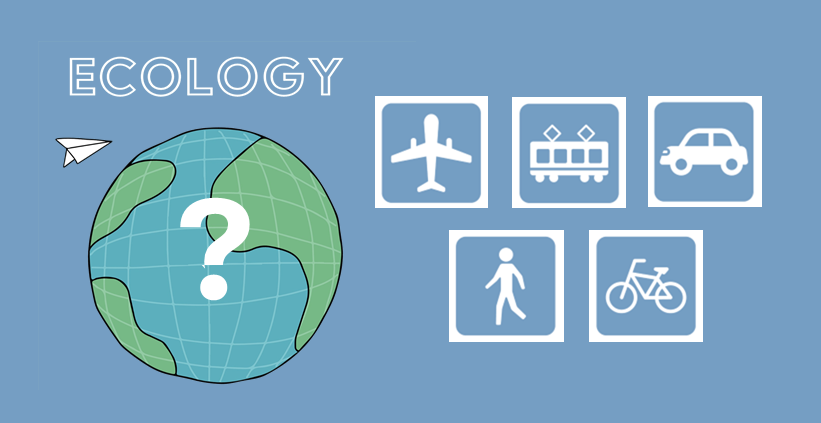

どの交通手段がもっとも省エネ?日常生活のエコな移動方法も調査!
人間が移動するとき、その手段によってエネルギーを消費する量が異なります。
消費するエネルギー源と量によって、どの方法が省エネになるのか比較してみましょう。
今回は、各種交通手段のエネルギー消費量はどれくらいなのか、比較・検証してみました。
日常生活のエコな移動方法も調査したので、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:各種交通手段のエネルギー消費量はどれくらい?
2:自転車・ランニングは熟練度によって変化する
3:二酸化炭素の排出量ではどれくらいの違いがある?
4:日常的にできるエコな移動手段とは?
5:まとめ
1:各種交通手段のエネルギー消費量はどれくらい?
 人が何かの手段により移動する際、その方法によって消費するエネルギー量が異なります。
人が何かの手段により移動する際、その方法によって消費するエネルギー量が異なります。
また、このように異なる移動手段のエネルギー量を比較する際は、エネルギーの単位や走行距離といった条件を揃える必要があります。
ここでは、単位は熱量を表す「ジュール(メガジュール)」で、10kmを移動する際のエネルギーで比較します。
また、今回比較する移動手段は次の5つです。
・飛行機・電車・自動車・自転車(人力)・ランニング(人力)
飛行機
飛行機は機体が非常に大きいことから、その機体を動かし空を飛ぶためには大変多くの燃料が必要になります。
その分、ジャンボジェット機であれば自動車などよりも一度に多くの人を運べます。
飛行機の機体の種類によって変わりますが、燃料1Lあたりの走行距離は0.1kmほどと言われています。
今回は計算しやすいように燃料はガソリンとしたときで換算した結果、10kmを移動するために必要な量は100Lになりました。
また、ガソリン1Lあたりのエネルギー量は約35メガジュールになるため、10kmを移動する際のエネルギー量は3,500メガジュールとなりました。
電車
JR西日本の資料によると1両を1km動かす際に必要なエネルギー量は19.2メガジュールになります。
仮に車両編成が10両であれば、さまざまな要素を無視すると10倍のエネルギーが必要になるため、1kmあたり192メガジュールが必要になります。
そのため、10kmを走行するために必要なエネルギー量は1,920メガジュールとなります。
自動車
自動車の燃費は車種によって大きく変わります。
あくまでも目安ですが、それぞれの燃費は次の通りです。
|
車種 |
燃費 |
10km走るのに |
エネルギー量 |
|
スポーツカー・トラック |
5km |
2L |
70 |
|
一般的な乗用車 |
10km |
1L |
35 |
|
軽自動車・エコカー |
15km |
0.67L |
23.5 |
|
ハイブリッドカーなど |
20km |
0.5L |
17.5 |
一般的な乗用車の場合は、1Lのガソリンで10kmほど走行できるため、10kmを走行する際のエネルギー量は35メガジュールとなります。
自転車
自転車の場合、消費エネルギー量は体重と運動時間、運動強度によって変わります。
ただし、自転車で運動強度を上げると移動速度が高くなるため、10kmを走破する時間は短くなります。
そのため、速く走った方が消費エネルギーが単純に大きくなるとは限りません。(基本的にスピードを上げた方が消費エネルギーは大きくなります)
国立健康栄養研究所改訂版「身体活動のメッツ表」をもとに算出した体重50kgの人が、それぞれのスピード(運動強度)で走ったときの10kmの消費エネルギー量は次の通りです。
|
運動強度 |
消費エネルギー量 |
消費エネルギー量 |
|
通勤・街乗りのスピード |
130kcal |
543,920ジュール |
|
中程度の運動 |
201kcal |
840,984ジュール |
|
高速走行 |
224kcal |
937,216ジュール |
このように自転車の場合で10kmを走行すると高速走行した場合で約1メガジュールとなります。
ランニング
ランニングによる消費エネルギーの計算方法は複雑ですが、一般的に「体重(kg)×走行距離(km)」で目安を計算できます。
例えば、体重が50kgの人が10kmを走ったときの消費エネルギーは500kcalとなります。
そのため、ジュールに換算すると2,092,000ジュールとなり、2.09メガジュールとなります。
各移動手段比較
|
移動手段 |
消費する |
1名あたりの |
|
飛行機 |
約3,500メガジュール |
約6.1メガジュール |
|
鉄道 |
約1,920メガジュール |
約1.2メガジュール |
|
自動車 |
約35メガジュール |
約7メガジュール |
|
自転車 |
約1メガジュール |
約1メガジュール |
|
ランニング |
約2メガジュール |
約2メガジュール |
上記のように、当たり前ですが消費量の1・2位は自転車とランニングとなりました。
飛行機(国内線ジャンボジェット)と鉄道(ロングシート車両乗車率100%)に関しては、一度に移動できる人数が多いので1名あたりの消費量に換算すると意外と少なく感じます。
2:自転車・ランニングは熟練度によって変化する
 先程の通り、人体がエネルギー源である自転車とランニングはさまざまな移動手段の中でも非常に消費エネルギーは小さいです。
先程の通り、人体がエネルギー源である自転車とランニングはさまざまな移動手段の中でも非常に消費エネルギーは小さいです。
しかし、その中でも運動効率が良い人とそうでない人では、消費するエネルギー量に大きな違いがあるでしょう。
例えば、日本トップクラスのマラソンランナーは42.195kmを1km3分のペースで走ります。
50m9秒で走るペースをフルマラソンの距離を維持するため、非常に心肺能力・運動能力は高いといえるでしょう。
このペースで10kmを走れば30分で到達します。
しかし、その真反対に普段から全く運動をしていない人であれば、10kmを走破するのは一苦労でしょう。
マラソンランナーの半分のスピードである1km6分のペースでも、普段から運動していない人は走れません。
また、このペースでは完走するのに60分かかります。
仮に走れたとしても心臓はバクバクと非常に激しく動き、非常に運動強度が高くなります。
この場合、運動時間はマラソンランナーの倍になり、運動強度も高くなるため消費されるエネルギー量は先程の一覧表の数値よりも大きくなるでしょう。
ランニングだけでなく自転車でも同じことがいえます。
特に一般的なシティサイクルと競技用のロードバイクなど使用する自転車の種類でも運動効率は大きく異なるでしょう。
また、他の移動手段と異なり、人間は疲労による影響が大きいことから、移動する距離の長さによっては効率が非常に悪くなったり、完走できなくなったりする点を忘れてはなりません。
3:二酸化炭素の排出量ではどれくらいの違いがある?
 それぞれの移動手段をエネルギーではなく、二酸化炭素の排出量で比較するとどうなるでしょう。それぞれについて解説します。
それぞれの移動手段をエネルギーではなく、二酸化炭素の排出量で比較するとどうなるでしょう。それぞれについて解説します。
自転車・ランニングは人体が出る分だけ
自転車とランニングは運動によって発生する二酸化炭素のみです。
人体から発生する二酸化炭素は体内のエネルギーを消費したときに発生することから、同程度の水準で運動したとき、発生する二酸化炭素の量は自転車の方が少なくなるでしょう。
ただ、あくまでも人体から発生する程度であるため、その量が環境に与える影響はありません。
飛行機・鉄道・自動車はどれが少ない?
それに対して、飛行機・電車・自動車の場合、どの移動手段が二酸化炭素排出量が少ないのでしょうか。
結論としては、電気で動いている電車が排出する二酸化炭素の量が少ないです。
飛行機と自動車はガソリンなどのエネルギー源を燃焼させて動いていることから、その移動手段本体から直接二酸化炭素が排出されています。
同じように、自動車の中でも電気自動車やハイブリッドカーは比較的二酸化炭素の排出量は少なくなります。
ただし、電車や電気自動車のように電気を動力が使われている場合、その電気を作る際に二酸化炭素が排出されることを忘れてはなりません。
4:日常的にできるエコな移動手段とは?
 ここまでの通り、さまざまな移動手段の中でも自転車が最も消費エネルギー量・二酸化炭素排出量が少ないため、エコな方法といえるでしょう。
ここまでの通り、さまざまな移動手段の中でも自転車が最も消費エネルギー量・二酸化炭素排出量が少ないため、エコな方法といえるでしょう。
10kmであれば頑張って走ることで30分以内で到着します。
しかし、先程の通り、使用する自転車の違いや自転車に乗る人の運動レベルによって、さまざまな影響が出ます。
普段から運動・トレーニングをしている人であれば効率が良い移動手段ですが、運動が苦手な人からすると苦しい手段となるでしょう。
また、今回は移動する距離を10kmに統一して比較しましたが、100km・1000kmと増やすと、そもそも移動自体が困難になります。
そのため、比較的短い距離を移動する際に、自転車を有効活用すると良いでしょう。
5:まとめ
この記事では、各種交通手段のエネルギー消費量はどれくらいなのか、比較・検証してみました。
結論としては、自転車が最もエネルギー消費量が少なく、ランニングよりも移動スピードが速いことから、移動手段として優れています。
また、体内のエネルギーをもとに動いているため、排出する二酸化炭素の量も少ないです。
ただし、人間であるため長時間の移動になると疲労が溜まり、やがて限界を迎える点に注意しましょう。