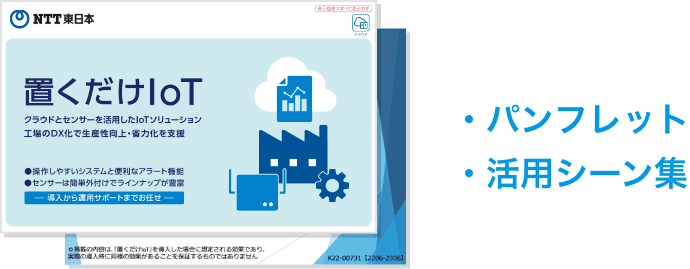クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
水道で水力発電できるか?発電する仕組みについても解説
-
2024.3.04 (月)Posted by


水道で水力発電できるか?発電する仕組みについても解説
近年では、技術の進歩によりさまざまな発電方法が登場しており、特に世界的にも環境配慮の取り組みが重視されているため、クリーンな発電方法が注目されています。
その中でも水道を使った発電方法が期待されています。
しかし、水道の規模にもよりますが適切に発電できるのか気になる人は多いでしょう。
そこで今回は、水道で水力発電できるのかについて解説します。
水道による水力発電の仕組みなどについても紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:水力発電の仕組み
2:水道で水力発電できるのか?
3:マイクロ水力発電を使った発電の事例
4:まとめ
1:水力発電の仕組み

水力発電は、高い場所から低い場所に水が流れる際のエネルギーを利用した発電方法です。
水の勢いが発電用のポンプ水車を動かすことで発電機の動力となり、電気が生じる仕組みです。
主な方式は、水路式(流れ込み式)、調整池式、貯水式、揚水式の4つで、水路式は水路や河川に発電用の水車を設置する方法で、河川などに流れ込む水をそのまま利用します。
調整池式、貯水式、揚水式は、いずれもダムや調整池を利用した発電方法で、蓄えられた水の放水を調整できるため、需要に合わせた発電がしやすい点が特徴です。
水力発電のメリットのひとつは、安定して電力を供給しやすい点です。
渇水のリスクがある以外は、太陽光発電や風力発電のように気象などの自然条件に大きな影響を受けません。
また、水路式以外の水を貯蔵しておくタイプの水力発電は、短い時間で発電を開始できて、電力需要に応じた調整がしやすい特徴があります。
電力の消費は、季節や時間帯ごとに変化しますが、そうした変化に合わせて供給しやすいです。
他にも、クリーンエネルギーである点も水力発電の大きな特徴で、発電量の多い火力発電は、石炭や石油、天然ガスを燃焼させてエネルギーを生み出すために多くの二酸化炭素を排出しますが、水力発電はほとんど二酸化炭素を排出しません。
2:水道で水力発電できるのか?

水力発電は基本的に水が落下する位置エネルギーを利用しますが、水の力を使って水車やタービンを回すことができれば発電は可能です。
つまり、水道設備を使った発電は理屈では可能であるものの、一般的な水道では発電量は少ないでしょう。
近年では、各地域の水道局が設備を改修し「マイクロ水力発電」に取り組む事例が増えています。
このマイクロ水力発電とは、上下水道水や農工業用水などの水の未利用エネルギーを活用して電気をつくる新しい水力発電です。
水力発電と同様に、水が落下するときなどの力を利用して発電用水車を回転させる発電方法です。
出力が1,000~10,000kW規模の水力発電を「小水力」、100k~1,000kWを「ミニ水力」、100kW以下を「マイクロ水力」と呼びます。
近年ではすべてを総称して「小水力発電」と呼ばれる場合が多いです。
例えば、水道管の中を水が移動するときのエネルギーを使い、水車・タービンを回すことができれば電力を起こせるでしょう。
さらに、高層ビル 学校 病院の排水、洗面台 トイレの洗浄水までも利用できることからマイクロ水力発電は高いポテンシャルを秘めています。
水道で発電するメリット
水道を使った発電には、さまざまなメリットがあるため将来的にも期待されています。
まず第一に、大規模な施設を必要とせず、省スペース・短時間でどこにでも設置可能であり、導入しやすいです。
特に、水道関連の施設は日本の至る場所にあるため、総数で考えると発電できるポテンシャルは非常に大きいといえるでしょう。
また、大規模水力発電所に比べ、生態系へ影響を与える可能性が少ない点もメリットです。
大型の発電施設を建設する際には、大規模なプロジェクトになりさまざまな費用が発生します。
また、建設場所を整備する必要があり、水資源が豊富な自然を切り開かなければなりません。
そのため、水道で発電する場合はこのような開発が必要ないため、生態系への影響も少ないでしょう。
太陽光発電や風力発電に比べ、天候の影響が少なく安定した電力を得られ、CO2の排出量が少ない点は、他の発電方法よりも優れています。
水力発電は猛暑・乾燥による影響は受けるものの、水道管などを使用することにより受ける影響を抑えられます。
他にも、水源地近くのコミュニティが運転・保守を行いつつ電力を消費する「地産地消」に適していることから、地域の活性化などにも繋がるでしょう。
水道で発電するデメリット
水道で発電するメリットは多いものの、デメリットも存在します。
例えば、法的な手続きに手間がかかり複雑であるため、設備を作っても実際に発電環境が整備されるまでに時間がかかる可能性があります。
他には、土砂や落ち葉などのゴミを取り除くメンテナンスが必要になり、場合によっては大きなコストがかかる可能性があります。
単独の発電設備で発電できる容量が小さいことから、ケースによっては赤字になるようなこともあるでしょう。
発電の安定性は優れているものの、まとまった発電量の確保が難しい点にも注意が必要です。
また、発電所を建設するよりも安価であるとしても、設置の費用がまだまだ高額であるため地域の自治体が取り組む際のハードルは高いでしょう。
自然環境に与える影響は少ないですが、発電には水資源が必要であるため、発電施設の構築により景観を損なう恐れがある点もデメリットです。
3:マイクロ水力発電を使った発電の事例
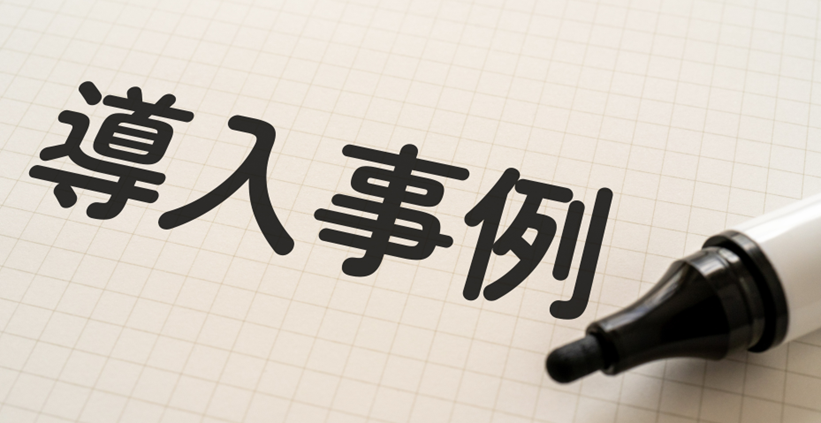
千葉県の事例
千葉県企業局では、環境への取り組みのひとつとして再生可能エネルギーの導入を進めていおり、その一つとして「マイクロ水力発電」を実施しています。
千葉県企業局では、平成20年度から幕張給水場(千葉市)と妙典給水場(市川市)に設置し、再生可能エネルギーである水力利用により発電により給水場の消費電力の削減を図り地球温暖化防止に貢献しています。
さらに、北船橋給水場(船橋市)に同設備を2基導入し、平成26年2月から稼働しています。
この増設により既存の設備とあわせて年間計画発電量は約334万kWhにもなり、電気使用量の約2.3%に相当する電気を発電しています。
また、約1,500tのCO2の削減効果が得られる見込みです。
京都の嵐山の事例
京都の嵐山・渡月橋の夜を飾っている照明の電力は、桂川を流れる水の力で生み出されています。
現在の渡月橋は、1994年から2000年にかけて改修されましたが、景観への配慮から照明の設置が見送られました。
その後、照明がないことで交通事故や防犯への不安が住民から寄せられたことにより、照明設備の申請を行っており、小水力発電のエネルギーを利用するということで照明の設置許可が得られています。
他の地域の事例
他にも、愛知県営水道尾張東部浄水場と高岡配水場の水位差によるエネルギーを利用して発電しています。
水道事業として愛知県初の官民連携マイクロ水力発電システムであり、年間想定発電量は約154千kWhで、一般家庭43軒分の電気使用量に相当します。
実際に2019年5月に運用が開始しており、事業期間内は、行政財産目的外使用料(約4万円/年)と売電利益還元料(約31万円/年)を合わせて約35万円/年が豊田市に支払われています。また、年間約75tのCO₂排出量の削減効果が見込まれています。
場合によってマイクロ水力発電のシステム・設備を提供する企業が支援するケースもあり、自治体から設置料を徴収せず、自社負担することもあります。
自治体は水道施設を貸すだけで、先に述べたように売電利益還元料などを得ることができるので、導入のハードルは下がるでしょう。
電力会社と水道ビジネス
中部電力のDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の中には、今後拡大していく事業領域の1つとして「水道事業」が入っています。
名古屋市上下水道局と「水道スマートメータによる水道使用量自動検針の試験導入」をおこなっており、電力スマートメータの通信網を活用し、安定的に水道使用量データを取得できます。
水道使用量の「見える化」や漏水の早期発見など、取得した水道使用量データの利活用に関する検討を行っています。
4:まとめ
この記事では、水道で水力発電できるのかについて解説しました。
水道による水の移動エネルギーや水圧により、水車やタービンを回すことで発電することが可能です。
さまざまな水道施設に発電設備を設置することにより、発電できるため今後期待されている手法の一つです。
さまざまなメリットはあるものの、発電量が小さいことから課題などが多く残っています。
それらの課題を解決できれば今後の電力を賄う効果的な方法として、注目されていくでしょう。