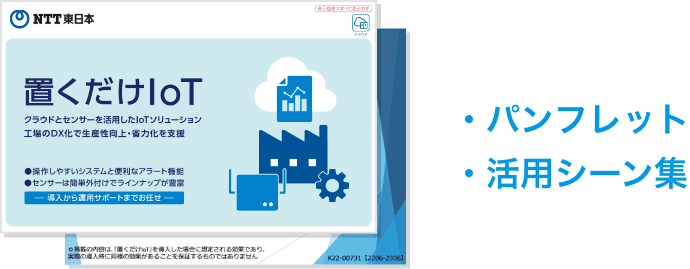クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
施設管理業でIT導入補助金を受けるためのポイント!対象や申請方法について解説
-
2024.4.03 (水)Posted by


施設管理業でIT導入補助金を受けるためのポイント!対象や申請方法について解説
近年では、国がDXを推進していることもあり、多くの企業がITシステムの導入により業務効率を改善しています。
特に施設管理を行っている企業であれば、ITツールの導入で施設内の状況を可視化したり、点検業務を省力したりなど業務の効率化ができます。
しかし、資金力がある大企業と異なり、中小企業の中には経済的な問題から導入に踏み切れないことがあるでしょう。
そのようなとき活用したいものが「IT導入補助金」です。
IT導入補助金は、名前の通りITツールを導入する際に補助金を受け取れるものです。
有効活用することによりITツールを導入しやすくなるでしょう。
そこで今回は、施設管理におけるIT導入補助金について解説します。
対象や申請方法についても解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:IT導入補助金の概要
2:IT導入補助金の対象とは
3:施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の活用例
4:施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の申請方法
5:まとめ
1:IT導入補助金の概要
 IT導入補助金とは、中小企業が生産性向上を高めるためにITシステムなどのツールを導入する際、経済的な負担を軽減するために費用の一部を国が補助する制度のことです。
IT導入補助金とは、中小企業が生産性向上を高めるためにITシステムなどのツールを導入する際、経済的な負担を軽減するために費用の一部を国が補助する制度のことです。
近年ではIT技術が発展しており、国も企業のITツールの導入を推進していることもあって補助金制度を整備しています。
ただし、ITツールの種類によっては初期費用が大きく、経済的な体力がない中小企業はコスト面がネックで導入できないことが多いです。
そこで、IT導入補助金を活用することにより、このような悩み・課題を抱える企業を支援することが制度の大まかな目的です。
また、IT導入補助金は申請が通らなかった場合は、ITツールの導入を見送ることもできるため、企業にとってリスクがない制度でもあります。
IT導入補助金にはいくつかの種類があり、それぞれ補助額が変わります。
他にも、IT導入補助金の詳細は年によって変更になることがあり、例えば、コロナ禍の影響・インボイス制度の導入といった事情により、補助枠が拡大されています。
2:IT導入補助金の対象とは
 対象となる中小企業等の定義は業種・組織形態によって異なり、施設管理・ビルメンテナンスの場合は「サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)」に該当するため、資本金5,000万円以下か常勤の従業員が100人以下とされています。
対象となる中小企業等の定義は業種・組織形態によって異なり、施設管理・ビルメンテナンスの場合は「サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)」に該当するため、資本金5,000万円以下か常勤の従業員が100人以下とされています。
また、IT導入補助金の対象は企業だけでなく、活用するITツールにも対象となるものがあります。
そのため、生産性向上が見込まれるものであれば何でも良いわけではありません。
IT導入補助金を受け取るためには、IT導入補助金の事務局に登録され認定を受けたツールである必要があります。
「生産性向上」という概念も企業によって異なるでしょう。
IT導入補助金では、補助金の類型によって決められたプロセスに適合しており、導入によってそのプロセスの生産性が向上すると認定される必要があります。
IT導入補助金の通常枠であるA・B類型の場合、ソフトウェアを導入する場合の決められたプロセスは次の通りです。
| 種別 | プロセス | |
| 業務プロセス | 共通プロセス | 顧客対応・販売支援 |
| 決済・債権債務・資金回収 | ||
| 調達・供給・在庫・物流 | ||
| 会計・財務・経営 | ||
| 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | ||
| 業種特化型プロセス | 業種固有プロセス | |
| 汎用プロセス | 汎用・自動化・分析ツール (業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフトウェア) |
|
施設管理・ビルメンテナンスの場合であれば、共通プロセスの中にある会計・財務の効率化などであれば実現しやすいでしょう。
対象外になるケースもある
「認定を受けたツール」であり「生産性向上」を実現できるものであっても、IT導入補助金の対象外になるものがあります。
IT導入補助金の対象は幅広いものの、場合によっては補助金を受け取れないため注意してください。
例えば、業務プロセスの効率化ではなく、販売している商品の付加価値を高めるものは、企業としての生産性向上に貢献しても、IT導入補助金の対象にならないものが多いです。
他にも次のようなケースは補助対象外となります。
・既に導入しているITシステム(ソフトウェア)の追加ライセンス
・単一の処理機能しかないもの
・一般販売されていない特定の顧客限定のシステム
・大幅なカスタマイズが必要となるもの
・組み込み系のソフトウェア など
3:施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の活用例
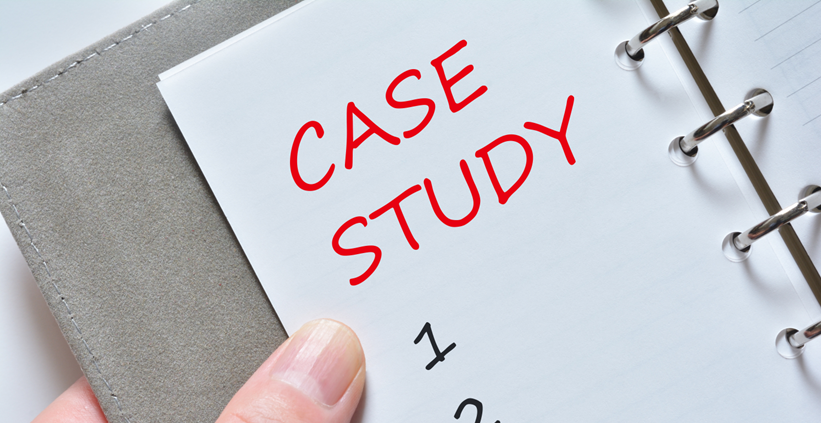 ここからは施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の活用例を紹介します。
ここからは施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の活用例を紹介します。
シフト作成の効率化を実現した事例
施設管理を行うとある企業では、特定の社員がシフト作成を担当していました。業務が多忙な月は翌月のシフトの提示が遅れてしまうことがあり、アルバイト・パートの従業員からは予定を組みにくいといった不満がでており課題となっていました。
そこで、AIを活用した勤務シフト作成の自動化ツールを導入しました。
AIの運用には時間がかかることから、この企業では従来の管理方法と併用しつつ学習させるようにしています。
AIの学習がひと段落し運用が安定化した後は、毎月の勤務シフトを自動で作成できるようになったのです。
従業員は早めにシフトを把握でき、シフト作成担当者の負担も減ったため業務の生産性が高まりました。
設備管理システムを導入した事例
ビルメンテナンス業界では、トイレの設備管理システムを導入した事例が多いです。
トイレ内に人を感知するセンサーとそれに対応したシステムを導入することにより、利用状況を把握できるようになります。
このシステムを活用することにより、現場に足を運ばなくとも状況を把握できるようになりました。
また、利用回数が多いトイレに清掃・点検・巡回の優先度を置くことにより業務効率も高まりました。
4:施設管理・ビルメンテナンスにおけるIT導入補助金の申請方法
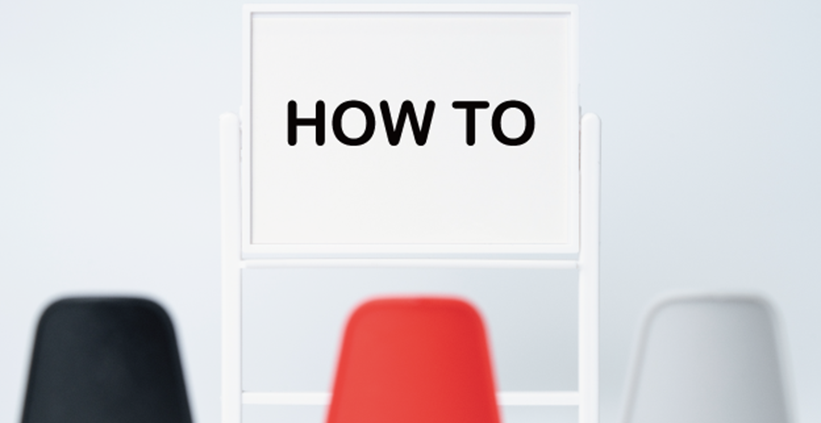 IT導入補助金を申請する流れは次の通りです。
IT導入補助金を申請する流れは次の通りです。
①制度について理解する
②ITツールを選定する
③必要なアカウントを取得する
④交付申請を行う
⑤ITツールの発注や契約などを行う
⑥事業実績報告
⑦補助金交付手続き
⑧事業実施効果報告
①制度について理解する
先程の通りIT導入補助金の中にはいくつかの類型(種類)があるため、まずは公式サイトや公募資料を読み、内容を理解しましょう。
その中から適用できるITシステムの種類などを検討する必要があります。
②ITツールを選定する
制度を理解した後は、補助金の交付申請の準備として、事業規模・経営課題に適したITツールを選定します。
そのためにも、自社の現状を把握し問題点・課題点を明確にしましょう。このとき、IT導入支援事業者も同時に選定します。
③必要なアカウントを取得する
IT導入補助金を申請する際は、「gBizIDプライム」のアカウントが必要になります。
未取得の場合は、「gBizID」の公式サイトから申請し約2週間ほどでアカウントIDが発行されます。
また、アカウント取得に加え「独立行政法人情報処理推進機構」が実施する「SECURITY ACTION」の宣言も必要です。
交付申請時には宣言済のアカウントが必要になるため、事前に対応しましょう。
他にも、「みらデジ」のポータルサイトにgBizIDで登録して、「経営チェック」を実施する必要があります。
④交付申請を行う
アカウントの取得などの準備が整った後、IT導入支援事業者とツールの導入に向けた商談を進め事業計画を策定していきます。
IT支援事業者から申請マイページの招待を受け、申請者の基本情報などを入力しましょう。
他にも、交付申請に必要な情報を入力し、書類を添付します。
その後、IT導入支援事業者がITツールの情報や事業計画を登録し、申請マイページ上で入力内容を確認後、申請に対する宣誓を行い事務局へ提出すれば完了です。
⑤ITツールの発注や契約などを行う
交付申請後に事務局から「交付決定」の連絡を受けた後に、ITツールの発注や契約などを進めましょう。
このように交付が決まってからツールの導入に関する発注・契約を進められます。
⑥事業実績報告
補助事業が完了した後は、実際にITツールを導入したことを示すために、証憑を提出します。
⑦補助金交付手続き
事業実績報告が完了すると補助金額が確定します。
この補助金額は申請マイページで確認でき交付されます。
⑧事業実施効果報告
最後に、決められた期限内に申請マイページに必要な情報を入力し、IT導入支援事業者の確認後、事業実施効果報告を提出してください。
5:まとめ
この記事では、施設管理におけるIT導入補助金について解説しました。
ビルメンテナンス・施設管理では、現状の業務の内容や現状を把握し課題に適したITツールを導入することにより、大幅な生産性向上に繋がる可能性があります。
例えば、シフト作成の自動化やトイレの利用状況の把握などのシステムにより、業務効率化や人手不足解消を実現した事例は少なくありません。
まず、現状の課題を明確にし、IT導入補助金について理解することが重要です。
自社に適したITツールを補助金を活用して導入し、業務効率を改善してみてください。