「医療・介護施設」の省エネポイントを徹底解説!
-
2024.11.18 (月)Posted by

「医療・介護施設」の省エネポイントを徹底解説!
多くの高齢者や患者を抱える医療・介護施設では、快適な空調を提供や医療・介護機器を稼働させる必要があるため、
多くのエネルギーが使用されます。
施設を維持させる中でコストカットは必須で、特に電気代は抑えたいところで、極力無駄を省き効率よく稼働させるためには、
省エネが欠かせません。
この記事では、医療・介護施設における省エネの必要性や対策方法、メリットや注意点などを紹介します。
<目次>
1:医療・介護施設で使用エネルギーが多い理由
2:医療・介護施設における省エネの必要性・メリットとは
3:医療・介護施設で省エネ対策を実施する際の注意点
4:医療・介護施設での省エネ方法
5:医療・介護施設での省エネには電流センサーを導入
6:まとめ
1:医療・介護施設で使用エネルギーが多い理由
 医療・介護施設で使用エネルギーが多い理由として、次の3つが挙げられます。
医療・介護施設で使用エネルギーが多い理由として、次の3つが挙げられます。
稼働させ続ける機器が多いため
医療・介護施設では稼働させ続ける機器が多いため、使用エネルギーは必然的に増えてしまいます。
患者の治療や診断に必要な医療機器や要介護者の生活を支える介護機器、その他の施設利用者や関係者が過ごすうえで
必要な空調・照明など、多くの機器を稼働させなければいけません。
なお、環境省によると医科大学の外来棟ほどの大きさとなる、延べ床面積が約75,000㎡の病院では、年間の電気代は1億円程にもなります。
空調管理が厳しく実施されるため
真夏に施設利用者が快適に過ごせる生活環境を提供するためには、エネルギーを節約し利用者に我慢をしてもらうことは難しいです。
空調を逐一調整し続けるため、一般的な設備よりも使用エネルギーは多くなる傾向にあります。
また、医療・介護施設では、一般家庭であれば冷暖房を使用しない真夏以外の場合でも、除湿や加湿といった細かい空調環境の調整が必要です。
24時間稼働となるため
MRIなどの高度医療機器やOA機器、施設利用者が夜間に使用する可能性のある廊下やトイレの電気などは常に稼働し続けるものとなります。
また、医療・介護施設では緊急患者等へ即対応できる体制を整える、トラブルに繋がる可能性を排除するなどから、
必然的に施設機器を稼働させる時間は長くなります。
2:医療・介護施設における省エネの必要性・メリットとは
 医療・介護施設における省エネの必要性・メリットとして、大きく次の3つにまとめられます。
医療・介護施設における省エネの必要性・メリットとして、大きく次の3つにまとめられます。
固定費を削減するため
医療・介護施設における省エネの必要性・メリットとして、固定費の削減が挙げられます。
ランニングコストが高騰すると他の設備へお金を回せず、かえって施設利用者や施設で働く人の利便性が下がる恐れが懸念されます。
また、利益が圧迫されることで人材不足といった問題へと繋がることもゼロではありません。
医療・介護施設における固定費の削減は単純に経営だけでなく重要な問題のきっかけとなる可能性があるため、注意を払っておきましょう。
災害時でも活動できるようにするため
災害時でも活動できる体制を整えるためという点も、省エネの必要性の一つです。
医療・介護施設では災害時に必要なエネルギーが足りなくなると、利用者の命に関わるケースが大いに考えられます。エネルギーが少ない中でも機能を維持しなければいけないのです。
そのため、災害時のエネルギーが足りない状況下で医療・介護機能を維持できるよう、使用エネルギーを最小限に減らした状態で
運営できる体制を整える必要があります。
環境問題への配慮をアピールするため
環境問題への配慮をアピールする点も、省エネを掲げる必要性の一つです。
昨今ではSDGsという言葉がポピュラーになり、環境問題への意識が高まっています。
環境問題へ配慮している施設は利用者にとっても良い印象を抱いてもらいやすく、リピーターとなる可能性に期待ができます。
3:医療・介護施設で省エネ対策を実施する際の注意点
 ここからは、医療・介護施設で省エネ対策を実施する際の注意点となる下記2点について解説します。
ここからは、医療・介護施設で省エネ対策を実施する際の注意点となる下記2点について解説します。
利用者が不自由にならないような管理が必要
医療・介護施設利用者の中には、病気を患い免疫が低下している、怪我により生活に制限がある、
一人で日常生活を送ることが難しい高齢者など、支えが必要な方々は少なくありません。
一般的には気にならない不便さも大きな障害となる、または不自由に感じることはあり得るでしょう。
そのため、省エネ目的で医療・介護機器や照明、空調などの電源を落とす場合は利用者への配慮が欠かせません。
事前にアナウンスをする、代替案を実施するなど、不自由にならない管理の徹底が求められます。
患者・施設利用者の体調管理に注意する
前述のように、医療・介護施設には支えを必要とする人が多く在籍しています。
少しの不便が利用者に辛い思いをさせてしまうだけでなく、体調にまで悪影響を及ぼす可能性は否めません。
例えば、高齢によって体温の調整が難しい場合、少しの空調の変化に順応できず体調を崩す恐れがあります。
そのため、省エネ対策を実施する際は利用者の体調管理を一番の懸念点とした上で実施しなければいけません。
4:医療・介護施設での省エネ方法
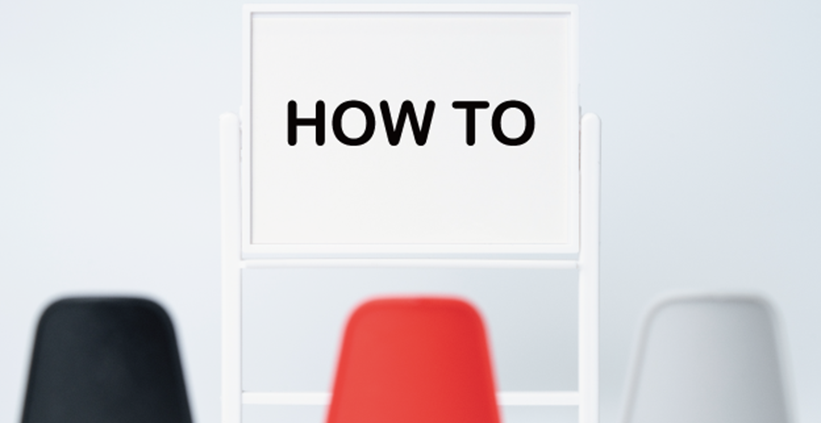 実際に医療・介護施設で実施できる省エネ方法として、下記の3点が挙げられます。
実際に医療・介護施設で実施できる省エネ方法として、下記の3点が挙げられます。
LED照明にする
省エネを意識するうえで、LED照明を活用する方法が有効です。
LED照明は消費電力が低い、かつ寿命が長いため、大きな節電効果が期待できます。
環境省によると、LEDは一般電球と比較すると、約85%もの省エネ効果が見込めると言われています。
そのため、利用者の部屋や廊下などの電球をLED照明に変更するだけで、年間のエネルギー使用率は抑えられるでしょう。
さらに、寿命が長いことから電球を交換する回数も減るため、業務効率化が図れる点もメリットです。
空調管理システムを導入する
空調管理システムは、使用エネルギーや空調環境をセンサーで察知し自動で効率的に稼働してくれるため、省エネ効果が期待できます。
例えば、冷房を26度で稼働させた場合、室内温度が低くなると自動で風量を減らして使用エネルギーを削減するため省エネに繋がるのです。
ただし、全自動の空調システムは導入コストが高額になることもあるため注意しましょう。
患者・施設利用者に協力を仰ぐ
マメに電気を消してもらう、体調が良い時は冷暖房を使用せず過ごしてもらうなど、施設利用者に協力を仰ぐことで余計なエネルギーを抑えられます。
また、施設で働く人達へ省エネを周知し協力してもらうことも対策の一つです。
夏場はクールビズを取り入れて冷房の使用エネルギーを下げることができれば、十分な省エネ効果が期待できるでしょう。
ただし、患者や施設利用者へ協力を仰ぐ際は、負担にならないかという点への配慮は欠かせません。
5:医療・介護施設での省エネには電流センサーを導入
 ここからは、具体的な医療・介護施設での省エネ方法を紹介していきます。
ここからは、具体的な医療・介護施設での省エネ方法を紹介していきます。
結論、医療・介護施設で省エネを実施するには電流センサーの導入がおすすめです。
電流センサーを導入し使用するエネルギーを見える化することで、適切な省エネ対策へと繋げられる期待が持てます。
※各種センサーについて詳しく知りた方はコチラ→「置くだけIoT」
使用エネルギーの正確な把握が必要
電力コストの削減には、どの機器にどれだけのエネルギーが使われているかを把握しなければいけません。
特に医療・介護施設においては、闇雲に電力削減を実施すると利用者や施設関係者の不自由へと繋がる恐れがあります。
例えば、不適切な空調の操作により施設利用者の体調へ影響が出たり、施設関係者の手間が増えたりする可能性は否めないのです。
しかし、使用エネルギーを計測する際に、個別で調べる方法はなく電気代から概算する方法はありません。
その際に、電流センサーが活躍してくれます。
センサー導入によってエネルギーを計測する
使用機器に電力センサーを設置することで、電力を計測します。
これにより、無駄なエネルギーを把握し効率的な電気の使用サイクルや、無駄を省く方法を考案していけるのです。
例えば、契約電力の場合はピーク時の電気代から年間の電気代が決定されるため、無駄に使用電力が集中すると電気代は高くなります。
そのため、センサーを導入し使用電力を正確に計測した上で、ピーク時の電力を分散することで年間の電気代節約に繋がるのです。
また、電力計測による数値の見える化は、目視で確認する手間も省けます。
大きな施設であれば施設関係者が手動で施設内を巡回しなければいけませんが、以降その必要はありません。
大きな施設ほどコストが回収しやすい
センサー導入の初期費用は概ね1台あたり約30万円です。
初期費用としては安くないと感じるかもしれませんが、年間の電気代が1億円程度になるほどの大きな病院では、少しの省エネ対策が大きな効果を生むことがあります。
省エネには電気代を抑える他、人件費の削減にも繋げられます。
特に大きな医療・介護施設ほど少しの省エネにより大幅なコストカットが実現できるかもしれません。
省エネ対策を考えている医療・介護施設は、ぜひセンサーの導入を検討してみてください。
6:まとめ
医療・介護施設における省エネ対策は、コストカットや環境問題への配慮など、様々なメリットがあります。
しかし、人間の手だけで、やみくもに必要な機器を止めるということは難しいでしょう。
そのため、省エネ対策を考えている医療・介護施設は、ぜひセンサー導入を検討してみてください。