ストレスチェック制度が全企業に義務化へ!ツールの活用で手軽に対応する方法
-
2024.11.08 (金)Posted by NTT東日本

ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法の一部改正を受けて、2015年12月1日に施行された制度です。常時50名以上の労働者がいる事業所は、1年に1回従業員に対しストレスに関する質問票(選択回答)を利用して、ストレスチェックを行うことが義務付けられています。ストレスチェックが義務付けられている理由は、労働者が職場で認識しないうちにストレスが溜まり、心身に悪影響を及ぼしてしまう恐れを未然に防止するためです。状態が悪化してしまうと、うつ病などのリスクへと繋がります。そのため、労働者の心の状態を適切に把握し、早期発見と予防を行うためにストレスチェック制度が導入されています。
また、政府は2025年3月14日にすべての企業にストレスチェックを義務付けることを柱にした労働安全衛生法の改正案を閣議決定しました。今後は、従業員が50名以下の企業も対象になっていくため、ストレスチェック制度に対応できるよう準備が必要になってくるでしょう。
・出典:JIJI.COM 全企業、ストレスチェック義務化 改正法案を閣議決定 2025年3月14日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031400351&g=eco
NTT東日本が提供するストレスチェック機能を搭載したeラーニング「ひかりクラウド スマートスタディ」は、気軽にストレスチェックができます。
ストレスチェックを利用する際は、1IDにつき月額たったの198円〜利用できます。
>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら
ストレスチェックの利用がないときは、オンライン研修ツール(eラーニング)としても利用ができます。ぜひこの機会に2週間の無料トライアルをお試しください。
※ひかりクラウド スマートスタディは、eラーニングプラットフォームのため学習コンテンツは含まれておりません。
オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

1ストレスチェックを実施するメリット
1.突発的な人的コストなどのリスクを防ぐことができる
組織や企業が労働者の心の状態に注意を払い、ストレスチェックを行うことで、労働者の心の状態を把握することできます。事前に労働者のストレスや不安の原因を知ることで、組織や企業は労働者の突発的に起こりうるリスクを未然に防ぐことができます。
2.職場環境の改善に繋げることができる
検査結果を集団的に分析することで、職場の環境改善につなげることができます。労働者が自分の健康をサポートされていると感じることで、従業員の職場への満足度向上や離職率の低下につながる場合もあります。
3.個人のメンタルヘルス不調のリスクを軽減させることができる
ストレスチェックを実施することで、労働者は個々に自身の体調や心の管理ができるようになります。そうすることで、メンタルヘルスの不調リスクを軽減することができます。
4.組織全体の成長に繋げることができる
ストレスチェックは健康経営にも繋がります。労働者の健康管理を経営的な視点に考えて実践することで、労働者がいきいきと継続的にはたらきやすい環境で仕事ができ、モチベーションの向上が期待できます。
2ストレスチェックの実施手順と具体的な方法
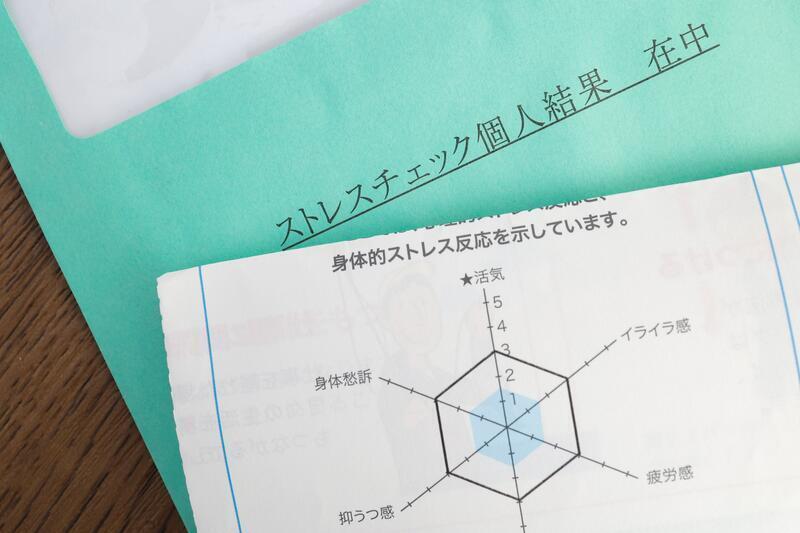
●事前準備
まず、はじめに会社として方針を示しましょう。 そして、実施方法(いつ・誰が・チェック方法・分析)などを話し合いましょう。 重要なのは、話し合った結果を社内規程として明文化し、全ての社員・スタッフに周知する事です。
<実施体制の例>
|
担当者区分 |
役割 |
|
制度全体の担当者 |
計画づくりや進捗状況を把握・管理する者 |
|
実施者 |
医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士 |
|
実施事務従事者社 |
質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当 |
●ストレスチェック実施*
ストレスチェックは、質問票の作成から実施結果の本人通知まで大まかに3ステップあります。
①質問票作成
質問票は決まった形式はありませんが、下記3つの項目を入れる必要があります
・ストレスの原因に関する質問項目
・ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
・労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目
※何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する57項目の質問票を使いましょう。
◎参考:厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57 項目)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/dl/stress-check_j.pdf
②配布~回収
記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。 回収時の重要なポイントは、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはいけません。
③評価~通知
回収した質問票は、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
※高ストレスとは、自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い者 評価の結果、医師の直接指導が必要な場合のみ、実施者から直接本人に通知されます。 その際、企業は評価結果を入手できないので、入手する場合は結果の通知後、本人の同意が必要です。 また、結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。
*出典元:厚生労働省 ストレスチェック制度導入マニュアルより抜粋
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf
3ひかりクラウド スマートスタディのストレスチェックは簡単・便利!
「ひかりクラウド スマートスタディ」をご利用いただくと、ストレスチェックの診断結果は、本人が受検後すぐに確認できます。 上記でご紹介した、ストレスチェック実施①「質問票作成」②「配布~回収」工程を、大幅に簡略化及び自動化が可能になります。 設問は予め設定されているため、すぐにストレスチェック診断が可能です。ストレスチェック診断後は、視覚化されたレーダーチャートと分かりやすい解説で個人のストレス状況を把握することが可能です。
>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら
※画面はいずれもイメージです。

- 「ひかりクラウド スマートスタディ」ならストレスチェックのさまざまなお悩み解決をサポート!
- 「年に1度しか利用していないのに費用が高い」
- 「従業員の受検状況の管理に時間が掛かっている」
- 「ストレスチェックを紙で実施すると集計が大変」
- 「従業員にパソコンを貸与していないからストレスチェックの実施が大変」
- ストレスチェックの診断結果を用いて、集団分析も可能です。
「ひかりクラウド スマートスタディ」ならストレスチェックのさまざまなお悩み解決をサポート!
ストレスチェック実施にあたって、こんなお悩みを抱えたことございませんか?
・「年に1度しか利用していないのに費用が高い」
・「従業員の受検状況の管理に時間が掛かっている」
・「ストレスチェックを紙で実施すると集計が大変」
・「従業員にパソコンを貸与していないからストレスチェックの実施が大変」
「年に1度しか利用していないのに費用が高い」
基本機能だけなら、従業員1名あたり月額198円 からご利用いただけます。また、マニュアルなどのコンテンツを登録することもできるので、eラーニングや情報共有ツールとして利用ができ、さまざまな用途にご利用可能です。 ※別途、初期費用がかかります。 ご利用にはフレッツ光などのインターネット接続サービスおよびプロバイダのこ契約が必要です(別途、月額利用料がかかります)。
>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら
「従業員の受検状況の管理に時間が掛かっている」
管理ユーザー画面で従業員の受検結果をすぐに確認できます。受検実施者、未受検者、高ストレス者の抽出も簡単に実施可能です。未受検者には、リマインドメールなどで受検を促すことも可能なため、管理者にかかる手間を軽減できます。
「ストレスチェックを紙で実施すると集計が大変」
診断結果や分析も自動集計です。ストレスチェックを紙で実施すると、診断結果の集計に大きな手間がかかり ます。「ひかりクラウド スマートスタディ」を利用すると、集計や会社全体の集団分析も自動で行うことで、運用にかかる人的コストや手間を軽減できます。
「従業員にパソコンを貸与していないからストレスチェックの実施が大変」
マルチデバイス対応をしています。従業員にパソコンを貸与していなくても、マルチデバイスに対応しているので、従業員が持っているスマートフォンなどでも受検可能です。
ストレスチェックの診断結果を用いて、集団分析も可能です。
たとえば、全社員の結果を分析することによってストレスの傾向などを把握でき、職場環境の改善に役立ちます。
・産業医が集団分析結果を元に会社全体のストレス傾向を発見できる
・産業医がストレス傾向を元に適切な指導ができる
4まとめ
このように、ストレスチェック制度は組織や企業だけではなく、労働者にとってもメリットがあることが分かります。 ストレスは現代社会において避けられない要因となりつつあり、その影響は個人の健康だけでなく、組織全体のパフォーマンスにも影響を及ぼしますため、この機会に改めてストレスチェック制度の対応方針やストレスチェック制度に対応したツールについて、検討してみてはいかがでしょうか。


