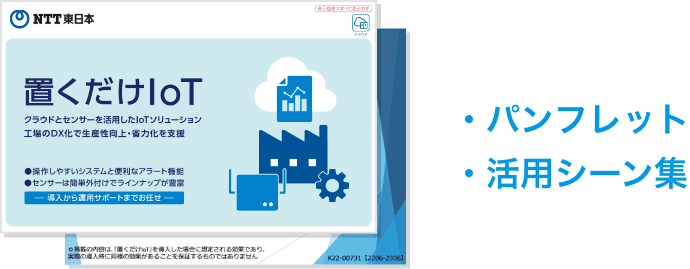クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
アナログ規制撤廃とは?具体的に何が変わるのかについて解説!
-
2024.2.01 (木)Posted by


アナログ規制撤廃とは?具体的に何が変わるのかについて解説!
近年では、デジタル技術が発展しており生活は豊かに、業務は効率化されています。
便利な世の中になっているものの、さまざまな法律・規制などによって一部ではデジタル化が進んでいません。
このようなデジタル化を阻害する規制を「アナログ規制」と呼びますが、諸外国と比較してデジタル化が遅れていることもあり、撤廃に向かって進んでいます。
そこで今回は、アナログ規制やその撤廃について紹介します。
具体的に何が変わるのかについても触れていくため、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:アナログ規制とは
2:アナログ規制の撤廃とは?
3:代表的なアナログ規制の7項目
4:アナログ規制撤廃と遠隔監視の活用
5:設備保守向けIoTサービスの活用も遠隔監視が可能
6:まとめ
1:アナログ規制とは
 近年では、デジタル技術の発展に伴って社会への浸透が進んでおり、人々の生活だけでなく働き方も大きく変わってきています。
近年では、デジタル技術の発展に伴って社会への浸透が進んでおり、人々の生活だけでなく働き方も大きく変わってきています。
デジタル化によるコスト削減や業務の効率化といったメリットが期待されていますが、法律・条例などの規制により、従来の手順を変えられないという問題が表面化しています。
このようなデジタル化を妨げる社会制度・ルールのことを総称して「アナログ規制」と呼んでいます。
2:アナログ規制の撤廃とは?
 政府は日本のデジタル技術の推進・活用が外国と比較して遅れている原因の一つに「アナログ規制」を挙げています。
政府は日本のデジタル技術の推進・活用が外国と比較して遅れている原因の一つに「アナログ規制」を挙げています。
そういった課題・原因のこともあり、2021年に「デジタル臨時行政調査会」を設置し、デジタル社会の実現を目指した構造改革に取り組んできました。
このデジタル臨時行政調査会は2022年6月「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を策定し、具体的にアナログ規制の見直しを進める方針を発表しました。
このような動きによりデジタル庁は2022年12月に、さまざまなアナログ規制が該当する法令9669条項を2024年6月までに見直す方針と工程表を取り決めています。
3:代表的なアナログ規制の7項目
 アナログ規制7項目とは、下記に示した表の項目である。
アナログ規制7項目とは、下記に示した表の項目である。
|
目視規制 |
人が現地に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、目視によって判定すること(検査・点検)や、実態・動向などを目視によって明確化すること(調査)、人・機関の行為が遵守すべき義務に違反していないかどうかや設備・施設の状態等について、一定期間、常時注目すること(巡視・見張り)を求めている規制 |
|
実地監査規制 |
人が現場に赴き、施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、書類・建物等を確認することによって判定することを求めている規制 |
|
定期検査・点検規制 |
施設や設備、状況等が法令等が求める一定の基準に適合しているかどうかを、一定の期間に一定の頻度で判定すること(第三者検査自主検査)や、実態動向・量等を、一定の期間に一定の頻度で明確化すること(調査・測定)を求めている規制 |
|
常駐・専任規制 |
(物理的に)常に事業所や現場に留まることや、職務の従事や事業所への所属等について、兼任せず、専らその任にあたること(1人1現場の紐付け等)を求めている規制 |
|
対面講習規制 |
国家資格等の講習をオンラインではなく対面で行うことを求めている規制 |
|
書面掲示規制 |
国家資格等、公的な証明書等を対面確認や紙発行で、特定の場所に掲示することを求めている規制 |
|
往訪閲覧縦覧規制 |
申請に応じて、又は申請によらず公的情報を閲覧・縦覧させるもののうち、公的機関等への訪問が必要とされている規制 |
このアナログ規制の影響を受けている代表的な例には「税理士」があります。
税理士法人の税理士は「常駐」の規定があり、例えコロナ禍であったとしてもテレワーク化が進みませんでした。
他にも、工場の設備点検などに関しても、「目視規制」の影響を受けています。
アナログ規制の類型と代替できるデジタル技術の例
このアナログ規制の撤廃に伴い、既存のアナログ規制の類型には次のようなデジタル技術を活用することで代替できると考えられています。
|
目視規制 |
ドローンやモバイルカメラ、ロボットなどで代替、AI(人工知能)や画像解析も活用 |
|
実地監査規制 |
センサーなどで常時監視異、常は自動通知する |
|
定期検査・点検規制 |
定点カメラやセンサーでリモート監査を可能に。センサーも活用 |
|
常駐・専任規制 |
テレワークを利用可能に、遠隔で専任者が必要 |
|
対面講習規制 |
インターネットなどで代替 |
|
書面掲示規制 |
オンライン講習も利用可能に |
|
往訪閲覧縦覧規制 |
許可申請や書類閲覧はオンライン化 |
アナログ規制撤廃により今まで現場で作業しなければなかったことも、デジタル技術を活用することによりリモート対応が可能になっています。
製造業の工場などでは、現場に専用の機械を設置することで、遠隔監視も実現できるでしょう。
法定点検などで目視が必要とされていた部分も遠隔で対応できるようになります。
4:アナログ規制撤廃と遠隔監視の活用
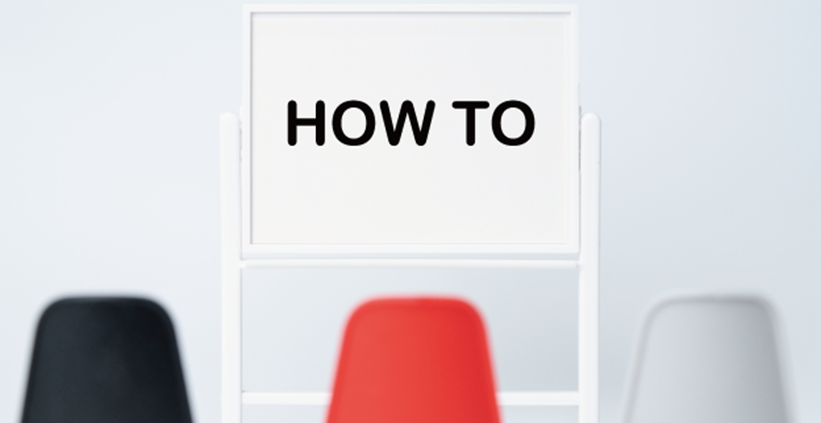 先程の通り、アナログ規制撤廃に向けて遠隔監視の体制を構築することは有効であるといえるでしょう。
先程の通り、アナログ規制撤廃に向けて遠隔監視の体制を構築することは有効であるといえるでしょう。
ここからは遠隔監視を活用するメリットについて紹介します。
リアルタイムで生産状況を把握する
遠隔監視の体制を構築することにより、遠隔地でもリアルタイムに生産状況を把握できるようになります。
例えば、製造業の工場などであればセンサーなどを設置した機械のデータを、遠隔地から収集したりモニタリングしたりできます。
製造に関するデータや映像を収集・可視化することにより、機械設備に異常が発生してもリアルタイムに検知できるでしょう。
他にも、化学プラントのような設備では流量や圧力、温度、振動などの各種データを収集、カメラの映像と合わせて使うことで、異常により早く気付くようなシステムを構築できます。
複数の製造ラインを一元管理する
複数の生産拠点を保有するような企業の場合、各施設に遠隔監視システムを導入することで、本部などで製造ラインを一元管理できます。
各施設にカメラやセンサーなどのIoT機器を設置し、管理システムを導入することにより、まとめて管理できることから、大規模な業務効率化を実現できるでしょう。
また、複数拠点の映像と各種データを本社などで一元管理し、熟練技術者による遠隔操作を実施することでより効率化を図れます。
例えば、設備ごとの電力量や生産量などを監視でき、過去のデータを蓄積し分析することで有効活用できます。
点検業務を省人化する
現在ではさまざまな業界が人手不足を課題に挙げており、製造業も例外ではありません。
施設内の点検作業は重要であるものの、人手不足によって満足に実施できていなかったり、作業者の負担が大きくなったりします。
そこで、遠隔監視システムを導入することにより人手による巡回を省人化できます。
先程の通り、本部などの中央管理室の画面で工場全体を監視できるため、担当者が現場に行き点検作業を実施する必要はありません。
実際に、監視カメラの撮影画質が良いもので、フルハイビジョン映像に匹敵するようなクオリティであれば、遠隔地でもモニター上で圧力計や流量計などを確認でき、点検業務が可能です。
他にも、近年ではドローンを使用することにより、高さがある建物や高い位置にある設備の点検も遠隔で点検・確認できるようになっています。
また、AIによる人物検出を導入することで、施設内に不審人物が侵入したり、危険区画に誤って人が立ち入ったりした場合に自動的にアラームが鳴らすことができます。
この仕組みを活用すれば、警備業務を省人化できるでしょう。
5:設備保守向けIoTサービスの活用も遠隔監視が可能
 NTT東日本が提供する「置くだけIoT~設備保守パッケージ~」は、データを取得したい設備に外付けのセンサーを設置し、システムを導入することによって遠隔監視を実現できるサービスです。
NTT東日本が提供する「置くだけIoT~設備保守パッケージ~」は、データを取得したい設備に外付けのセンサーを設置し、システムを導入することによって遠隔監視を実現できるサービスです。
センサーの種類は30種類以上もあるため、工場などの各設備に適したものの導入が可能です。
これらのセンサーとネットワーク機器のゲートウェイ、およびクラウドライセンスがセットになっているため、一括で導入できます。
必要なセンサーを各設備に設置することで、データを自動で記録し、クラウドを介して遠隔地でも状況を確認できます。
また、異常が発生するアラートが発生するため、早期発見・早期解決に繋がるでしょう。
アナログ規制撤廃を受けて、こうしたサービスの活用を検討することも一手です。
6:まとめ
この記事では、アナログ規制やその撤廃について紹介しました。
今後は各企業・業種におけるデジタル化は加速していくでしょう。
実際に、製造業などであれば法定点検が必要なものでも、カメラ・センサ・ドローンなどを活用することにより遠隔監視が可能になります。
自社に適した仕組みを採用し、業務の効率化を目指しましょう。