電力を見える化するメリットとは?注意点もあわせて紹介!
-
2024.11.18 (月)Posted by


電力を見える化するメリットとは?注意点もあわせて紹介!
近年では、世界的にもエネルギーに対する関心が高まっていて、企業だけでなく家庭でも電力を見える化できる動きが加速しています。
企業と比較すると家庭の電力消費量はそこまで大きくありませんが、電気代が高騰する昨今では、家計に大きな影響を及ぼすでしょう。
実際に電力の使用状況を見える化することにより、さまざまなメリットがあります。
手軽に電力を見える化できれば、電気代を節約しやすくなるでしょう。
しかし、電力の見える化を実現する際、場合によってはデメリットもあるため注意が必要です。
そこで今回は、家庭で電力を見える化するメリットについて紹介します。
注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:電力を見える化するメリット
2:電力を見える化する方法
3:電力を見える化する際の注意点
4:電気代を節約する方法
5:まとめ
1:電力を見える化するメリット
 電力を見える化する主なメリットは次の4つです。
電力を見える化する主なメリットは次の4つです。
節電するポイントが具体的になる
電力を見える化することにより、リアルタイムで消費電力の状況を把握することが可能になるため、削減すべきポイントが明確になり、省エネのために取り組むべき課題が見えてきます。
例えば、企業においては、電力使用量の多い機器を把握することや、家庭においては、家にいる時間にどれだけ電力を消費しているのかなどの情報を得ることができます。
その情報をもとに、電力消費量の少ない機器に変更することや、時間帯別に電力の管理を行うなどの対策を行うことが可能となります。
また、電力使用量が常に目に入るようになるため、省エネに対する意識を高めることにもつながります。
スマートフォンやタブレットからいつでも省エネに取り組んだ結果の数値を把握できるため、継続的に省エネに取り組むモチベーションにもなります。
家計簿をつけるよりも楽
電力を見える化する機器・ツールを使用する場合、専用ツールのサイトやアプリを使うことで、家庭の電力消費量をスマートフォン・タブレット・パソコンなどで確認できます。
先程の通り、電力消費の内訳を押さえられるだけでなく、毎月の電気代も自動的に記録されます。
そのため、家計簿を付ける手間は必要ありません。
もし電気代の節約に熱心な人であれば、毎月の請求額以外にもさまざまな項目を控えているでしょう。
電力の見える化を実現することで、これらの手間がなくなり、より詳細な情報を記録できます。
毎月の出費を減らせる
電力を見える化し明らかな無駄が見つかるなど、節電するポイントが具体的になると、毎月の電気代を大幅に削減できる可能性があります。
仮に毎月1,000円の節電になれば、年間で12,000円もの電気代の削減になります。
他にも、無駄な電力消費量を抑えることにより、電化製品の劣化も多少防ぐことに繋がるでしょう。
今の家電のパフォーマンスを保ったまま、長く使うことができれば、間接的な節約に繋がります。
節電で浮いたお金で保険などの見直しができる
ここまでの流れにより電気代の節約に成功すると、毎月の支出枠に余裕が生まれます。
いわゆる「ラテマネー」と言われるちょっとしたお金かもしれませんが、節約した分を他の支出に回すこともできるでしょう。
例えば、1,000円ほどの電気代を節約できた場合、現在加入している保険を見直してより保障が充実したものに変えられます。
他にも、携帯電話のプランを見直すなど、サブスクリプション形式で支払っているものを見直せるでしょう。
2:電力を見える化する方法
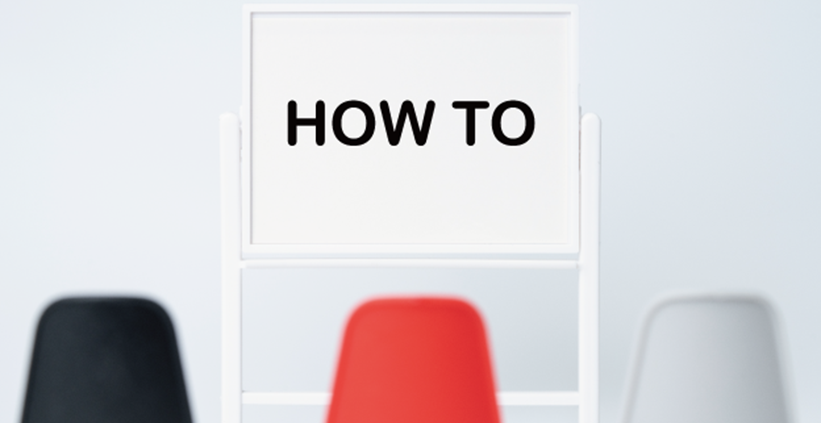 家庭で電力を見える化する主な方法は次の2つです。
家庭で電力を見える化する主な方法は次の2つです。
スマートメーターを確認する
スマートメーターは通信機能を使って電気使用量データを送信し、受け取った送配電事業者から小売電気事業者に通知します。
電気使用量を30分ごとに計測します。電力消費量の多い時間や少ない時間といった、細かい使用量の把握が可能になります。
スマートメーターの導入により、契約している電力会社のウェブサイトで、電気の使用量をグラフなどで確認できる場合があります。
また、オール電化の家では、スマート家電と連動させることで、より簡単に電気の「見える化」が可能になっています。
スマートメーターを利用すると、電気がいつ、どのくらい使われている、といった電力の使用状況が電力会社に通知されます。
見える化できる一方でデータにより、各ご家庭の生活パターンが推測しやすくなるので、万が一データが漏洩した場合には、空き巣などの被害に遭う可能性も考えられます。
HEMSを活用する
HEMSとはHome Energy Management Systemの略で、家庭内のエネルギー全体を管理するシステムのことです。
HEMSを導入し、スマートメーター(通信機能を持つ次世代の電力量計)と連携することで、どの機器がどれだけの電力を消費しているのか、電気使用量が多い部屋はどこか、などの情報をモニターに表示することが可能になります。
HEMSが連携できるのは電気機器だけではありません。
太陽光発電装置や蓄電池、電気自動車を導入すれば、太陽光発電装置で作った電気を蓄電池や電気自動車にスムーズに蓄えられます。
蓄えた電気は、電気料金の高い時間帯に使うこともできますし、停電時に緊急用として使うことも可能です。
また、水道やガスとの連携も想定されており、水道やガスの使用量もモニター画面で「見える化」できます。
3:電力を見える化する際の注意点
 電力を計測しやすいスマートメーターを利用する際、大きなデメリットはあまりありませんが、「家庭内の電力消費量を電気会社に細かく知られるのは監視されているようで抵抗がある。」という意見もあります。
電力を計測しやすいスマートメーターを利用する際、大きなデメリットはあまりありませんが、「家庭内の電力消費量を電気会社に細かく知られるのは監視されているようで抵抗がある。」という意見もあります。
そのデータがマーケティングなどに利用されることを懸念する人もいるでしょう。
また、万が一データがハッキングなどで覗き見され、外部に漏れると、個人情報の漏えいになります。
他にも、スマートメーターを交換する際には費用がかかりませんが、電力を見える化するHEMSなどの導入・システム構築にはコストがかかる場合があります。
近年では、これらの環境があらかじめ整備された物件もありますが、これから新しく導入する場合はお金がかかることがあります。
また、HEMSのメリットの一つはエネルギーの節約ですが、それによってどれだけ料金が安くなるかは住人の節電行動に任されます。
つまり、費用をかけてシステムを導入したとしても、使用者の行動が何も変わらなければ節約には繋がりません。
さらに、HEMSという情報機器を導入することで、初期設定やその後のメンテナンスが発生します。
特にインターネットに接続する機器ですので、HEMS機器やスマートフォンのアップデートがあったり設定変更が必要になったりすることもあります。
このとき、知識のある人であれば自分でカスタマイズ、メンテナンスできる場合もありますが、住宅メーカーにお願いする場合には、費用がかかったり、宅内で設定作業をお願いしたりするなどといったことが発生します。
4:電気代を節約する方法
 電気代を節約する最適な方法は家庭によって異なりますが、電気料金は単価と使用量によって決まるため、消費電力が大きい電化製品の使用時間を短くすると節約に繋がります。
電気代を節約する最適な方法は家庭によって異なりますが、電気料金は単価と使用量によって決まるため、消費電力が大きい電化製品の使用時間を短くすると節約に繋がります。
他にも、照明やテレビなどは使っている人がいない場合でも点けっぱなしになっていることが多いため、小まめに消すように意識することが大切です。
また、季節によって使い分けるエアコンや暖房などの家電は消費電力が大きいため、電気代が高くなりやすいです。
例えば、トイレの便座が温まる機能がありますが、蓋が開いていると熱が逃げてしまい冬の時期は多くの電気を無駄に使ってしまいます。
特に家庭の中でもエアコンなどの空調類は消費電力が大きい傾向にあり、設定温度と室温のギャップが大きいほど電気代は高くなりやすいです。
実際に、年間の家庭の電気料金の推移を見てみると、夏と冬は電気代が高くなりやすいです。
5:まとめ
この記事では、家庭で電力を見える化するメリットについて紹介しました。
家庭でも電力を見える化することにより、使用電気の無駄を見つけやすく節電を実現しやすいです。
実際に、無駄な電気代を節約できれば浮いたお金を他の支出に回せるでしょう。
ただし、あくまでも電気の使用状況を把握しやすくなるだけなので、システムを使っても節電になるわけではありません。
むしろ、導入コストを考えるとマイナスになることもあるでしょう。重要なことは電力を使う「人間」の行動が変わることです。
電力を見える化した場合は、目的に合わせて行動をしっかり変えるようにしましょう。
