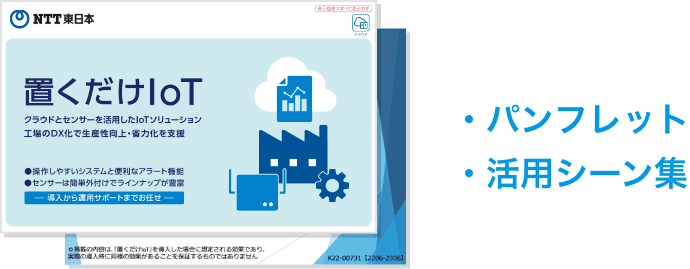クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
乾電池の仕組みはどうなっている?歴史や進化の過程も紹介!
-
2023.12.01 (金)Posted by
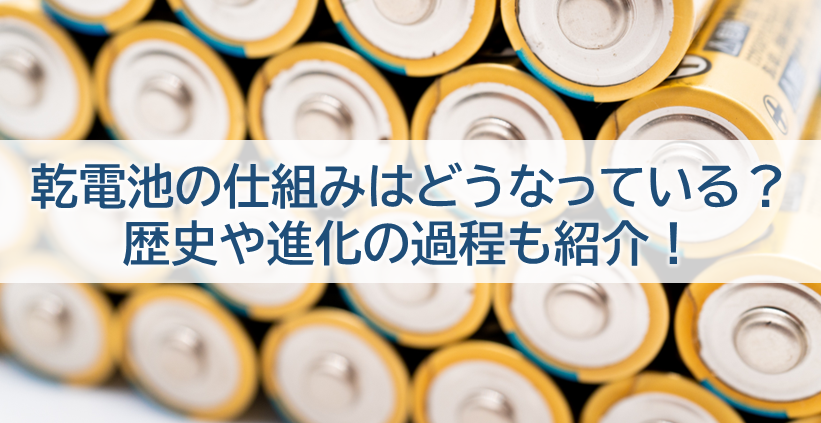

乾電池の仕組みはどうなっている?歴史や進化の過程も紹介!
日常生活で使用する機会が多い「乾電池」。しかし、その仕組みや歴史を詳しく知る人は多くないでしょう。
仕組みや歴史を知ることで、より乾電池を効率良く利用できるようになるでしょう。
実際に、近年では乾電池はさらに進化しており、電源の確保としてさまざまな用途で利用されています。
乾電池の歴史は複雑であり、海外ではさまざまな学者が開発し続けていました。
そこで今回は、乾電池の仕組みや歴史を解説します。
未来型の電池まで紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:乾電池の仕組み
2:乾電池の歴史
3:乾電池の進化や最新情報
4:まとめ
1:乾電池の仕組み
 まずは乾電池の大まかな仕組みについて解説します。
まずは乾電池の大まかな仕組みについて解説します。
電子イオンが溶け出ている
電池から電気を取り出せるのは、内部にある構造から電子イオンが溶け出ているためです。
現在の乾電池の原型と言われている1800年頃に誕生した「ボルタの電池」を例に説明すると、まず電解液である希硫酸に銅板と亜鉛版を入れます。
希硫酸は金属を溶かす液体であり、そこに入れる銅板・亜鉛版は少しずつ溶け始めます。
このとき銅板は乾電池のプラス極に、亜鉛版は乾電池のマイナス極となります。
この金属が溶けるとき、亜鉛版から亜鉛イオンが電子を残した状態で溶け出します。
このとき、亜鉛版に残された電子は導線を伝って銅板へ移動し、この電子の移動により電流が発生する仕組みです。
銅板へ移動した電子は希硫酸の中で水素イオンと結合し、水素ガスになるため銅板は亜鉛版よりも電子が増えることはなく、取り出した電流により電球などが点灯するような電気が生まれるのです。
乾電池の構成要素
電池の種類によって細かい構成要素は異なりますが、ボルタの電池のように金属と液体(電解液)を利用して電気を取り出しています。
電池には大きく分けて使い切りの「一次電池」と、充電して繰り返し使える「二次電池」があります。
一次電池にはマンガン乾電池やアルカリ乾電池があり、最もオーソドックスなマンガン乾電池はプラス極側に二酸化マンガン、マイナス極側に亜鉛、電解液に弱酸性の塩化亜鉛・塩化アンモニウムが使われています。
乾電池の中では長時間電気を取り出せるアルカリ乾電池も、基本的にはマンガン乾電池と仕組みは同じです。
ただし、プラス極側に二酸化マンガンと黒鉛、マイナス極側に亜鉛粉末が使われており、電解液には水酸化カリウムが使われています。
この水酸化カリウムがアルカリ性であるため、アルカリ乾電池と呼ばれています。
電池切れの状態
ここまでの説明の通り、乾電池は種類によって使われる素材や配置は異なるものの、金属や電解液を使用する仕組みは同じで、内部のプラス極の材料とマイナス極の材料との間での化学反応により電気が発生します。
このとき、プラス極とマイナス極に電球などの導線を当てることにより電気が流れますが、使い続けると電気が発生する化学反応が終了していきます。
基本的に乾電池では電気を取り出す化学反応が起きるたびに電圧が下がっていき、一定量を下回ると電流が生まれなくなります。
2:乾電池の歴史
 ここからは乾電池が生まれた歴史を簡単に紹介していきます。
ここからは乾電池が生まれた歴史を簡単に紹介していきます。
世界最古の電池
世界最古の電池は約2000年以上前のものとされる、イラクの首都バグダッドの遺跡から発見されたつぼ型の「バグダッド電池」です。
基本的な仕組みは今と変わらず、つぼの中に金属と電解液が入っており、電気を取り出しています。
遺跡から発見されたことにより、どのような用途で使われていたか、電解液の内容ははっきりと分かっていませんが、電解液は酢・酒(ブドウ酒)などが使われていたと推測されています。
ボルタなど海外で電池が発明される
生物の実験ではカエルの神経・筋肉に電流を流して動かす実験が有名ですが、このカエルの足の実験が実用的な電池の起源といわれています。
時代は1780年頃、イタリアの生物学者であるガルバーニが、カエルの足に鉄の柵と電解液を使い、電流によって足が動く様子を観察しました。
その後、同じイタリアのボルタが1800年頃に「ボルタ電池」を開発します。
先程の説明の通り、銅・亜鉛・電解液を使った仕組みを考案し、銅と亜鉛を導線で繋ぐことにより電気を取り出しています。
その後、海外ではフランス人のルクランシェが1868年頃に「ルクランシェ電池」を開発しており、改良され続けていて今の乾電池の形が決まります。
しかし、この頃の電池は電解液が漏れ出てしまうことから不便さがありました。
1888年にはドイツ人のガスナーが電解液がこぼれない電池を発明。
この電池は電解液である液体がこぼれないことから「乾いた電池(乾電池)」と呼ばれるようになりました。
1800年後半に日本で発明される
ガスナーと近い時期に、実は日本でも独自に乾電池が開発されていました。
発明者は「屋井 先蔵」氏であることから「屋井乾電池」と呼ばれています。
この頃に日本国内で使用されていた電池は液体式のダニエル電池と呼ばれるもので、手入れが必要な上に冬場は凍結して使えない点がデメリットです。
このように日本でも、海外と同様に電池の液体が起こす不具合が課題となっていました。
そこで屋井氏が炭素棒にパラフィンを浸み込ませる仕組みの乾電池を開発。
実際にはガスナーが開発した1888年よりも前である1887年であると言われているため、世界初の乾電池は屋井乾電池と呼ばれています。
充電池の普及
ここまで開発された乾電池は基本的に使い切りの一次電池であり、その後改良されたものが多く登場しました。
そこから1900年代になると、繰り返し使える二次電池が開発されます。
現在では主流となっている充電池の原型であるニカド電池は1899年にスウェーデンのユングナーが発明したものが最初と呼ばれています。
そこから改良が続き、1960年頃にアメリカで商品化され、日本では1963年頃に国内での量産体制が生まれました。
その後、1990年代にニッケル水素電池、リチウムイオン電池などが次々と開発されていきます。
3:乾電池の進化や最新情報
 近年でも乾電池は進化を続けており、便利になっています。
近年でも乾電池は進化を続けており、便利になっています。
ここからは、乾電池の進化や最新事情を紹介します。
小型化とエコ化
近年では乾電池はさまざまな進化を遂げていますが、その中でも小型化に成功したものが注目されています。
いわゆるマイクロ電池が開発されたことにより、電化製品自体も小型化されており利便性が高まっています。
特に海外ではセンサーやチップなどに使用できる電池が開発されており、世界最小のバッテリーと呼ばれているものは塩一粒ほどの大きさです。
また、国内では環境に優しいエコの電池が開発されています。
パナソニックが開発したエボルタ、三洋電機のエネループは長寿命・繰り返し使える能力が優れていることにより評価されています。
エボルタは2008年に発売され、従来よりも1.5倍ほど寿命が伸びていることで当時は注目されました。
エネループは繰り返し充電しても劣化しにくく、充電したてのように使えます。
このように資源を大切にした地球に優しい電池が注目されています。
未来型の乾電池の種類
未来型の電池として開発が期待されているものをいくつか紹介します。
固体電解質電池
電池の材料に水分を使わないことで、温度変化が大きな過酷な環境でも使用できると期待されています。
また、永久埋め込み型の人工腎臓など人工的な臓器の電源としても活躍するでしょう。
バイオ電池
こちらも人体に埋め込んで使うタイプの電池で、血液中のブドウ糖から電気を起こすもので、医療分野での活躍が期待されています。
海水電池
海水を利用して電気を起こす方法で、発電方法としてもクリーン・経済的という観点から注目されています。主に海上の施設の電力供給に役立ちます。
紙電池
紙のように薄い電池のことであり、さらに紙のように自由自在に加工できる点が特徴です。
温度電池
温度の変化を利用して電気を起こし充電する電池であり、温度変化が激しい地域で活躍します。
プラスチック電池
プラスチックをもとにした電池で、電池ケースが不要となり形に制限がないためさまざまな用途での活用が期待されています。
服電池
服に太陽電池が内蔵されており、便利で環境に優しいです。
4:まとめ
この記事では、乾電池の仕組みや歴史について紹介しました。
電池の起源は約2000年以上も前からありましたが、本格的な実用化が始まったのは1800年頃です。
また、世界最初の乾電池は日本のものであるという説もあり、面白い歴史があるでしょう。
さらに、未来型の電池には人体に埋め込み、半永久的に使えるものなどさまざまなものがあります。
この機会に電池のことを詳しく知って、今後に役立ててみてください。