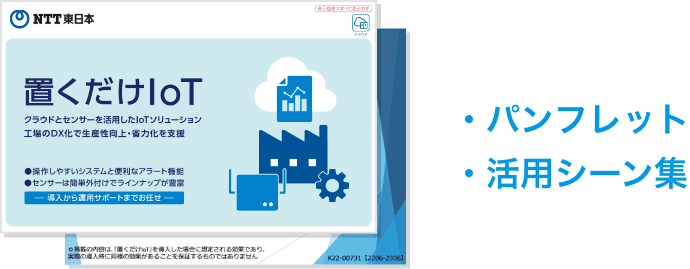クラウドとセンサーを活用したIoTソリューションで製造現場の生産性向上・省力化を支援します。稼働監視、故障予知、コスト削減などの活用シーンも公開中。
おどろき発電方法を紹介!一般的な発電方法もおさらい
-
2023.11.17 (金)Posted by
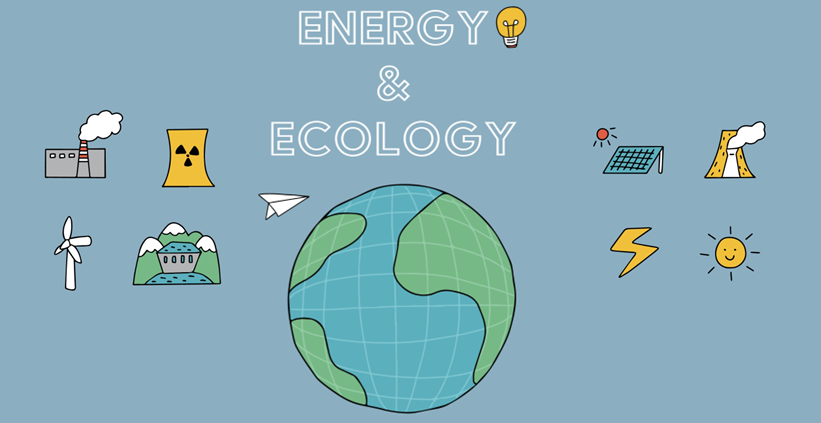

おどろき発電方法を紹介!一般的な方法との違いについても解説
普段使用している電気はどこかの発電所にて生まれているものです。
発電方法にはさまざまな方法があり、火力発電・水力発電・原子力発電などが国内の電力事情を支えています。
しかし、近年では環境配慮の観点からさまざまな発電方法が注目されており、世の中には驚きの発電方法もあります。
そこで今回は、発電方法について詳しく解説します。
驚きの発電方法についても触れるので、ぜひ参考にしてみてください。
<目次>
1:国内の一般的な発電方法
2:注目されている環境配慮型の発電方法
3:おどろきの発電方法
4:まとめ
1:国内の一般的な発電方法
 まずは一般的な発電である次の3つの方法の特徴について紹介します。
まずは一般的な発電である次の3つの方法の特徴について紹介します。
基本的にはいずれの方法もタービンを回転させることによって発電しています。
火力発電
火力発電は、石油・石炭・天然ガスといった資源を燃焼させた際に生まれるエネルギーを使って蒸気を発生させ、タービンを回転させることにより電力を生む方法です。
このように燃焼による蒸気を使って発電するため汽力発電とも呼ばれています。
また、火力発電では蒸気を活用するケースが多く、燃焼時に発生するガスを使いタービンを回すガスタービン発電なども火力発電の一種です。
さらに、汽力とガスの両方を組み合わせたコンバインドサイクル発電などもあるなど火力発電の種類はさまざまですが、それぞれの方法によって発電の効率(エネルギー変換効率)は異なります。
火力発電は資源があれば安定的に発電できる点が最大のメリットです。
例えば、一般的に火力発電は気候・周辺環境などの影響に左右されにくいです。
また、他の発電方法と比較すると発電効率は高く、さまざまな地域で採用されています。
ただし、発電時に温室効果ガスの排出量が多い点がデメリットです。
水力発電
水力発電は水の位置エネルギーを利用して発電する方法です。
ダムなどを活用し、高い位置にある水を低い所へ流れ落ちる際のエネルギーを活用しタービンを回して発電します。
水力発電にもさまざまな種類があり、川の流れを利用する水路式、河川の水量を調整池で調整して発電する調整池式、ダムに貯まった水を活用する貯水池式があります。
水力発電のメリットはコストパフォーマンスが高く、火力発電のように資源を輸入する必要はありません。
エネルギー変換効率も高くロスが小さい方法であり、温室効果ガスも排出しない点もメリットです。
しかし、水力発電は気候の影響を受けやすく、降水量が少ない日が続くと発電量が低下するリスクがあります。
原子力発電
原子力発電の仕組みは基本的に火力発電と同様であり、ウラン燃料を使って得たエネルギーを活用して蒸気を生み、タービンを回して発電します。
核燃料であるウランは原子核が2つ以上に分裂する「核分裂」の際に大きなエネルギー(高熱)が発生し、その熱を活用します。
原子力発電は燃料になるウランが安価であり、産出国が多いことから供給が安定している点がメリットです。
また、仕組みは火力発電に似ているものの核分裂の際には温室効果ガスは発生しません。
このように原子力発電のメリットは多いですが、事故が発生した際のリスクが大きいです。
事故などにより発電所から放射能・放射性物質が漏れ出ると周辺に大きな悪影響を及ぼします。
また、高レベルの放射性廃棄物の処理・原子炉の廃炉に莫大な費用が発生する点もデメリットです。
2:注目されている環境配慮型の発電方法
 一般的な3つの発電方法は資源を利用することから、近年では環境に配慮した発電方法が注目されています。
一般的な3つの発電方法は資源を利用することから、近年では環境に配慮した発電方法が注目されています。
その中でも注目されている環境配慮型の発電方法は次の4つです。
太陽光発電
太陽光発電とは、名前の通り太陽の光エネルギーを利用して発電する方法です。
主にソーラーパネルを使用し、その面に陽の光を当てることで電気が生まれるため、火力発電・原子力発電のように発電自体にコストはかかりません。
また、発電時に温室効果ガスを排出しない点もメリットです。
近年では、戸建て住宅の屋根に設置し自宅で発電して電気代を賄うケースが増えてきました。
また、活用されていない広大な土地にソーラーパネルを設置し、発電する企業も少なくありません。
他にも、化石燃料などを使用しないことから、資源が枯渇する心配もないでしょう。
ただし、太陽光発電は天候に左右されやすく、雨や雪が多いと満足に発電できません。
太陽光発電に不向きなエリアでは安定供給が難しいため、場所を選ぶ点が大きなデメリットです。
風力発電
風力発電は巨大な風車を使用して発電する方法です。
風車を利用したエネルギー活用方法は昔から世界的に根付いており、羽が回転することにより発電機が動く仕組みです。
風は気圧の差によって生まれるため、資源を使用することなく枯渇する心配はありません。
また、燃料も不要であるため温室効果ガスが発生しない点もメリットです。
風力発電の規模によって変わりますが、羽の直径は50m〜100m近くになるものもあります。
羽が大きいほど回転させるために強い風が必要になりますが、その分、得られるエネルギーも大きくなります。
設備が巨大になり、風がない地域では発電できません。
また、風が強すぎるエリアでは風車が壊れるリスクが高まるなど、太陽光発電と同様に場所を選ぶ点がデメリットです。
バイオマス発電
バイオマス発電の仕組みは基本的に火力発電と同じですが、燃料が異なります。
バイオマス発電で使用される燃料は、生ごみ・木くず・家畜の排泄物といったゴミなどの廃棄物です。
これらを燃料として再利用することにより、化石燃料などの貴重な資源を使用せずに済むため、環境に優しいと考えられています。
また、これらの材料の中には発酵させることによりガスが発生し、それを燃料として活用し発電するものもあります。
このような燃料を使用し蒸気・ガスを使ってタービンを回し発電します。
バイオマス発電の場合、火力発電と同様に温室効果ガスなどが発生しますが、化石燃料に由来するものではなく自然から生まれているものである点に違いがあります。
ただし、火力発電などと同様の電力を発電させるためには大量の材料が必要となり、調達するコストが高く安定性に欠ける点もデメリットです。
地熱発電
地熱発電とは名前の通り、地熱を利用してエネルギーを変換する方法です。
地下にある熱を活用するため、化石燃料やバイオマス燃料などの資源は不要であり、自然由来のエネルギーであるため温室効果ガスも発生しません。
しかし、火山帯などでなければ地熱を活用できないため、世界的に見ると地理的に限定的な発電方法であるといえるでしょう。
日本は火山帯に位置しているため、今後の発電方法として注目されています。
また、バイオマス発電などと異なり安定的に発電でき、太陽光発電と異なり時間帯や天候に左右されない点もメリットです。
ただし、発電効率は悪く、発電施設の建設にコストがかかるのが主なデメリットです。
3:おどろきの発電方法
 ここまで紹介した方法だけでなく、世の中には驚きの発電方法があります。ここからは次の3つの発電方法を紹介します。
ここまで紹介した方法だけでなく、世の中には驚きの発電方法があります。ここからは次の3つの発電方法を紹介します。
うどんを活用した発電
うどんを活用した発電は日本で生まれた特殊な方法で、大きくはバイオマス発電に分類されます。
讃岐うどんで有名な香川県では年間に膨大な量のうどんが廃棄されており、食品ロスが深刻な問題となっています。
香川県内では小麦粉換算で、年間3000トン以上が廃棄されている試算から、高松市は、県内外で6店舗を展開するさぬき麺業(高松市)と協定を結び、贈答用の製造工場などから、製造過程で出る切れ端など月約400~600キロを提供。
そこで、炭素と水素が含まれる廃棄うどんを微生物の力で発酵させてメタンガスを発生させ、そのガスを燃焼させることにより発電させる方法が考案されました。
単純計算で、うどん1日20キロで年23万円の売電収入が見込めるといい、脱炭素と食品ロス削減の「一石二鳥」を狙う営みになっています。
通勤ラッシュを利用した床発電
発電方法の中に「床発電」というものがあり、歩いたときの振動から電力を発生させる仕組みです。
もちろん火力発電などと比較すると、得られる電力の量は小さいものの活用されるシーンは少なくありません。
通勤ラッシュでは多くの人が発電できる床を踏むことになるため、多くのエネルギーを得られると考えられています。
自動改札など駅に設置されるケースが多く、構内の電力として活用されています。
また、駅構内以外でも、振動を電気に変換する発電の仕組みから、サッカースタジアムでサポーターが応援時にするジャンプによる振動を発電に活かす試みがあります。
その他、高速道路を走る車による振動であったり、振動から発電する仕組みの実用化は進んでいます。
しかし、振動から電気をつくるのは、非常に微弱(びじゃく)な電気となってしまう為、振動から電気をつくる量を増やす技術も今後の課題となるでしょう。
牛の排せつ物から発生するガスによる発電
牛の排泄物をタンクに集め、微生物の力により発酵させることにより大量のガスが発生します。
このガスを活用することによりバイオマス発電が可能になるのです。
従来までは牛糞は優れた肥料として使われていましたが、発酵させることにより発電できるため、農業分野での活用が期待されています。
岡山では、畜産農家と大阪の電気工事会社がタッグを組み、バイオマスプラントを設置する計画も進んでおり、1日あたり約400トンにもなる牛ふんの悪臭は長年にわたり地域の悩みの種になっていたが、発電以外でも、プロジェクトはその軽減策としても期待を集めている。
ガスを発生させる過程で働く菌は、酸素のない環境で生育する嫌気性の菌であるため、牛ふんの発酵は密閉空間で行われ、外部に悪臭が漏れない仕組みだ。
実際に、農業と畜産を共存させやすく、ビニールハウスの温度調整などの電力を賄えることができれば、作物の安定的な生産やコスト削減などを実現できる可能性があります。
4:まとめ
この記事では、発電方法について詳しく解説しました。
近年ではさまざまなエネルギーを電力に変換する取り組みがされており、環境に配慮した発電方法が注目されています。
中には香川県のうどんを活用した方法もあり、今後は技術の発展によってさらに発電方法は増えていくでしょう。