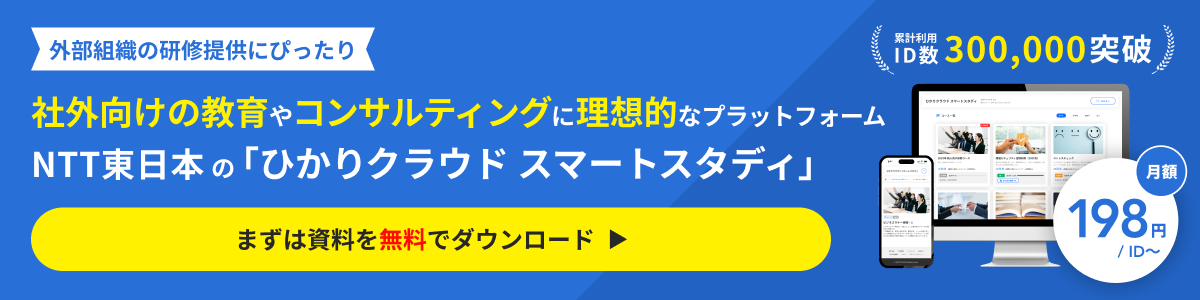オンライン研修を企画・販売するための6つのステップ
-
2025.7.11 (金)Posted by NTT東日本

テレワークの普及や学び直し(リスキリング)への関心が高まる中、オンライン研修のニーズが急増しています。企業の人材育成担当者が自社ノウハウを提供したり、個人でも自らの専門知識を活かして外部向けに研修コンテンツを販売するケースが増えています。
本記事では、オンライン研修を企画し、販売するための6つの基本ステップをご紹介します。
NTT東日本では、プラットフォーム型のeラーニング「ひかりクラウド スマートスタディ」を提供しています。
eラーニング教材(テキスト・動画・テストなど)をアップロードすることで、社外にオンライン研修用のコンテンツを配信できます。
>> NTT東日本のeラーニングサービスを知る
オンライン研修の動向や導入ステップまるわかり!

- 目次:
1目的とターゲットを明確にする

オンライン研修を企画する際に最も重要なのが、「なぜその研修を行うのか」、「誰のために行うのか」という根本的な問いにしっかりと答えを出すことです。
目的とターゲットが曖昧なままでは、研修の構成や訴求方法がちぐはぐになり、結果として参加者の満足度や販売実績にも悪影響が出てしまいます。
目的を設定する
まず、「目的」の設定についてです。これは単に「研修を提供したい」だけではなく、受講者が研修を受けることでどんな変化や成果を得られるかを明確にすることが求められます。
たとえば、「新人営業担当者が初めての顧客訪問に自信を持てるようになる」や「経理担当者が最新の法改正に対応できるようになる」など、具体的な成果イメージがあることで、研修の方向性も明確になります。
ターゲットを設定する
次に、「ターゲット」の設定です。オンライン研修の特性上、対象者は地域や業種を超えて広く設定することもできますが、誰にでも当てはまる内容を目指すと、かえって誰にも響かないものになりがちです。
そこで、年齢、職種、キャリアの段階、抱えている悩みや課題など、できるだけ明確なペルソナを設定しましょう。
たとえば「入社3年以内の若手エンジニア」「育児と仕事を両立したいフリーランスの女性」「中小企業の管理職」など、具体的であるほど、言葉のトーンやコンテンツ内容も適切に調整しやすくなります。
加えて、ターゲットが研修を必要としている背景にも目を向けるとよいでしょう。
法改正、業界の変化、スキルの陳腐化、キャリアチェンジなど、ニーズを把握することで、より実用的かつ求められる研修につながります。
2コンテンツを設計する

ターゲットと目的が明確になったら、次に取り組むべきは具体的な研修コンテンツの設計です。
オンライン研修は、受講者が一人で学習する時間も長くなるため、内容構成や進行のテンポが学習の質に直結します。
そのため、単なる知識の羅列ではなく、ストーリー性と体系性を持ったカリキュラムの構築が求められます。
トピックを選定する
次にそのトピックを小さな単位に分け、それぞれのセッションで何を伝えるのかを明確にします。 各セッションのゴールを設定することで、受講者も進捗を実感しやすくなります。
教材の形式を決める
また、ライブ配信か録画型かの選択も大きなポイントです。 ライブ配信であれば双方向のコミュニケーションがあり、受講者のエンゲージメントを高めやすい一方、録画型であれば繰り返し学べるというメリットがあります。
さらに、理解度のチェックポイントや実践的な演習を入れることで、受講者が学んだ内容を“自分ごと”として定着させることができます。アウトプットの設計まで踏み込めば、研修の価値は格段に上がります。
3プラットフォームを選ぶ
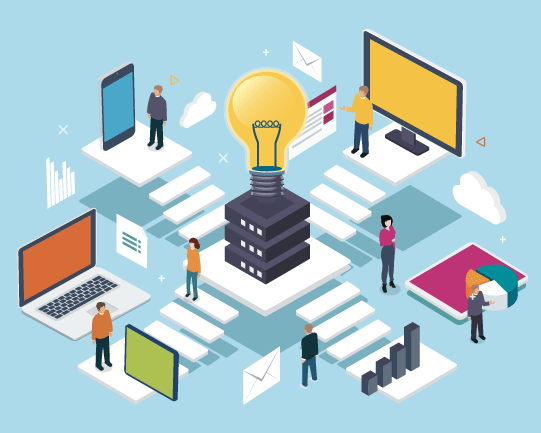
オンライン研修の内容がある程度固まったら、配信プラットフォームの選定をしましょう。
どんなに優れたコンテンツでも、受講者がスムーズにアクセスできない、操作が複雑、といった体験をしてしまうと、価値が半減してしまいます。
プラットフォームは、受講体験そのもののクオリティを左右する要素として、慎重に検討しましょう。
自社で立ち上げる
ブランディングやデザインの自由度が高く、ユーザーとの直接的な接点を持ちやすいのが利点です。
ただし、システム構築やセキュリティ対策、決済導入などにある程度のコストと手間がかかるため、リソースやスキルが必要になります。
研修プラットフォームを利用する
これらはあらかじめ動画アップロード機能や受講管理機能など必要な機能が整っているため、導入準備が比較的スムーズです。
ただし、アップロードに制限があったり、カスタマイズ性が低かったりすることもあるので、その点は事前にチェックが必要です。
ライブ配信がメインの場合
特に双方向のやり取りを重視したい場合や、質疑応答を交えたいシーンでは、こうしたツールのリアルタイム性が強みになります。
録画機能やチャット機能を活かすことで、参加者とのエンゲージメントも高まります。
さらに、YouTubeやInstagramなどのSNSを活用した限定配信も可能です。特に無料コンテンツの一部を公開して認知を広げる導線としては効果的です。
4集客・プロモーション戦略を立てる
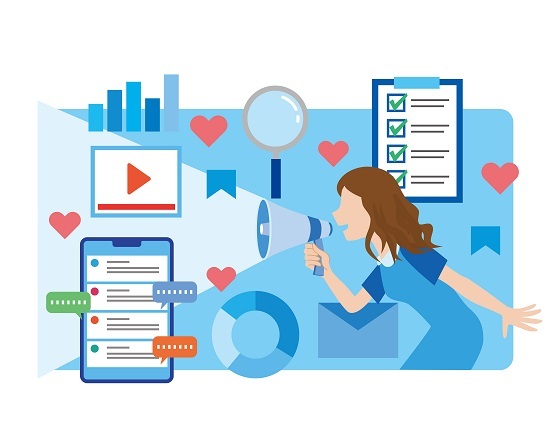
どんなに優れた研修でも、受講してもらえなければ意味がありません。
オンライン研修の成功を左右するのが、効果的な集客とプロモーション戦略です。どれだけ多くの人に「知ってもらえるか」が大きな鍵を握ります。
訴求メッセージを決める
「最新のトレンドが学べる」「現場で使えるノウハウが身につく」「キャリアアップに直結」など、受講者が得られるベネフィットを明確に言語化します。
その際、ターゲットに合わせた言葉のトーンを意識することで、より響く表現になります。
マーケティング手法を決める
一方、個人向けは日常的に使われているSNSが効果的です。プラットフォームごとにユーザー層や反応が異なるため、それぞれの特性に合わせた発信内容を検討しましょう。
また、「無料トライアルセッション」や「導入企業限定の早期申込特典」など、企業側の意思決定ハードルを下げる施策も非常に有効です。
特に新規導入を検討する段階では、実際の内容や講師の品質に対する懸念が多くあるため、短時間の無料体験や、社内で使える一部コンテンツを先行提供することで、担当者や決裁者の不安を払拭することができます。
導入前に納得してもらうことで、スムーズな稟議・契約決定につながります。
5販売を開始する

オンライン研修を商品として世に出すには、適切な価格設定が重要となります。 価格を決めるにあたって参考にしたいのが、競合となる類似サービスの市場調査です。
同じようなテーマの研修が、どのような価格帯で販売されているかを調べ、その中で自分の研修がどの位置に立つのかを見極めましょう。
価格を競うのではなく、自分の研修の差別化ポイント(独自性、特典、講師の実績など)を整理し、それにふさわしい価格を提示することが大切です。
販売を開始したら、SNSやメールなどでの定期的なリマインドやコラムやブログの集客も欠かせません。
人は何度か情報に触れることでようやく興味を持ち、行動に移します。 一定期間内に集中して訴求を行う期間を設けることで、緊張感と勢いを持って販売を展開できます。
最後に重要なのが、「価格に見合った価値がある」と受講者に実感してもらうこと。 そのためにも、販売前の期待づくりと、受講後の満足度向上の両輪を意識しましょう。
6フィードバックをもとに改善する

オンライン研修は「一度作って終わり」ではなく、継続的に価値を高めていくプロダクトです。 受講者の声に耳を傾け、そのニーズや反応をもとに改善を重ねることで、研修の質も、ビジネスとしての信頼度も格段に向上します。
言い換えれば、フィードバックは「次の成功の設計図」といっても過言ではありません。
まずは受講後のアンケートや満足度調査を実施し、率直な感想や改善点を集めましょう。
特に注目したいのは、「どこで学習がつまずいたか」「どの部分が最も役立ったか」「もっと知りたかったことは何か」などの具体的な声です。
自由記述形式の回答を通じて、想像していなかったニーズや、講師側の伝え方の癖などにも気づくことができます。
加えて、受講後の行動変化や成果の確認も重要です。たとえば、スキル習得によってどのような業務改善ができたか、資格試験に合格したか、転職や昇進に役立ったかなど、ポジティブな事例があれば、今後の販促材料にもなります。
そうした声を集めておけば、コンテンツの磨き込みと同時に、受講者のロイヤルティも高まっていきます。
改善の対象は内容だけではありません。配信方法や教材形式、進行スピード、サポート体制などの受講体験の設計全体も見直しの余地があります。
たとえば、動画が長すぎて集中力が続かない、資料がPDFのみでスマホでは見づらい、質問がしづらいといったフィードバックは、次回の実施時に活かせる重要なヒントです。
受講者からの声は、その研修を本当に必要としてくれた証。 ひとつひとつを大切に受け止めながら、自信を持って次のステップへ進んでいきましょう。
7まとめ
本記事では、オンライン研修を提供する6つのステップを紹介しました。トライ&エラーでまずは試してみる、フィードバックをもとに改善する、を繰り返し、より良い研修提供にしましょう。
NTT東日本では、社外への研修や教材提供をサポートするクラウド型のeラーニングプラットフォーム「ひかりクラウド スマートスタディ」を提供しています。
ひかりクラウド スマートスタディは、オリジナルの教材コンテンツ(テキスト、動画、テストなど)をアップロードして社外のお客さまにeラーニングを気軽に提供することが可能です。また、タイムリーにお客さまのニーズに合ったカリキュラムを作成することができるなど、充実した機能とサポートでこれからオンラインの販売に初めて取り組む企業さまでも簡単に活用可能できます。
また、初期費用5,500円~、月額利用料1IDにつき198円〜と安心の定額制なのもおすすめポイントといえます。ぜひ、この機会に2週間の無料トライアルを試してみてはいかがでしょうか。
>> ひかりクラウド スマートスタディの詳細はこちら