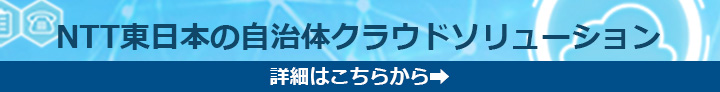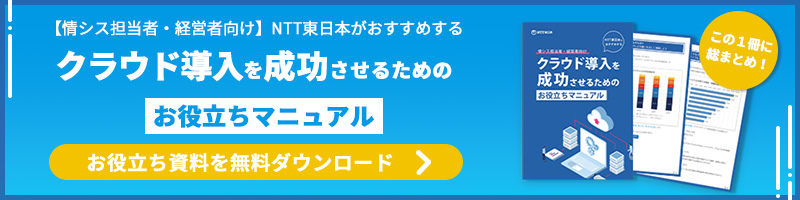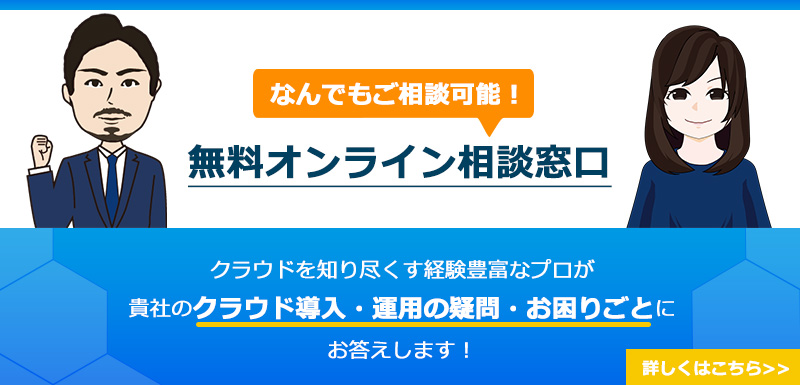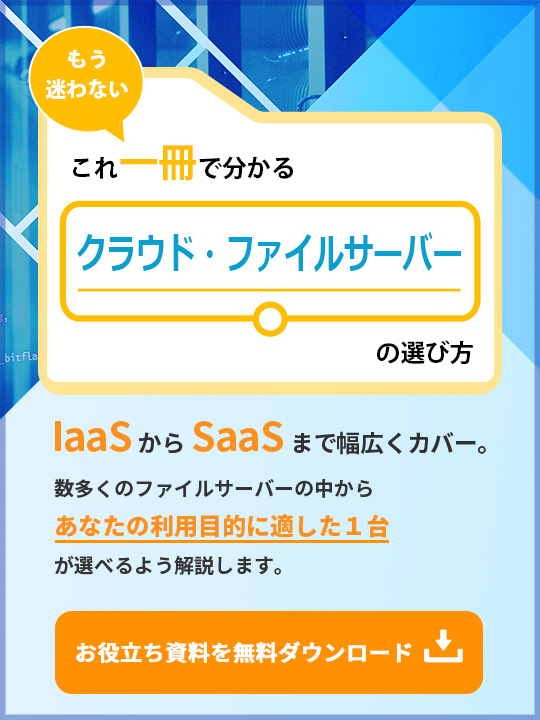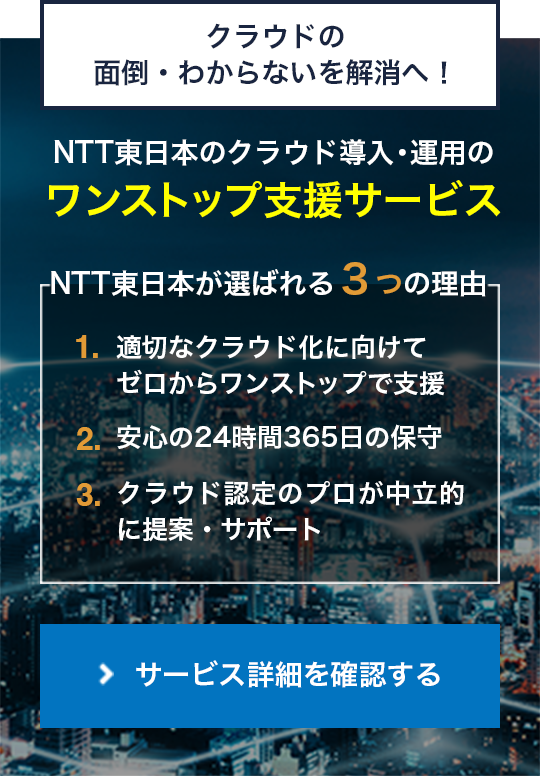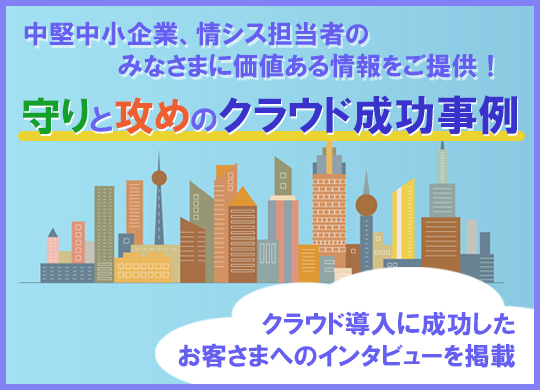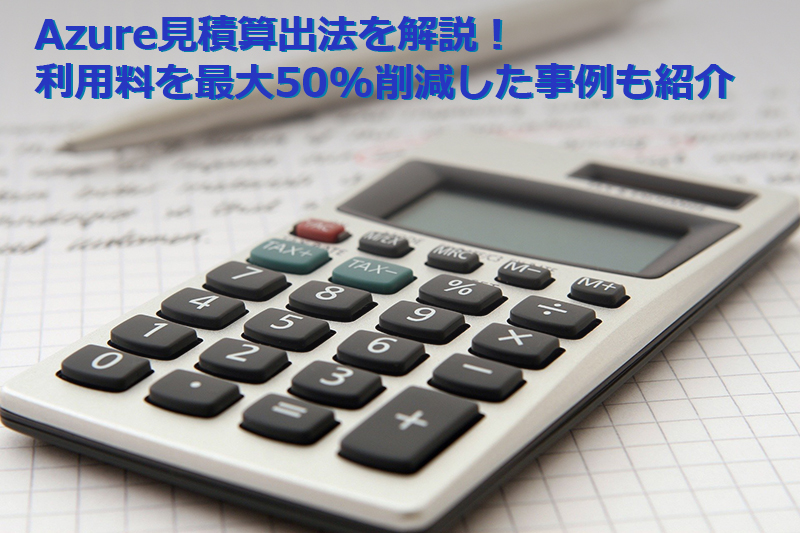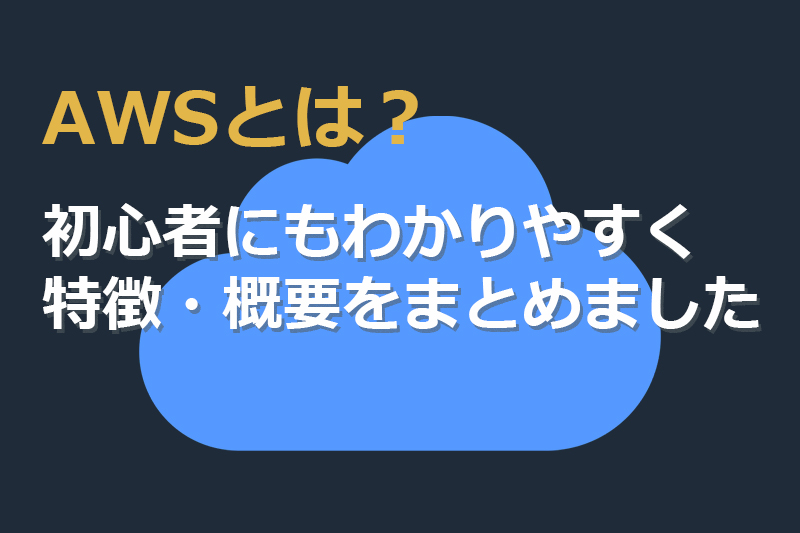AWS Ambassadorと見るAWS Summit Japan 2025基調講演の内容から今後について考察を深める

 |
こんにちは、白鳥です。 |
|---|
6/25,26にAWS Summit Japan 2025が行われました。当社ブースにご来場いただいた皆さま本当にありがとうございました。
本コラムでは、基調講演及びスペシャルセッションのレポートを兼ねた記事となります。

想定する読者
- AWS Summit Japan 2025に参加しより見識を深めたい方
- AWS Summit Japan 2025には参加できなかったが、基調講演の内容理解を深めたい方
本コラムでは、基調講演及びスペシャルセッションの要約は行いません。
キーフレーズ「Builderによる価値創造」「Building Blocks」
2つのセッションともに、参加者のことをBuilderと呼び、Builderによる価値創造の大切さとBuilderへの感謝、そしてBuilderが価値創造を行うためのBuilding BlocksとしてのAWSの各サービスの進化への取り組みの説明を行っておりました。こうしたBuilding Blocksの進化の大切さをテーマにしたセッションはre:Invent 2024のMatt Garman氏のCEO Keynoteから増えてきています。以前よりAWSはBuilderもBuilding Blocksも提唱しており、ことさら2024年以降の新しい概念でもなく、マーケティングワードでもありません。2つのセッションで語られたBuilderとBuilding Blocksというワードの意味から、理解を深めていきたいと思います。

Builder とは?
AWSが言うBuilderとは、業種や規模は異なっていても新たな価値創造への意思を持つ人と言っています。新たな価値創造とはビジネスモデルの変革を行うこと、その手段としてBuilding Blocksを使いながら、デジタルトランスフォーメーションとカルチャーイノベーションを推進できる人のことを言います。Builderはエンジニアに限らず、すべてのロールの方が含まれます。re:Invent 2023のWerner Vogels氏のKeynoteで「Now Go Build」というキーワードが発せられていましたが、今思うとこのワードもBuilderを目指せ、というメッセージであったと理解しています。
Builderのロールモデルに挙げられるのは、セッション冒頭の動画インタビューで出てきたAWS Heroの方です。業種業態や所属組織を問わずグローバルに新たな価値創造をけん引している方となります。
Building Blocksとは?
Builderが価値創造を行うためのパーツが、このBuilding Blocksになります。テクノロジーでいえば、AWSの各種サービスやアプリケーション開発、AWSと接続するためのネットワークサービスなどとなります。
AWSではこれらのBuilding Blocksを疎結合にし、使いたいときに使えるだけ使えるよう、またより安全で高可用性になるような設計を各種サービスの中でも行い、Builderが使いやすくなるような工夫をしています。基調講演及びスペシャルセッションの多くはCompute/Storage/Database/Inferenceの4つのパートに分けて具体的な説明を行っておりました。
なぜBuilderを目指す必要があるのか?
ではなぜBuilderを経営層もエンジニアも含め、すべてのロールの方がBuilderを目指す必要があるのでしょうか?これは、2つの理由があります。
1つ目は、生成AIの進化にあります。すでに最新の生成AIの基盤モデルは、単一の人間の持つ知識量を上回っています。それだけではなく、専門知識やドメイン知識といった深い領域をRAGやMCPなどを使って付加することによって強化することができます。まだ生成AIが人間の知識に及んでない分野や領域、新たな知識を創造することはまだ人間に優位性があるかもしれませんが、これも時間の問題かもしれません。しかし、この知識を使って新たな価値を創造したり、意思決定を行ったりすることは人間にしかできない行為です。
2つ目は、世の中の課題の複雑化にあります。NTT東日本が光回線を日本中に届ける課題にチャレンジしていた時代に比べて、より複雑なニーズへの対応や目まぐるしく変わる社会情勢の変化への対応が必要になっています。そのため、経営者が経営課題だけ、エンジニアが技術課題だけ解決しているだけでは本当の意味での課題解決はできず、少しずつ変わる課題設定に対して迅速で柔軟かつ継続的に対応していく必要があります。
また、イノベーションは一人で起こすことはできません。より多くのBuilderが同じ共通の目標やコンテキストを持ちながら自由闊達に小さな課題解決を続けることで、より大きな課題を解決できるようになり初めてイノベーションが実現できるようになります。
AI時代のBuilderに求められる人物像とは?
では、AI時代のBuilderは、どのような人物が適しているでしょうか?ここからのパートは私個人の考えとなります。この1年間、私はAWS Ambassadorとして数多くのBuilderやデジタルトランスフォーメーション推進者の方とお話をさせていただきました。その中での共通点をいくつかご紹介します。
- コンフォートゾーンを”少しだけ”脱却することをいとわない
- 新しいもの、知らないことはまず触ってみる。結果の無駄や、知的な失敗を恐れない
- 課題解決はできるところから迅速かつ粘り強く取り組んでいる。今できないことも、いつかできると信じて取り組んでいる
- 自身の能力発揮や自己実現より、相手との信頼関係を築くことを優先する
- 時に思い通りにならないことがあっても、その中でも楽しさや面白さを見出して取り組んでいる
- 上記の積み重ねによる自分自身のアイデンティティや強みを確立している
ほかにも必要な要素はあると思いますが、総じて実現したいことと課題意識がはっきりしており、熱意をもって取り組まれていることが共通してあげられると考えています。
AI時代のBuilderを目指すために必要なこと
では、AI時代のBuilderを目指すには、どのように取り組んでいけばよいでしょうか?
AIに付加すべき人間のコンテキストは、その人個人が持つ経験だと考えています。現時点のAIは多数の経験を知識やデータベースに持っていますが、その過程で個人の経験やその時に感じた感情や感覚をそぎ落としてしまっていますので、こうした感情や感覚を制約条件として活用できるようにします。
こうした経験をさらに拡大していくにはどうしたらよいでしょうか?ITエンジニアと他の職種で異なるように見えますので、少し整理したいと思います。
ITエンジニアの場合
ITエンジニアの場合、ITの知識は十分に蓄えておりその知識をつかってAIの性能を充分に引き出すことができる状態にあると思います。その場合に必要な経験はIT以外の経験になると思います。ITの部分はAIを使って最大限の生産性を発揮し、それ以外のかかわりを増やしていくことが大切になると考えています。具体的には、このような行動が挙げられます。
具体的な行動例
- 自身の専門領域の深化(AIと対等に話せる領域を増やす)
- 自身の専門領域以外の生成AI活用(AIに支援してもらえば対応できる領域を理解する)
- 趣味でも構わないのでIT以外の領域とのかかわりを持ち、経験を広げる(感情や感覚といった現代のAIが持たない領域を強化する)
- 経験による感情や感覚を言語化し整理する
ITエンジニア以外の職種や学生の場合
ITエンジニア以外の職種や学生の場合はどうでしょうか?私は、実現したいことを形にし続けることだと考えています。幸い、AIによって専門知識、とくにソフトウェア開発の領域は最新の生成AIサービスとAWSを使うことである程度カバーできる状態にありますので、小さなものを実現していくことが必要であると考えています。具体的には、次のような行動が挙げられます。
具体的な行動例
- 実現したいことを見つけるために、さまざまな領域での経験を積む
- AIを使って実現したいことを形にする(いったん品質は度外視)
- 形にするのが難しい場合は、課題を細分化して最小限の要件に整理する
- 新たに生じた課題をAIまたは専門職に相談して知見を広げる
BuilderとBuilding Blocksについてのまとめ
今後多くの職種がAIに代替されるという予想もありますが、多彩な経験や知見をもとに、ビジネスモデルの変革やカルチャーイノベーションに向けた意思決定を行える人材は今後よりいっそう貴重な人材になっていくと考えています。今回示した人物像にとどまらず、多様な人物がBuilderとして活躍していくと思いますので、ぜひBuilding Blocksを活用しながら進めていければと思います。また経営やマネジメントを行う皆さまにおかれましては、ぜひこうしたBuilderが活躍できる組織作りを推進していただければと思います。

最後に
今回はAWS Summit Japanの基調講演及びスペシャルセッションの内容から、少しBuilderの人物像について整理を行ってみました。NTT東日本にもこうしたBuilderが多数所属しておりますので、是非お気軽にお問い合わせください!
RECOMMEND
その他のコラム
相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします
クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。