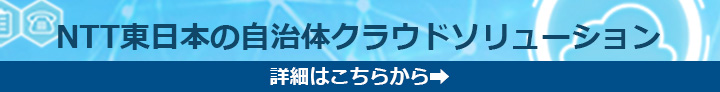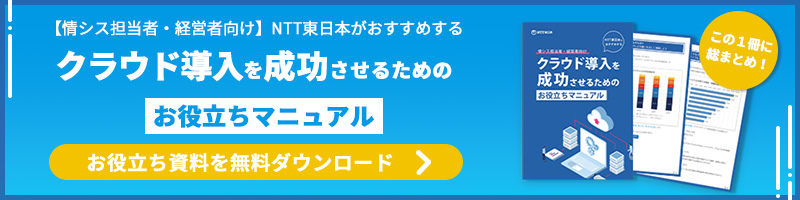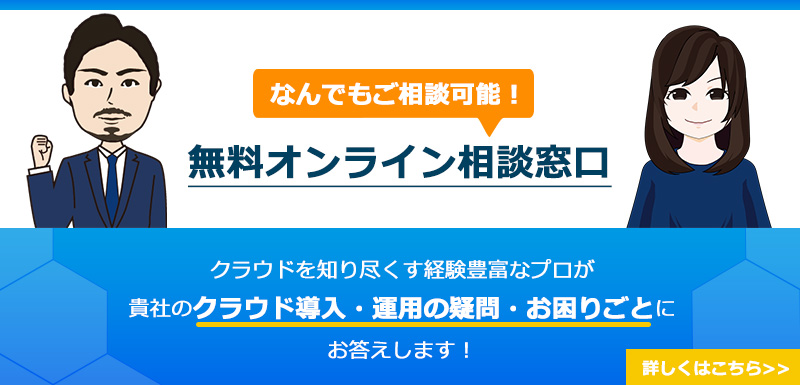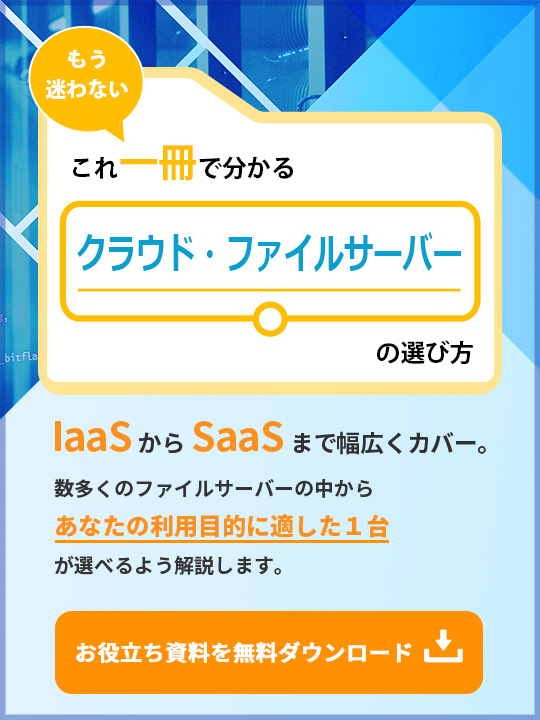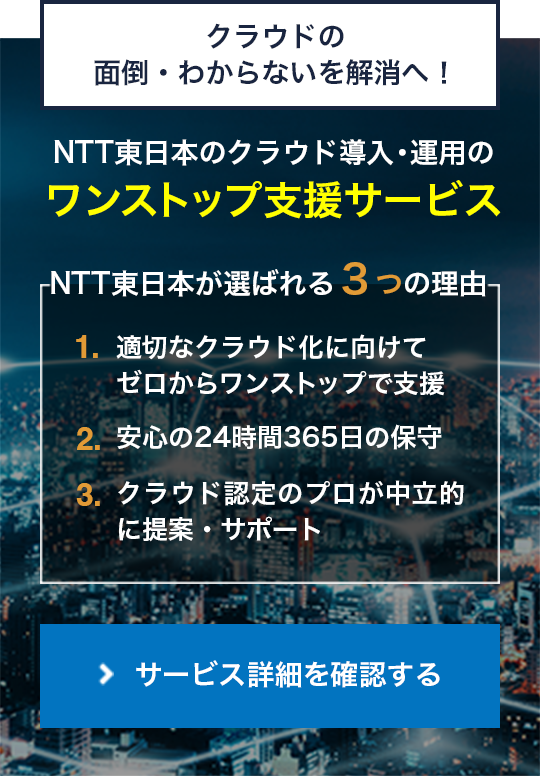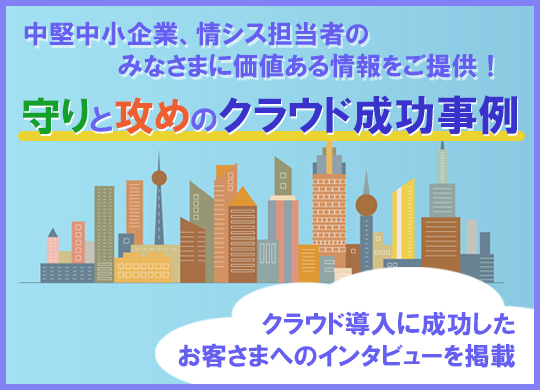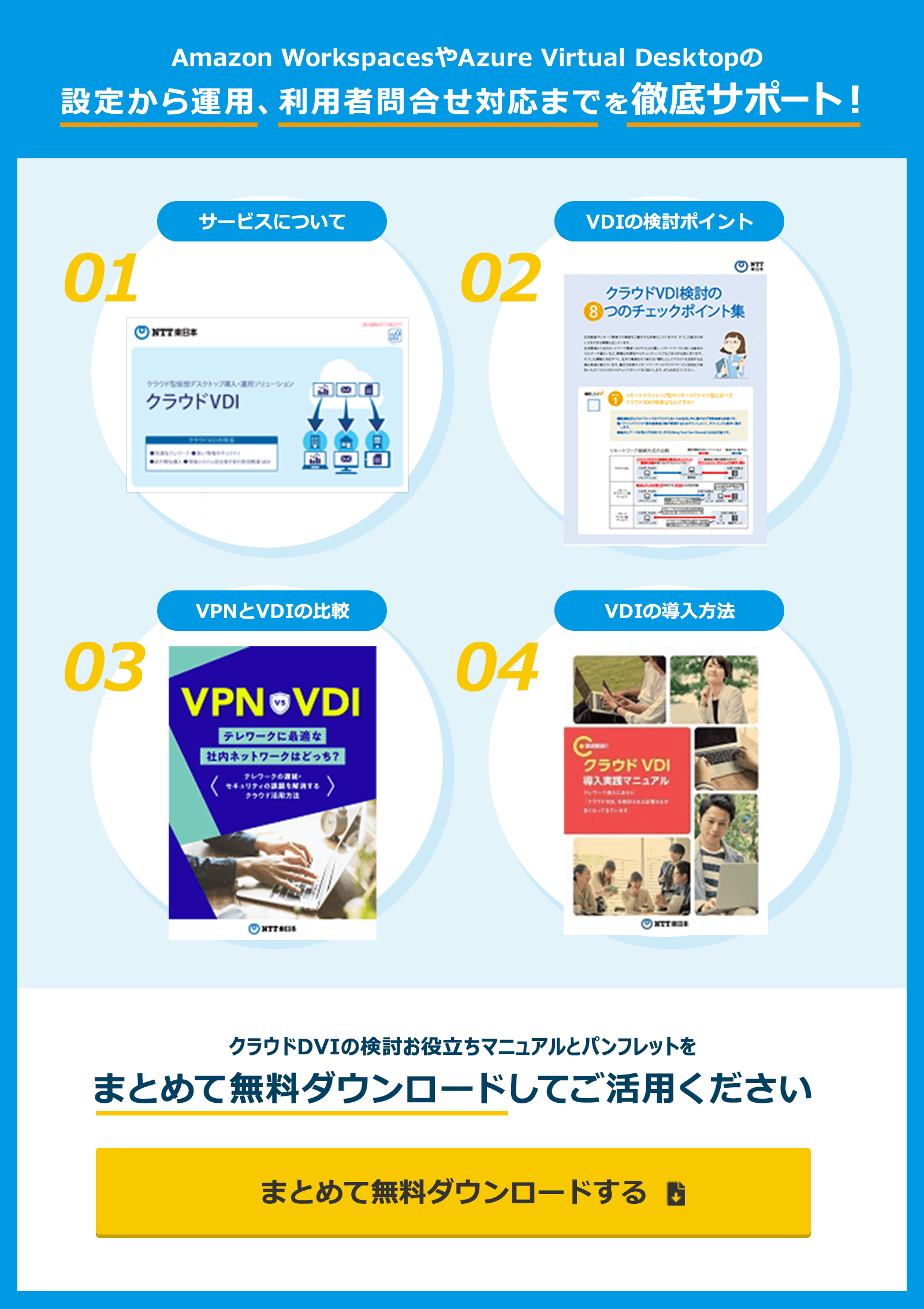生成AI活用を成功させる“伴走支援”とは

生成AIによる業務効率化の期待が高まる一方で、「ツールは導入したが現場では使われていない」「PoC(概念実証)で終わり、実運用に結びついていない」といった課題も顕在化しています。こうした課題に対し、今注目されているのが「伴走支援」というアプローチです。
本コラムでは、生成AI導入における典型的なつまずきや停滞の要因を整理し、伴走支援が求められている理由や支援内容などを解説します。
目次:
- 1. 生成AIの導入における課題
- 1-1. 導入しても活用が進まない
- 1-2. 現場の理解・リテラシー不足
- 2. 伴走支援が求められる理由
- 2-1. ユーザーのスキルに合わせた柔軟な対応が必要だから
- 2-2. 導入~定着(内製化支援)までの継続的なサポートが受けられるから
- 2-3. 専門人材のリソース不足を補えるから
- 3. 伴走支援の内容
- 3-1. 導入前の企画・設計
- 3-2. PoCの実施と評価
- 3-3. 導入後の定着促進
- 4. NTT東日本における生成AIの伴走支援
- 4-1. NTT東日本の「伴走支援」の特長と支援内容
- 4-2. 導入事例
- 5. 生成AIサービス選びにお悩みならNTT東日本の「生成AIサービス」
- 6. まとめ
1. 生成AIの導入における課題
多くの自治体や企業では、生成AIのポテンシャルに注目し導入を進めつつありますが、実際の現場では「導入後の活用が進まない」「現場で使われない」「成果が見えにくい」といった課題に直面しているケースが少なくありません。主な課題を整理します。
1-1. 導入しても活用が進まない
生成AIの導入に際し、多くの企業・自治体ではPoCや実験的導入を行っています。しかし、明確な方針を持たずに、「システムを導入しただけ」「PoCを実施しただけ」で満足してしまい、現場での実用化が進まないケースも見受けられます。背景には、目的の明確化が不十分なままツールを導入してしまったことや、利用者への説明・トレーニング不足などが挙げられます。また、評価指標(KPI)の設計が曖昧なまま進めてしまうと、効果検証が難しく、結果として「生成AIは効果がない」という誤った認識を生んでしまうことも少なくありません。
1-2. 現場の理解・リテラシー不足
生成AIに対する現場職員の理解度やデジタルリテラシーの水準も、活用の定着を阻む要因となっています。特に自治体では、情報セキュリティや職員の異動頻度などの事情から、新しい技術に慎重になる傾向が強く、「生成AIは難しそう」「使い方がわからない」という声が多く聞かれます。こうしたリテラシーのギャップを埋めるには、導入に先立つ研修や継続的なトレーニング、簡易的なマニュアルの整備が不可欠です。
2. 伴走支援が求められる理由
伴走支援とは、新しいテクノロジーやツール・サービスなどの導入を検討する段階から、実際の業務活用、そして現場への定着や自走までを一貫して支援する取り組みを指します。単なるシステムの導入や初期設定のサポートにとどまらず、導入後の継続的なフォローを通じて、現場での活用を着実に根付かせることを目的としています。
2-1. ユーザーのスキルに合わせた柔軟な対応が必要だから
従来の支援では、操作説明やマニュアル提供といった初期対応が中心でした。しかし生成AIのような先進技術の場合、「どう使うか」だけでなく、「どの業務に適用すべきか」「どうすれば効果が出るか」といった検討が欠かせません。こうした判断には、現場の業務理解やユーザーのスキルレベルを踏まえた柔軟な対応が必要になります。また、技術だけでなく組織文化や現場の課題にも目を向け、ユーザーと対話を重ねながら支援内容を設計・実施することで、表面的な導入で終わることなく、実効性のある活用へとつなげやすくなります。
2-2. 導入~定着(内製化支援)までの継続的なサポートが受けられるから
生成AIは導入後、実際の業務にどう組み込み、どう定着させるかが成果を左右します。そのためには、初期段階の導入支援だけでなく、運用フェーズに入ってからの支援が欠かせません。伴走支援であれば、導入から定着までの流れを一貫してサポートできるため、現場の自走力や活用意識を高めることにつながります。
2-3. 専門人材のリソース不足を補えるから
多くの自治体・企業では、生成AIの導入や活用を担う専門人材が限られており、「対応できる担当者がいない」「知識が追いつかない」といった課題に直面しています。新しい技術を導入しても、運用や定着が進まないケースでは、外部の伴走支援によって技術的・実務的な不足を補うことが有効です。例えば、ユースケースの整理やプロンプトの設計支援などを通じて、専門的な知見を現場に伝えることができ、限られた体制でも生成AIの活用が可能になります。
3. 伴走支援の内容
伴走支援は、技術導入支援だけでなく、生成AIを組織に根付かせるための包括的なプロセスを支えるものです。支援は一度きりではなく、導入前から導入後まで、段階ごとに課題と目的に応じた内容で提供されます。
3-1. 導入前の企画・設計
最初のステップでは、組織内の課題や業務プロセスを丁寧にヒアリングし、生成AIの導入目的を明確にします。どのような生成AIツールがどの業務に適しているか、また、どのような期待効果があるかを具体化し、実現可能な計画を立てます。生成AIには多様な機能・提供形態があるため、セキュリティ要件や操作性、コストなどを考慮しながら、自組織に適したサービスを選ぶ必要があります。伴走支援では、こうした企画段階の検討を外部の視点から効果的にサポートすることが可能です。
3-2. PoCの実施と評価
次の段階では、PoC(概念実証)によって、実際の業務への適用可能性を検証します。このフェーズでは、対象業務を絞り込み、生成AIが有効に機能するかどうかを小規模に試すことで、想定とのギャップや新たな課題を洗い出すことができます。また、導入に伴うリスクの評価も欠かせません。PoCの段階でこれらを把握し、対応策を検討することで、本格導入時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
3-3. 導入後の定着促進
生成AIの本格導入後に重要となるのが、活用の定着です。導入しただけでは利用が進まないケースも多く、継続的な教育やルール整備が不可欠です。具体的には、職員向けの操作マニュアルや生成AIガイドラインの策定、活用スキルを高めるためのトレーニングの実施などが挙げられます。特に、生成AIはプロンプトの工夫次第で出力結果が大きく変わるため、実践的な研修が効果的です。また、導入後の利用状況を把握し、フィードバックをもとに内容を見直す運用サイクルを確立することで、継続的な改善と活用拡大を促進できます。
4. NTT東日本における生成AIの伴走支援
NTT東日本では、自社の生成AI活用で培ったノウハウと現場視点に基づき、自治体・企業の生成AI導入を支援する「伴走型」のサービスを提供しています。単なるツール提供にとどまらず、導入前の準備から、定着・内製化までを段階的にサポートする点が特長です。主な伴走支援の内容を紹介します。
4-1. NTT東日本の「伴走支援」の特長と支援内容
NTT東日本の伴走支援は、「生成AIを導入して終わり」ではなく、「どう活用し、どう現場に根付かせるか」を見据えた支援設計がなされています。
4-1-1. 生成AI概論研修
生成AIに対する理解を深めるための基礎研修です。「生成AIの概要」「活用するためのステップ」「リスクと対策」といった基礎知識を座学形式で学びます。生成AIに初めて触れる自治体・企業の職員に向けた内容で、社内啓発やリテラシーの底上げに効果的です。
4-1-2. 生成AIガイドライン策定支援
生成AI活用にあたっては、情報の取り扱いや情報セキュリティ、業務範囲などを整理したガイドラインの整備が不可欠です。本支援では、他自治体の事例や社内ノウハウを踏まえたうえで、個別組織に適したルール設計を支援します。既存ガイドラインの見直しや、記載例の修正助言提案も含まれます。
4-1-3. プロンプトハンズオン研修
生成AIを効果的に活用するには、プロンプトの設計スキルが重要です。この研修では、プロンプトエンジニアリングのテクニックについて、実際に手を動かしながら学びます。実務を想定した演習を通じて、応用力を高めることができます。
4-1-4. ユースケース創出ワークショップ
自治体や企業における具体的な業務課題をもとに、生成AIの適用可能なユースケースを検討するワークショップです。グループワーク形式で課題を抽出し、活用アイデアを出し合いながら、PoCや本導入に向けた足がかりをつくります。
4-1-5. 伴走型技術支援
想定のユースケースや、ワークショップで顕在化したユースケースに対し、生成AIの業務適用を技術的に支援します。お客さまの環境で作成したコンシェルジュに対し、ドキュメント作成のアドバイスやRAGのパラメータ設定の見直しなどを繰り返し行い、精度向上を図ります。
4-2. 導入事例
NTT東日本の生成AI伴走支援は、すでに複数の自治体や企業で導入され、成果を上げつつあります。ここでは、自治体での導入事例として、藤沢市、横浜市の取り組みをご紹介します。
4-2-1. 「藤沢DX」への活用 - 藤沢市役所 さま
藤沢市役所さまは、人口減少と職員数の減少が見込まれる中、市民への行政サービスを維持・向上させるために「藤沢DX」を推進。職員の業務効率化や、質の高いサービス提供を目的として、RAGを活用したNTT東日本の自治体向け生成AIソリューションを導入しました。
RAGとは?仕組みと導入メリット、使用の注意点をわかりやすく解説
| 【自治体向け 生成AIソリューション導入運用支援 利用前の課題】 |
|---|
|
| 【自治体向け 生成AIソリューション導入運用支援 利用後の効果】 |
|---|
|
導入事例の詳細はこちらをご覧ください
来る職員減少に備え、RAG構築による課題解決を検証。「藤沢DX」における生成AIソリューションのユースケースに迫る
4-2-2. 事務事業やデータ活用業務に「RAG」を活用 – 横浜市さま
横浜市さまでは、2022年から「横浜DX戦略」を推進しており、事務手続きをDX化することで、市民サービスの向上と職員の負担軽減を実現しました。2023年12月からは、さらなる効率化を求めて生成AIの全庁導入などの取り組みを進めてきました。そして、より実用性の高い環境での活用をめざし、2024年11月から「RAG」の実証を実施。生成AIの導入効果を高めるため、導入準備や業務プロセスの改善といった伴走支援を行いました。
RAGとは?仕組みと導入メリット、使用の注意点をわかりやすく解説
| 【RAGに期待する効果】 |
|---|
|
| 【RAG実証によって得られた効果】 |
|---|
|
導入事例の詳細はこちらをご覧ください
5. 生成AIサービス選びにお悩みならNTT東日本の「生成AIサービス」
SaaS型で提供するNTT東日本の「生成AIサービス」では、社内の営業データを活用できるチャット型のAIアシスタントとして日々の業務を強力に支援します。外部のデータベースから情報を検索し、信頼性の高い回答を出力する「RAG」の構築も可能です。また、プロンプトのテンプレート化や、利用状況を可視化できるレポート機能なども提供しています。その他にも、生成AIを効率的に利用するためのサポートや知識・技術習得のための研修などをオプションにて実施できます。適切な生成AI環境のカスタマイズをトータルで伴走支援いたしますので、生成AIサービス選びやAIアシスタントの導入などをご検討中の方は、NTT東日本にご相談ください。
6. まとめ
生成AIを導入し、現場に定着させて活用するためには、導入前の企画段階から導入後のサポートまで一貫して伴走支援するパートナーの存在が大きな役割を果たします。伴走支援を活用することで、技術的な導入支援だけでなく、組織の理解促進や人材育成といった本質的な課題にも対応することが可能になります。生成AIの導入をお考えの方は、ぜひNTT東日本にお任せください!
RECOMMEND
その他のコラム
無料ダウンロード
自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを
この1冊に総まとめ!
あなたはクラウド化の
何の情報を知りたいですか?
- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?
- 【AWS・Azure・Google Cloud】
どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?
- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?
初めての自社クラウド導入、
わからないことが多く困ってしまいますよね。
NTT東日本では
そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を
1冊の冊子にまとめました!
クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・
- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。
- 情シス担当者の負担が減らない。。
- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。
理想的なクラウド環境を実現するためにも、
最低限の4つのポイントを
抑えておきたいところです。
-
そもそも”クラウド化”とは?
その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって
最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための
具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を
実現するためのロードマップ
など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。
またNTT東日本でクラウド化を実現し
問題を解決した事例や、
導入サポートサービスも掲載しているので、
ぜひダウンロードして読んでみてください。
面倒でお困りのあなたへ
クラウドのご相談できます!
無料オンライン相談窓口
NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から
ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで
”ワンストップ支援”が可能です!
NTT東日本が選ばれる5つの理由
- クラウド導入を
0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を
中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、
第3者目線でチェック
してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守
- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで
”課題解決”と”コスト軽減”を両立
特に以下に当てはまる方はお気軽に
ご相談ください。
- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない
- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている
- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい
- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない
- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい
- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている
クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、
クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。
相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします
クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。