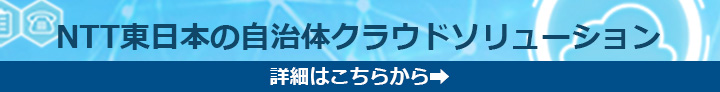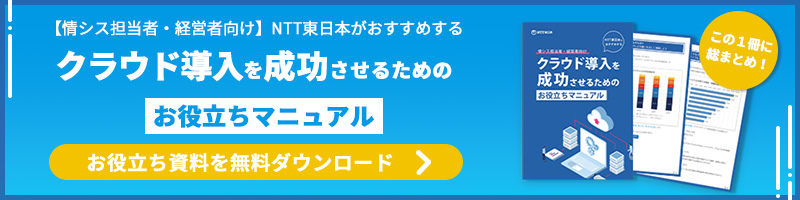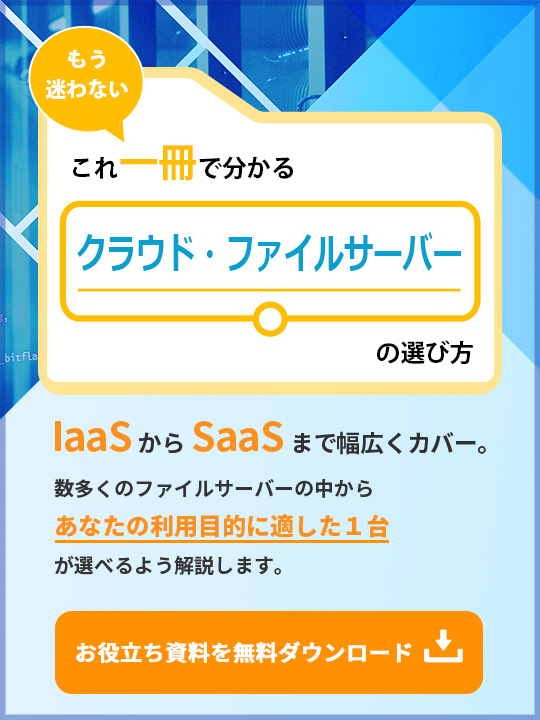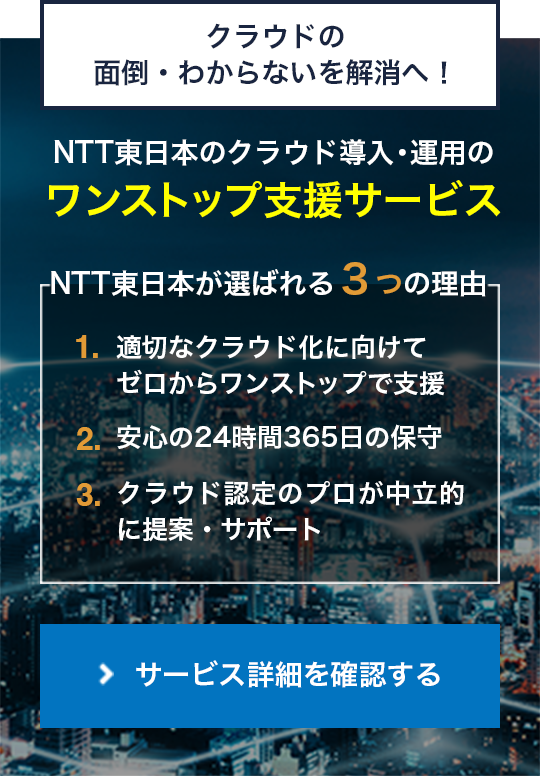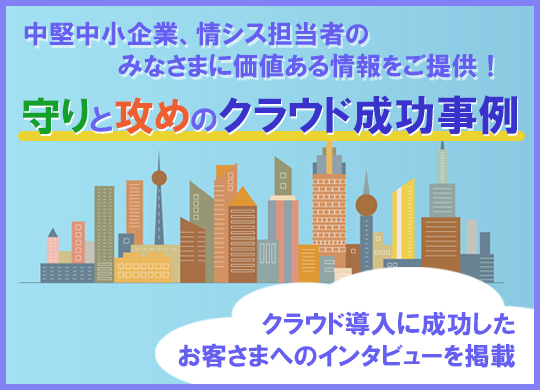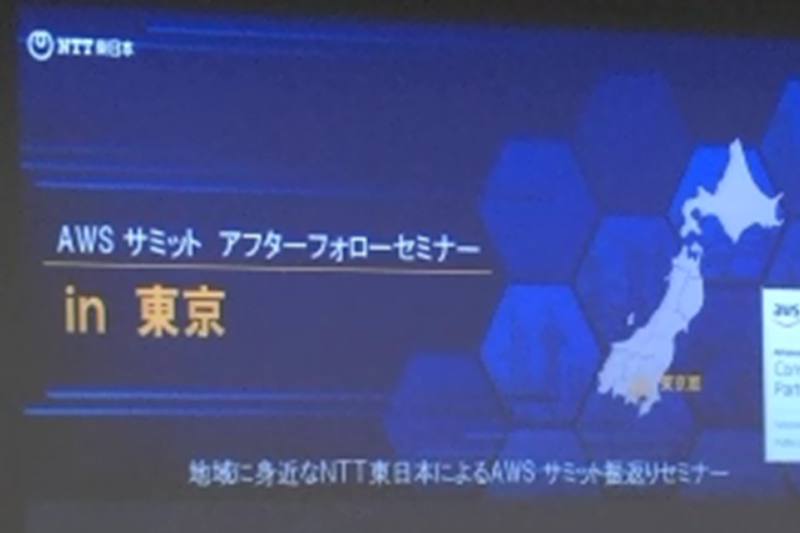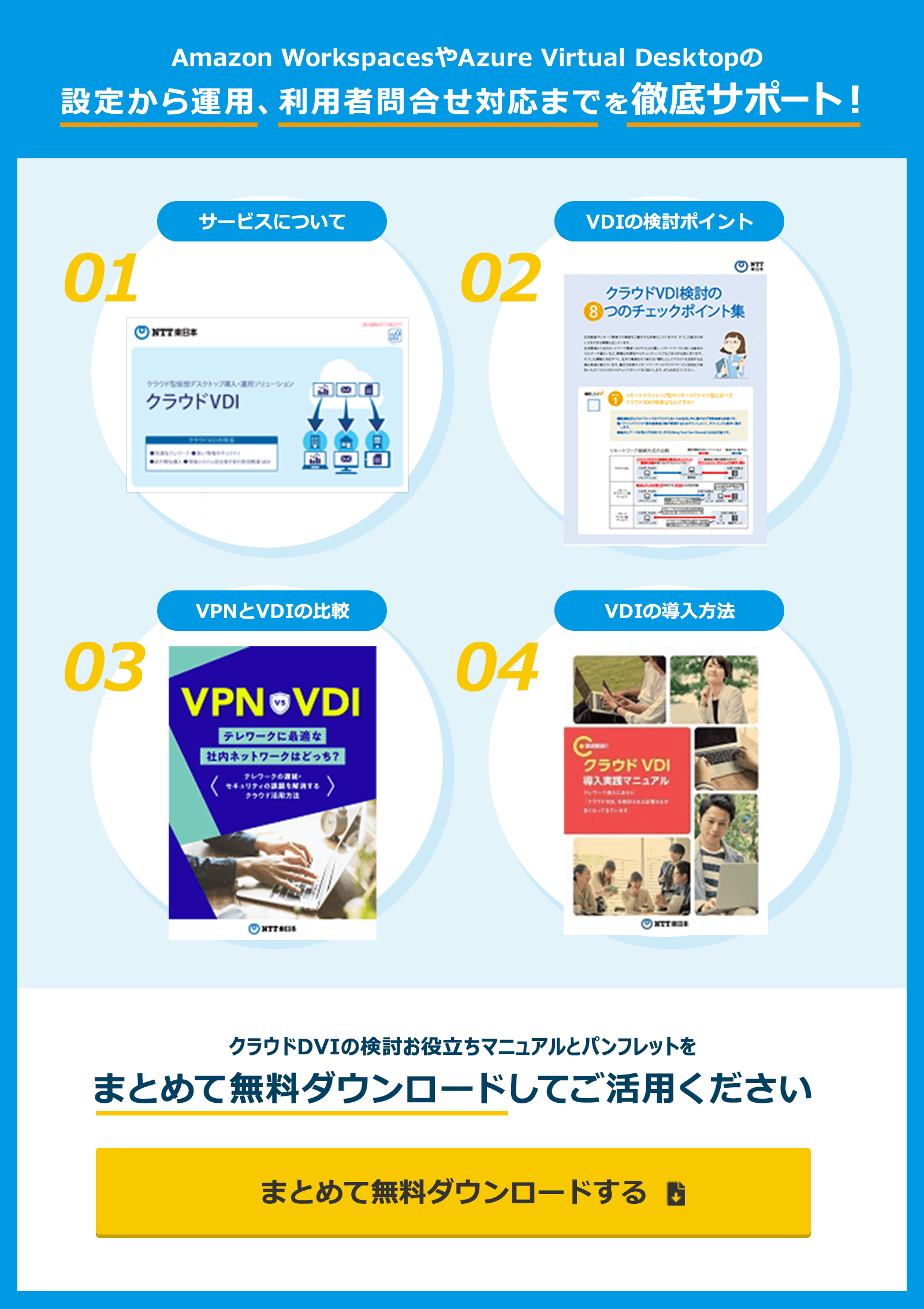AWSの料金を見積もるためにAWSの料金体系を理解しよう

クラウドの運用費用など、クラウドの利用に課題がある方は、NTT東日本へお気軽にお問い合わせください。
AWSの料金体系の基本は、「使ったら使った分だけ支払う」です。つまり、使ってみないと正確な請求金額はわかりません。しかし、それではいくら請求が来るかわからないので、社内稟議が通せないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは、AWS利用前でもAWS利用料の概算見積もりを把握するための基礎的な知識について解説します。
AWSの料金体系
AWSと一口にいっても、仮想サーバーを構築できるAmazon Elastic Compute Cloud (EC2)や、オブジェクトストレージのAmazon Simple Storage Service(Amazon S3)など、120以上のサービスがあり、それぞれ料金は異なります。実際にそのすべての料金体系をすべて覚えておくことは困難を極めます。まずは、AWSの基本的な料金体系について理解を深めるために、AWSの課金要素を押さえておきましょう。
なお、本記事に記載の料金や料金体系は、執筆時点(2019年9月現在)でAWSのホームページに掲載されている情報をもとにしています。実際の金額積算に当たっては、料金単価などを含めご自身で確認・算出をお願いいたします。
AWSの課金要素には、サーバー、ストレージ、データ転送の3つがあります。
- サーバー
- AWS上で構築する仮想サーバーについて、リソースの起動から停止するまでの実稼働時間に応じて、時間単位で必要となる料金体系です。選択するサーバーのOS、コア数、およびメモリ容量に応じて、時間単価は異なるものの、1時間あたり約2円です。休日や夜間など、サービスを止める場合は金額を安く抑えることができるため、必要なサービスレベルに応じた稼働時間を設定するとよいでしょう。
- ストレージ
- 必要となるストレージ容量に応じて、1GB単位で課金されます。ストレージは、EC2用のローカルハードディスクとして使う場合や、オンラインストレージとして使う場合など、選択するサービスにより単価は異なります。おおよその目安として、1ヶ月間の1GBの契約で約10円となっています。
- データ転送
- AWSを利用するために発生するデータ転送にかかる料金です。AWS内の同じデータセンター内のデータ転送や、AWSに向かうデータ転送は無料ですが、AWSからインターネットへのデータ転送は有料です。データ転送にかける料金の概算は、1GBあたり約20円となっています。データ転送にかかる料金をあらかじめ把握するためには、AWSからどの程度のデータをダウンロードするのかという見積値が必要になります。
AWSの料金を見積もる際のポイント
AWSの料金を見積もる際には、いくつかの注意点があります。より精度の高い金額を把握するために、サーバー、ストレージ、データ転送それぞれについて、以下のポイントについて押さえておきましょう。
サーバー
AWSで仮想サーバーを構築する場合、EC2を使うことがよくあります。EC2には、以下のような4種類の契約方法が準備されています。サーバーの用途にもよりますが、一般的にはサーバーの利用料がAWS利用料の大半を占めるケースが多いでしょう。金額を抑えたい場合は、4つの契約方法についての理解を深め、最適な契約方法を選択するようにしてください。
- オンデマンドインスタンス:EC2上で構築した仮想サーバーの数に応じて料金が発生する、最も基本的な料金体系です。サーバーを使った後に、稼働時間に応じて請求されます。
- リザーブドインスタンス:あらかじめ1年分または3年分を支払うことで、割引を受けることができる料金体系です。仮想サーバーを使うことが確実な場合に有効な契約方法で、全額前払い、一部前払い、または前払いなしを選択することができます。
- スポットインスタンス:オークション形式で入札し、低価格で利用することができる料金体系です。しかし、他のユーザーが高値で応札した場合は使用が停止されてしまいます。一時的に、安価で仮想サーバーを使いたい場合に検討したい料金体系です。
- Dedicated Hosts:物理的なサーバーを占有したいユーザー向けの料金体系で、他の契約方法より料金設定は高くなっています。セキュリティやパフォーマンスの点からサーバーを専有したい場合は、価格も考慮に入れながら検討するとよいでしょう。
なお、EC2の場合は、上記の契約方法以外にも、負荷分散や詳細モニタリング、グローバルIPアドレスの数によって追加料金が発生することがあるので注意してください。EC2はサーバーを起動している時間に応じて課金されるため、夜間などシステムを使わない場合は、サーバーを停止しておくことで、費用を削減することができます。
ストレージ
AWS上のストレージサービスには、主に以下の3つがあります。利用するサービスにより料金体系が異なるので注意してください。
- Amazon EBS:Amazon EC2⽤ のHDDのことです。確保したストレージ容量に応じて課金されるので最低限必要な量を確保すればよいでしょう。
- Amazon S3:AWS上のオブジェクトストレージサービスです。実際に利用しているストレージ容量に応じて課金されます。
- Amazon Glacier:アーカイブ専⽤のストレージサービスです。実際に利用しているストレージ容量に加え、アーカイブデータを取り出す際に課金されます。最も安価なストレージサービスですが、データの取り出しに時間がかかるほか、一度に大量のデータを取り出すと費用がかかるので注意しましょう。
データ転送
固定料金ではなく、実際に流れたデータ量に応じて課金されます。インターネットから入ってくるデータは無料ですが、インターネットへのデータ転送や、データセンター間のデータ転送に対して課金されます。データ転送に応じた課金には、ボリュームディスカウントが自動的に適用され、転送量が10TBを超えると、随時割引が適用されます。
クラウドの運用費用など、クラウドの利用に課題がある方は、NTT東日本へお気軽にお問い合わせください。
AWSの「簡易見積もりツール」の概要
Amazonでは、「簡易見積もりツール」という、AWS料金の見積もりができるツールが提供されています。簡易見積もりツールのマニュアルも準備されているため、確認しながら必要項目を入力すれば、簡単に見積もり金額を入手することができます。
簡易見積もりツールの主な操作手順は、以下の通りです。
- AWSを稼働させるリージョンを選択する。
- 右側のメニューから、見積もりを取得したいAWSのサービスを選択する。
- 選択したサービスごとに必要な項目やオプションなどを入力する。
簡易見積もりツールを使う前に、クラウド構成例が不明という場合もあるかもしれません。AWSのホームページ![]() では、基本的な構成例とその推奨構成が紹介されています。このページを参考にして簡易見積もりツールで見積もり取得を行えば、検討しているサーバー構成と必要な金額を簡単に見積もることができるでしょう。
では、基本的な構成例とその推奨構成が紹介されています。このページを参考にして簡易見積もりツールで見積もり取得を行えば、検討しているサーバー構成と必要な金額を簡単に見積もることができるでしょう。
意外と簡単なAWSの金額算出方法
AWSの料金体系は複雑でわかりにくいと考えていませんか。たしかにAWSはサービス内容が多く、それぞれに異なる料金が設定されており、すべて覚えることは簡単なことではありません。しかし、AWSの基本的な料金体系は決して難しいものではなく、基本を押さえるだけで概算費用を算出することができるのです。
さらに、AWSには簡易見積もりツールが整備されており、マニュアルが整備されているうえに、入力項目も少ないので、AWSのサービスを複数使うような複雑な構成の場合でも、見積もりは簡単に取得できます。
AWSの利用を検討されている方は、まずは概算金額を把握するために、簡易見積もりツールを利用してみてはいかがでしょうか。
オンプレミスとクラウドの相違点を理解し、クラウド移行の経済性(TCO)を評価しよう
RECOMMEND
その他のコラム
無料ダウンロード
自社のクラウド導入に必要な知識、ポイントを
この1冊に総まとめ!
あなたはクラウド化の
何の情報を知りたいですか?
- そもそも自社は本当にクラウド化すべき?オンプレとクラウドの違いは?
- 【AWS・Azure・Google Cloud】
どれが自社に最もマッチするの? - 情シス担当者の負荷を減らしてコストを軽減するクラウド化のポイントは?
- 自社のクラウド導入を実現するまでの具体的な流れ・検討する順番は?
初めての自社クラウド導入、
わからないことが多く困ってしまいますよね。
NTT東日本では
そんなあなたにクラウド導入に必要な情報を
1冊の冊子にまとめました!
クラウド化のポイントを知らずに導入を進めると、以下のような事になってしまうことも・・・
- システムインフラの維持にかかるトータルコストがあまり変わらない。。
- 情シス担当者の負担が減らない。。
- セキュリティ性・速度など、クラウド期待する効果を十分に享受できない。。
理想的なクラウド環境を実現するためにも、
最低限の4つのポイントを
抑えておきたいところです。
-
そもそも”クラウド化”とは?
その本質的なメリット・デメリット - 自社にとって
最適なクラウド環境構築のポイント - コストを抑えるための
具体的なコツ - 既存環境からスムーズにクラウド化を
実現するためのロードマップ
など、この1冊だけで自社のクラウド化のポイントが簡単に理解できます。
またNTT東日本でクラウド化を実現し
問題を解決した事例や、
導入サポートサービスも掲載しているので、
ぜひダウンロードして読んでみてください。
面倒でお困りのあなたへ
クラウドのご相談できます!
無料オンライン相談窓口
NTT東日本なら貴社のクラウド導入設計から
ネットワーク環境構築・セキュリティ・運用まで
”ワンストップ支援”が可能です!
NTT東日本が選ばれる5つの理由
- クラウド導入を
0からワンストップでサポート可能! - 全体最適におけるコスト効率・業務効率の改善を
中立的にご提案 - クラウド環境に問題がないか、
第3者目線でチェック
してもらいたい - 安心の24時間・365日の対応・保守
- NTT東日本が保有する豊富なサービスの組み合わせで
”課題解決”と”コスト軽減”を両立
特に以下に当てはまる方はお気軽に
ご相談ください。
- さまざまな種類やクラウド提供事業者があってどれが自社に適切かわからない
- オンプレミスのままがよいのか、クラウド移行すべきなのか、迷っている
- オンプレミスとクラウド移行した際のコスト比較を行いたい
- AWSとAzure、どちらのクラウドが自社に適切かわからない
- クラウド環境に問題がないか、第3者目線でチェックしてもらいたい
- クラウド利用中、ネットワークの速度が遅くて業務に支障がでている
クラウドを熟知するプロが、クラウド導入におけるお客さまのLAN 環境や接続ネットワーク、
クラウドサービスまでトータルにお客さまのお悩みや課題の解決をサポートします。
相談無料!プロが中立的にアドバイスいたします
クラウド・AWS・Azureでお困りの方はお気軽にご相談ください。