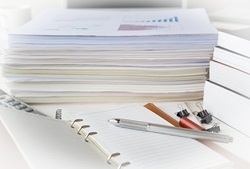【2023年開始】適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?企業や個人事業主の対応ポイントをわかりやすく解説

「インボイス制度とは何なのか」「インボイス制度の導入で何が変わるのか」と悩んでいる方がいるのではないでしょうか。インボイス制度(適格請求書等保存方式)によって、2023年10月から仕入税額控除を受けるには「適格請求書」が必要となります。大企業から個人事業主まで広範囲に影響する制度改正です。
そこで今回の記事では、インボイス制度の概要について解説します。既存制度からの変更点や導入に向けて何が必要かを理解できる内容となっているので、ぜひ最後までお読みください。
適格請求書等保存方式(適格請求書等保存方式)とは?

インボイス制度は、消費税率が10%と8%(軽減税率)の2種類になったことを受けて導入されたもので、税率をきちんと区分して収めるための制度です。この記事では、以下の項目について解説していきます。
- ・インボイス制度
- ・適格請求書(インボイス)
- ・仕入税額控除
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
インボイス制度とは、仕入額の消費税控除を受けるための新しい制度で、2023年(令和5年)10月1日から開始の予定です。正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。
2019年(令和元年)10月の消費税引き上げでは、税率10%の導入の一方で、食料品などに軽減税率として8%の税率が残されました。インボイス制度は、この2つの税率に対応するためにつくられました。大企業から個人事業主まで、あらゆる事業主に関係する制度です。
インボイス制度は、2つの税率が混在するなか、事業者が売上で納める納税額から仕入の納税額を控除するためのしくみです。仕入の取引先から仕入の消費税額を明記した請求書を受け取って申告すれば、消費税の二重払いにならずにすみます。この請求書が「適格請求書」(インボイス)です。
なお、適格請求書を発行する売手は、あらかじめ認定を受けた「登録事業者」でなければなりません。
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)は以下のように定義されています。
|
“「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。” |
現行の区分記載請求書等保存方式で使用されている「区分記載請求書」に、二重税率に対応した項目を追記したものが「適格請求書」です。
追記する項目は、「登録番号」や「税率ごとの取引額や税額」です。適格請求書は以下のような内容で、下線部が従来と異なる項目です。
|
仕入税額控除
仕入税額控除とは、「仕入にかかった消費税(仕入税額)を差し引いて、納税額を計算すること」です。事業者の納税額は、消費税納付の際に控除できます。
取引で納める消費税の内容を具体的に計算してみましょう。仕入額は「本体+消費税」です。たとえば、100万円の品を仕入れると消費税10%で110万円を仕入先に支払います。これを本体価格200万円で販売した場合、売上は「200万+200万×10%」で220万円になります。
しかし、この20万円を税務署に納税すると、仕入の際に払った10万円が消費税の二重払いになります。この部分を差し引くのが仕入税控除です。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)を導入する2つの目的

インボイス制度は、なぜ導入されることになったのでしょうか。目的は大きく以下の2点です。
- ・免税事業者の益税を防ぐため
- ・複数税率に対応するため
益税を防ぐため
現行の制度では、特に中小以下の事業者を対象とする簡易課税や免税の特例から以下のようなことが起こっています。
|
これらでは、消費者が支払った消費税の一部が納税されず、事業者の手元に残ります。とはいえ、合法的に残ったもので、「益税」と呼ばれます。
インボイス制度には、インボイスの導入によって税額を細部まで明確にして、益税をなくすという目的があります。税務署側から言えば、取りこぼしをなくすわけです。
そのため、これまで免税や減免の恩恵を受けてきた中小以下の事業者にとっては、税負担が増す制度でもあります。
複数税率への対応
インボイス制度は、複数の税率に対応することを目的としています。2019年10月1日の消費税率10%導入の際、食料品などに対する8%の軽減税率が開始されました。
こうしたなかで適切な納税額を算出するには、2つの税率のうち、どちらの税率が適用されているのか把握する必要があります。どの商品や取引に、どの税率が適用されるかを詳細にして申告することで、二重税率の問題を解消するのがインボイス制度の狙いです。
適格請求書等保存方式の導入による既存制度からの変更点4つ

インボイス制度は2023年10月1日に開始されますが、具体的には、どのような点が変更になるのでしょうか。内容について詳しく説明します。
適格請求書では記載事項が追加される
適格請求書では、現行制度で使用されている「区分記載請求書」の項目に加え、以下の項目の記載が必要になります。
- ・登録番号(Tプラス13桁の数字か法人番号)
- ・適用される税率
- ・税率によって区分された消費税額等(税率ごとの端数処理は1回ずつ)
これらの項目によって、適用税率などを正確に把握できるようになります。
適格請求書を発行できるのは登録した課税事業者のみ
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録された課税事業者のみです。適格請求書発行の事業者になるには、事前に税務署へ事前登録を申請しておく必要があります。税務署申請から登録までの流れは以下のとおりです。
|
登録事業者は「適格請求書」の発行義務がある
登録事業者には、取引先から求められた際、適格請求書を発行する義務があります。インボイス導入前よりも記載項目が増えるため、経理の事務負担は増えます。
こうした負担を減らすために作られたのが「適格簡易請求書」です。適格請求書の交付が難しい業種などで、適格請求書の交付義務が免除されます。
そして、代わりに「適格簡易請求書」として、レシートの交付が認められます。簡易請求書は以下の内容を省略できます。
|
対象の業種は、飲食店業や旅行業などです。内容を省略できるだけでなく、決められた書式もありません。また、電子データでの発行が可能なため、該当する方は作成しやすい方法で発行すると良いでしょう。
仕入税額控除の要件
インボイス制度で仕入税額控除を受けるには「適格請求書」または「適格簡易請求書」、またそのほかの関連書類が必要になります。
現在、税込3万円未満の課税仕入れについては帳簿への記載のみで仕入税額控除できる制度がありますが、これは廃止されます。適格請求書などの書類なしでは仕入税額控除はできなくなります。
必要な請求書や書類の範囲は以下のとおりです。
|
一方、インボイス制度の開始から一定期間は、免税事業者からの課税仕入れであっても控除できる経過措置が設けられます。
仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなすもので、適用される割合と期間は以下のとおりです。
|
【事業者】適格請求書等保存方式(インボイス制度)で受ける影響

インボイス制度の開始で、課税事業者や免税事業者にはどのような影響が予想されるでしょうか。ここでは、それぞれの視点に沿った影響を解説します。
課税事業者が受ける影響
課税事業者は、インボイス制度開始にあたって、以下のような影響を受けると考えられます。
- ・適格請求書発行事業者に関する登録が必要
- ・経理処理が複雑化する可能性がある
- ・消費税の納税額が増加する可能性がある
以下で、それぞれについて詳しく説明します。
適格請求書発行事業者の登録が必要
インボイス制度開始で、ほとんどの企業は適格請求書の発行に対応しなければなりません。年間課税売上が1,000万円以下の零細事業者、法人成り後の2年間の免税期間が過ぎていない事業者は納税免除されますが、一般的な企業は発行が必要です。
また、適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者の登録が必要です。適格請求書を発行できるのは登録事業者だけとなっているためです。登録は「適格請求書発行事業者に関する登録申請書」を税務署に提出して申請します。
受付は既に開始しています。2023年10月に間に合わせるには、半年前の2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。早めの申請をおすすめします。
経理処理が複雑化する可能性がある
課税事業者は、適格請求書に記載された消費税額から納付額を正確に計算しなければなりません。どのような品物・サービスの消費税を、どの税率で納めるのかをそれぞれ計算するためです。
免税事業者と課税事業者の双方から仕入れを行うケースでは、両者の消費税額を別々に計算しなければなりません。そのため、経理処理の負担が増す傾向にあります。
消費税の納税額が増加する可能性がある
取引先が免税事業者の場合、適格請求書は発行できません。そのため、免税事業者からの仕入商品にかかった消費税は控除できません。
免税事業者と取引するたびに、消費税の納付税額が必要以上に加算される可能性があるため注意が必要です。
免税事業者が受ける影響
免税事業者は、これまでは「益税」として消費税の納税が免除されてきましたが、インボイス制度導入で益税は大幅に縮小します。さらに、従来の取引先との契約継続が難しくなることも考えられます。
取引先と取引継続が困難になる
免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先にとっては消費税納税額が必要以上に高くなります。そのため、免税事業者とは取引したくないと考える可能性もあるでしょう。また、免税事業者の取引が打ち切られる、もしくは、取引先がほかの事業者に乗り換えるということが起こるかもしれません。
公正取引委員会は、このような事態を想定しており、必要に応じて交渉を行うようすすめています。一方的な取引打ち切りは、独占禁止法および下請法に抵触する可能性があります。公取委の相談窓口が設けられているので、相談してみるのも良いでしょう。
消費税の納付義務が発生する
取引先が減らないようにするため、年間売上高1,000万円以下の零細事業者でも課税事業者になるという選択肢があります。その場合、消費税納付義務が発生しますし、適格請求書発行事業者の登録や経理事務の対応など、さまざまな負担がかかることになります。慎重に検討しましょう。
課税事業者が適格請求書等保存方式に対応するために必要な準備

年間売上1,000万円超の課税事業者はインボイス制度開始にあたって、以下のような準備が必要です。
- ・取引先が的確請求書発行事業者登録をしているか確認する
- ・インボイスに対応した会計システムやレジを導入する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく説明します。
取引先が適格請求書発行事業者登録をしているか確認する
取引先が免税事業者の場合、消費税の仕入税額控除は受けられません。このため、まず取引先が適格請求書発行事業者の登録を行っているのか、もしくは登録を行う予定があるのか確認する必要があります。
インボイスに対応した会計システムやレジを導入する
インボイス制度に対応するため、適用税率や税額などの事項を記載できる経理(受発注・請求書管理など)システムを導入する必要があります。また、店舗のある業種では、必要事項が過不足なく記載されたレシートや領収書を発行できるレジ導入を検討することも必要です。
免税事業者が適格請求書等保存方式に対応するために必要な準備

現在、免税事業者となっている事業者は、インボイス制度に向けて現状のままでいるか、適格請求書発行事業者になるかの選択をする必要があります。ここでは、それぞれの選択肢について詳しく説明します。
適格請求書発行事業者になる
課税事業者となる場合、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があります。
上記の期間が過ぎて登録する場合は、事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出も必要となるため注意しましょう。
免税事業者のままでいる
取引先に課税事業者がそもそもいない場合は、適格請求書を発行する必要はありません。免税事業者のままでも消費税の納税額に変更はなく、特に問題ありません。
適格請求書等保存方式の開始前に企業・個人事業主は早めに準備しよう

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは、消費税の適切な納税を目的として作られ、2023年10月1日から開始予定です。消費税10%導入で発生した2種類の消費税率に適切に対応して、徴税するためのしくみです。開始にともなって、請求書には新たな項目の記載が必須になります。これが「適格請求書」(インボイス)です。
適格請求書では記載項目が増えるため、経理処理が増えます。事業者によっては今後の対応が迫られるため、早めに準備しておきましょう。
以下の資料では、ほかにもインボイス制度によって生じる影響や事前の準備について解説しています。インボイス制度への対策を知り、制度開始に備えたい方は、ぜひご確認ください。
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。