| Writer:NTT東日本 北森 雅雄(Masao Kitamori)
請求書の受領や処理を自動化・効率化する5つの方法|メリットや選定ポイントを紹介

「請求書の処理を自動化したい」「毎月請求書の処理に手間がかかる」とお悩みの方が、いらっしゃるのではないでしょうか。毎月発生する請求書の受領・確認業務を自動化することで、大幅な効率化につながります。
そこで今回の記事では、請求書処理を自動化する方法やメリット、ツールの選び方について説明しています。請求書周りの業務を自動化する方法がわからない経理担当の方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次:
1.請求書の処理における4つの課題
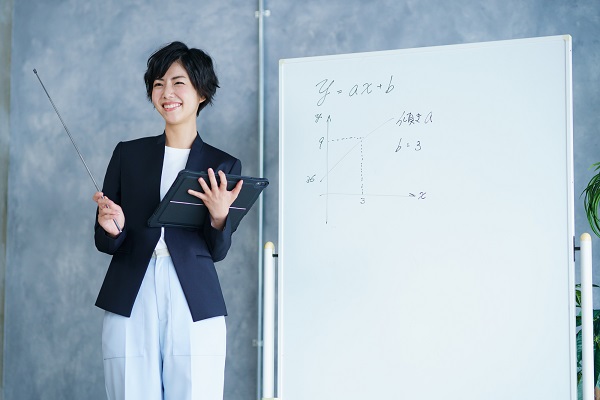
請求書の処理には、受領の際に発生してしまう課題がいくつかあります。これらの課題は業務のスムーズな進行を妨げてしまいます。
- ・取引先の企業ごとにフォーマットが異なる
- ・受領後の入力作業に時間と手間がかかる
- ・人的ミスが発生しやすい
- ・データ化やファイリングに負担がかかる
この章では、取引先から請求書を受領する際の課題について解説します。
1取引先の企業ごとにフォーマットが異なる
取引先によって請求書のフォーマットが異なります。企業ごとにレイアウトや記載項目の場所が異なるため、それに合わせて請求書を確認しなければなりません。
また、手入力での請求書処理は、ミスを防ぐのが難しく、内容を誤って転記してしまうリスクが高いです。取引先によって、項目の名称なども異なるのもミスを発生させてしまう要因となります。
2受領後の入力作業に時間と手間がかかる
受領後は、膨大な数の請求書を手入力で会計システムへ入力し、振り込みまで行う必要があります。そのため、時間がかかる上に属人性の高い業務です。
請求書業務は月末など決まった時期に集中して行う傾向にあるため、入力作業が大きな負担となります。担当者への負担となり、ストレスや集中力に影響してしまうでしょう。
3人的ミスが発生しやすい
電卓やExcelで請求金額などを計算したり、手作業で会計システムへ入力をすると、数字の打ち間違えなどからどうしても人的なミスが発生しやすくなります。
ミスを防ぐために、複数人でチェックをしている企業もありますが、確認作業だけで負担となってしまいます。その分、時間や人件費がかかってしまうでしょう。
4データ化やファイリングに負担がかかる
請求書を受領したら、スキャンを行いデータとして保管をしつつ、原本もファイリングして適切に保管する必要があります。
これらの業務は手間や時間がかかります。また請求書原本をファイリングしたら、保管しておく場所を確保しなければなりません。
請求書の原本は、原則7年保管する必要があります。その間保管をしておく場所が必要になり、請求書の量が増えてくるとスペースを圧迫してしまいます。
2.請求書の処理を自動化・効率化する6つの方法

取引先から受領する請求書を処理する際、手作業で行うと手間や時間がかかってしまいます。しかし、自動化・効率化することで、円滑な経理処理や従業員の負担解消が可能です。
- ・請求書のフォーマットを統一する
- ・入力の二度手間をなくす
- ・承認プロセスを簡略化する
- ・請求書受領代行サービスを活用する
- ・業務自動化ツールを活用する
- ・会計ソフトを活用する
この章では、請求書の処理を自動化・効率化する具体的な方法を6つ解説します。
1請求書のフォーマットを統一する
取引先に電子化された請求書を発行してもらい、フォーマットを統一しましょう。ただし、取引先にお願いをして、利用方法などのサポートを行う必要があります。
また、クラウド上で登録してもらうことにより、初めから自社の形式に最適化された請求書を即時に受領可能です。
自社に最適化された請求書が届けば、確認作業にかかる手間やミスが減り、従業員のストレスも軽減できるでしょう。
2入力の二度手間をなくす
アナログな方法にはなりますが、請求書を受領してからデータ入力、銀行振込に至るまでのプロセスを再度見直してみましょう。そして余計な作業が発生していないか、確認が必要です。
請求書受領後の返信メールについて、テンプレートを作成して用意しておいたり、データ入力のマニュアルを整備しておいたりすることも、効率化につながります。
3承認プロセスを簡略化する
請求書の受け取りサービスに、ワークフローシステムが導入されていれば、承認プロセスもスムーズに進められます。
請求書のみならず、取引先に関わる稟議書や見積書、契約書、領収書などのファイルを、一元管理する機能があると、上長などの承認者が情報を確認する手間が省けます。
書類の原本を出してきて確認を依頼する手順が省けるため、承認者や担当者の負担が削減できます。
4請求書受領代行サービスを活用する
請求書の受領代行サービスを活用するのも、自動化・効率化するための方法の1つです。受領手続きや受領後のスキャン、データ化など一連の流れを代理対応してもらえます。
請求書の受領業務を外部へ委託すると、自動的にデータ化されたものを受け取れるため、効率的に業務が進められます。代行サービスは、手作業で行っていた作業が軽減され、費やしていた時間を有効に活用できる方法です。
5業務自動化ツールを活用する
業務を自動化してくれるツールを活用することで、請求書に関わる多くの業務を効率化できます。自動化してくれるツールとして、OCRやRPAが挙げられます。
これらを使いこなせれば、人が関わる業務における負担を削減できるでしょう。
OCR
OCR(Optical Character Recognition)は、AI技術を活用して手書きの文字を読み取り、書類を電子データ化するツールのことです。紙に書いた文字をデータ化するだけではなく、読み取った書類の種類や項目まで把握し、適切な場所へデータを格納してくれます。
さまざまなフォーマットの読み取りに、活用できる便利なツールです。
RPA
RPAは「Robotic Process Automation」の略語で、頻繁に行っている定型作業を、ソフトウェアロボットに覚えさせ、代替させることです。
あらかじめ設定しておいた業務プロセスを、自動的に実行できるのが特徴です。受領した請求書データを、自動的に自社のシステムへ入力してくれます。
6会計ソフトを活用する
会計ソフトを活用すると、請求書処理が楽になります。請求書をデータ化したあとは、会計ソフトに取り込むことで、業務負担が減ります。
会計ソフトはさまざまな種類があるため、しっかりと比較をしてから導入を決めましょう。
3.請求書業務を自動化する2つのメリット

専用のツールを導入することで、請求書周りの業務を自動化できます。従来は経理担当者がやっていた業務を機械が代替するので、手作業のときに発生していた課題の解決につながるでしょう。
請求書業務を自動化することで得られるメリットには、以下のようなものがあります。
- ・業務負担を軽減できる
- ・オンライン上で作業が完結する
この章では、請求書業務を自動化する具体的なメリットについて、2つ解説します。
1業務負担を軽減できる
請求書の受領を自動化することで、月末などに集中してかかっていた経理担当者への業務負担を、軽減できます。
月末になると請求書業務に追われ、残業や早出、休日出勤をしていたという担当者の方もいるのではないでしょうか。これらの業務負担が軽減できるというのは、大きなメリットです。
業務負担が減ると、従業員もストレスから解放されます。また、今までかかっていた処理に時間がかからなくなるため、他の業務にリソースを割くことが可能です。
2オンライン上で作業が完結する
請求書受領を自動化することで、ネット環境がある場所であれば、外出先や自宅など、どこでも確認や作業ができるようになります。コロナ禍でも経理担当者だけ出社している企業は、多いのではないでしょうか。
請求書周りの作業を自動化できれば、受領や確認作業だけのために、出社することがなくなります。リモートワークの実施を検討している企業には、請求書受領の自動化をおすすめします。
4.請求書業務を自動化するツールを選ぶ4つのポイント

請求書業務を効率化するには、自社のリソースや状態に合わせた最適なツール選定が必須です。ツールを選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。
- ・自社の業務フローに合った機能
- ・ツールの導入形態
- ・費用対効果
- ・サポート体制の充実度
この章では、それぞれの選定ポイントについて具体的に解説します。導入後、円滑に経理業務を進めたい方はぜひ参考にしてください。
1自社の業務フローに合った機能
社内の業務フローに合っている機能が搭載されており、既存システムとどの程度連携ができるのかをチェックしておく必要があります。
操作方法が直感的かつ容易なツールであれば、教育や業務の引き継ぎがスムーズです。逆に操作方法が難しいと、せっかく導入をしても、浸透するのに時間がかかってしまいます。
2ツールの導入形態
ツールの導入形態には、オンプレミス型とクラウド型の2種類があります。オンプレミス型は、自社に設置したサーバーでシステム構築して作業を行うタイプで、サーバーの維持やメンテナンス費用が毎月発生します。
クラウド型の場合は、設置費用がかからず、ユーザー数ごとの月額課金が主流です。オンプレミス型は、セキュリティ対策が強固であり、クラウド型はアップデートへの対応が早いというメリットがあります。自社の費用感やニーズに合わせてツールの導入形態を決めましょう。
3費用対効果
自動化ツールを導入する際は、まず費用対効果を確認する必要があります。費用対効果を確認するためには、導入初期費用、月額利用料金のほかに、運用にかかる工数や人件費軽減の割合、人的ミスによる損失防止効果がどれだけ得られるかという観点で確認をすると良いでしょう。
また、請求書入力を自動化させるとき、設定の変更が容易なツールを選ぶことも大切です。設定に変更があった際、自社ですぐに対応できるツールの方がコストがかかりません。
4サポート体制の充実度
自動化ツールを導入したばかりの頃は、サポート体制が充実していると、万が一の事態が起こっても安心です。電話やメールによるヘルプデスクがあったり、各種の勉強会が開催されていたりなどの、サポート体制が整っているかどうかを事前に確認しておきましょう。
また、トレーニングガイドが提供されるのかも確認しておくと、問題が発生した際にサポートデスクに相談せずとも自身で解決できるでしょう。
5.請求書業務の自動化はNTT東日本の「おまかせRPA」

NTT東日本が提供している「おまかせRPA」は、Windowsの端末上でさまざまな業務を自動化できるRPA(業務効率化)ツールです。操作しやすいGUIにより、プログラミングせずに直感的な画面操作だけで業務自動化できます。インターネット環境があれば、パソコンにインストールするだけで利用でき、1ライセンスから導入可能です。
操作感や機能を確認できるように、2ヶ月間のトライアル版も用意されているため、実際に試してみてから導入を決めると良いでしょう。
また、NTTが提供する他サービスとセットで導入するのもおすすめです。「AIよみと〜る」で請求書を電子化し、「おまかせRPA」でパソコン上の作業を自動化、データ化したものは会計サービスの「freee」へ投入することで、効率的なバックオフィス処理を実現します。
効率的なバックオフィス業務の導入を検討している方は、以下のリンクを参考にしてください。
6.請求書業務を自動化して経理のDX化へ

請求書周りの業務を自動化して、経理担当者の負担を減らしていきましょう。請求書処理の自動化ができれば、経理業務の改善ができ、他の重要な業務に集中して取り組めます。
自動化というと難しいように感じるかもしれませんが、専用のツールを導入すれば簡単に実施できます。最初は操作が難しいと感じるかもしれませんが、サポート体制がしっかりしているツールを選べば、スムーズに自動化を推進できるでしょう。
ただし、自動化するときは現場担当者の方にも相談をしてみましょう。現場担当者の方の意見・ニーズを聞きつつ、自動化を進めていけば、今よりも円滑な請求書業務が実現できます。自社に合ったツールを見つけて、請求書業務を自動化・効率化をしていきましょう。
この記事を書いた人
NTT東日本 ビジネス開発本部 北森雅雄
NTT東日本に入社後、自治体向けのシステムエンジニアとして、庁内ネットワークや公共機関向けアプリケーションなどのコンサルティングからキャリアを開始。
2018年から現職にて、プロダクト(SaaS)開発、デジタルマーケティング全般のディレクションに従事。
2022年に業務のデジタル化を分かりやすく発信するオウンドメディア(ワークデジタルラボ)のプロジェクトを立ち上げ。
NTT東日本にかかわる、地域のみなさまに向けてデジタル化に役立つ情報発信を展開。
