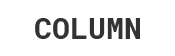
生成AIで自治体業務を効率化!導入事例やメリットについて解説

生成AIは、大量のデータを学習し、新しい文章や画像、音声を自動生成する技術で、ChatGPTのような自然言語モデルが含まれます。従来のルールベースAIとは異なり、生成AIは柔軟に応答できる点が特徴です。本コラムでは、生成AIの概要、自治体導入の背景とメリット、具体的な活用事例、導入課題と対策について解説し、生成AI導入を検討する自治体に役立つ情報を提供します。
1. 生成AIとは?
近年、人工知能(AI)の進化が加速する中で、特に注目されているのが「生成AI」と呼ばれる技術です。生成AIとは、膨大なデータを学習し、それをもとに新しい文章や画像、音声などを自動生成するAI技術のことを指します。例えば、ChatGPTのような自然言語モデルは、人間の質問に対して自然な文章を作成したり、要約を行ったりすることが可能です。従来のAIはルールベースで動作し、決められたパターンに基づいて回答を返すものでしたが、生成AIはより柔軟に応答し、状況に応じたコンテンツを生み出せる点が特徴です。
この技術は、すでにさまざまな業界で活用されており、自治体業務においても導入が進められています。生成AIを活用することで、業務の効率化やコスト削減が可能となり、住民サービスの向上にもつながるため、多くの自治体がその可能性を探っています。
2. 自治体に生成AI導入が求められる背景
日本の自治体は、少子高齢化や人口減少といった社会的な課題に直面しており、それに伴う行政サービスの効率化が求められています。特に、職員の数が減少する一方で業務量は増加傾向にあり、限られた人員で質の高い行政サービスを提供することが大きな課題となっています。
参考:生成AIで自治体の業務はどう変わる?導入状況や課題について解説
また、住民からの問い合わせ対応や行政文書の作成、データ分析など、多岐にわたる業務において時間と労力がかかっているのが現状です。
こうした状況を受けて、生成AIの導入が注目されています。AIを活用することで、単純作業を自動化し、職員がより重要な業務に集中できる環境を整えることが可能になります。さらに、生成AIの高度な自然言語処理能力を活かし、住民からの問い合わせ対応や文書作成の効率化を図ることで、行政サービスの質を維持しながら、業務の負担を軽減できると期待されています。
3. 自治体業務における生成AI活用のメリット
3-1. 業務効率の向上
自治体の業務には、申請書類の作成や問い合わせ対応、議事録の作成など、多くの文書作成業務が含まれます。従来、これらの業務は職員が手作業で行っていましたが、生成AIを活用することで、自動化や補助が可能となります。例えば、会議の議事録を自動で要約し、重要なポイントを抽出するAIを活用すれば、職員が一から書き起こす手間が大幅に削減されます。また、住民からの問い合わせに対しても、AIが適切な回答を自動生成することで、職員の負担を軽減できます。
3-2. コスト低減
自治体では、業務の効率化だけでなく、運営コストの削減も重要な課題です。生成AIを導入することで、従来は外部委託していた業務の一部を内部で処理できるようになり、コスト削減につながります。また、AIを活用した自動対応システムを導入することで、住民からの問い合わせ対応にかかる人件費を削減することができます。
3-3. 住民満足度の向上
生成AIの導入は、自治体職員の負担軽減だけでなく、住民の利便性向上にも寄与します。例えば、AIを活用したチャットボットを導入すれば、住民はいつでも必要な情報を得ることができるようになります。また、多言語対応が可能なAIを導入することで、外国人住民への行政サービスの充実が図れます。さらに、行政手続きの説明文を簡潔に要約するAIを活用すれば、住民が理解しやすい形で情報を提供することができ、利便性が向上します。
4. 自治体での生成AIの活用事例
すでに日本国内のいくつかの自治体では、生成AIの導入が進められています。
ここでは、NTT東日本が支援した神奈川県藤沢市の事例を紹介します。
4-1. 生成AI導入の背景
今後予想されている藤沢市全体の人口減少や、行政サービスの担い手である職員の減少を受けつつも、行政サービスを必要とする市民へ確実に届けるためには、既存業務の在り方を見直しつつ省力化を図りながら、サービスレベルを維持、向上していく必要がありました。そのため、継続的なDXの取り組みが必要不可欠だとの考えから、DX化を推進する取り組みの一つとして生成AIの利用が推進されました。
4-2. 生成AIのユースケース
藤沢市では、生成AIソリューションのPoC(概念実証)を通じて、DXアプローチに適した仕組みを構築しました。具体的なユースケースを紹介します。
道路管理課
道路管理課では、市民や業者からの道路や水路に関する多岐にわたる問い合わせに電話で対応していますが、対応する担当が分かりにくく、電話対応件数が多いことや専門知識が必要なケースがあることが課題となっています。そこで、生成AIを用いて、初めて道路部門に配属された職員を対象に、電話応対を要約し、適切な担当課を回答する「要約・回答コンシェルジュ」を構築し、検証しました。
建設指導課
計画建築部は都市計画から建築物の安全基準までを担当する専門性の高い部署で、主に技術職員で構成されています。建築指導課では建築基準法に基づき設計図書を審査し都市の安全を確保していますが、技術職員の採用難と膨大な紙・Excel資料によるノウハウ習得の困難さが課題です。これらの課題に対処するため、RAG機能を用いてAIに建築基準法を学習させ、法規運用支援AIを構築しました。データ整備やプロンプト調整を繰り返し、一定の精度で回答が得られるようになり、業務利用の可能性を実感しました。
4-3. 検証結果と得られた成果
PoC(概念実証)を通じて、これまでイメージできていなかった生成AIの活用シーンを創出することが可能になりました。このPoCにより、行政職が生成AIに期待する役割や得られるメリットがより鮮明にイメージできるようになりました。
さらに、AI技術の進展に伴い、使用者側のスキルセットの向上も不可欠であることが実感され、生成AIの活用を取り巻く課題も明確になりました。PoCに参加した職員からは、「生成AIは難しいというイメージが払拭された」「活用しないともったいない」といった意見が寄せられ、庁内のAIに対する意識が変わることが期待されています。
5. 自治体での生成AI導入における課題と対策
5-1. 技術的な課題
生成AIの導入には、技術的なハードルも存在します。例えば、生成AIが提供する情報の正確性の問題が挙げられます。AIは学習データに基づいて回答を生成するため、場合によっては誤った情報を提供するリスクがあります。これを防ぐためには、生成AIの出力内容を職員がチェックする体制を整えることが重要です。また、自治体が保有するデータを適切にAIに学習させることで、より信頼性の高い回答を提供できるようになります。
5-2. 組織的な課題
自治体が生成AIを導入する際には、職員のAIリテラシー向上が不可欠です。新しい技術を導入しても、職員が使いこなせなければ十分な効果を発揮できません。そのため、職員向けの研修やマニュアルを整備し、適切な活用方法を周知することが求められます。また、AIの導入には、組織全体の合意形成も必要となります。AIの活用によってどのような業務が効率化されるのかを明確にし、関係者の理解を深めることが重要です。
6. 自治体での生成AI導入ならNTT東日本にお任せください
NTT東日本では、自治体向けに生成AIの環境提供や活用促進に関するコンサルティング、生成AIのユースケース創出に向けた技術支援を行っております。
また、生成AI導入にあたってのガイドライン制定やセキュリティを遵守した生成AIシステム環境の構築などの支援を行っています。
NTT東日本の提供する生成AIソリューションの詳細はこちらの資料をご覧ください!
7. まとめ
生成AIは、自治体業務の効率化やコスト削減、住民サービスの向上に大きな可能性を持つ技術です。すでにいくつかの自治体では、文書作成の自動化や住民対応のAI化が進められ、成果を上げています。しかし、その導入には技術的・組織的な課題もあり、適切な運用体制の整備が必要です。今後、生成AIの活用がより一般的になることで、自治体業務のさらなる効率化と質の向上が期待されます。
生成AIの活用に向けて、地域DXアドバイザーや生成AIエンジニアが徹底サポートいたします。

