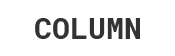
生成AI導入後の活用促進策:社員研修と運用ガイド

近年、生成AI(Generative AI)の技術は急速に進化し、多くの企業が業務効率化のためにその導入を検討しています。しかし、生成AIの活用にはさまざまな課題が伴います。特に、導入が進んでいる一方で、実際の業務での活用が進まない企業も多く存在します。主な原因として、従業員のスキル不足、適用領域の不明確さ、適切な運用ルールの欠如が挙げられます。さらに、情報システム部門におけるセキュリティやコンプライアンスの懸念、経営層や管理職の理解不足も、導入後の活用推進を阻害する要因となっています。生成AIを効果的に活用するためには、技術導入だけでなく、全社的な意識改革や業務プロセスの見直しが求められます。また、社員が生成AIの特性を理解し、業務に応じた活用方法を習得するための適切な研修も不可欠です。本コラムでは、生成AIの導入と活用を成功させるためのリスクと対策について詳しく解説します。NTT東日本の生成AI研修や運用ガイド作成支援をご紹介し、企業が生成AIを安全かつ効果的に活用するための具体的な方法を提案します。生成AIの導入を検討している方々が、本コラムを通じてそのメリットとリスクを理解し、成功に向けた一歩を踏み出す助けになれば幸いです。
1. 生成AIの活用の現状と課題
1-1. 生成AIの活用が進まない原因
生成AIの導入が進んでいる一方で、実際の業務活用が進まない企業も多く存在します。主な原因として、(1)従業員のスキル不足、(2)適用領域の不明確さ、(3)適切な運用ルールの欠如が挙げられます。特に、情報システム部門においては、セキュリティやコンプライアンスの観点から、生成AIの利用に慎重になりがちです。その結果、現場での利用が限定的となり、導入効果を最大化できないケースが多く見受けられます。また、経営層や管理職の理解不足が、導入後の活用推進を阻害する要因となることもあります。生成AIを効果的に活用するためには、単なる技術導入にとどまらず、全社的な意識改革や業務プロセスの見直しが求められます。
1-2.研修の重要性
生成AIの活用を促進するためには、適切な研修が不可欠です。社員が技術の特性を理解し、業務に応じた活用方法を習得することで、導入効果を高めることができます。また、研修を通じて、生成AIのリスクや倫理的課題についても学ぶことで、安全かつ効果的な活用が可能となります。情報システム部門の担当者は、全社的なAIリテラシー向上を目的とした研修計画を策定する必要があります。特に、業務ごとに適用できるユースケースを示すことで、より実践的な学習が可能となります。さらに、研修後に実務での活用を評価し、必要に応じて追加研修を実施することで、スキルの定着を図ることが重要です。
2. 生成AI活用の社員研修の計画と実施
2-1. 研修の目的と目標設定
研修の目的は、社員が生成AIの基本概念や適用可能な業務領域を理解し、実務に活かせるスキルを習得することです。具体的な目標として、(1)生成AIの基本機能の理解、(2)実際の業務での活用方法の習得、(3)適切な運用ルールの確立が挙げられます。情報システム部門は、業務部門のニーズを踏まえた研修計画を策定する必要があります。また、目標設定には、定量的な評価基準を導入し、研修効果を測定できる仕組みを構築することが望ましいです。例えば、研修前後での理解度テストの実施や、研修後の業務適用事例の報告を義務化することで、実際の成果を可視化することができます。
2-2. 研修内容の設計
研修は、(1)基礎知識編、(2)実践編、(3)リスク管理編の3つのセクションで構成すると効果的です。基礎知識編では、生成AIの基本原理や市場動向を学びます。実践編では、業務への適用方法を実際に操作しながら習得します。リスク管理編では、情報漏えいや著作権問題など、生成AI特有のリスクについて学び、適切な運用方法を確立します。さらに、業務に即したケーススタディを取り入れることで、より実践的な学習を促します。例えば、営業部門では顧客対応の自動化、マーケティング部門ではコンテンツ生成の最適化など、具体的な適用事例を交えた研修が求められます。
2-3. 研修の実施方法
研修の形式として、オンライン講義・ワークショップ・ハンズオン演習を組み合わせると効果的です。オンライン講義では理論を学び、ワークショップでは業務に活用するためのディスカッションを行います。ハンズオン演習では、実際に生成AIを活用する演習を実施し、実務への応用力を高めます。また、企業内のエキスパートや外部講師を招いての講義を取り入れることで、実践的な知識を深めることが可能となります。研修後にアンケートを実施し、受講者のフィードバックを収集することで、継続的な改善を図ることが重要です。
3. 生成AI運用ガイドの作成
3-1. 運用ガイドの目的
生成AIの適切な運用を確立するためには、明確なガイドラインが必要です。運用ガイドの目的は、業務適用の指針を示すこと・セキュリティやコンプライアンスの遵守を徹底すること・生成AIの活用事例を社内で共有することです。
運用ガイドを策定し、企業全体の統一的なルールを定め、生成AIを利用する際のデータ入力方法や、業務プロセスへの組み込み方を標準化することで、組織全体での効率的な活用が可能となります。
3-2. 運用ガイド
運用ガイドには、生成AIの活用範囲・データの取り扱いルール・業務適用時のベストプラクティス・リスク管理の手順を明記する必要があります。
生成AIの活用範囲について
生成AIを使用できる業務領域と、使用が制限される領域を明確に定める必要があります。例えば、顧客対応の自動化には活用可能ですが、機密情報の生成には利用しないといったガイドラインを設定します。
データの取り扱いルールに関して
個人情報や機密データを扱う際の暗号化やアクセス制御の方法を定め、適切なデータ保護策を講じることが重要です。
業務適用時のベストプラクティス
生成AIの適切な活用方法を示し、従業員が効率的に利用できるようサポートします。例えば、メール文書作成の補助やマーケティング資料の草案作成といった具体的なユースケースを提供することで、実務での活用を促進できます。
リスク管理の手順について
生成AIが出力する情報の正確性を担保するためのチェックプロセスや、誤情報が発生した場合の対応策を明記することが求められます。
運用ガイドを効果的に運用するためには、実際の業務に即したトレーニングやガイドラインの浸透を促すために、定期的な社内勉強会やワークショップを開催し、従業員が適切なAI運用のスキルを継続的に習得できる環境を整えることが重要です。
4. 生成AI活用促進のための取り組み
4-1. 社内コミュニケーションの強化
生成AIの活用を推進するためには、全社的なコミュニケーションの強化が重要です。多くの企業では、生成AIに関する理解が個々の社員によって異なり、活用のばらつきが生じることが課題となっています。そのため、社内での情報共有や意見交換の場を設けることが、生成AIの活用の促進につながります。
具体的な取り組みとして、定期的な勉強会やワークショップの開催・社内SNSやポータルサイトを活用した情報共有・各部門の活用事例の発表会の実施が挙げられます。特に、業務における具体的な活用例を共有することで、他の部門でも応用可能なアイデアが生まれる可能性が高いです。また、社員が気軽に相談できる専門チームなどを設置することで、疑問や課題を迅速に解決し、活用のハードルを下げることができます。
4-2. 成功事例の共有
成功事例を共有することで、生成AIの活用メリットを社内に広め、他の部門での活用を促進できます。企業によっては、生成AIの導入によって業務効率の向上や、新たなビジネス価値の創出などのケースがありますが、その情報が適切に共有されなければ、他の部門の活用意欲は高まりません。
成功事例を共有するためには、社内ニュースレターやポータルサイトでの掲載、定期的な成功事例発表会の開催、部門ごとの生成AI活用レポートの作成/配布が有効です。特に、具体的な数値データやビフォー・アフターの比較を交えた事例を紹介することで、他部門が自身の業務に適用する際のイメージを持ちやすくなります。
4-3. 継続的な教育とトレーニング
生成AIは日々進化しており、企業がその変化に適応し続けるためには、社員の継続的な学習とスキル向上が必要です。初回の研修のみで終わらせるのではなく、定期的なトレーニングを実施し、先進の技術動向や活用方法をアップデートしていく必要があります。
継続的な教育とトレーニングの方法として、eラーニングプラットフォームを活用したオンデマンド学習、専門家や外部講師を招いた定期的なセミナーの実施、業務に即した実践型ワークショップの開催が効果的です。特に、実務に直結するスキルを身につけるためのハンズオン演習を取り入れることで、より実践的な知識を習得できます。また、トレーニングの成果を測定し、社員ごとに適切なレベルの学習コンテンツを提供することで、習熟度に応じた成長を促すことが可能です。
5. 社員・職員向けの研修ならNTT東日本にお任せください!
NTT東日本では、自治体向けに生成AIの環境提供や活用促進に関するコンサルティング、生成AIのユースケース創出に向けた技術支援を行っております。
また、生成AI活用コンサルティングの一環として生成AIの基礎・実践研修も行っております。
NTT東日本の提供する生成AIソリューションの詳細はこちらの資料をご覧ください!
6. まとめ
本コラムでは、生成AI導入後の活用促進策についてご紹介しました。NTT東日本の生成AI活用支援サービスを活用することで、LLMの活用・定着を円滑に進め、ビジネスの成功をサポートすることができます。
生成AIの活用に向けて、地域DXアドバイザーや生成AIエンジニアが徹底サポートいたします。

